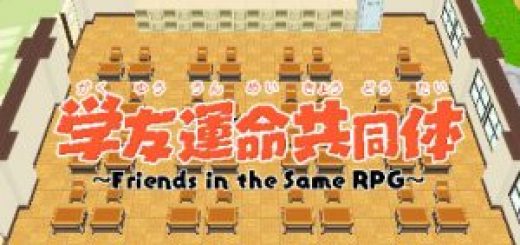『FFXV』を開発・宣伝するうえで、『GTAV』、『DQIX』、『Destiny』から学んだこととは? SQEX田畑端氏の基調講演をリポート
文・取材・撮影:編集部 ロマンシング★嵯峨
●重要なのは、疑問を抱き、掘り下げていくこと
2016年10月22日、福岡県福岡市の九州大学 大橋キャンパスにて、コンピューターエンターテインメント開発者向けのカンファレンス“CEDEC+KYUSHU 2016”が開催。
この中で、『ファイナルファンタジーXV』(以下、『FFXV』)ディレクターとして知られるスクウェア・エニックス 田畑端氏による基調講演“GTA ドラクエ Destinyから教わったこと”が行われた。
この基調講演では、田畑氏が「話したい」と思うテーマを冒頭で提示。
来場者はそれを受け、聞きたいと思うテーマに対して拍手をして、拍手が大きかったテーマから語っていくという形式が採用された。
提示されたテーマは、下記の5つ。
・GTAから学んだこと
・ドラクエから学んだこと
・デスティニーから学んだこと
・会社説明会プランナー編
・もしレベルファイブにいたらやってみたいこと
では、拍手による投票の結果はどうなったかというと……なんと、ほとんど差がなかったため、田畑氏が順番をその都度考えて語っていくことに!まずは、“GTAから学んだこと”から語られた。
●『グランド・セフト・オートV』から、間口の広さの大切さを学ぶ
テーマ“GTAから学んだこと”、“ドラクエから学んだこと”、“デスティニーから学んだこと”の3つを、田畑氏は“学ぼうシリーズ”を呼ぶ。
そして、このシリーズで伝えたいことは、“疑問を掘り下げること”だと語る。
常日頃、疑問を抱いても、「どうしてそうなのか」と掘り下げないまま進んでしまうことが多いが、物事は何事も、理由があって、そのようになっている。
たとえば、RPGにおけるバトルについて。
バトルというものは、「こんなバトルだったらおもしろいな」という、漠然としたアイデアから始まるものではない。
たとえば、クリアーまで30〜40時間ほどかかるRPGを作るとして、クリアーまでに行う戦闘の回数を考えると、コマンドベースのバトルなら、400〜500回になる。
バトルが1回、3分で終わるとしたら、3分×400〜500回で20時間以上かかる。
ゲームプレイの半分以上の時間をバトルに使うことになり、残り時間でその他の要素を行うことになる。
ならば、戦闘を2分で終わるようにして、10回ほど戦ったら、自分より強かった敵に勝てるようになるバランスにしよう……などと全体の設計を考えて、バトルは作られていくのだ。
そのように、何事も必然性を持って作られていることが多い。
それを知り、今後の仕事に活かしてほしいというのが、“学ぼうシリーズ”の主旨だ。
では、『グランド・セフト・オートV』について田畑氏が疑問に思ったことは何か。
それは、「なぜ、そんなに売れまくる?」。
発売初日に8億ドル以上の売り上げを叩き出し、7つのギネス記録を打ち出した『グランド・セフト・オートV』。
それは単純に“ゲーム内容がいいから”だけではないはずだ、と田畑氏は考え、どんな人が買っているのかを調査した。
結果、リアル、フリーダム、バイオレンスというキーワードに、非常にたくさんの人たちが惹かれたことがわかった。
“リアル”といえば、100%の人がどんなものか想像できる世界。
“フリーダム”というのも、100%の人に伝わるコンセプト。
“バイオレンス”は、人間の中に存在するであろう本能。
つまり、『グランド・セフト・オートV』は、国籍や年齢に関係なく、ゲームの内容が伝わるものだった。
さらに、操作がカンタンであること、現実ではやってはいけないことをやれるということに衝動を掻き立てられ、その衝動・欲求にゲームデザインが応えてくれることも、さらにゲームの間口を広げた。
ゲームの入り口は広くあるべきだと学んだ田畑氏は、『FFXV』にも、その学び――広い地域で支持されるノウハウを活かした。
ユーザーインターフェースは、「覚えることが多そう」とユーザーに敬遠されないよう、シンプルに。
操作についても、最初に覚えた操作でプレイを続けられるような設計を採用。
世界観は、まずは現代に近い世界観からスタートし、だんだんと『FF』らしい世界に移っていくものにした、と田畑氏は語った。
●『ドラゴンクエスト』が教えてくれた“線の戦略”
続いてのテーマは、“ドラクエから学んだこと”。
ここでは、『ドラゴンクエストIX星空の守り人』を題材に、田畑氏の学びが語られた。
親子で遊べる国民的ゲームとして知られる『ドラゴンクエスト』シリーズ。
2009年に発売された『ドラゴンクエストIX』は、シリーズ最高出荷本数を記録した。
これも“内容がいいから”だけではないはずだ、と田畑氏は考え、その理由を考察。
そして、「そういえば、ニンテンドーDSで、過去作のリメイクが出ていたな」、「『ドラゴンクエストモンスターズ』も出ていたな」、「アーケード(『ドラゴンクエスト モンスターバトルロード』)もあったな」と思いいたる。
リメイク作によって過去作ファンが、『ドラゴンクエストモンスターズ』によって新規ファンが刺激され、さらに『ドラゴンクエスト モンスターバトルロード』で、親子で楽しむ風潮が生まれた。
加えて、グッズを展開することで、“ゲームはプレイしていないがグッズは知っている”という人々、つまり“『ドラゴンクエスト』というIPに親しみを覚えている”人々が数多く存在していたこともあり、結果、『ドラゴンクエストIX』は大ヒットにつながった。
田畑氏はこれらの施策を“線の戦略”と考え、『FFXV』にも導入。
手軽に見られる映像作品『ブラザーフッド FFXV』、『キングスグレイブ FFXV』を制作したり、秋葉原にオープンしたスクウェア・エニックス カフェで『FFXV』メニューを展開したりと、ゲーム発売前にキャラクターや世界に触れてもらう施策を進めた。
また、日本だけでなく世界各地でも、そのような企画を進め、幅広い世代との接点作りを心がけていったという。
●プランナーはさまざまな能力が求められる何でも屋
ここで、“学ぼう”シリーズは一度お休み。
つぎのテーマは“会社説明会プランナー編”で、田畑氏が以前、学生向けの会社説明会にて述べた内容を軸に、プランナー職に必要なもの、求めるものが語られた。
プランナーとは、ゲームをおもしろくするための“なんでも屋、便利屋”。
田畑氏は、便利でないプランナーは無価値だとあえて言い切る。
田畑氏は、プランナーが直面する問題と、その解決方法を提示しながら、プランナーに必要な資質を紹介した。
たとえば、社長が新企画に食いつかない場合。
新しい企画を考えるべきなのか、緻密な収支計画を立てて「この企画はイケます」と説得するべきなのか……田畑氏が考える正しい答えは前者だ。
最初に企画がイマイチだと思われると、その印象を根本から覆すのは難しい。
企画が相手の胸に届いていない以上、数字を並べて突破したところで、プランナーとしての信頼は得られない。
必要なのは、第三者が「勝てる」と思うビジョンの提示で、オーケーが出るまで何度もやり直せる精神力、執着力が必要だと語った。
つぎの事例は、自分は『進撃の巨人』を読んでいないが、先輩に『進撃の巨人』を題材にアイデアを説明されたとき。
知っているとも知らないとも言わずにうまくやり過ごすべきか、正直に「知らないので教えて」と聞くべきか。
田畑氏の答えは前者。
相手の言いたいことを察知できるなら、聞くことは必要はないという。
察知する能力はプランナー業務を支える重要なものであり、察知したことを他者に伝えてハブとなることで、業務が円滑に進む、と田畑氏。
最後の事例は、同世代と比べて自分の年収が低い場合、転職活動をするべきか、給料が高い社内の人にアドバイスをもらうべきか。
答えは後者。
田畑氏が伝えたいのは、給料を上げることの大切さではなくて、問題を解決するために、誰かに頼ることの大切さ。
ゲーム開発において、問題は最速で解決することが重要。
プランナーには問題解決能力が求められる。
精神力、執着力、察知力、問題解決能力などが求められるプランナー。
では、スクウェア・エニックスでは、いったいどんな人がプランナーとして働いているのか?ここで、田畑氏が『FFXV』のプランナー陣のプロフィールを紹介した。
共通しているのは、個性が強いということ。
長所を見つけて伸ばしていくことが重要だということだ。
●もし田畑氏がレベルファイブにいたら……?
ここまで語ったところで、田畑氏は箸休めとして、テーマ“もしレベルファイブにいたらやってみたいこと”を選択。
やってみたいこと、それはずばり“ドラクエを作る”こと!
いま、田畑氏は『FF』というIPを発展させるため、最新作を担当している。
『FF』を放り出して、別のことをできる立場ではない。
しかしレベルファイブにいたら、『ドラゴンクエスト』を作れるのではないか?と考えたのだとか。
●『Destiny』は「ヒットしてほしい」と皆が願った
最後のテーマは、“デスティニーから学んだこと”。
バンジーが手掛ける『Destiny』は、2014年のE3で発表されるや否や話題を呼び、E3発表トレーラーの再生数は937万回にも上った。
新規IPでありながら圧倒的な予約数を獲得したことでも話題となったが、この爆売れムードはどこから来たのか。
田畑氏は、“『Destiny』がPS4普及に貢献してくれるのではないか”という業界人の期待が、そのムードを後押ししたと考えた。
タイトルの底が見えないプロモーションを行い、「どんなゲームなのか」というユーザーの期待を保てたことも勝因だと分析する。
このゲームがヒットしてほしいと皆が願う状況を、『FFXV』でも作り出すためには、まずは信頼してもらうことが必要だと田畑氏は考えた。
そのために、プロジェクトの状況、事実を伝え続けた。
また、「このゲームが、完成するとどうなるのか」と期待を保ってもらうため、ゲームを開発中の段階から見せるプロモーションを行うことに。
何度も行われてきたアクティブ・タイム・レポートには、田畑氏の並々ならぬ思いがあったのだ。
『グランド・セフト・オートV』から広い地域で支持されるノウハウを、『ドラゴンクエストIX星空の守り人』から幅広い世代との接点作りを、『Destiny』から発売前の戦いかたを学んだ『FFXV』。
その学びの実践の結果は、11月29日にきっと明らかになるはずだ。
開発者の学びを促すCEDEC+KYUSHU 2016の始まりを飾った、今回の基調講演。
参加者たちは改めて、続くセッションで何を学んでいくべきなのか、真剣に考えさせられたに違いない。