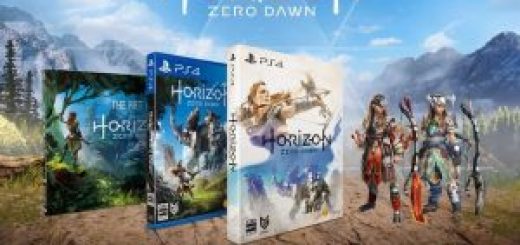Nintendo Switchは“二人三脚”で盛り上げる 任天堂とカプコンのタイトル開発の取り組みを報告
文・取材:編集部 古屋陽一、取材・撮影:編集部 工藤エイム
●カプコンの最新ゲームエンジンRE ENGINEもNintendo Switchに対応を検討
2017年2月18日、大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)にて関西圏のゲームクリエイターを対象としたカンファレンス“GAME CREATORS CONFERENCE’17(GCC’17)”が開催された。
大阪で開催されるセッションということで、関西圏のゲームメーカーが意欲的に参加しているGCC’17だが、ひときわ注目を集めたのが、トリを取る形で行われたカプコン 伊集院勝氏と任天堂 光吉勝氏による“Nintendo Switchにおけるタイトル開発〜プラットフォーマーとサードパーティーの二人三脚の取り組みについて〜”。
発売前のNintendo Switchをテーマにしたセッションということで、たくさんの聴講者を集めて行われたこの講演では、GCCの実行委員を務めるカプコンの伊集院勝氏をホスト役に、伊集院氏が日頃お付き合いのある任天堂 業務部の光吉勝氏を特別ゲストに招き、プラットフォーマーとサードパーティーが相互の立場から、Nintendo Switchにおけるタイトル開発をテーマに語るという、貴重な機会となった。
まずは、登壇者の紹介から。
カプコンの伊集院勝氏は『ロックマンDASH』シリーズや『鬼武者2』などのメインプログラマーを経て、カプコンの自社ゲームエンジンMT FRAMEWORKのディレクターなどを担当し、現在は技術研究開発部技術開発室にて、ゲームエンジンのディレクティング業務やハードウェア・ミドルウェアメーカーとの対外折衝業務を担当している。
一方、光吉氏は1991年に任天堂に入社後、1993年よりソフトメーカーとのやりとりを担当する業務部に異動し、いまにいたるまで開発者の技術的な相談窓口となり、新規プラットフォームの情報開示からゲームを具現化するまでの企画相談、技術サポートに従事している。
「企画の相談から商品を発売するまで、さまざまなお手伝いする部門」(光吉氏)というのが業務部だ。
つまり、伊集院氏と光吉氏は長きにわたっての信頼関係にあり、そんな親しいフランクな関係性が講演の端々からうかがえた。
たとえば『めがみめぐり』の開発では、カプコンのプロデューサーである野中大三氏や伊集院氏をはじめとするタイトル開発スタッフが某鉄道会社を訪問した際、サポートとして光吉氏を含む任天堂 業務部メンバーが同行したというから、その関係性の深さがうかがえるだろう。
セッションは、4つのパートに分けて行われたのだが、本稿でもその流れを順次追っていくことにしよう。
■Nintendo Switchについて任天堂からサードパーティーに示された未来図とは?
セッションでは、「関西圏の開発スタジオにNintendo Switchに対する理解を深めていただく」ことを目的として、光吉氏がカプコンに同ハードを開示した際のプレゼン内容をかいつまんで紹介。
光吉氏によると、まずは任天堂が家庭用ゲーム機の開発を進めるうえで目指す未来像を提示したという。
それは、簡単に言うと「ゲーム業界が抱えている課題と解決策、そしてそこから導きされた答え」だったという。
ひとつの具体例として挙げられたのが、スマートデバイスとの関係。
近年スマートデバイスは大人気を博しているが、光吉氏はプレゼン時に、「任天堂はスマートデバイスにも取り組む」と説明したという。
当然のことだが、まだ、『スーパーマリオラン』などが配信される前の段階だ。
そんな、任天堂のスマートデバイスに対する決意を聞いた伊集院氏は、「なるほど」と思ったという。
伊集院氏は、自身のお子さんがスマートデバイスに触っている様子を見て、タッチデバイスとコントローラーの隔たりを感じており、ふたつながらの機能を備えたNintendo Switchは、「両方の世代の架け橋になるのではないか」と大いに期待したというのだ。
「ゲームデバイスとスマートデバイスの違いはコントローラー」というのは故・岩田聡氏の言葉。
その違いを埋めるのが、Nintendo Switchであるというわけだ。
任天堂では、新規ハードの魅力を伝えるときに、それぞれ大切にする言葉を掲げるそうだが(平たく言うとキャッチコピーのようなものか)、Nintendo Switchの場合は“持ち運べる据え置き型ゲーム機”。
「Nintendo Switchは、場所とプレイシーンを問わず、ゲームを楽しめる機会を積極的に作り出せるマシン。
我々が目指すのは、テレビ出力もできる携帯ゲーム機ではなくて、あくまでも“持ち運びができる据え置きゲーム機”です」(光吉氏)。
さらに、ユーザーにとっては利便性の高い“持ち運べる据え置き型ゲーム機”は、開発者にとってもメリットが高く、「据え置き機向きか、携帯ゲーム機向きか、どちらのゲームデザインで作るかのハードウェア選びで頭を悩ませることがなくなり、両方のよさを活かしたゲーム制作に打ち込むことができる」と光吉氏は語る。
ちなみに、カプコンにプレゼンしたタイミングでは、Joy-Conの仕様は固まっておらず、同デバイスの詳細は開示されていなかったようだ。
開発機材として、タッチデバイスとクラシック コントローラPROだけ渡されたという伊集院氏は、“誘い誘われプレイ”という、Nintendo Switchのコンセプトがどこにかかるのかで、頭をひねったという。
その後Joy-Conの情報が開示され、「任天堂さんの思い描くビジョンとJoy-Conは相性がいいと思った」と伊集院氏は腑に落ちたようだ。
そのコンセプトが如実に反映されたのが、カプコンがNintendo Switch向けに開発中の『ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ』で、「格闘とは本当に相性がいいです」とは光吉氏の言葉。
おつぎに光吉氏は、Nintendo Switchのハード性能を紹介。
まず光吉氏は、2月に行われた任天堂の経営方針説明会における質疑応答での「Nintendo Switchの課題は何だったのか?」との質問に対して、技術フェローの竹田玄洋氏が“ハイパフォーマンス・ローパワー”と返答したというやりとりを紹介。
そのコメントを補足する形で光吉氏は、「PCのハイパフォーマンスのグラフィックスを実現する、NVIDIAのGe-Forceをバッテリー駆動の携帯ゲーム機でも使えるように工夫したゲーム機」と説明した。
「テレビモードや携帯機モード、条件が大きく異なる状況下でも、それぞれ最適なスペックを提供できるハードウェア」(伊集院氏)というわけだ。
以下、光吉氏はNintendo Switchの特徴的な性能を紹介。
無線LANは、IEEE 802.11acという最新の高速規格に対応。
とくに、Nintendo Switchではドックに置くことによりテレビに表示されるのだが、それを切り離した途端に通信が切れるということはあってはならないことから(有線LANではなく)無線LANにこだわったとのこと。
最新の高速規格に対応したのも、無線LANにしたのも、シームレスにゲームに遊んでもらうためとの配慮によるものだ。
また、携帯モードのパフォーマンスを上げるための工夫も明らかにされた。
Nintendo Switchのスマートフォンやタブレットの違いとして、光吉氏がまず挙げたのが、独自OSの採用。
「この独自OSはスマートフォンやタブレットのOSに比べると、シンプルなぶん動作が軽く、ハードウェア資源の大半をゲームアプリで活用することが可能になっています。
ゲーム専用機らしいゲームアプリに特化したOSです」と伊集院氏。
なお、OSのバージョンアップがあっても、それまでに発売されたゲームに影響が出ると話にならないので、そのへんもしっかりと対応すると光吉氏。
“互換性”は任天堂ハードの必須項目とも言えるが、「地道な努力で対応していく」(光吉氏)とのことだ。
余談として……任天堂のプラットフォームは、よく“品質管理にうるさい”と思われがちかもしれないが、それは“お客様ファースト”という考えがあるからだと光吉氏は言う。
「将来動かなくなることがあってはいけないので、ガイドラインにきちんと適合して作ってくださいということです。
きびしいという噂がありますが、まあ本当にきびしくなっていますが(笑)、ご協力いただきたいです」(光吉氏)とのことだ。
さらに、静音ファンも話題になった。
Nintendo Switchにはスマートフォンには採用事例のあまりない静音ファンを搭載しているのだが、伊集院氏によると、「とても小さいファンなのに、多段階制御でかなりの排熱余力があるのに驚きました」とのこと。
光吉氏も「ファンを回し過ぎると携帯時にうるさいので、けっこうファンの音は気にしながら、バランスを見ながらやっています」とのことだ。
■開発中のハードウェアにおけるタイトル制作真っ先に走りだしたのはゲームエンジン関係チームだった
では、Nintendo Switchというハードを受けて、カプコンの開発陣はどのように動き出したのか。
ここでは、『ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ』の事例をもとに、具体例が紹介された。
新規ハードの研究や開発環境の構築を担当する伊集院氏は、新しいハードが発表になった際は、いち早く情報を仕入れ社内開発者と共有し、「ときにハードメーカーに思い切った要求もする」(伊集院氏)立場にある。
いわば、「鉄砲玉ですね(笑)」という存在だ。
カプコンでは、Nintendo Switchの検証にあたっては、まずはMT FRAMEWORKを使用した。
カプコンのマルチプラットフォーム用ゲームエンジンとして知られるMT FRAMEWORKだが、Nintendo Switchの検証に使用したのは、「過去の実績があるので、Nintendo Switchの得手不得手が比較しやすい」との理由によるものだ。
慣れ親しんだMT FRAMEWORKを使うことで、新ハード開発時にともなう“慣れるまでの苦労”を軽減するという意味あいもあったという。
Nintendo SwitchにMT FRAMEWORKを載せるにあたり、カプコンでは基本的な方針として、“ハードウェア検証環境の早期構築”などを目標として設定した。
今回、短縮化に大きく貢献したのが“PCエミュレーション環境の構築”だったらしい。
任天堂から提供されるハードウェアの開発環境には、GPUエミュレータが提供されているため、同じシェーダーコードを使ってPC上で動作をさせることができる。
この機能がNintendo Switchではさらに強化されていたというのだ。
この仕組みはかなり好評で、Nintendo SwitchではGPUだけではなくて、提供される大半のAPIについてもPCでのエミュレーション環境を構築しているという。
PCエミュレーション環境は、安定動作するまで開発実機を使わなくても、イテレーション(短い間隔で反復しながら行われる開発サイクルのこと)が行えるなど、メリットは多いそうだ。
Nintendo Switchの開発環境の検証を経て、MT FRAMEWORKへの移植作業に取り掛かったというカプコンだが、担当スタッフは、なんとふたり!その時期はとても作業が立て込んでいて、人手不足の極みあったそうで、ある程度の実装期間を要することを覚悟していたらしい。
それが蓋を開けてみると、おおよそ1ヵ月で基本的な機能が移植できたという。
これだけの短期間で移植できた要因としては、MT FRAMEWORKへの移植慣れしたスタッフの存在やNintendo Switchそのものがポテンシャルを引き出しやすいハードウェア構成だった点などがあるようだ。
「遊び心のあるギミックに、王道のファミリー構成がたいへん任天堂らしいハードです」と伊集院氏もNintendo Switchを絶賛。
会場では、任天堂の各ハードにおけるゲームエンジン開発の制作人月が紹介されていたが、ニンテンドー3DSが4人×約4ヵ月(16人月)、Wii Uが5人×約3ヵ月(15人月)だったのに対して、Nintendo Switchが2人×約1ヵ月(2人月)というから、いかにNintendo Switchへの対応が短期間だったかがわかる。
「すごいですね。
驚きの数字ですね」と光吉氏も感嘆するほど。
「継続は力なりといいますか、社内開発の実績を積み上げてきた成果」(伊集院氏)とのことで、カプコンが任天堂ハード向けに取り組んできた蓄積もものをいったようだ。
■プラットフォーマーとサードパーティーの関係性仕様をめぐる意見交換が、パートナーシップを育む土壌に
ここで、Nintendo Switchの仕様が決定される際の、任天堂とカプコンとのやりとりが紹介された。
こういったエピソードを聞くと、Nintendo Switch開発にあたっては、いかに任天堂がサードパーティーと密接な意見交換をしていたがかよくわかる。
Nintendo Switchの仕様決定にあたって、カプコンがまっさきに要望を出したのが、メインメモリ搭載量。
最初に提示された資料では、その当時に発売されていた据え置きゲーム機と比較しても充分なメモリ量だったらしいが、カプコンでは「これでは足りない」と伝えたらしい。
というのも、そのころカプコンではRE ENGINEの開発が進んでおり、そこで要求される据え置きゲーム機用タイトルとしてのクオリティーやゲーム仕様を満たすには、どうしても提示されたメモリでは足りなかった。
「次世代ゲーム機への互換性などを視野に入れると足りない」と、伊集院氏は伝えたようだ。
カプコンがどんな据え置きゲーム機向けにどんな新規タイトルを開発しているのか、極めて気になるところだが、そこは本稿では置いておくとして、「伊集院さんの、メインメモリがまず足りないという第一声を、よく覚えています(笑)」(光吉氏)というから、光吉氏にとっても大懸案事項だったようだ。
メモリ増量は、カプコンだけではなくて、多くのサードメーカーの要望でもあったようで、「メモリをどれくらいほしいかと聞くと、だいたいプログラムの方は“無限にほしい”と言われるので」と会場を笑わせたあとで、光吉氏は「たくさん載せたいのは山々ですが、コストの兼ね合いもありまして」と実情を語る。
結果、“ほかの機能をカットしてまでメモリを増やすべきか”などを論点に、上層部を交えて激論を重ねて、現状のスペックに至ったという。
社内外からの多くの要望を受けた議論を経て、機能とコストのバランスを最適化した結果、最終製品のスペックが決定したようだ。
つぎにカプコンで話題に上がったのがタッチスクリーン。
カプコンではWii Uの代から「静電容量式にしてほしい」とリクエストを出していたそうだが、今回のNintendo Switchでようやく念願がかなったという。
このタッチスクリーンに関しては、伊集院氏から驚愕のエピソードが披露された。
任天堂から「タッチスクリーンは本当に必要か?」と質問されたというのだ。
タッチスクリーンといえば、Nintendo Switchにとっては欠かせないUIとも思えるが、光吉氏によると、「Nintendo Switchドッグに置いたときに、スクリーンは指で操作することはできないので、タッチができないことから、本当に必要かな?との意見もあり、お求めやすい価格に抑えるために、どうすればいいのかということで、極端な質問をさせていただいた」とのこと。
伊集院氏もこの姿勢に対して、「まさに聖域なしで機能と価格のバランスを取りながら、ハードウェアを仕上げていくというのは非常にきびしい道のりなのだ」と痛感したそうだ。
最後は、任天堂に要望を伝えた上で「運を天に任せる心境」だとした。
なお、伊集院氏によると、当初提案された段階から、「Nintendo Switchに関しては、機能の追加や向上はあっても、削減されたり、性能が低下した点はなかった」そうで、「開発者としても、いちユーザーとしても非常にうれしかった」とのことだ。
メインメモリ、タッチスクリーンときて、おつぎは動作クロックと使用電力量。
これについてはカプコンと任天堂は深い関係にあるようで、当初光吉氏は、動作クロックと使用電力量には相関関係があると思い込んでいたという。
クロックが高くなると、消費電力も多くなるというものだ。
それが、初期の開発段階では、検証に高負荷(市販ゲームレベル)のアプリケーションがなくて、測定しようにも正確な値が取れなくて、困っていたのだという。
そのときに“1ヵ月で対応したゲームメーカーがある”(カプコンのこと)と思いついた光吉氏は、「なんとかならない?」と伊集院氏に相談したところ、カプコン側で、測定に使用できるようにと、開発中のタイトルを提出してくれたのだという。
他社に開発中のタイトルを提供するとは、まさに破格と言えるが、任天堂とカプコンとの良好な関係を物語るエピソードと言える。
「カプコンさんには、初期段階からさまざまな実験にご協力いただいて、良好なパートナー関係を築けたと感じています」と光吉氏も感謝の言葉を口にする。
もちろん、任天堂ではカプコンのみならず、たくさんのサードメーカーと親密な関係を築いているそうだが、「今回カプコンさんとはお互いの持ち味を活かして、ゲーム機としての完成度を高められたと言えると思います」と光吉氏。
伊集院氏も、「新規ハードウェアを開発するときは、プラットフォーマーが決めた仕様の中で、サードメーカーがソフトを作るという“一方向”的な関係を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にはそんなことはありません。
私たちが提示された性能から何ができて、何ができないのか、我々が作りたいものをこの設計思想の中でどう表現すべきなのか、そういったことを意見交換しながら、いっしょに作り上げていく。
この協力体制と、試行錯誤の中で生まれる信頼関係があってこそ、タイトル開発だと考えています。
まさに、“二人三脚”で高めていったと自負しています」と語る。
■今後の取り組み それぞれが目指す、新たな地平とは?
講演では、Nintendo Switchに対する任天堂とカプコン両社の取り組みも紹介された。
カプコンの今後の検証課題は、“エンジンレベルでの省電力化”。
伊集院氏によると、一般的なSOC(System-on-a-chip/一個の半導体チップ上にシステムの動作に必要な機能の多くを実装する設計手法)では、CPUやGPUに依存することが多くなっており、Nintendo Switchにもその傾向があるという。
そこでカプコンは、「ゲームシーンの描画負荷にあわせて、GPUクロックを変動させたらどうか?」と任天堂に提案したのだという。
そこで、カプコンからの意見を受けて任天堂が調査したところ、“GPUクロックの変動が必ずしもプラスにはならない”という結果に達したという。
Nintendo Switchの電力コントロールはかなりすぐれたレベルにあるため、単にクロックを遅くするとGPUの単位時間あたりの消費電力量は減るものの、処理時間が長くなることで、トータルで逆に加算されてしまうこともあるらしいのだ。
その報告を受けてカプコンでは提案を取り下げたものの、電力消費量削減の取り組みを諦めたわけではないという。
よりローパワーでできる方法がないか検証中だという。
さらにカプコンでは、Nintendo Switchに充分なメモリが確保されたことで、RE ENGINEの対応も検討しているらしい。
ご存じの通りRE ENGINEとは、『バイオハザード7レジデント イービル』で採用された、カプコンの第8世代機向けの最新自社ゲームエンジン。
これまで使用してきたMT FRAMEWORKに比べてグラフィッククオリティーやパフォーマンスの向上はもちろん、トリプルAクラスのタイトルが効率的に開発できるように、さまざまな工夫が凝らされているという。
Nintendo Switchへの対応については、据え置き/携帯とパフォーマンスが大きくことなるふたつのモードがあることから、これらへの対応が不可欠になるという。
「(初めてのことで未知数なので)対応は簡単ではないが、なんとか実用化にこぎつけてユーザーの皆さんに第8世代ならではのハイクオリティーなタイトルをご提供できるようがんばりたい」(伊集院氏)とのことだ。
任天堂の今後の取り組みとしては、開発環境サポートの充実化が挙げられた。
任天堂では、Nintendo Switchの開発環境に対して多くの開発者に参入をうながしたいと考えていて、50000円を切る価格での提供を考えているという。
いまはまだ準備を進めている段階だが、インディーゲームクリエイターにも手の届く価格でお届けしたいということで、「弊社の開発者ががんばって準備しました」(光吉氏)という。
任天堂が、昨年7月に個人のゲーム開発者へも門戸を開いたことはご存じの通りだが、Nintendo Switchはインディーゲームクリエイターにとっても、極めて魅力的なプラットフォームとなりそうだ。
・任天堂がBitSummitに初参加!その理由を担当者に直撃個人クリエイターにも門戸を開く
いよいよ3月3日に発売されるNintendo Switch。
本セッションは、同ハードに対する並々ならぬ意欲がうかがえる内容となった。
・インテリジェントシステムズの川出亮太氏が語る『ファイアーエムブレム 0(サイファ)』や『スーパーペーパーマリオ』に見る、ゲームを作る “目的”の大切さ
・『バイオハザード7』がCoopを不採用にし、新たな主人公、カメラシステムを一新した理由が語られる
・『GRAVITY DAZE 2』手書きのようなグラフィックの制作工程、短期間でクオリティーを落とさず背景を制作するカギとなった“自動化”についてリポート