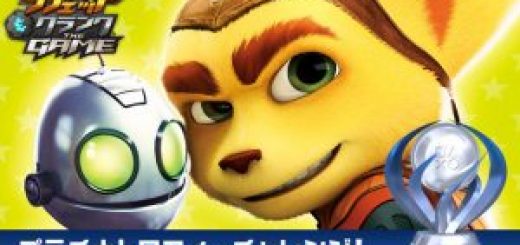京都の企業はなぜ高収益なのか。カギは祇園のお茶屋と立地にあり
では、任天堂はどうであろうか。
任天堂はこれまで様々なゲーム機を発表しているが、実際のモノ作りは外部に任せている。
任天堂がシャープに出資をしたホンハイを昔から製造外注先として使っていたことは有名だ。
ちなみにアップルのiPhoneもホンハイに発注されている。
その役割分担をアップルは明確にしている。
アップル製品の裏側には以下のような表記がある ー”Designed by Apple in California Assembled in China(デザインはカリフォルニアのアップル、組み立ては中国)”
こうすることで任天堂は自ら生産設備を持つ必要がなく、固定費や生産ラインのための投資や減価償却が必要なくなる。
また、任天堂はゲーム機のコンテンツを自分たちでも作りこみ、マリオやゼルダシリーズなどのゲームソフトを発表している。
その一方で、他社ソフトウェアメーカーにも開発機やハードウェアとしてのプラットフォームを公開し、ソフトウェアの提供をしてもらっている。
その取り組みの中で、スクウェア・エニックスやカプコンなどのゲームソフトウェア会社が大きくなってきた。
プラットフォームを取り巻く周辺企業を積極的にサポートする中でエコシステムが強化されていったのである。
任天堂は自分たちだけに有利なプラットフォーム運営をしているという批判もあるが、本当に自分たちだけが有利なビジネスを展開しているのであれば、任天堂のゲーム機がここまで普及し、任天堂そのものも大きくなったであろうか。
もちろん、任天堂が開発するハードウェアの入力インターフェース(コントローラーなど)が扱いにくいという指摘がソフトウェアメーカーからされるところもあるが、そこは任天堂のプラットフォームであることと任天堂のソフトウェアの良さを最大限引き出すための手段であることを考えれば致し方ないことであろう。
任天堂からしてみれば、自分たちのプラットフォームに外部から参加したソフトウェアメーカーがヒット作を飛ばすことで自社のハードウェアが普及し、さらにソフトウェアが売れるというのがメリットのある姿である。
いずれにせよ、自社、顧客、参加企業の「三方よし」でなければ、プラットフォーム運営は成功しない。
このように自分たちの限られたリソースの中で最も得意な領域に集中し、またエコシステムをより強固なものにして収益を最大化させる工夫をしてきたのが任天堂である。