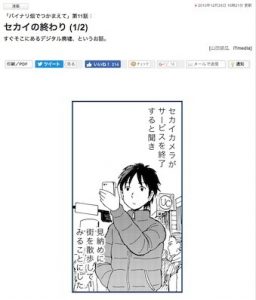「セカイの終わり」とPokemon GO コノ、オオゾラニ、エアタグヲ
週刊少年チャンピオンで「AIの遺電子」を連載中の山田胡瓜先生がITmedia PC USERで描いている「バイナリ畑でつかまえて」に「セカイの終わり」という1篇がある。
セカイカメラが終了するというので街に繰り出し、エアタグが残っている場所を探す青年。
彼は代々木公園で、ある少女を見かける。
その代々木公園はいま、Pokemon GOでポケモンを集めようという、ポケモントレーナーたちが集う「聖地」となっている。
彼らは、エアタグ舞うセカイカメラの空間を知らない。
すぐそばの代々木競技場で、セカイカメラが初めて披露されたことも。
●セカイのはじまり
セカイカメラの発表は2008年9月。
いまから8年前のことだ。
当時の興奮しきった自分のブログがなつかしい。
iPhone 3Gが日本で発売された翌月。
初代iPhoneは2007年で、日本で発売されることはなかった。
セカイカメラが動くようになったのは4カ月後の2009年だが、これがきっかけとなってARブームが起き、広告分野などで一定の成果を得つつも、セカイカメラ自体はその5年後に終了する。
エアタグというのは、テキストや写真をセカイカメラにアップロードすると、それが風船のようにプカプカ浮かんで、そこを訪れた人が見ることができるというもの。
セカイカメラのサービスが始まったときには秋葉原をはじめあちこちで「姉ヶ崎寧々」エアタグの大量発生が見られたりしたものだ。
ちなみに、ラブプラスのiOSバージョンにもAR機能があったのを覚えている人はいるだろうか。
2010年には頓智ドットにKDDIの資本が入り、KDDIで研究されていたAR技術「実空間透視ケータイ」との連携が行われた。
そのあたりの経緯は、この当時AR関係を丹念に追っていた山田祐介記者の記事が詳しい。
この直前には、セカイカメラをゲームプラットフォームとして展開しており、AR版ボンバーマンと言えるソーシャルゲーム「ばくはつカブーン」やRPG「セカイユウシャ」をリリースした。
このときの頓智ドットは、「Social」「Location」「AR」を統合した「SoLAR」、つまりソーシャルARゲームをプッシュしていた。
セカイカメラにARソシャゲ機能が追加されたのは2010年7月2日。
Pokemon GOの6年と4日前だ。
「現実空間に魔物??セカイカメラが向う“ARゲーム”の世界」という記事タイトルをこう置き換えてみてはどうだろう。
「現実空間にポケモン??Nianticと任天堂が向う“ARゲーム”の世界」
●セカイの終わり
だが、このゲーム戦略は成功を収めることができなかった。
CEOが創業者・井口尊仁氏から楽天出身の谷口昌仁氏にスイッチしたのが2011年12月。
その後、tabというキュレーションサービスを開始した。
2014年には社名を頓智ドットからtabに変更。
このサービスは継続中だが、2014年1月にセカイカメラを終了。
後にtabは2015年設立のオープン・ランウェイズというところに吸収されている。
CEOは頓智ドットの谷口氏のまま。
現在はtabよりも、tabモールという「店頭にない商品を、ウェブサイトを通じて百貨店などの店舗にお取り寄せし、実物を確認、試着してから購入できるサービス」がメインのようだ。
もはや「セカイカメラ?なんですかそれ」といった感じだ。
一方、当時セカイカメラとARアプリ分野で競っていた製品はいまどうなっているのか。
セカイカメラに少し遅れてARタグを実装していたライバルのLayarも、既にない。
イギリスで同種の製品・サービスを提供しているBlipparに吸収され、日本でLayarを扱っていたシステム・ケイもLayar終了の案内を出している。
Layarを吸収したBlipparはどちらかというと、Google Goggleのような、カメラで撮影した物体を認識して、そこを起点とした情報を提供するアプリ・サービスだ。
Layarがマーカー必須だったのに対し、Blipparはマーカーレスで企業ロゴなどを認識してコンテンツ提供をしているのが特徴。
しかし、ユーザーが自分の好きなものを投稿できるARプラットフォームは、見当たらなくなってしまった。
2009年あたりには、セカイカメラやLayarだけでなく、memory treeというアプリもあった。
memory treeにAR機能はなかったけど、時間と場所にひもづいた写真を投稿でき、その場所でiPhoneを振り下ろすと、そこで投稿された写真をかき集めて表示できるというもの。
アート的な試みが評判だったが、生き残ることはできなかった。
●セカイが終わった理由
セカイカメラを終了させた谷口CEOは、「ARを見るために手をかざすのは恥ずかしい」「情報が整理されず混沌としてた」「毎日使う必然性」という3つの「失敗」を挙げている。
セカイカメラはもともと自由にテキストでも写真でも投稿できる、別の新たなレイヤーを創りだそうぜ、という「Tagging The World」がテーマで、だからこそ「姉ヶ崎寧々」タグが大量発生したりしていたのだが、「手をかざすのが恥ずかしい」も「混沌」も、セカイカメラがやってきたことの全否定である。
実空間の位置にひもづけた情報をマッピングすることで起きる問題は、2009年7月に発足したAR Commonsという団体が、慶応大学の岩渕潤子教授(当時)を代表にディスカッションしていた。
当時はGoogleストリートビューのプライバシー問題が取り沙汰されており、同様の問題がARで起きるのではということで議論されていたのだが、Pokemon GOで現在顕在化している問題の多くはここで予想されていのではないだろうか。
その成果はどこかで反映されているのだろうか。
AR Commons自体は活動を終えているようだが、いつの日か復活するというのはありうるのか。
ちなみに、長崎の平和公園にポケモンジムやポケスポットが設置されて長崎市が困惑しているという話だが、いい機会なので、平和公園にかぎらず、長崎の被爆証言や被害の状況をARで表示するプロジェクト、Nagasaki Archiveについても言及しておこう。
普段は目にしない情報を現実空間にマッピングしてレイヤー化するメリットは当然ながら、あるのだ。
ちなみに長崎はネコが多い。
平和公園にも人懐っこいネコがいて、訪問客をなごませてくれるので、リアルニャースと戯れるのもいいのではないだろうか。
いつか実家に帰ったら、そのすぐそばにあるこの公園でPokemon GOをかざしてみようと思う。
谷口CEOが指摘したセカイカメラ失敗の要因その3である、「毎日使う必然性がない」こと。
それが利用者に知られてしまったのは、たしかに痛いことだ。
だから、徐々に使われなくなっていったのだと自分は考える。
いまならばiOSにもAndroidにも備わっている通知機能で、どこでおもしろいエアタグに出会えるのか、アプリを起動していなくても知らせてくれるのだろうが、当時はアプリ自体をバックグラウンドで常に動かしておく必要があったのだ。
●セカイからポケモンへ
そして、セカイカメラは消え、同種のARアプリも壊滅してしまったのに、なぜPokemon GOは大ヒットしたのか、という疑問。
理由はいくつもある。
1999年に発売されたポケモンスナップはある意味、Pokemon GOのプロトタイプとも言えるものだった。
それはバーチャル世界でポケモンの写真を撮るというものだったが、それを実世界で撮影できるようにしたのがPokemon GOのAR機能。
これは「Pokemon GOにはAR機能はいらなかったんじゃないの?」という問いへの答えになるのではないだろうか。
位置ゲーとしての性質はそもそも初代ポケモンからあったわけで、マサラタウンに始まり、特定の場所にしかいないポケモンをゲットして、ジムで他のトレーナーと渡り合って、というPokemon GOの要素はここですべて入っている。
ある意味、元から位置ゲーだったのだ。
そして1998年発売のポケットピカチュウ。
歩数計をゲームの報酬に使えるというよくできたウェアラブルデバイス。
歩いた距離に応じて卵を孵化させられる、Pokemon GOの機能を思わせるではないか。
このように、ポケモン側には位置ゲーム、ARゲーム、健康促進としての要素は十分にあって、その成果は実証済み。
毎日投稿するためのインセンティブとしては、ポケモン図鑑を完成させるという目的は万人に受け入れられるものだし、いずれポケモンの交換機能が実装されれば、ますます離れられなくなる。
POI(Point of Interest)の新設と管理については、Ingressエージェントが次々に申請し、敷設していったものがスクリーニングされて現在のポケモンジム、ポケストップになっている。
位置情報はGoogle Mapベースなのだが、それはそもそもNianticのジョン・ハンケCEO自身が率いて構築していたものだ。
地理情報をレイヤー化するというのも、ハンケCEOが作り上げたGoogle Earthの大きな特徴だった。
位置ゲーとして、これ以上のバックグラウンドとインフラは見込めないだろう。
そして世代の問題。
初代ポケモン世代はいま、30代に近づいている。
筆者の息子たちもこのジェネレーション・ポケモンに属している。
つまり、初代ポケモン親世代である。
その初代ポケモン世代が世の中を牽引するようになってきて、その下の世代もポケモンは広く浸透している。
このIP資産と、長く敷設してきた位置ゲー、AR/VRの「タネ」は、これまで挙げた成功の要素として何よりも大きいだろう。
ポケモンがセカイカメラのゲームプラットフォームで動く世界線はありえたのか?
当時ではいろんな意味で無理だったろう、というのが正直なところだ。
その判断をするには、スマートフォン、ソシャゲというビッグウェーブに任天堂が飲み込まれる必然があったはずだ。
セカイカメラのゲーム戦略から6年。
その間にネットワークは3GからLTEへ。
iPhoneのキャリアはソフトバンク1社から、MVNOを含めほぼ全社へ。
OSは通知機能を実装して、若者のiPhoneシェアは過半数。
ガラケーは駆逐された。
ソシャゲでの課金システムに多くの人は躊躇しなくなっている。
このタイミングでGoogleから独立し動きやすくなったNianticと組めたというのは、最高の組み合わせといっていい。
そういえば、セカイカメラを実装するために必要だったカメラAPIへのアクセスも当初、Appleは禁じていたのだった。
セカイカメラが頼りにしていたクウジットの高精度な室内測位システムPlaceEngineも、Appleからリジェクトに遭っていた。
当時は大変だったのだなと、こんな文章を書きながら思い出している。
そんなこんなでぼくらはいま、ポケモンといっしょに暮らすことができているのだ。
●それでもまた、エアタグを浮かべたい
Pokemon GOはすばらしい。
それはそれとして、エアタグもまたすばらしい。
自分で好きなものを好きな場所に投稿できるからだ。
いまは、そういうのは流行らない。
お金にはならない。
サーバ運営コスト、POIの管理、プライバシー、フィルタリングの問題などなど。
いま、Pokemon GOで使えるAR的ガジェットとしてVufineというウェアラブルディスプレイを使っているのだが、これを連動したら、今風のセカイカメラが作れるんじゃないかな、とも思う。
妻との想い出をすべてプライベートクラウドに挙げておいて、その場所、その時間になれば自分専用のアプリに写真や動画、声が届いて、目の前にオーバーレイされる。
そんなARアプリもいつか使えるようにあるといいなあ。
そんなことを考えている。
ポケGO人気に便乗してどこかがやってくれないかなあ。
実は、Nianticの知られざるアプリ「Field Trip」がそれに一番近いのだけど……。
いまはドローンと同じで、自由にエアタグを飛ばせない。
そんなわけで、セカイカメラの終わりを描いた名作を含む、山田胡瓜先生の短編集「バイナリ畑でつかまえて」が、電子本だけじゃなくて紙でもつかまえられるようになる、しかも加筆・修正もあるそうなので、8月2日以降、ぜひお読みいただいて、心をチクチクさせてほしい。
コノ、オオゾラニ、エアタグヲ。