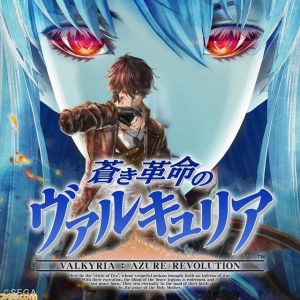土曜日だけど日曜気分! 『おどるポンポコリン』を27000人で歌った“アニメロサマーライブ2016 刻-TOKI-”2日目リポート
●新旧さまざま曲が“刻”を越えて披露された
2016年8月26日〜28日の3日間、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで開催される夏の一大イベント『アニメロサマーライブ2016 刻-TOKI-』。
その2日目の模様をリポートする。
開幕は、B.B.クィーンズ with B応Pによる『We are B.B.クィーンズ』、『おどるポンポコリン』の2曲でスタート。
国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』のオープニング曲ということもあり、会場の一体感もバッチリで、楽しさ全開の幕開けとなった。
さらに、A応Pならぬ“B応P”という、A応Pのメンバーによく似た謎のユニットも参加し、“アニサマ2016”の開幕を盛り上げた。
ライブの前半戦に“アニサマ”初出演のアーティストが多く登場した2日目。
開幕のB.B.クィーンズから、A応P、Poppin’Party from BanG Dream!、TRUE、北宇治カルテットと初出演アーティストが連続。
その後も、早見沙織さん、MICHIさん、プラズマジカ(SHOW BY ROCK!!)、イヤホンズ、高垣彩陽さん、OxTと初出演アーティストが登場し、そのパフォーマンスでさいたまスーパーアリーナを魅了した。
また、異色とも言えるユニットにも注目。
Poppin’Party from BanG Dream!は、作品出演キャストが実際に楽器を演奏するバンド形式のユニットとして会場を沸かせる。
また、イヤホンズの『あなたのお耳にプラグイン!』は、テレビアニメ『それが声優!』のエンディングテーマで、エンディングにトークコーナーやリクエストコーナーがあるというもの。
今回も構成はそのままに、“アニサマ”のステージからリポートを行ったかと思えば、リクエストコーナーでは『美少女戦士セーラームーンR』のエンディングテーマ『乙女のポリシー』を披露することに。
しかも、まさかの本人登場というサプライズで、石田燿子さんと永井ルイさん(作曲)とともに同曲を歌い上げた。
“アニサマ”恒例のコラボは、Liaさんとfhanaが今回のアニサマのテーマである“刻”に合わせて『時を刻む唄』を、高垣彩陽さんと早見沙織さん、そしてfhanaの佐藤純一さんとで『Komm, susser Tod〜甘き死よ、来たれ』を披露。
会場全体を歌声で魅了する。
2日目は“聴かせる”コラボとなった。
2日目のトリを務めるのは、LiSA。
LiSAがステージに登場したかと思いきや、さらにmarinaがステージに登場し、テレビアニメ『Angel Beats!』のユニット、Girls Dead Monsterが一夜限りの復活!ふたりで『Crow Song』を歌い上げる。
今回の“アニサマ”が“刻”というテーマだったからこそ、6年前にLiSAが初めて“アニサマ”に出演したときと同じ、Girls Dead Monsterとして歌うことができたというLiSA。
6年前は自分のことを知っている人はほとんどいなかったが、6年経つと自分に声をかけてくれる先輩や後輩が増えて、アウェイだと思っていた“アニサマ”が、いつの間にかホームになっていたと胸の内を語った。
最後は、『シルシ』をアカペラから歌い上げる。
声の限りに、同曲を響かせたLiSA。
多くのメッセージを、アニソンファンに歌で伝えた。
最後は“アニサマ2016”出演者全員でテーマソング『PASSION RIDERS』を歌唱。
5時間にわたるライブを締めくくった。
明日2016年8月28日(日)は、いよいよ“アニサマ2016”最終日。
どんな“刻”が過ごせるのか、期待がより大きくなる2日目となった。
■“アニメロサマーライブ2016 刻-TOKI-”2日目セットリスト
01. We are B.B.クィーンズ 〜 おどるポンポコリン/B.B.クィーンズ with B応P/テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』主題歌
02. はなまるぴっぴはよいこだけ/A応P/テレビアニメ『おそ松さん』OPテーマ
03. 全力バタンキュー/A応P/テレビアニメ『おそ松さん』OPテーマ
04. Yes! BanG_Dream!/Poppin’Party from BanG Dream!
05. STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜/Poppin’Party from BanG Dream!
06. DREAM SOLISTER/TRUE/テレビアニメ『響け!ユーフォニアム』OP主題歌
07. トゥッティ!/北宇治カルテット/テレビアニメ『響け!ユーフォニアム』ED主題歌
08. Bravely You/Lia/テレビアニメ『Charlotte』OPテーマ
09. 鳥の詩/Lia/テレビアニメ『AIR』OPテーマ
10. やさしい希望/早見沙織/テレビアニメ『赤髪の白雪姫』OPテーマ
11. ブルーアワーに祈りを/早見沙織
12. Checkmate!?/MICHI/テレビアニメ『だがしかし』OPテーマ
13. Hey!カロリーQueen/竹達彩奈/テレビアニメ『だがしかし』EDテーマ
14. ライスとぅミートゆー/竹達彩奈
15. 流星ドリームライン/プラズマジカ(SHOW BY ROCK!!)/テレビアニメ『SHOW BY ROCK!!』挿入歌
16. 青春はNon-Stop!/プラズマジカ(SHOW BY ROCK!!)/テレビアニメ『SHOW BY ROCK!!』OP主題歌
17. それが声優!/イヤホンズ/テレビアニメ『それが声優!』OPテーマ
18. あなたのお耳にプラグイン! 〜 乙女のポリシー/イヤホンズ with 石田燿子 feat. 永井ルイ/テレビアニメ『それが声優!』ED、テレビアニメ『美少女戦士セーラームーンR』EDテーマ
19. Steppin’ out/FLOW/テレビアニメ『デュラララ!!×2結』OPテーマ
20. BURN/FLOW/テレビアニメ『テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス』OP主題歌
21. 風ノ唄/FLOW/PS4、PS3用ソフト『テイルズ オブ ベルセリア』OPテーマ
22. GO!!/FLOW/テレビアニメ『NARUTO-ナルト-』OPテーマ
23. 虹を編めたら/fhana/テレビアニメ『ハルチカ〜ハルタとチカは青春する〜』OP主題歌
24. calling/fhana/テレビアニメ『テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス』EDテーマ
25. 時を刻む唄/Lia×fhana/テレビアニメ『CLAMMAD 〜AFTER STORY〜』OPテーマ
26. おしえてブルースカイ/大橋彩香/テレビアニメ『コメット・ルシファー』ED主題歌
27. 裸足のままでもこわくない/大橋彩香/テレビアニメ『コメット・ルシファー』ED主題歌
28. Rebirth-day/高垣彩陽/テレビアニメ『戦姫絶唱シンフォギアGX』EDテーマ
29. Komm, susser Tod〜甘き死よ、来たれ/高垣彩陽×早見沙織 feat.佐藤純一(fhana)/『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、キミに』挿入歌
30. Naked Dive/SCREEN mode/テレビアニメ『無彩限のファントム・ワールド』OPテーマ
31. ROUGH DIAMONDS/SCREEN mode/テレビアニメ『食戟のソーマ 弐ノ皿』OPテーマ
32. Divine Spell/TRUE/テレビアニメ『レガリア The Three Sacred Stars』OPテーマ
33. Clattanoia/OxT/テレビアニメ『オーバーロード』OPテーマ
34. STRIDER’S HIGH/OxT/テレビアニメ『プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ』OPテーマ
35. 創傷イノセンス 〜 Resonant Heart/内田真礼/テレビアニメ『悪魔のリドル』OPテーマ、テレビアニメ『聖戦ケルベロス 竜刻のファタリテ』OPテーマ
36. ギミー!レボリューション/内田真礼/テレビアニメ『俺、ツインテールになります。
』OPテーマ
37. Beat your Heart/鈴木このみ/テレビアニメ『ブブキ・ブランキ』OPテーマ
38. Love is MY RAIL/鈴木このみ/テレビアニメ『アンジュ・ヴィエルジュ』OPテーマ
39. Redo/鈴木このみ/テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』OPテーマ
40. Crow Song/Girls Dead Monster/テレビアニメ『Angel Beats!』挿入歌
41. Brave Freak Out/LiSA/テレビアニメ『クオリディア・コード』OPテーマ
42. oath sign/LiSA/テレビアニメ『Fate/Zero』OPテーマ
43. シルシ/LiSA/テレビアニメ『ソードアート・オンラインII』EDテーマ
44. PASSION RIDERS/アニサマ2016出演アーティスト/『アニメロサマーライブ2016 刻-TOKI-』テーマソング
●第2弾、第3弾も開催予定!
バンダイナムコエンターテインメントは、『ガンダム』ゲーム生誕30周年を記念して、ディスカウントセール“歴代ゲーム祭り!”第1弾をPlayStation Storeにて開始した。
下記の『ガンダム』タイトルが最大30%オフのディスカウント価格で配信中。
第1弾の実施期間は8月26日〜9月11日で、今後第3弾までのセールが予定されている。
※ガンダムゲーム年表
■対象タイトル
・PSP/Vita『機動戦士ガンダムAGE ユニバースアクセル』
価格:6151円 → 4305円(30%OFF)
・PSP/Vita『SDガンダム ジェネレーション ワールド PSP the Best』
価格:2880円 → 2016円(30%OFF)
・PSP/Vita『機動戦士ガンダムSEED 連合VS.Z.A.F.T.PORTABLE PSP the Best』
価格:2880円 → 2016円(30%OFF)
・PSP/Vita『機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V PSP the Best』
価格:2880円 → 2016円(30%OFF)
・PS3『真・ガンダム無双』
価格:8208円 → 5746円(29%OFF)
・Vita『真・ガンダム無双』
価格:7180円 → 5026円(30%OFF)
・PS3『ガンダムブレイカー』
価格:8208円 → 5746円(29%OFF)
・Vita『ガンダムブレイカー PS Vita the Best』
価格:3024円 → 2117円(29%OFF)
●たくっち氏の紹介動画、ついに完結!
スパイク・チュンソフトは、発売中のニンテンドー3DS版『テラリア』について、“女性ゆっくり実況者”ことYouTuber・たくっち氏による紹介動画第5弾を公開した。
動画は今回が最終回。
『テラリア』の世界観をベースにしたオリジナルストーリーを楽しもう。
KADOKAWAが、ニンテンドー3DS用ソフト「RPGツクール フェス」を開発していることを発表しました。
11月24日に発売予定で、希望小売価格はパッケージ版が5800円、ダウンロード版が5300円(ともに税別)。
「RPGツクール」は画像や音楽などの素材を収録し、プログラミングができなくても使えるゲーム制作ソフトシリーズ。
今作は3DSで快適にゲームが作れるように画面構成を工夫しており、マップに表示されるグラフィックを、プリセットパーツを利用してデザインする機能を搭載しています。
制作したゲームは3DSでプレイでき、サーバーにアップロードして自由に配布することが可能。
遊ぶのに必要な「ツクールプレイヤー」は、ニンテンドーeショップで無料配信されます。
米国の金融政策に関係するイベントを控えて様子見気分が強い中、持ち高調整の売りに押された。
日経平均株価は前日比195円24銭安の1万6360円71銭、東証株価指数(TOPIX)は16.37ポイント安の1287.90と、ともに続落。
東証1部上場銘柄の77%が値下がりし、18%は値上がりした。
出来高は15億4608万株、売買代金は2兆0391億円。
業種別株価指数(33業種)は、保険業、輸送用機器、空運業などの下落が目立った一方、鉄鋼、化学が上昇した。
個別では、トヨタ、ファナックが下押し、日産自、ソニーは軟調。
JAL、任天堂が値を下げ、ユニーGHD、ファミリーマートはさえない。
三井住友、菱地所が売られ、東京海上は安い。
ソフトバンクGが緩み、ファーストリテは弱含み。
半面、スズキ、東エレク、日本電産が買われ、JFE、新日鉄住はしっかり。
花王、信越化が値を上げ、サッポロHDは堅調。
カプコンは大幅高。
反落。
ゼニス羽田が甘く、ジースリーHDは大幅安。
半面、アライドHDが急伸し、アサヒインテックは買われた。
出来高は1億3105万株。
軟調。
出来高は31万8200株。
(続)
コーエーテクモゲームス(ガスト)は、プレイステーション 4、PlayStation Vita用美少女従魔RPG「よるのないくに2 〜新月の花嫁〜」を12月22日に発売する。
価格はPS4通常版が7,300円(税別)、プレミアムボックスが10,300円(税別)、スペシャルコレクションボックスが16,300円(税別)、ダウンロード版が7,300円(税別)。
PS Vita通常版が6,300円(税別)、プレミアムボックスが9,300円(税別)、スペシャルコレクションボックスが15,300円(税別)、ダウンロード版が6,300円(税別)。
ダウンロード版は発売後2週間10%OFFとなる。
「よるのないくに2 〜新月の花嫁〜」は、主人公とともにバトルやストーリーで活躍する美少女ヒロイン「リリィ」が新たな要素として登場する。
前作「よるのないくに」のダークな世界観はそのままに、主人公のパートナー「リリィ」たちがゲーム内の随所に登場し、主人公と惹かれあい絡みあうことで、本作品のコンセプトである「美少女」の要素が大幅に強化されている。
プロデューサーは、「よるのないくに」の菊地啓介氏、シナリオは「零・影牢シリーズ」の柴田誠氏、シナリオ監修は、Production I.Gの藤咲淳一氏が担当する。
また、キャラクターデザインも、「よるのないくに」から引き続き四々丸氏が起用されている。
■キャラクター紹介□蒼き血に魅入られた少女「アルーシェ・アナトリア」
本作の主人公で教皇庁の騎士。
巫女リリアーナを護衛中に、妖魔に襲われて死亡してしまう。
その後人工の半妖となって蘇り、半妖となったことで妖魔を倒す力を得たアルーシェ・アナトリアは、リリアーナを救うために戦う。
真っ直ぐな性格で、考えるよりも行動で物事を示すタイプ。
リリアーナと、聖騎士ルーエンハイドとはいつも一緒に過ごしてきた幼馴染であり、2人との再会に喜びを感じている。
□優しさと強さを兼ね備えた巫女「リリアーナ・セルフィン」
思慮深く、心優しき少女。
教皇庁に仕える巫女の1人だったが、“月の女王”に捧げる「刻(とき)の花嫁」に選ばれる。
優しい性格で誰にでも分け隔てなく接すると同時に、芯の強さを持ちあわせている。
対象の時間を遅らせる能力を持っており、過去にその力で邪妖に襲われていたアルーシェを助けたことがある。
□自らの意思を剣で示す騎士「ルーエンハイド・アリアロド」
アルーシェとリリアーナの幼馴染。
感情の力を刃に変える「気剣オーズ」の使い手。
幼馴染であるアルーシェをよく理解し、好感を持っているが、教皇庁の対抗組織「ルルド教団」の聖騎士として、リリアーナを生け贄に捧げることを防ぐため、アルーシェの前に立ちはだかる。
熱い性格で自分の正義を振りかざすなどやや高慢に見えることもあるが、根は素直。
■幼馴染の絆
半妖としての2度目の生に戸惑うアルーシェ、生け贄としての役目を受け入れるリリアーナ、運命に抗うルーエンハイド。
かつて幼馴染として同じ道を歩んでいた3人の歩みは、夜の闇に惑わされ、離れ離れになっていた。
3人が再び足並みを揃えるとき、彼女たちの絆が闇を照らす光となり、やがて物語は真実に近づいていく。
■ともに戦う美少女ヒロイン「リリィ」
「リリィ」は、アルーシェと協力し、ともに戦ってくれる頼もしい美少女ヒロインたちのこと。
アルーシェは状況に応じて「リリィ」を選んで邪妖たちとの戦いに挑み、絆を深めていく。
絆が深まることで「リリィ」たちは新たな能力に目覚め、絆を確かめ合うイベントが発生する。
選択する「リリィ」ごとに戦い方が変わる。
今後も多くの「リリィ」が登場する予定となっている。
■初回限定特典とプレミアムボックスを紹介
初回封入特典は、「ゲーム内で使えるダウンロードシリアル」。
プレミアムボックスには、「主人公特別衣装ダウンロードシリアル」や「よるのないくに2 オフィシャルサウンドトラック」などが同梱される。
スペシャルコレクションボックスは、プレミアムボックスにさらに特典を加えたものとなっている。
・ゲーム内で使えるダウンロードシリアル
・アルーシェ専用衣装 ダウンロ―ドシリアル
・「よるのないくに2」ビジュアルブック
・「よるのないくに2」オフィシャルサウンドトラック
・匂いつきB3ポスター
・特製アルーシェ3Dカード
・美少女ブロマイドセット
・秘密の温感.お風呂ポスター
・美少女アクリルキーホルダー 3個セット
・特製A3タペストリー 3本セット
・アルーシェ専用衣装 ダウンロ―ドシリアル
・「よるのないくに2」ビジュアルブック
・「よるのないくに2」オフィシャルサウンドトラック
・匂いつきB3ポスター
・特製アルーシェ3Dカード
・美少女ブロマイドセット
■「ガスト美少女祭り」を開催中
ガストから今後発売予定のタイトルと連動して展開されるお祭り企画。
発表されるタイトルとともに企画内容が発表される予定となっている。
詳しくはガスト美少女祭りポータルサイトをみてほしい。
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
蒼き雷霆ガンヴォルト 爪(3DS)CEROレーティングB(12歳以上対象)インティ・クリエイツ1960円8月25日発売
セガゲームス コンシューマ・オンライン カンパニーは、PS4/PS Vita『蒼き革命のヴァルキュリア』の発売日が2017年1月19日に決定したことを発表しています。
『蒼き革命のヴァルキュリア』は、『ヴァルキュリア』シリーズ最新作となるRPGです。
本作では、復讐を果たすため国をも巻き込む戦争を仕掛けた主人公「アムレート」たち、そして目的遂行の最大の敵として現れる「ヴァルキュリア」の物語が描かれます。
今回は特報映像とともに発売日が発表。
初回特典・店舗別予約特典やキャンペーン情報も公開されています。
◆特典情報
■初回特典
本作の初回版には、本編の前日譚を描くフルボイス追加ストーリーDLC「断章:ヴァナルガンド結成」プロダクトコードが封入。
主人公「アムレート」が所属するアンチ・ヴァルキュリア部隊“ヴァナルガンド”がいかに結成されたのかといったストーリーが展開されます。
■販売店別予約特典
対象の店舗で本作を予約すると、キャラクタービジュアルを使用したアイテムなど店舗オリジナルの予約特典が先着でプレゼントされます。
デザインは決まり次第、公式サイトの該当ページで発表されます。
●アニメイト全店
・オリジナルピンバッジ3個セット
●Amazon
<Amazon.co.jp 限定予約特典>
・装備品「ラグナイト(Amazon.co.jp 特殊仕様)」プロダクトコード
<Amazon.co.jp 予約特典>
・装備品交換アイテム「ラグナイトのかけら30個」プロダクトコード
●あみあみ
・オリジナルアクリルマルチスタンド
●いまじん / いまじんWEB ショップ
・オリジナル大型布ポスター
※布ポスターパック販売分/販売方法はお取り扱い店舗までご確認ください。
●ゲーマーズ全店
・オリジナルB2タペストリー
●ゲオ
・アイテム未定
●セガストア
・蒼き革命のヴァルキュリア DXパック
※「DXパック」はゲームソフトのほか、「A3タペストリーアムレート&ブリュンヒルデ」「ヴァナルガンド部隊章マグカップ」「アクリルキーホルダー5 種セット」がセットになった限定版です。
販売価格などはセガストアでご確認ください。
●ソフマップドットコム
・タカヤマトシアキ描き下ろし オリジナルB2タペストリー
●トレーダー3号店
・清原紘描き下ろし オリジナルB2タペストリー
●PlayStation Store(DL版)
<DL版限定予約特典>
・装備品「ラグナイト(ダウンロード版予約特典特殊仕様)」
<DL版予約特典>
・装備品交換アイテム「ラグナイトのかけら 30個」
●WonderGOOゲーム取扱店 / WonderGOO楽天市場店
・清原紘描き下ろし オリジナルB2タペストリー
※ご予約時に各店舗にて特典の有無を必ずご確認ください。
※各店舗ともに特典数量には限りがございます。
無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。
※特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引渡し時にお渡しいたします。
※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。
※特典内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。
◆キャンペーン
■事前登録キャンペーン
『蒼き革命のヴァルキュリア』のソフト発売前に事前登録を行うと、「事前登録限定フルボイス追加ストーリーDLCプロダクトコード」が発売日当日にメールでプレゼントされます。
登録期間は2017年1月18日まで。
応募方法などの詳細は公式サイトをご覧ください。
■Twitterキャンペーン
公式サイトや特報映像にて『蒼き革命のヴァルキュリア』のボイス出演キャストが公開されています。
これを記念し、ヴァルキュリアプロジェクト公式Twitterアカウント(@valkyria_sega)をフォローし、応募用ツイートをリツイートした人から抽選で1名に、主人公アムレート役の小野大輔さんのサイン色紙と『蒼き革命のヴァルキュリア』のポスターをセットでプレゼントするキャンペーンが実施されます。
応募方法などの詳細は公式サイトをご覧ください。
◆出展情報
また、2016年9月15日〜18日に開催される「東京ゲームショウ2016」では本作のPS4版が出展されます。
バトルをいち早く体験できるのみならず、最新映像の公開や試遊体験者およびコーナー来場者には「バトル体験版Ver.2.0」をDLできるプロダクトコードが配布予定です。
※バトル体験版Ver.2.0 は10月上旬より上記の配布プロダクトコード所持者を対象に先行ダウンロード配信を行います。
配信日詳細は後日公開させていただきます。
また、「バトル体験版 Ver.1.0」所持者は、「バトル体験版 Ver.2.0」を本プロダクトコードなしでプレイ可能です。
※本プロダクトコードは、試遊体験者、並びに事前登録キャンペーン応募者を対象に配布します。
※「バトル体験版 Ver.2.0」は PlayStation 4版です。
◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
『蒼き革命のヴァルキュリア』は2017年1月19日発売予定。
価格は以下のようになります。
・PS4版:7,990円(税別)
・PS Vita版:6,990円(税別)
※DL版同額
(C)SEGA
22日の日経平均は続伸。
前週末19日のNYダウは45ドル安。
原油先物価格は7営業日続伸したが、サンフランシスコ連銀のウィリアムズ総裁が年内の追加利上げを支持する発言をして軟調。
CME先物清算値は16475円、大阪先物夜間取引終値は16510円。
フィッシャーFRB副議長が21日の講演で「物価・雇用の改善」を指摘して22日の朝方は為替が乱高下し、取引開始直前のドル円は100円台後半、ユーロ円は113円台半ば。
日経平均始値は53円高の16599円。
高値は9時1分の16631円。
安値は9時23分の16540円。
終値は52円高の16598円。
台風が上陸して大荒れの天気の中、日経平均は開始直後から下落し9時台はマイナスに2回タッチするが、為替が円安方向に振れて10時台後半から16600円台に値を戻す。
相変わらずの薄商い。
前引けは38円高の16584円で日銀のETF買いの可能性はなくなった。
小池東京都知事が和服姿で五輪旗を受け取り、安倍首相が〃地球を貫く土管〃からスーパーマリオに扮して現れてリオ五輪の閉会式終了。
任天堂 も、土管(ヒューム管)メーカーのゼニス羽田HD も旭コンクリート工業 も日本ヒューム も反応してプラス。
後場は16600円にタッチしてもすぐ16500円台後半に押し戻され、どんよりした動き。
プラス圏でも盛り上がらないまま時間が経過する。
2時台は為替の円安が進みドル円が101円に接近したのを受け16600円台の時間帯が長くなったが、大引けでは16600円をわずかに割り込んだ。
日中値幅は91円という小動きだった。
日経平均終値は52.37円高の16598.19円、TOPIX終値は+8.01の1303.68。
売買高は14億株、売買代金は1兆6278億円と薄商いが続く。
値上がり銘柄数は1412、値下がり銘柄数は446。
プラスは26業種で、上位は首相コスプレ効果?で3.11%高の任天堂率いるその他製品を筆頭に陸運、建設、ゴム製品、電気・ガス、サービスなど。
銀行1業種がプラスマイナスゼロ。
マイナスは水産・農林、鉱業、保険、鉄鋼、繊維、石油・石炭の6業種。
上海総合指数は0.74%安だった。
23 日の日経平均は3営業日ぶりの反落。
シカゴ連銀全米活動指数は高水準でも原油先物価格が下がり週明けのNYダウは23ドル安で続落。
NASDAQはプラス。
S&P500はマイナス。
朝方の為替レートはドル円が100円台前半、ユーロ円が113円台半ば。
CME先物清算値は16545円。
大阪夜間取引終値は16520円。
日経平均始値は48円安の16549円。
高値は1時13分の16663円。
安値は2時12分の16452円。
終値は100円安の16497円。
マイナスで始まり、序盤に為替のドル円が100円を割り込みそうになると16500円台をかろうじて維持。
その後はドル円が100円をキープしたので徐々に値を戻し、10時台後半は16500円台後半に。
しかしプラス浮上どころか16560円付近で動かなくなり37円安で前引け。
「日銀の707億円ETF買いのライセンス」をゲットした。
ファイザーが買収を発表したメディベーションと前立腺がん治療薬「イクスタンジ」を共同開発し日本で販売するアステラス製薬 は小幅高で反応薄。
ルノーが燃費データごまかしたという報道が飛び出しても日産 はそれほど反応なし。
後場は前引けよりやや安く始まるが、0時台のうちにプラスに浮上して1時13分に65円高までいき「日銀から707億円が入るか?」と思いきや、そこからズルズル下げる一方で止まらない。
1時台はマイナスに落ちただけでなく16500円付近まで下げ安値更新。
2時台に16400円台半ばまで下げて止まった。
腹の探りあい、キツネとタヌキの化かしあいのような心理戦が、また繰り返される。
結局この日は日銀から707億円は撃ち込まれなかった。
薄商いで他に材料が見当たらないので、東京市場は日銀を中心に回っている。
終盤は戻しても16500円にタッチするのが関の山で、ヨタヨタと100円安で終了した。
日経平均終値は100.83円安の16497.36円、TOPIX終値は-6.12の1297.56。
売買高は15億株、売買代金は1兆8181億円。
値上がり銘柄数は657、値下がり銘柄数は1196。
プラスは11業種で、その上位は電気・ガス、医薬品、食料品、空運、不動産、陸運など。
マイナスは22業種で、その下位は保険、鉄鋼、鉱業、石油・石炭、機械、非鉄金属など。
上海総合指数は0.15%高だった。
24日の日経平均は反発。
ヨーロッパのPMIが良く新築住宅販売は予想外のプラス。
原油先物価格は堅調。
好決算の企業があった住宅、小売のセクターも上昇。
「ジャクソンホール待ち」で朝の高値からズルズル下がってもNYダウは17ドル高で3営業日ぶりに反発。
NASDAQ、S&P500もプラス。
ロンドン時間で為替のドル円が99円台をつけたが、朝方は100円台前半、ユーロ円は113円台前半。
CME先物清算値は16540円。
大阪夜間取引終値は16550円。
日経平均始値は52円高の16550円。
高値は9時26分の16648円。
安値は10時38分の16544円。
終値は99円高の16597円。
黒田日銀総裁が「日銀フィンテック・フォーラム」であいさつしたが金融政策に関する発言はなし。
日経平均は大阪夜間取引終値にさや寄せしてプラスで始まり、序盤に16640円付近まで上昇し9時台は16600円を保ったが、10時台16600円を割り込んで動きが小さくなる。
為替のドル円は動いても100円台前半の範囲内。
11時台もプラス圏を保ったまま前引けは83円高の16580円。
前引けプラスなら日銀のETF買いを考えなくてもよく、落ち着いて取り組めて精神衛生上もいい。
後場は3ケタ高で16600円台に乗せて再開するが定着できない。
16600円の少し下で時々16600円にタッチする値動きが最後まで続き、前日の100円安を99円高でほぼ取り戻して終えた。
日中値幅は104円だった。
日経平均終値は99.94円安の16597.30円、TOPIX終値は+9.15の1306.71。
売買高は13億株、売買代金は1兆6077億円。
値上がり銘柄数は1237、値下がり銘柄数は587。
プラスは28業種で、上位は金属製品、保険、輸送用機器、陸運、非鉄金属、証券など。
マイナスは水産・農林、石油・石炭、小売、不動産、鉱業の5業種。
上海総合指数は0.12%安だった。
CEDEC 2016最終日となる8月26日、目玉となる基調講演「ドラゴンクエストへの道〜ドラゴンクエスト30周年を迎えて〜」が開催された。
講演は「ドラゴンクエスト」シリーズのゲームデザイナー、堀井雄二氏と、スクウェア・エニックス執行役員エグゼクティブ・プロデューサーの齊藤陽介氏が登壇し、斎藤氏が堀井氏に「ドラゴンクエスト」シリーズ30年の思い出を聞いていった。
■漫画、ライター、そしてマイコン。
「ドラゴンクエスト」前夜その1
話題は「ドラゴンクエスト」誕生以前、堀井氏の幼少期から話がはじまった。
堀井氏は幼い頃から「工夫すること」が好きだったそうで、小学生のときに自分でスマートボールをベニヤ板で作成し、玉が入賞の穴に入ると5個の玉が一気に出てくる仕組みをも考えて組み込んでいたという。
また学生時代には麻雀にもハマったそうだが、ただ麻雀を遊ぶだけでなく、牌を裏返しに並べ、めくって出た数字だけ進むすごろくを遊んだり、トランプの「七並べ」ならぬ「牌並べ」をして遊ぶなど、新しい遊びも考えて楽しんでいた。
堀井氏は高校生当時漫画家になりたかったそうで、高校3年生の夏休みに東京を訪れ、当時漫画雑誌に住所がそのまま載っていた永井豪氏の事務所を訪れて、いきなり原稿を持ち込む。
その時永井氏は会ってくれたそうだが、「ふーんという感じ」で反応はイマイチ。
「これはキツイから学校へ行こう」となり、ただし漫画家になる夢は捨てずに、早稲田大学に入学して漫画研究会に所属することとなる。
そこでは有名な先輩がいたり、編集者のツテがあったりして、そのうち物書きの仕事が舞い込むようになると、「漫画を描くよりも文章を書くほうが楽だな」となって、自分で書いた文章にイラストを付けたりしつつ、そのままフリーライターとしての道を歩んでいく。
当時書いた記事として話題に上がったのは、山口百恵さんの楽曲「美・サイレント」にある「あなたの○○○○が欲しいのです」という歌詞をめぐって、「○○○○」には何が入るのかを好き勝手想像していくというコラム。
読者の反応がとても良く、思い出深い記事になっているそうだ。
その後堀井氏に大きな転機となるが、27歳で出会う「マイコン」。
世間で話題となっており、堀井氏自身も「買ってみるか」となったそうだが、当時はキーボードに触ったことがなく、いきなり高いものは購入できなかった。
そこで目を付けたのが「パピコン」の愛称が付いていた日本電気の「PC-6001」。
何十万円もするような本格的なものに比べると簡素ではあるが、当時10万円ほどで購入できたため、購入を決意。
BASICの教則本「みんなで使おうBASIC」も購入し、「なんかできそうだな」と徐々に覚えていったという。
初めて作ったのは名前や血液型などを入力して結果を表示させる占いプログラム。
誰かが遊びに来るとわかったときは、占い結果の出力文にあらかじめその人の詳細な情報を書き込んでおいて、試しに占いを遊んだ友人がその当たり過ぎる結果を見て「こんなにわかるのか」と驚いてしまう、というイタズラを楽しんでいたそうだ。
当時はBASICで書かれた「スタートレック」や「信長の野望」といったゲームを楽しみ、さらにBASICのパラメータを書き換えられるという仕様を活かし、ステータスを改造して遊ぶといったことも行なっていたという。
■ゲーム開発本格始動! 「ドラゴンクエスト」前夜その2
それから半年ほどが経過し、堀井氏が取り掛かったのがテニスゲームの「ラブマッチテニス」。
ただしBASICでは速度が出せなかったため、「マシン語入門」という本を購入して16進数でマシン語を導入することを決意。
このマシン語が「頭がこんがらがる」ほど大変で、「次の日何を書いたか覚えてない」こともあった。
そんな折、堀井氏は当時のエニックスが伝説のゲームコンテスト「第1回ゲーム・ホビープログラムコンテスト」を開催することを知る。
堀井氏はすでに週刊少年ジャンプで文章を書いており、「マイコンゲーム特集」の担当者でもあった。
コンテストの取材も依頼されたのだが、堀井氏はしれっとそのコンテストに「ラブマッチテニス」を応募。
「受賞作が決まった」というのでエニックスに行ってみると、見事「ラブマッチテニス」も入選しており、取材しながら自分も受賞するという状況を体験したそうだ。
コンテスト入選の13作品はエニックスから発売もされ、それが評判だったということで、次回作の依頼が来ることになる。
そのとき堀井氏が目を付けていたのが、「海外で流行っている」と聞いた「ミステリーハウス」に代表されるアドベンチャーゲーム。
アドベンチャーゲームは言葉をやり取りするゲームということで、漫画作りにも通じる「物語を作る」ことができ、さらに依頼作なので「誰かに遊んでもらえる」ものになるので、堀井氏はこれに着手することになる。
そうしてできあがったのが、「ポートピア連続殺人事件」(1983年)だ。
ちなみに「ポートピア連続殺人事件」の物語は、その最初と誰が犯人かという最後をまず作っておいて、その後中間をどうするかを組み立てていったという。
その後はPC用の「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ」(1984年)、「軽井沢誘拐案内」(1985年)とアドベンチャーゲームを発表。
それまでは堀井氏が1人でゲームを開発していたが、「オホーツクに消ゆ」ではシナリオだけを担当し、ここで初めて分業を経験したという。
ちなみに「オホーツクに消ゆ」では行動をいくつかの種類から選択する「コマンド選択式」が初めて導入されており、また当時は「ウィザードリィ」や「ウルティマ」といったRPGに絶大にハマっていたそうで、RPGを作りたい気持ちが出てきて、「軽井沢誘拐案内」ではアイテムを拾ったり、戦闘する要素が見られており、「ドラゴンクエスト」に繋がる要素がこの2作品から窺い知れる。
時を遡って1983年、世間で話題となっていたのが任天堂のファミコンだ。
当時は子供人気も圧倒的なほどの大ブームで、堀井氏自身も「ドンキーコング」などをプレイして、「これが家でできるのか」と驚いていたという。
堀井氏はそのうち「ファミコンでRPGを作りたい」と思うようになり、実現に動き出すことになる。
エニックス側からは「その前にアドベンチャーゲームを出さないか」と言われたため、「ポートピア連続殺人事件」の移植版制作を挟んでから、「ドラゴンクエスト」制作に取り掛かっていった。
ちなみに「ポートピア連続殺人事件」の移植を担当したのは、現スパイク・チュンソフト代表取締役会長で、「ドアドア」で「第1回ゲーム・ホビープログラムコンテスト」の優秀賞を獲得していた中村光一氏。
堀井氏と同じく「ウィザードリィ」と「ウルティマ」にハマっていたため、3Dダンジョン要素も移植の際に盛り込んでいる。
■ダイジェストで振り返る「ドラゴンクエスト」〜「ドラゴンクエストX」
こうして、堀井氏の「RPGを作りたい」という強い気持ちが結集したのが、「ドラゴンクエスト」(1985年)だ。
「ドラゴンクエスト」というネーミングは「ドラゴン」という馴染みのある言葉に、「クエスト」という当時馴染みのない言葉を組み合わせて作っている。
ただし容量が64KBしかないためかなり節約して組み上げたそうだ。
ここからは、「ドラゴンクエストX オンライン」までの全シリーズを、堀井氏のコメントと共に振り返っていった。
「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」(1987年)では容量が2倍になり、パーティー編成ができるようになった。
ただし慣れない人も想定して、最初は1人からスタートすることにしたという。
斎藤氏は当時を振り返り、「海外RPGは誰を雇うかだけだったので、ストーリーの中で仲間が増えていくのには驚いた」と述べた。
「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」(1988年)では、容量がさらに倍になり、パーティープレイも含めて様々なことができたという。
「DQI」と「DQII」に繋がる「ロト」と「アレフガルド」の秘密が本作で明かされるが、「DQI」制作時に「DQIII」の構想はなかったそうだ。
社会現象にまでなった「DQIII」の大きな反響は、「ドラゴンクエストIV 導かれし者たち」(1990年)の開発時に大きなプレッシャーになったという。
「DQIV」でのコンセプトは、「DQIII」ではキャラクターごとの背景設定がなかったのに対し、「キャラクターそれぞれに人生がある」というもので生み出されたものだとした。
続く「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」(1992年)では、「プレーヤーをゲームで本気で悩ましたい」と思い、結婚イベントができあがったとした。
また「親子3代かけて魔王を倒す」というのもコンセプトの1つとなっている。
シリーズ作を重ねる度に「毎回どんな遊びをしようか」と考えるそうだが、「ドラゴンクエストVI 幻の大地」(1995年)の時は、「いきなり2つの大陸を行き来したらどうか」という発想でできあがった作品になる。
ちなみに「魔法のじゅうたん」を使うとどこでも行けてしまうため、木や水をなんとか利用してマップを作っていったという。
「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」(2000年)では、プラットフォームがプレイステーションになり、容量が格段に増えた。
スタッフも大勢入れて、ストーリーもやりこみ要素も増やしていった(斎藤氏いわく「長かった……」)。
「ツンデレ」という言葉がない時代に「ボロクソ言う」幼なじみ、マリベルを作ったのが印象に残っているという。
「ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君」(2004年)では、レベルファイブと「たまたま出会った」ことで、「DQ」の世界がフル3Dで表現できたのが、何よりのウリだとした。
「ドラゴンクエストIX 星空の守り人」(2009年)は、ニンテンドーDSの機能「すれちがい通信」によってネットワークプレイの敷居が下がり、マルチプレイのようなものができたのがよかったとした。
すれちがい通信では、メタルキングスライムだけが登場する「まさゆきの地図」が大きな話題になった。
「ドラゴンクエストX オンライン」(2012年〜)は「DQIX」のアイディアの延長で、「オンラインゲームでやろう」というもの。
サービスが開始されたのは2012年からだが、実は構想自体は10年前からあったのだそうだ。
■「ゲレゲレ」、「かいしんのいちげき」命名の由来は? 堀井氏質問コーナー
続いて講演は、事前に応募した質問コーナーへ。
内容は以下のとおりとなる。
質問:戦闘の際、「DQI」では「○○が あらわれた! コマンド?」というメッセージが出ていました。
2作目からは「コマンド?」がなくなっているが、これはどういう意図でしょうか?
堀井氏:これは、言われるまで気づきませんでした。
これ以前のアドベンチャーゲームは選択肢がなく、「コマンド?」と回答を促すコメントが普通だったので入れていて。
でも「DQII」からは「コマンド?」の文字はいらないと気付いて、削除しました。
質問:バランス調整はどのくらい時間や人数をかけていますか?
堀井氏:「DQIV」、「DQV」、「DQVI」で言えば、最初にシナリオ作ったあとは、2カ月くらいはずっとデータを作っていました。
その後もテストで頭からプレイしてもらって、そのレポートを集めて、数字を調整していく作業を延々とやります。
データ作成は、あまりマニアックな方ではないので、自分が気持ちよくプレイできるかどうかで決めています。
バランス調整は毎回ギリギリまでやっていて、「もうダメだ」と言われても、何かバグが出たら「ついでにこれも直して」と言っていました。
質問:「DQV」で、モンスターを仲間にできるシステムはどうしてできたのでしょうか?
堀井氏:これは「DQIV」で、ホイミンを仲間にして楽しかったからです。
斎藤氏:ちなみに(キラーパンサーの)「ゲレゲレ」という名前はどこから?
堀井氏:思いつきです(笑)。
作品内で、必ずどこか1個ふざけるようにしています。
質問:「DQX」のシナリオはVer.1発売の時点でどこまでできていましたか? また現時点ではどこまでできていますか?
斎藤氏:Ver.3では新たに竜族が登場するが、人間ではない5種族と竜族がいるという設定は最初から決まっていました。
今後ということで言うと、Ver.4はここ数ヶ月でプロットの話を始めたところです。
新しい職業も決まってきていて、ある程度骨格は見えている。
Ver.5はこれからで、プレーヤーの動向を見ながら決めていきます。
質問:「DQI」で、ゲーム開始直後に「竜王の城」が見えます。
これをデザインした意図は? またワールドマップはどこから描き始めたのでしょうか?
堀井氏:「竜王の城」を最初に書いた気がします。
人間は目的がわかった方ががんばるから、始まってすぐ「ここに行け」とわかりやすくしています。
ただ、行き方がわからないので、それを探ることになります。
斎藤氏:マップはどのように作っていくのですか?
堀井氏:まずフィールドマップの形を作って、その中にバランス良く中身を配置していきます。
マップに出た時に別の街がちょっと見えるようにしたりもします。
斎藤氏:「DQ」チームは、シナリオのチームが街の構造も作ります。
世界の設計図を書いて、人を置いてからシナリオを作るというのが特徴的です。
堀井氏:ずっとその方法でやってきたので、それが踏襲されていますね。
質問:「アレフガルド」という名前は、どこから来ているのでしょうか?
堀井氏:地名を命名するときは、まず世界地図の索引を見ます。
そうすると○○ガルド、○○ヴァニアのような語尾が「地名っぽい」とわかってきます。
「アレフガルド」は、始まりを意味する「アレフ」に、「ガルド」をくっつけました。
実際の地名をモジッたりもしますが、そうしないと地名らしく見えないんですね。
マップを作る際も、世界地図を見て、実際の地形を参考に作ったりもします。
ちなみに日本は北半球なので、北に海が多い方が世界っぽいく見えます。
質問:「Critical Hit」を、なぜ「かいしんのいちげき」と名付けたのでしょうか?
堀井氏:「かいしんのいちげき」、という気がしたんです。
会心! と爽快な感じで。
質問:ゲームデザイナーとして、最も必要で大事なことはなんですか?
堀井氏:まずは自分が面白がる“発想力”、それをシステム化、データ化していく“忍耐”、そして「やっぱり違った」となったときに切る“勇気”、この3つですね。
■「ドラゴンクエストXI」で「ふっかつのじゅもん」が復活!
講演の最後は、現在開発中の「ドラゴンクエストXI」の話をしませんか? という斎藤氏の発案で、現在の状況が少しだけ明かされた。
開発状況としてはシナリオはすべて完成していて、現在はマップやシナリオなどをゲームに実装して、それらを実際に触りながら詳細を詰めていっている段階だという。
両氏は昨日も5、6時間ほどこうした打ち合わせをしていたそうで、1エピソードのチェックに3時間ほどかけながら、色々とアイディアを出しているのだという。
ちなみにこれらのチェックは実装のレスポンスが早い3DSの3Dモードで行なっており、仕様が固まったら3DS版の2DモードやPS4版に反映させていくという方法を取っている。
バトルのチェックは、PS4版でも行なっているそうだ。
最後におまけとして、「DQXI」には「カジノ」と「ふっかつのじゅもん」が入るという。
特に「ふっかつのじゅもん」は「30周年らしいもの」になるそうなので、その詳細を楽しみに待ちたい。
マーベラスは、PS4/PS Vitaソフト『Fate/EXTELLA(フェイト/エクステラ)』の新たなプレイ動画を公開しました。
RPGとして展開してきた『Fate/EXTRA』シリーズの最新作となる『Fate/EXTELLA』は新たな進化を遂げ、手に汗握るハイスピードアクションを実現。
サーヴァントと呼ばれる古今東西の歴史・神話の英霊たちの激戦と、“聖杯戦争後” の物語を描きます。
これまで、「ネロ・クラウディウス」や「玉藻の前」、「無銘」に「ギルガメッシュ」といった面々のプレイ動画が公開されましたが、新たに「エリザベート」、「呂布」、「ガウェイン」の映像がお披露目されました。
才色兼備のスーパーアイドルを自称するランサー「エリザベート」、三国志に名高い、裏切りの武将であるバーサーカー「呂布」、太陽の騎士でありエクスカリバーの姉妹剣を持つセイバー「ガウェイン」と、いずれも魅力と迫力溢れるキャラクターばかり。
その華麗なアクションを動画で直接ご覧ください。
YouTube 動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=FLq6YOek8S8
YouTube 動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=VvYAowWiDb0
YouTube 動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=CqE-wkU_QdY
『Fate/EXTELLA』は11月10日発売予定。
価格は、PS4の通常版・ダウンロード版が7,980円(税抜)、限定版が9,980円(税抜)。
PS Vitaの通常版・ダウンロード版が6,980円(税抜)、限定版が8,980円(税抜)。
また、PS4版とPS Vita版が同梱となるプレミアム限定版は、19,990円(税抜)です。
(C)TYPE-MOON (C)Marvelous Inc.
文・取材・撮影:ライター 喫茶板東
●YOUはなぜ日本のゲーム業界へ?
2016年8月24日〜26日の3日間、パシフィコ横浜で開催された、日本最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2016”。
1日目に開催されたセッション“日本で働くガイジンクリエイターに訊く日本のゲーム産業、開発環境、労働環境ってどうですか?”のリポートをお届けしよう。
本セッションの登壇者は、黒川文雄氏、ハンサリ・ギオーム氏、コチョール・オザン氏、ジェームス ラグ氏、ウィリアムソンジェームス氏の5名。
黒川氏が司会となり、日本のゲーム業界で働く外国人4名にアレコレ聞いていくという、パネルディスカッション形式での進行となった。
なぜこのセッションを開催する運びとなったかは、黒川氏の実体験からとのこと。
氏が主催するイベント“黒川塾”で外国人クリエイターを招待したところ、日本人が気がつかないことを、たくさん発見できたそうだ。
そこで、日本のゲーム業界で働いている親しい友人に、日本のゲーム開発環境や、出身国と日本における違いなどを聞いて、受講者に役立ててもらおうと思ったそうだ(→参考記事はこちら)。
まずは登壇者の自己紹介もかねて、4名がどのようなきっかけで来日し、お仕事を始めたかについて話を聞いてみた。
ギオーム氏は、日本のマンガやアニメ、ゲームに興味を抱き、大学を卒業した10年前に来日。
当時はまだゲーム業界で働きたい意思はなく、普通の会社に就職し、2年後に独立して、自身の会社であるWizcorpを起業したそうだ。
就職については「けっこう苦労しました」と語るギオーム氏。
2006年時、氏は特別なスキルを所持しておらず、また職種はSEを希望していたため、英語力はとくにアピールポイントにはならなかったそうだ。
「外資系や海外とやりとりしている会社ならば、まだ需要はあったかもしれない」(ギオーム氏)。
自身で起業したきっかけについては、「勢い」という簡潔な答え。
奥さんが日本人のためビザ的な問題がなく、また2008年当時は、大規模な資本金がなくとも起業できたため、「けっこう簡単に会社を作れた」そうだ。
また退職してから起業するまではフリーランスで活動していたそうだが、法人化したほうが税金が安くなったり、会社が大きくなったときにアレコレ便利、というメリットがあったことも一因とのこと。
オザン氏は、来日して約13〜4年目。
元々は、フランスにある会社の日本支社代表で、動画配信やモバイル広告、動画エンコード、ストリーミングなど、技術系の仕事を行っていたそうだ。
代表として日本の企業とさまざまなやりとりを行ったが、「まだ24歳の外国人にとっては、けっこうハードルが高かったですね(笑)」と、当時を振り返る。
その会社を退職してからゲーム業界へ入ったそうで、最初は先ほどのギオーム氏の会社に入社したそうだ。
GREEのゲームなどに関わり、未経験ながらも「けっこう上手くいけた」とオザン氏。
それから1年ほど経過したとき、ウォーゲーミングジャパン立ち上げに参加。
「自分は(開発よりも)パブリッシングが向いていると感じたし、ウォーゲーミングジャパンの川島(康弘)代表と馬が合ったことが大きな理由」と、入社するきっかけを語ってくれた。
同社では、最初はモバイルゲーム『World of Tanks Blits』のパブリッシングプロデューサーを務め、同タイトルを成長させていく。
今月から全タイトルのパブリッシングを見るゼネラルマネージャーに就任し、「なんか急展開で……」と自身の出世速度の速さに驚きを隠せない様子だ。
またオザン氏は、日本人と外国人の交流を図るゲーム業界人向けイベント“Insert Coin!”も主催。
ライン社に勤める友人と協力して開催しており、毎回テーマを決めてゲストを誘っているとのこと。
ただ、以前は2ヶ月に1回のペースで行っていたが、仕事が忙しくて、ここ8ヶ月ほど開催できていないそうだ(→参考記事はこちら)。
ラグ氏が来日した理由は、当時あまり海外向けにローカライズされていなかった、PCエンジンのゲームが遊びたかったことだそうだ。
また、マンガの『ドラゴンボール』も読みたかったんだとか。
そのために、とくに卒業後のキャリアなどを考えず、大学では日本語を専攻。
「流れに身を任せて現在に至ります」と、過去を振り返った。
ゲームやマンガといった日本カルチャーのファンであるラグ氏だが、当初は日本産ということを意識せずに楽しんでいたそうだ。
後に開発会社を調べると、タイトーやカプコンなど、日本のメーカーが開発していたものだと気づいたのだとか。
アニメでも同じような体験があり、当時イギリスで放送されていた『Battle of the Planets』は英語吹き替えということもあり、アメリカ製のアニメだと思い込んでいた。
だが、こちらも調べると、日本のアニメ『科学忍者隊ガッチャマン』であることを知ったそうだ。
そのようなことがきっかけで、日本語を専攻することを選び、やがて日本でゲームに関わる仕事をしたいと思うように。
当初はゲーム業界の人材紹介会社、いわゆる引き抜きを行っていたそうだが、「もしかすると、これは悪いことなのかなあ」と考えるようになった。
また、もっと開発に近づきたいという思いもあって、開発会社であるピラミッドに入社したそうだ。
「ほとんど拾っていただいた形ですね」とラグ氏。
ピラミッドで7年ほど開発や開発進行の仕事を行い、今年に入ってから、「日本のコンテンツをもっと海外に届けたい」という思いが強くなり、現在はデジカに移籍。
日本国内のゲームを海外に配信するチームに所属し、ケイブの弾幕シューティングなどを海外にリリースしており、「非常に幸せです」と現状を語ってくれた。
ウィリアムソン氏は、高校生のころ、日本に1年間留学しており、そのときに日本語を覚えたそうだ。
大学を卒業後、友だちがCGの仕事をしていたことがきっかけでCGと出会い、CGの専門学校へ入学。
CGと日本語ができるなら、ゲームしかない!と思い、2003年に新卒でグラスホッパー・マニファクチュアに入社、『Killer7』の開発に関わったそうだ。
入社には外国人特有の苦労もあったとのこと。
まず新卒で来日すると、労働ビザがなかなか下りないそうだ。
ただ、現在の奥さんと結婚することで、この問題はクリアーできたとか。
その後はスクウェア・エニックスへ移籍。
当初はモーションキャプチャーやフェイシャルアニメーションなどを担当し、その後違う分野にもチャレンジしたいという思いを抱き、モバイルのゲームデザインやクリエイティブデザイン、運営も担当。
再び、初心に戻ってCGをやりたい思いがこみ上げて、12年在籍したスクウェア・エニックスを退社し、現在はアカツキで3Dディレクションを担当しているそうだ。
彼らの歩みを聞いて、「まったく逆を想像してみてほしい」と黒川氏。
「我々日本人がアメリカやヨーロッパへ行き、入りたい会社を捜し、就職することを想像すれば、彼らの苦労が少しは理解できるのではないか」と、その大変さを語る。
さらに、「個人的には、日本の会社は少しクローズしているイメージがある」と続ける黒川氏。
「なかなか受け入れてもらえなかった苦労話や思い出はありますか?」と、4名に訪ねた。
ラグ氏は「僕はさっきも申し上げたように、本当に流れに任してしまった身なので、捜しかたによるかもしれませんね」とコメント。
「ちゃんと扉をトントンして、日本語で話せば、閉まっている扉でも開くことは多いんじゃないかな」と、話せば分かるという意見を述べた。
オザン氏は「でも会社の方針とかもあるし、(ある程度は仕方がない)」と語る。
日本のゲームメーカーは日本人向けにゲームを作っており、日本で受けるゲームや日本市場をいちばん分かっているため、日本向けのゲームを作るのであれば、外国人という付加価値は低いのでは、と分析。
逆に、海外へ進出したい会社、インターナショナルな会社であれば、外国人であるという付加価値を感じてくれるかもしれない、とも語る。
ギオーム氏は「ゲームの内容もコア化していると思います」と、日本産ゲームの内容にも言及。
「以前は海外のデザインや色などを取り入れて、新鮮な物を生み出したいと考えたプロデューサーは、たくさんいたと思うんです。
でもいま、とくにモバイルでは、内容がかなり固まってしまっている」と、日本産ゲームの現状を指摘。
RPGならこういう絵、アクションならこういう演出と固定化されて見えるそうだ。
ただ、そこから外れてしまうとプロモーションが難しくなったり、売れない場合のリスクは誰が取るのか、という話にもなりかねないと語る。
そのため「現在は、外国人が日本のゲーム業界に入りにくいと思います。
海外のプロデューサーとして、とくに日本市場向けに何かを開発するのは、かなりハードルが高い」とギオーム氏。
●日本のゲーム業界は変わったように見える?
続いての話題は、「日本のゲームは、90年代、2000年代頃と比べると、内容が画一化されているという印象を受ける?」という内容。
ギオーム氏は「個人的にはふたつ理由があると思います」と回答。
理由のひとつは、日本は昔、海外の市場で売れるゲームを目指していたこと。
アタリショックが発生し、アメリカのコンシューマー市場ががら空きになったところに任天堂がカジュアルなコンテンツで市場を取り、セガやその他の大手メーカーも海外向けにゲームを作成していたと語る。
また当時は日本のゲーム市場もそれほど大きくなかったことも要因のひとつ。
その後、日本の市場も成長し、国内だけでも儲けられるようになったから、海外をあまり視野に入れなくなったのでは、とコメントした。
もうひとつの理由は、ゲームクリエイターの意識の変化。
20年前などのゲームクリエイターは、アーティストとしてゲームを作成していたとギオーム氏は分析。
だが、いまの若いクリエイターは子どものころからゲームで遊んで育ち、ゲームクリエイターを目指すようになったため、「彼らはゲームの概念がはっきりしていて、くり返しというか、ゲームの内容がコア化していく」と語る。
だが、ラグ氏はこの意見に反論。
「ファミコンで『ドラゴンクエスト』が出た直後、非常に多くの『ドラゴンクエスト』クローンが開発されましたから」と、ほかのゲームを参考にゲームを開発することは、ファミコン時代からあった事象だとコメント。
続けて「あくまで僕の考えなんですけれど、80年代や90年代のゲームは、海外の映画に影響を受けていた」と語る。
当時はシュワルツェネッガーみたいなキャラクターが多くのゲームに登場し、それを海外でリリースすると「おっ、シュワちゃん出てるじゃん」となって、みんな買ったという。
日本と海外で同じ映画を見て、同じ影響を受けたから、それがゲームに反映されると、海外でも受けがよくなるという持論を述べた。
「現状でも、アニメや海外の映画、ドラマからは影響を受けているとは思いますが、当時と違ってライセンスはしっかりクリアーしないといけない問題。
また国内向けのコンテンツを作るのは当然の流れ」(ラグ氏)。
ウィリアムソン氏は「ゲーム(という文化)が始まったときは、『ドラゴンクエスト』という新しいIPを生み出している状態。
そこから長年続き、IPは固まってしまって、フリー・トゥ・プレイのビジネスモデルにもなっているため、IPを使ったほうが宣伝しやすい。
クリエイティブで挑戦的な物より、集客しやすい物のほうが多く作られている」とコメントした。
つぎの話題は、現在の国産ゲームについて。
黒川氏は「かつて日本はゲームにおいてあこがれの国だったと思いますが、現在は日本向けにゲームを作成している印象がありますし、テイストも似通っている。
また以前、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)で“日本のゲームはもうダメだ”という発言が話題になったこともありました。
海外のデベロッパーから見た日本のマーケットや、日本にあこがれていた外国人が現在の日本の状況をどう思っているか、お聞かせください」と疑問を投げかけた。
オザン氏は「日本のゲームがダメだというのは、どういう基準ですかね(笑)。
質ですか、売り上げですか?売り上げだったら、いまも十分に高いと思います。
単純に、日本の市場がダメというよりは、海外の市場がいまは盛り上がっているから、同じ目線で比べられているだけだと思います」と回答。
モバイル業界ではゲームの数が圧倒的に多いし、10年前と比較しても非常に成長しているそうだ。
さらに、新しいクリエイターたちは、インディーでさまざまなゲームを作ろうとしている。
「日本では“職人魂”がまだ強いと感じますし、日本でヒットしているゲームは、メガゲームを除いて、そんな“職人魂”を持ったゲームだと思う」とコメントした。
さらに「あまり自社を持ち上げることはしたくないんだけど……」と謙遜しつつ、同様の精神を『World of Tanks』にも感じると語る。
「戦車にかける愛情がすごく、細部までこだわっている。
日本の“職人魂”と同じ魂を持っているから、ヒットしているのかな、とも思います」と分析した。
ウィリアムソン氏も、海外のゲーム市場が盛り上がっていた、という意見に賛同。
「そのとき、日本のゲーム会社は、グローバルで売るためにはグローバルに合わせなければいけないと思い、日本から『Gears of War』のクローン作品がたくさん出たりした。
言いかたはきびしいけれど、“海外に魂を売り渡した”ように感じたんですよ」と、当時の状況と、外国人の心情を分析。
「現在は日本のゲームは日本向けに集中していて、よくわかっているゲームを作っている。
日本市場を第一に考えて、海外では字幕だけとか、最低限のローカライズでリリースしている。
でも、これは純粋な日本の物だから、海外ではリスペクトされているんです」とコメントした。
●『ガルパン』と“BABYMETAL”から見る日本らしさ
というわけで、話題は“日本らしさ”へ。
黒川氏は「日本のオリジナリティーや、日本ならではの物って、日本にいる自分たちからはよくわからない部分でもあります。
皆さんが感じた“日本ならではの物”がありましたら、教えてください」と質問。
オザン氏は「弊社では、日本のオフィスはすーごく注目されているんです。
発想がすごくおもしろい」と、発想に“日本らしさ”があるとコメント。
以前、『World of Tanks』とアニメの『ガールズ&パンツァー(GIRLS und PANZER)』がコラボを行ったとき、最初に本社の人に『ガルパン』を見せたところ、その反応は「ハァ!?」だったそうだ。
「戦車と女子高生、なんじゃそりゃ!って感じですよね。
海外だと、戦車イコール戦争ですから。
でも実際にアニメを見て、バンダイビジュアルさんがすごくいい仕事をしたという理由も大きいんですけれど、みんなすごくおもしろいと言ってくれて」と、コラボの秘話を明かす。
「このような発想は、日本人しか思いつけない、おもしろい内容」とオザン氏。
また、同じく混ぜた例として、初代Xbox用の格闘ゲーム『格闘超人』も話題に。
『格闘超人』は音楽の表現に宗教的な問題があり、リリース後に「コレはまずいんじゃないの?」と問題になって、リコールになったと解説するラグ氏(→参考記事はこちら)。
「混ぜるのはいいけれど、それを海外で出すときは気をつけないといけない」と注意を喚起した。
ウィリアムソン氏は「僕はイギリス出身ですけれど、ヨーロッパと北米はたいてい敵対視しています。
移民も多く、ほかの文化に対する理解は、日本に比べて、よくも悪くもある。
“ここは混ぜちゃ危険”とわかるから、やらない。
その感覚がない日本だから、混ぜることによって、いいものが産まれるわけです」とコメントした。
さらにギオーム氏は、この“おもしろい発想”について、ゲーム以外にも言及。
「最近だと“BABYMETAL”ですね。
メタルとアイドルの融合は、アメリカでもヨーロッパでも、絶対に生まれなかった。
これは日本人しか思いつかない物で、海外でもかなりヒットしています。
そういったオリジナリティーは、けっこう期待されているんじゃないかな」とコメント。
さらに「音楽を聴くとすごくしっかりしていて、アイドルも本格的。
そういうオリジナリティーがあります。
これが“なんちゃってメタル”だと、うまくいかなかったと思います」と、ここでも“職人魂”を感じられることをコメントした。
ウィリアムソン氏はゲームの実例を紹介。
「海外で売るときは、何かユーザーから親しみやすい現実を元にしなければならない」と語る。
その例のひとつが、重そうな剣を持ち上げるときの仕草。
ファンタジーではよく見かける光景だが、「一応ちょっと重く持ち上げている雰囲気があったほうが、海外のユーザーに響く」と語るウィリアムソン氏。
その理由として「ハリウッドの洗脳が強かったからでは」と推測した。
対して日本は軽々と振り回したりする、おもしろければいい、というスタンス。
「縛りのない、新しい発想をいいと思い、バンバン取り入れていく。
そこが長所なのでは」とウィリアムソン氏。
最後に、黒川氏は登壇者に今後の展望について質問。
4名に、それぞれどのような未来のビジョンを持っているのか、語ってくれた。
ギオーム氏は自社の展望を語る。
「弊社はゲーム会社で、ソフトウェア開発業務を行っています。
特殊な会社で、90パーセント以上が外国人。
エンジニアは全員外国人で、コンピューターサイエンスのマスターが海外から入社しており、そこが強み。
ソフトウェアエンジニアリングという分野は、日本では教えている学校が少なく、カリキュラムもあまりない。
結果として、実際にソフトウェアのエンジニアリング理論を学んでいる人が少ないんです。
弊社はその観点で開発を見ているので、今後はソフトウェアエンジニアリングや開発の概念、最終的にマネジメントのフォロソフィー(考えかた)を広めていきたい」と展望を教えてくれた。
オザン氏は「単純に未来は明るいなあと思います。
いろいろ新しい技術が出てきていますし、たった1ヵ月で『ポケモンGO』が新しい市場を作りました。
遊びかたも成功事例を作ったから、ビジョンというか、モバイルはこれからもずっと伸びると思います。
個人的には日本で仕事をし続けたいし、ウォーゲーミングは外資系だけどやっぱり日本にもすごく力を入れたい。
日本のためにゲームを作りたい気持ちも強いです。
それをどう実現するかを、いまいろいろ社内で考えていて、まだ答えは出ていないですけれど、外資系として会社の魂を守りながら、日本の心に響くゲームを作るのが今後の勝負だと思います」とコメント。
ラグ氏は「僕はピラミッドでシューティングゲームを作ってきて、パブリッシングさせていただいているので、そういう意味では幸せです。
それが続けばいいなあと思いつつ。
あとピラミッドで担当した『PATAPON (パタポン)』というゲーム、キャラデザインがフランスの方ですが、中身は日本の技術集団によって作られたゲームで、国内よりも海外で反響が大きかったんですよ。
でもこれは偶然だとは思っていなくて、日本と海外が何か融合したクリエイティブなものに携わっていきたい。
架け橋になっていきたいですね」と語った。
ウィリアムソン氏は「ゲームを作りたいですね(笑)。
作りかたはいろいろあると思うんですけど、いい人といっしょに、できるだけ幅広く、新しい体験と新しい遊び、楽しい体験を作り続ければ僕は幸せだと思います」とコメント。
こうして盛況の内に、セッションは幕を閉じた。
外国人のクリエイターという海外からの目線で、日本のゲーム業界の一端を垣間見られる、貴重でユニークな意見が飛び出したセッションだった。
これらの意見が、今後国産ゲームの発展に役立ち、さらにすばらしいゲームが開発されることを願おう。
そのほかでは、6位に入ったシンガー・ソングライターの新居昭乃さんのアルバム「30th anniversary album リトルピアノ・プラス」も注目してもらいたい作品。
“幻想系”の先駆けとして1980年代から活躍してきた新居さんのデビュー30周年記念作で、10月上映予定のアニメ「ゼーガペインADP」の主題歌も収録しています。
過去には菅野よう子さんとコラボするなど“レジェンド”と言っても過言ではない新居さんの魅力を、この機会にぜひ堪能してもらえればと思います。
ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントは、PlayStation Vita/ニンテンドー3DS用アクションアドベンチャー「LEGO ニンジャゴー ニンドロイド」を11月22日に発売する。
価格はパッケージ版が4,700円(税別)、ダウンロード版が4,200円(税別)。
「LEGO ニンジャゴー ニンドロイド」は、レゴブロックをモチーフとしたアクションゲーム「レゴゲーム」シリーズの新作タイトル。
本作には、前作に当たる「LEGO ニンジャゴー ローニンの影」以前のストーリーを収録。
ニュー・ニンジャゴー・シティを舞台に、ウー先生のもとで修行に励むニンジャたちが、新たな武器やビークル、スピン術を用いてオーバー卿とサイボーグ軍団「ニンドロイド」たちに立ち向かう。
c2016 The LEGO Group. TM & c WBEI. (s16)
ドバイの漫画、アニメ、ゲームファンに支持を得るポップカルチャーストア「ギーク・ネーション(Geek Nation)」で8月25日、ゲーム「進撃の巨人(Attack of Titan: Wings of Freedom)」の発売イベントが行われた。
(ドバイ経済新聞)
ミカサに扮したコスプレーヤーすみーあやさん
今回発売されたのは、コーエーテクモゲームスのプレイステーション4(PS4)およびXBox用ソフトで、「進撃の巨人」の登場キャラクターを操作し、巨人を倒して進むハンティングアクションゲーム。
PS4用は、通常のソフトと、サウンドトラックCDやマフラータオルなどが同梱(どうこん)されたトレジャーボックスの2種類が店頭に並んだ。
ドバイにも熱烈なファンを誇るアニメのゲーム化ということもあり、イベント開始時刻の夜7時には多くの客が来場。
ゲームソフトや、フィギュアなどの関連商品を手に取っていた。
店舗中央に置かれた3台のテレビで同作を体験プレーできるようになっており、来場者は次々にゲームの世界に入り込んでいた。
進撃の巨人のTシャツを着てイベントに参加した男性は、「オンラインでTシャツを購入し、初めて着てイベントに参加した。
グラフィックがきれいで、ゲームはとても面白い」と感想を語った。
会場に用意されたスクリーンではアニメの第1話が流され、進撃の巨人にちなんだコスプレコンテストも開催。
ヒロイン・ミカサのコスプレで登場したコスプレーヤー、すみーあやさんが優勝した。
すみーあやさんは「昔から日本のアニメが好きだったが、2012年のコミコンでコスプレを見て『これだ』と思った。
2013年からコスプレーヤーになり、今回の衣装もすべて手作りして臨んだ。
進撃の巨人のストーリーが好きで、キャラクターも魅力的」と語った。
文・取材・撮影:ライター 戸塚伎一
●スマイルブームを直撃
独自開発のBASIC言語によるプログラミングを楽しめる、スマイルブーム開発のダウンロード専売ソフト『プチコン』シリーズ。
現時点での最新作となるニンテンドー3DS用ソフト『プチコン3号SMILE BASIC』(以下『プチコン3号』)のこれまでとこれから、そして、2016年夏リリース予定のWii U用ソフト『プチコンBIG』の最新情報について、北海道札幌市のスマイルブーム本社で伺ってきた。
■『プチコンBIG』のリリースは、そう遠くない!?
――まずはWii U用ソフト『プチコンBIG』の進捗はいかがでしょうか?
小林大枠はほぼでき上がっています。
先週くらいまでは、ふわっと順調にいってたんですけど、別々に調整していた各環境が、最終的に作り込んでいったらどんどんぶつかりはじめて……。
これ以上話すと、ただの開発環境の愚痴になるからやめますけど(笑)。
――そこはひとまず、クリアーして。
小林なんとか。
細田まあ、大変な機械ですね
小林『プチコン3号』との互換性という意味では、従来のスクリーンモード(0〜4)を使う範囲では、まったく問題ありません。
作品の公開サーバーも共通なので、どちらで制作したものでもダウンロードできます。
――同一のプログラムで、Wii U、3DSでそれぞれ異なる挙動をさせることも可能でしょうか?
小林機種判定をしてモード切替できるようにしているので、がんばれば作れます。
共有できないのは、ローカル通信命令とマイク命令かな。
命令のフォーマットが全然違うので。
細田“XON WiiU”命令で起動させると、さまざまな拡張命令を使えるようになります。
小林Wiiリモコンを4本接続できたりします。
いまはリモコンの音声出力のところで苦労していますが、こういう周辺機器をどこまで対応させるかというのはキリがないですよね。
『WiiFit』はどうするんだとか。
あと、最近やっと気づいたのが、Wii U GamePadのバイブレーション機能。
これ、忘れていたねってなって、命令の名称を決めるのにやたらと時間がかかりました(笑)。
――総当たり的というか……ご苦労されているんですね。
小林Wii U GamePadだけでも動くことがけっこう重要なので、単純にふたつぶんのゲーム機用に作っているがゆえの大変さもあります。
ただ、こういう末節の部分に手をつけられるようになったという意味では、もう終わりが近いです。
細田あまり延ばすと、新機種が出ちゃいますからね(笑)。
――ソフトの価格は?
小林まだリリース日も発表していないので、いまのところは『プチコン3号』よりはお高くなります……ということで。
細田お布施したいと言ってくださる大人の方が、けっこういるんです。
「何でもいいから売ってくれ」と。
――BASIC保存委員会的な。
それだけ、コンシューマハードのプログラミング環境は貴重なものだということですね。
小林『プチコン』が好きな方が、5年ほどついてきてくれています。
「この会社があるうちはこういうヘンなものが出る」という期待で買ってくれているところが、あるようです。
■『プチコン3号』成熟の方向性
――『プチコン3号』がリリースされてから、もうすぐで2周年を迎えようかというところですが、ここまで運営・展開してきての感想は?
小林初代の『プチコン』(※2011年発売。
ニンテンドーDSi用ソフト)は初っ端にばーっと売れて、そのあとは1日数本ペースで売れていきました。
『プチコン3号』もしばらくはそんな感じだったのですが、オバマさん(アメリカ合衆国大統領)がプログラミング教育に関する発言をしてから急に持ち直して、いまもだらだらと売れて続けています。
――『プチコン』の企画の際には、プログラミング教育が注目される時代の流れを、ある程度意識されていたのでしょうか?
小林ない……ですね。
僕が作りたかったから作ったものです。
プラットフォームをニンテンドーDS(3DS)にしたのは、子どもたちではやっている、売れていた環境だったから。
おっさんユーザーよりも、子どもたちに触ってほしいという気持ちがありました。
もともとが黒い画面に文字……という、表面をどんなに飾りつけても限界があるソフトなので、MiiverseやTwitterで発信された情報をキャッチし、あとはユーザーさんどうしの交流に任せるという形でフォローしていきましたね、
――ユーザーが作った作品で、これはすごいというものはありましたか?
小林グラフィックをいじれる人たちの作品は、絵的にすごいものがたくさんあります。
グラフィックはプリセットのキャラクターを使用していても、アイデアで“やられた感”があるものはいまだに出てくるので、そういう意味では楽しいです。
細田技術面では「こんなことできるようには作ってないぞ」というものが、けっこうあります。
――そこはやはり、セミプロの犯行というか……。
細田ずばり、プロですね(笑)。
小林逆に、セオリーを知らないがゆえに、すごいものができているケースもあって。
細田『プチコンmkII』(※2012年発売。
ニンテンドーDSi用ソフト)以降は、「とりあえず速く動くようにしておけば、(最適化されていないプログラムも)力技で何とかなるだろう」という気持ちで作っています。
それにしても、3Dモデルを使ったりとか、『DOOM』みたいな一人称視点アクションゲームを作ってみたりとか、ふつうはやらないよねというのが……。
最近では、PC-8001(※NECが1979年にリリースした8ビットCPUパソコン)のエミュレータを作っている方もいましたね。
――はぁ!?
細田BASICで作ったエミュレータにPC-8001用のプログラムデータを読ませると、実機の6割程度の速度で動くそうです。
――もうなんか、正気の沙汰ではないですね!というか、こういうのはアリなんですか?
小林当時の市販ソフトのROMイメージが同梱されていたりするとさすがにまずいですが、これ自体はただのエミュレータなので、我々が関知するところではないかなと。
――これもまた、細田さんの設計思想が実を結んだ形である……と。
細田ふつうやらないですけどね(笑)。
あと『プチコン3号』は、絵作りの面で若干ハードルが高かったんですけど、グラフィック作成ツールを作るのが好きな何人かによって便利なツールが断続的に更新され、それらを使った優れたグラフィックのゲームが開発される……というサイクルができています。
我々は、「キミたち、そこまでやるんだ」と思いながら、見守っています(笑)。
小林『プチコンBIG』ではWii U GamePadが使えるので、お絵かきという点ではもっと環境がよくなると思います。
ちょっとした商業ベースの2Dゲームくらいなら作れると思います。
――『プチコン』シリーズ以外にも、ゲームプログラムコンテンストの開催や、ユーザー投稿作品集『プチコンマガジン 創刊号』のリリース、プログラムリストページが延々と続くムックを監修されたりと、ゲーム会社としては独自の活動をされています。
今後もそういった活動は?
3DSでゲームをプログラミングできる『プチコン3号 スマイルベーシック』の公式マガジンが6月27日に創刊決定
小林もちろん、やっていきたいと思います。
このあいだ任天堂さんが発表した個人クリエイター登録制度は、いざ開発機を買うとなると何十万円もしてなかなか手を出しづらいと思いますが、『プチコン』ならもっと安くお手軽に、任天堂ハードで動くゲームを作れるので、そういう需要には応えていきたいですね。
――『プチコン3号』で作った自作ゲームをニンテンドーeショップ(ニンテンドー3DS、Wii Uを対象としたオンラインストア)で販売できるようにする仕組み作りにも、多くのユーザーが期待を寄せていると思われます。
小林『プチコンマガジン』を作るのにもそこそこ手間がかかるので、もうちょっとラクにユーザー作品を世に出せる方法を考えています。
漠然と話している段階なんですけど、“◎◎さんの作品を遊べるプレイヤー”という形でショップでリリースして、作品ひとつひとつを“追加コンテンツ”として提供するのはどうだろうと考えています。
プラットフォーム内プラットフォームという形にはなりますが、ショップの仕組み自体はすべて親のプラットフォームを使うから、問題ないんじゃないかと。
仕組みとしては、『プチコン3号』と、バンダイナムコエンターテインメントのカタログIPコラボ素材との関係に近く、いろいろと柔軟にいけそうな気がします。
――それはかなり現実的なアイデアですね!
細田この間思いついたばかりなんですけどね(笑)。
小林一番大きいのは、ユーザーさんが何か出す際にも必要になる、CEROの審査費用をユーザーに負担してもらうわけにはいかない、という点です。
うちががんばってプレイヤーの審査を通して、そこに乗るコンテンツをうちで管理・チェックすれば、審査基準に見合ったものだけが流通する、『プチコン』を持っていないユーザーも『プチコン』製のゲームを遊べる……というわけです。
――感覚的にはSteam(米Valve社が運営する、PCゲームダウンロード販売サイト)に近いですね。
小林ニンテンドー3DSの中に入っているSteam……そう言われてみるとそういう感じですね。
いま、こういった位置づけのゲーム制作環境はこれしかないので、何とか維持して、ゲームを作りたい子たちを支援していきたいですね。
――支援しなくても勝手に作っちゃうような人たちも含めて。
小林おじさんたちも結構いますね(笑)。
”――おじさんと言えば(笑)、バンダイナムコエンターテインメントのカタログIPのコラボ素材の続報はいかがでしょうか?『ギャラクシアン』と『パックマン』のデータがリリースされてから(※各100円)しばらく経ちますが。
※Wii U版『プチコンBIG(仮)』の開発が決定!3DS版『プチコン3号 SmileBASIC』との上位互換を実現
細田いま僕が、データを作成しています。
――え?
小林オリジナルと同じものを入れようということで、これがけっこう大変なんです。
細田もともとカタログIPオープン化プロジェクトは「二次創作していいよ」というもので、オリジナルの完コピで作れとはひと言も言われていないのですが、昔遊んだ世代からすると、そのままの状態で出したいじゃないですか。
――たしかに、オリジナルのグラフィックデータがバンダイナムコさんからもらえる、という仕組みではありませんが……。
細田『ギャラクシアン』、『パックマン』までは順調だったんですけど、つぎは『ギャラガ』、『ゼビウス』、『マッピー』だなとなったときに、「これは大変だぞ」と。
決して手を止めているわけではなく、毎日1〜2時間、泣きながらドットを打っています。
――ええと……ドット絵を作成しているのは細田さんおひとりなんですか。
細田はい。
――『プチコン』のメイン開発者がみずからコラボ素材も作っているって、おかしいでしょう!
細田『プチコン』本体ですらそんなに利益を出していないのに、その追加素材となると売り上げがさらに落ちるので、ほかの人に発注できないんですよ。
――そのような生々しい事情が。
細田とは言え、『ギャラガ』と『マッピー』はリリースの準備ができつつあるので、そろそろつぎのタイトルに取りかかろうかなと思っています。
■プログラミング学習の潮流に際し、スマイルブームの舵取りは?
――昨年、大阪府立泉尾高等学校でのバソコン演習の教材に『プチコン3号』が導入されて以降、プログラミング学習関連の活動も精力的に行っているようです。
こうした分野は今後も意識的に関わっていくのでしょうか。
[関連記事『プチコン3号 スマイル ベーシック』がプログラミングの実習教材として学校教育に導入決定
小林意識しているようでしていないところがあるんですけど、できる範囲でやっていっているところはあります。
我々は別に先生ではないので、「けっきょく、プログラミング学習で何ができるの?」って言われると何とも言えないのですが。
やれることをやっていこう……という意味では、先日も愛別(北海道上川郡愛別町)の教育委員会の要請を受けて、小学生向けプログラミング体験のワークショップを行いました。
――少し前に小林さんのSNSアカウントで、ニンテンドー3DS本体を大量に購入したとの投稿がありましたが、今回のイベント合わせだったんですね。
小林そうなんです。
今回初めて、低学年の参加者が多いイベントだったんですけど、アルファベットは読めない、ニンテンドー3DS本体を触ったことがないという子がけっこう多くて、何をしようかと悩んだ結果、はじめにコンピュータの仕組みに関する話を軽くして、残りの時間で4〜5行程度のプログラム10個をできるだけ入力してもらうことにしました。
案の定、4個くらいが精いっぱいだったんですけど、低学年の子たちも文字を記号として認識しながらがんばって入力して、おのおの実行結果を確かめることができたようです。
――そこにはちゃんと、感動体験があったと。
小林入力した文字がそのまま表示されるというプログラムは、実行してもピンとこない子たちがいたのですが、音が出たりスプライトのキャラクターが表示されるプログラムの反応はよかったですね。
おもしろさを感じるのはこのへんかな、ということがよくわかりました。
細田それまでのワークショップは、いきなり200行くらいのプログラムを打ちましょう、みたいな苦行を強いる内容だったので、今回でやっと(小林氏が)気づいてくれたようです。
――細田さんはワークショップ活動はされていないんですか?
細田僕はしていないです。
後ろから文句言うだけです(笑)。
小林これまでの子ども向けワークショップは、親がいっしょについて参加する形で、それで何とかなっていたこともあって、(方針転換する)踏んぎりがつかなかったんです。
ただ今回はそうではないということで、思いきってシンプルな内容にしてみました。
――ふつうの子どもたちにとってのプログラミングのハードルは、小林さんが想定していたよりもだいぶ高かったと。
小林そうですね、ふつうに考えて。
ただ、こういったイベントを経験することで、素養はまったくのゼロではない子どもたちになったはずです。
大人がきっかけを与えない限り、触れることは一生ないかもしれない分野なので、今後何か気づくきっかけにはなっていると思います。
そういう意味では、愛別町の教育委員会の考えかたはおもしろいなと思います。
――ひょっとしたら、BASICに理解のある第一次パソコン世代が、活動方針の決定権を持つ役職についている影響もありそうですね(笑)。
小林たしかに、教育委員会の方が、1980年代にBASICをやっていたと仰っていました。
担当者も昔『ベーマガ』(※電波新聞社が発行していたプログラム投稿雑誌『月刊マイコンBASICマガジン』の略称)読者で……みたいな話をしましたね(笑)。
――2020年度からの、公立小学校でのプログラミング学習の必修化に際し、スマイルブームさんでアクションを起こされたりはするのでしょうか?
小林『プチコン』はメインの仕事の片手間で作っている商品なので、本格的に何かできるかと言われたら難しいですが、求められればできる限りやっていきたいと思います。
――個人または団体で『プチコン』を広めたい、教材にしたいという動きにたいしては?
小林けっこう自主的にやられているところが、ぽつぽつできているようです。
先日も広島県のPC教室の方から「『プチコン』を教室で使うには許可が必要ですか?」という連絡がありましたが、まったく問題ありません。
むしろ、わからないことがあれば説明しますし、必要とあれば、うちで作った講義用資料を送ったりもできます。
──AI、人工知能によるディープラーニングの流れに関して、何か思うところはあるのでしょうか?
細田先進的なことやろうとすると、どうしてもやっぱりやることが高度になっちゃうので、あくまでも初心者向けの環境を考えた時に、そのあたりの要素は、盛り込みづらいですね。
ディープラーニングをやろうとすると、まずその説明が必要になりますし、数学的な話も前提として避けられなくなるので、小学生には絶対無理だなと。
――スマイルブームの基本姿勢としては、そういう高度な話題に興味を持つ前段階を今後も担っていきたい……ということでしょうか。
小林初っ端としての手軽な環境を提供したいですね。
細田その環境であえて無茶をしたい人は、してもらえばと(笑)。
――少し気が早いですが、『プチコンBIG』以降の展開についてどのようにお考えか、教えてください。
小林BASIC作りは僕らの趣味なので(笑)、これからも続けていくと思いますが、これまでと同じコンセプト・方向性でそのまま次世代機にいくか、より初心者に寄るか……悩みどころではあります。
――BASICよりもさらに初心者向けとなると、Scratchのようなブロック言語などもありますが。
小林Scratchのような仕組みは、『プチコン3号』上でも全然作れると思います。
わりとふたりとも「作っちゃえばいいじゃん」という考えかたが、根底にあるんです。
何かを作るための環境を快適な状態で用意すれば、リッチなコンテンツは誰かが作ってくれるだろう……という期待はありますね。
――理論学習に特化させるよりも、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の土台としての特性を維持する方向になりそうですね。
細田当初考えていたことは『プチコン3号』と『プチコンBIG』でほぼほぼ実装できたので、さあつぎは何やろうかなというのはあります。
小林つぎは3Dだって話も、あるにはあります。
――おおっ!
細田グラフィックが3Dになると、ハードルがいきなりがくんと上がるので、そこのフォローが難しいですね。
いざ手をつけるまでに準備しなければならないものが増えるんです。
小林『SmileGameBuilder』(スマイルブームが2016年9月8日にリリース予定の、PC用RPG作成ソフト)のグラフィックが、2Dと3Dの境界をいい感じで橋渡ししているので、あの仕組みがもしかしたら使えるかもしれななぁと思っています。
――実現化、気長に期待しています!
文・取材:編集部 ブラボー!秋山、撮影:カメラマン 永山亘
●『ドラゴンクエスト』30周年を駆け足で振り返る濃密な80分
2016年8月24日〜26日の3日間、パシフィコ横浜で開催されている、日本最大級のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2016”。
3日目の基調講演は、“ドラゴンクエストへの道〜ドラゴンクエスト30周年を迎えて〜”。
登壇者に、堀井雄二氏(ゲームデザイナー)と斎藤陽介氏(スクウェア・エニックス)を迎え、多くの聴衆の注目を集めたこの基調講演の模様をお届けしよう。
『ドラゴンクエスト』30周年を迎えた2016年。
それを記念して、今回の基調講演では、“いまだからこそ聞きたいドラゴンクエストの開発にまつわる話”をテーマに、事前に公募した多くの質問に、堀井・齊藤両氏が答える形式でのセッションとなった。
メインホールで行われたこの基調講演だが、開場30分前にはすでに満席となる盛況ぶり。
さすが国民的RPG『ドラゴンクエスト』と言ったところか。
●知っているようで知らない!? 堀井氏の深〜い経歴
基調講演の冒頭は、堀井雄二氏がゲームデザイナーに至るまでの経歴について。
小さいころからゲームが大好きだったという堀井少年は、『スマートボール』(いまでも温泉街などで見かける、ピンボールのような遊技機)を工夫して、独自のゲーム台を作ったり、麻雀牌を利用したすごろくのようなルールのゲームを作っていたという。
また、堀井氏が漫画家志望だったことは有名だが、「子どものころになりたかった職業は弁護士」と言う発言には、齊藤氏も「それは初耳でした」と驚いていた。
そして高校3年の夏休み、マンガ原稿を持って上京し、某漫画家の自宅を訪ねた堀井氏。
しかし、自信作に対する先生の反応がイマイチで、「これはダメだな」と思ったものの、その後大学に進学し、漫画研究会に入ることとなった。
漫研の先輩に編集者がいた関係で、フリーライターとして活動していたころは、なんと『セブンティーン』の記事を書いたこともあったそうだ。
そのころの堀井氏は、「このままライターで食べていけるな」と思っていたのだが、ある日転機が訪れた。
忘れもしない27歳のとき、テレビに接続できて、約10万円のパソコン“PC-6001”を購入。
触りながら徐々に覚えていき、こうして、プログラムから自作ゲームの開発へとのめり込んでいったわけだ。
最初に作ったのは、占いのソフト。
占う人が決まっていたので、前もってその人の情報を入れておいたところ、よく当たるので「すごく驚かれた」と笑った。
その後、堀井氏が作ったゲームが、かの『ラブマッチテニス』や『ポートピア連続殺人事件』というわけだ。
フリーライターとしても活動していた堀井氏は、面識のあった集英社の有名編集者・鳥嶋氏から、ある取材を依頼されることになった。
それは、エニックス(当時)が開催した“ゲームプログラミングコンテスト”。
取材するついでに『ラブマッチテニス』を応募したところ、見事に入選。
またこのコンテストで、森田和郎氏(のちに『森田将棋』を制作)や『ドアドア』を応募した中村光一氏らと知り合うことに。
フリーライターを生業としながらも、続く『ポートピア連続殺人事件』でゲーム業界に名前が知られるようになった堀井氏は、やはりライターという稼業からか、シナリオも重要な要素であるアドベンチャーゲームに魅力を感じるようになったようだ。
ちなみに『ポートピア連続殺人事件』は、冒頭と最後を最初に作り、後から残り(コマンドを入力するシステムなど)を作ったそうだが、この時点で、すでにゲーム作りのノウハウを独学で習得していたと言えるかもしれない。
同時に、『ウィザードリィ』をはじめ、パソコンのRPGを相当やり込んでいた時期でもあり、『ドラゴンクエスト』シリーズの“根幹”のようなものが形成されていた時期なのだろう。
『ポートピア連続殺人事件』に続き、『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』、そして『軽井沢誘拐案内』を作ることになるわけだが、『軽井沢誘拐案内』の終盤にはRPGを意識したゲームシステムが導入されている。
●『ドラゴンクエスト』誕生の経緯、『DQ』〜『DQX』30年の思い出
ここからは、いよいよ本題へ突入。
まず、『ドラゴンクエスト』というタイトルについて聞かれた堀井氏は、すでになじみのある“ドラゴン”と、逆に当時はまだなじみのない“クエスト”を組み合わせるといいなと思ったそうだ。
そして、初代『DQ』から『DQX』まで、駆け足で思い出を振り返った。
『ドラゴンクエスト』・・64キロバイトという容量。
いろいろなものをそぎ落としながら、形にしていった。
『ドラゴンクエストII』・・初代『DQ』から容量が倍になり、パーティープレイが可能になったが、いきなり増えても変なので、最初はひとりでスタートし、だんだんとパーティーを集めるスタイルに。
『ドラゴンクエストIII』・・さらに容量が増え、キャラクターの職業を選択する要素などを入れることができた。
『ドラゴンクエストIV』・・『DQIII』が大ヒットして、本当にプレッシャーがあったという。
『DQIV』から始める人もいるだろうから、全5章のオムニバス形式を取った。
『ドラゴンクエストV』・・プレイヤーを本気で悩ませたかった。
そして、主人公の世代が変わっていく要素も入れた。
『ドラゴンクエストVI』・・どんな遊びを入れようか悩んだ。
それで、いきなりふたつの大陸を行き来できたらおもしろいだろうと考えた。
ただし、シナリオが破たんしないように。
※齊藤氏は、本作から開発に参加
『ドラゴンクエストVII』・・プラットフォームがPSになり、容量が格段にアップした。
シナリオに藤澤仁氏らが参加。
『ドラゴンクエストVIII』・・アイデアが出尽くした感があったが、たまたまレベルファイブと出会い、彼らが後方視点の3Dグラフィックを提案してくれた。
『ドラゴンクエストIX』・・ニンテンドーDSで発売されたことで、外に持ち運ぶという要素が生まれた。
“まさゆきの地図”など、テレビの前だけではない遊びかたの提示。
バーチャルがリアルを侵食した。
『ドラゴンクエストX』・・オンラインゲームとして、10年ほど前から構想があった。
続いては、“皆さんからいただいた質問にお答えして行きましょう”のコーナー。
興味深い質問が多かったので、コメントともども抜粋。
コマンド?
Q.ファミコン版の初代『DQ』では、戦闘モードに入ると「○○があらわれた!コマンド?」というメッセージが表示されるが、2作目以降でなくなった。
そもそも、なぜ“コマンド?”というフレーズがあったのか?
堀井言われるまで気づかなかったね(笑)。
齊藤これは、パソコンでアドベンチャーゲームを作っていたころの名残ですよね。
それで、『DQII』以降はいらなくなったと。
バランス調整について
Q.おもに終盤のバランス調整やデバッグが気になっている。
時間や人数はどのくらいかけているのか?
堀井一概には言えないですが、1ヵ月くらいはプレイデータを集めることに使っていますね。
齊藤堀井さんが設定したポイントごとに、キャラクターのレベルや装備などを報告していました。
国民的RPGだけに、どういった層を意識してます?
堀井自分の感覚ですね。
そんなにマニアックでもないし。
でも、バランス調整は本当にギリギリまでやっています。
マスターがあがっても、「もし、つぎにバグが出たら、変えてもらおう」と(笑)。
シナリオについて
Q.10年間はサービスを継続したいという『DQX』は、Ver.1の時点でどこまでシナリオができていた?また、現時点でどこまでシナリオができている?
齊藤Ver.3で登場する竜族は、Ver.1の時点ですでに決まっていました。
Ver.4は、つい先日いろいろな話をして、ある程度の骨格ができてきたけど、それ以降、Ver.5はこれから。
マップについて
Q.『DQ』では、ゲーム開始時に“竜王の城”を望むことができるが、その意図とは?
Q.“アレフガルドのワールドマップはどこから描き書き始めた?
堀井最初から目的地を示したんです。
ただ、最初はそこへの行きかたががわからない。
まずはフィールドマップの形から作り、それから町を配置しています。
まずは、マップを描いてから人を置いて、それから微調整していきます。
命名について
Q.“アレフガルド”という地名や由来や各都市の名前のコンセプトは?
堀井実際の世界地図を何度も見て、ある程度のヒントを得ることが多いです。
齊藤ファンタジーだから架空の名前をつけるというわけじゃないんですね。
堀井「このリアス式海岸は〜」とか。
Q,“クリティカルヒット”を「かいしんの一撃!」と名付けたのはなぜ?
堀井言葉の持つイメージからです。
齊藤温かみがあったり、少し毒のあるようなセリフも多いですよね。
宣伝になりますが、「ドラゴンクエスト名言集」という本が出ていますので。
堀井「あなたはゲームデザイナーに向いていますか」というチャートを作りましたね。
いちばん大事なもの
Q.堀井さんが考える、“ゲームデザイナー”としていちばん必要で、いちばん大事なものとは?
堀井まずは発想力。
そして、その発想力をシステムにするための忍耐。
ダメになったときに、それを捨てる勇気。
★最後に『ドラゴンクエストXI』の話も……
「いっぱい話したいけど、話すと怒られる(笑)」という堀井氏。
昨日も、実際にプレイしながら齊藤氏と長時間の打ち合わせをしたそうだ。
システムはともかく、シナリオに関してはほぼ完成している状態で、現在は3DS版の3D表示を基準にしつつ、バトルのチェックはPS4版で行うなどしているとのこと。
「30年前に作ったときは、こんなに長く続くとは思わなかった。
自分でも感無量。
ありがたい。
」と『ドラゴンクエスト』30周年を振り返る堀井氏。
ゲーム業界も変わってきて、表現できることが増えてたがゆえに、逆に難しくなってきたと感じているという。
また、ゲームをプレイする時間があまり取れない人に向けても、最初に「おもしろそう」と思わせる“つかみ”が重要だと語る。
その堀井氏は、サバゲーを楽しんだり、『人狼』のイベントに出演するなど、つねにアンテナを多方向に広げている。
ゲームはもちろん、ゲームに限らず、いろいろなエンターテインメントに触れることは重要だと感じた基調講演だった。
PS4/Xbox One/PCで2017年1月24日に発売を予定するカプコンの「バイオハザード7 レジデントイービル」は、去る6月に開催されたE3 2016に合わせてPlayStation VRへの完全対応を発表し、ゲームファンやVRファンを大いに驚かせた。
驚きの内容の最たるものは、VR対応がスピンオフやオプション的なものではなく、フルボリュームのホラーアドベンチャーゲームである本作を、隅々まで全てVRでプレイできるという、まさに完全対応を果たすというところだ。
CEDEC 2016では「『バイオハザード7レジデント イービル』におけるVR完全対応までのみちのり、歩みの中の気づき」と題されるセッションが行なわれ、本作のVR完全対応についての内幕が詳らかに語られた。
登壇したのはカプコン技術研究開発部、技術開発室プログラマの高原和啓氏。
カプコン内製の最新ゲームエンジン「RE ENGINE」の開発コアメンバーとして基盤技術を担当する高原氏は、「バイオ7」においてはVR完全対応のサポートも担当し、かたちとしてはエンジンとタイトルを同時並行開発するというハードワークで、本作の開発に貢献している。
その高原氏によれば、「バイオ7」で謳うVR完全対応という言葉が示す開発のゴールは、「ゲームを最初から最後までPlayStation VRでプレイできること」。
とはいえ、「バイオ7」はもともとVR非対応のタイトルとして開発が進められており、途中からVR完全対応を果たすというのは簡単なことではない。
しかも、VR対応に向けた作業がスタートしたのは、「バイオ7」自体の開発開始から2年近くを経過してからのことであった。
開発中のゲーム(しかもAAAクラスのボリュームを持つ完全新作)を、途中からVRに完全対応させるというのは、高原氏が「世界初の試みではないか」というとおり、他に例のないケースだ。
多くの場合、VRゲームは、最初からVR向けに設計開発すべきだという考えがこの業界にはあり、リリース後にアップデートやユーザーMODでVR対応を果たしたタイトル(PCでいくつか存在する)も、VRはあくまでオプショナルな位置づけに置かれているケースが多い。
果たして、高原氏は「バイオ7」のVR完全対応という、他に誰もやったことのないプロジェクトをいかにして形にすることができたのだろうか。
そのあたりを本セッションでは詳しく聴くことができた。
■「KITCHEN」をきっかけに始まった「バイオ7」のVR対応プロジェクト
本作のVR対応について、「誰もやっていないことに挑戦するのは、開発者としてやりがいを感じた」と語る高原氏だが、実際、その試みのユニークぶりを、「実はだれもやりたいくないだけでは?」と表現している。
というのも、一般に言って、VRで快適に遊べるゲームを作るには、既存のゲームを途中からVRに対応させるよりも、はじめからVRタイトルとして作ったほうがずっと楽だからだ。
しかも「バイオ7」そのものは2014年1月から本格的な開発がスタートしており、VR完全対応を決めた2015年10月時点で、すでにゲームシステムのほぼ全てが実装済みであった。
ノンVRゲームとして設計された「バイオ7」を後からVRに対応させるには、基本操作、UI、演出、その他の細々とした要素を改めてVR向けに作りこまなければならず、「まるで2つのゲームを同時に作るようなものだった」と、高原氏も語っている。
そもそもなぜ、ゲーム本体の開発がかなり進んだ段階でのVR対応を決めたのだろうか。
それは、2015年3月のGDC 2015初披露された、およそ3分間のホラーVRデモ「KITCHEN」の存在がある。
「KITCHEN」自体は極めて実験的要素の強い作品で、VRにおける恐怖体験の検証、VRタイトル開発の基礎検証、そしてPlayStation VR向けの開発環境の整備、といった目的で作られた。
つまりその前の時点では、「バイオ7」のようなタイトルをVR対応させることの価値は明瞭でなく、そのための開発基盤といった体制の部分も、準備が整っていなかったということである。
PS VR(当時はProject Morpheus)自体が開発の途上にあったのだから仕方がない。
そして実際に「KITCHEN」をE3 2015やTGS 2015で披露したところ、非常に強いフィードバックを得られたことが、「バイオ7」のVR完全対応という決断に繋がる。
「KITCHEN」の開発によってPS VR向けの開発基盤も整い、VRタイトル開発のノウハウも、多少ながら得られた。
それに加えて体験者の反応も上々であったことが、開発陣に「バイオ7」自体をVR化しようというモチベーションを与えた、というわけだ。
高原氏によれば、もともと、「バイオ7」自体が2014年1月の開発開始当初から、ぼんやりとではあるがVR対応を計画していた、ということも、この決断には有効に作用している。
本作は「バイオ」シリーズで初めての主観視点カメラの作品であり、主観視点のゲームは基本的にはVR対応をしやすい。
ゲームの設計として、最初からベースになる要素を持っていたわけだ。
□「VR疲れ」の回避と、快適なプレイのための数々の調整と変更
VR完全対応への作業がスタートした2015年10月から、ほぼ8カ月後の2016年6月のE3 2016までの間に、本作のVR対応はひとまず、E3デモという形で果たされた。
そこでは、通常の画面でプレイするノンVRモードとは異なる点がいくつもある。
ただプレイしただけでは気づかない点も多く、今回、高原氏のセッションでそのあたりのノウハウが明らかになったのは多くのゲーム開発者にとって収穫といえるだろう。
本作のVR対応にあたって、エンジンとゲームの開発チームにとって非常に重要なキーワードとなったのが「VR疲れ」だと高原氏。
VR疲れというのはカプコン内部の用語で、VR特有のVR酔いや、HMD装着にともなう眼精疲労といった肉体的・神経的な負担を総称したものだ。
経験者なら理解できることと思うが、酔いの激しいVRコンテンツをプレイしたり、そうでなくても長時間HMDを装着したあとに感じる、頭の芯からグッタリしてしまう、あの感じのことである。
VR疲れの要素のうち、VR酔いについては各所で語られていることなので高原氏は触れなかったが、もう1つの要素、眼精疲労については、その構成要素として「ステレオ違反」、「深度違反」といったものを挙げている。
例えば、オブジェクトの影が左右の映像で異なるように表示されたり、左右のカメラでLODレベルが異なるオブジェクトが表示されたりすると、立体視を得る際に齟齬が発生し、オブジェクトのエッジ等がちらちらとブレて見える(ステレオ違反)。
また、UI要素など、深度情報を無視して描かれるオブジェクトが、他のオブジェクトに重なって表示される際、ピント合わせが困難になり、ユーザーの視覚におかしな負担をあたえてしまう(深度違反)。
VR疲れは非常に不快な感覚をユーザーに与えるだけでなく、実際に消耗を強いる。
高原氏によれば、デバッグのため「バイオ7」のVRモードをプレイするスタッフの中にはひどいVR疲れのためその日は仕事ができなくなるようなケースもあったという。
それで、チーム内では「VRのデバッグは定時後にしよう」とか、「バイオ7は金曜にやろう」といった風潮があったとも。
未調整のコンテンツをプレイしなければならない開発者勢は大変である。
VR疲れへの耐性には大きな個人差もあるというが、高原氏自身は、最初は非常にVR疲れを感じやすい体質であったものの、1日何時間もチェックする仕事を続けているうちに、慣れてしまった。
無意識にVR疲れをしにくい操作をするといったものだ。
この、耐性が養われてしまうというのは開発者にとって痛し痒しなところ。
業務効率は上がるが、今度はVR疲れを感じやすい人の気持がわからなくなってしまうという副作用がある。
というわけで高原氏は、VRタイトルの品質管理について、VR疲れを誘発する表現を知識として蓄えることに加えて、社外の品質管理サービスを用い、VR耐性の少ないスタッフにテストしてもらうことが重要だと語っている。
また、快適なVRを作るためのノウハウ共有について、ソニー・インタラクティブ・エンターテインメントノウハウVRコンサルテーションチームに「非常にお世話になっている」と高原氏。
こういった品質管理体制を得た上で、「バイオ7」のVRバージョンでは、通常モードから数多くの改変が行なわれている。
以下に重要なものを挙げてみよう。
・スナップターン
本作のE3デモ版では、スティックによるカメラ移動操作を採用しており、スティックを倒すと視点が滑らかに回転していた。
だがこの表現はVR酔いを感じる人が多いということで、最新のバージョンでは「スナップターン」というテクニックが実装されている。
これは、スティックを倒すたび、非常に高速に30度の回転が行われるというものだ。
他のVRタイトルでもこの手法を取っている例がいくつかあるが、これによりVR酔いは軽減されるのは確かである。
ただし、回転が完全に一瞬であると臨場感の低下や空間識失調を招くことがあるため、本作では数フレームをかけてある程度なめらかに回転する手法をとっている。
・遅延追従する懐中電灯の明かり
通常モードでは、プレーヤーのカメラ操作に少し遅れる形で、懐中電灯の明かりが追従してくる。
これは、視点操作について「まず顔を向けて、それから胴体がついてくる」という動きを反映したものだ。
しかしこれをVRでやってしまうと、画面自体が遅延しているように感じられ、VR酔いを誘発してしまうという。
そのため、VRモードでは明かりが即時追従するように調整された。
・移動速度、しゃがみモーションなどの調整
屋内の狭い空間を動き回ることの多い「バイオ7」をVRでプレイすると、左右に迫る壁面の効果で、等速移動であっても幻視的な加速度を感じられることが多いという。
VRでの加速度感は、VR酔いの原因となるベクションを強く引き起こす。
これを避けるため、通常モードでは約6.1km/hとなっている移動速度を、VRモードでは約4.2km/hに低速化している。
また、通常モードに存在する歩行・走行時のカメラの揺れも、VRモードではカットされている。
また本作では、しゃがむことによって狭い通路を通るといったアクションも基本要素となっているが、通常モードでは立つ/しゃがむの遷移に0.5秒ほどをかけ、なめらかに動作するように調整されていた。
VRではこれが酔いの原因となってしまうため、VRモードでは0秒、つまり1フレームでしゃがみ状態に遷移できるようになっている。
・各種イベントにおけるカメラ制御
本作ではドアやピアノ、冷蔵庫、その他の様々なガジェットを操作できる。
通常モードでは、インタラクトイベントの発生時に時に主人公の手が表示され、規定のイベントアニメーションが再生される仕組みになっている。
しかしVRモードでは、そういった手のアニメーションは全て削除されている。
なぜかというと、手のアニメーションに際して、表示の破綻を起こさないため、カメラの制御も行なう必要があるためだ。
VRでカメラの強制移動をやらかすと、ユーザーは強く不快な思いをしてしまう、というのがその理由だ。
通常モードで見られる、オープニング時に主人公が立ち上がるイベント等も同様に、強制カメラ制御を伴うものであるため、VRモードではバッサリ削除されている。
このようにVRモードでは、ゲームを通じて、いっさいの強制カメラ制御を取り外すことで、演出性よりも快適さを重視した作りをとった。
プレーヤー自身がホラー空間に入り込むVRでは、むしろそういった演出は最初から不要なのかもしれない。
・複雑なリアルタイムイベントは「2DVR」化
本作では各所のポイントで、複雑かつ長尺のリアルタイムイベントが発生する。
複数のキャラクターの動きや、プレーヤーカメラの複雑な制御によって実現するタイプのイベントだ。
当然、VRでそのまま見せると非常に不快な思いをしてしまう(カメラ制御を完全に奪ってしまうため)のだが、ストーリー進行上重要な意味を持つこの種のイベントをバッサリカットしてしまうわけにはいかない。
そこで苦肉の策、最後の手段としてとられたのが、高原氏が「2DVR」と称するテクニックだ。
これは、プレーヤーカメラをVR空間内にそのまま置くのをやめて、いったん、表示を2Dの矩形画面に切り替え、VRシアター的にイベントシーンを表示する手法だ。
VR的な「その場にいる」感覚は完全になくなってしまうものの、VR酔い等の問題からは切り離される。
まさに苦肉の策であるが、これにより「バイオ7」の全シーンをHMDをかぶったまま楽しめるのだから、作品的に効果ありだと言える。
□VR完全対応へのチャレンジは続く
その他にも本作では、インベントリー画面などのUI要素をVR向けに再設計したり、プレーヤーが手にもつアイテムの表示距離を、VRモードでは特別に調整したりといった、細々な工夫を凝らし、VRでのプレイの快適さ、自然さを確保しようとしている。
高原氏が「2つのゲームを同時に作っているようなもの」と語るのは、まさにそこで、ゲームの全ての要素についてVR向けの検証と改善が必要になるという点だ。
本作はいつでもVR/ノンVRでのプレイを切り替えられるようになっているため、VR対応のために通常モードの要素を犠牲にすることができない。
初めからVRタイトルとして作ったほうが楽だというのはそこで、既存ゲームのVR対応というものに困難が伴う理由だといえる。
2017年1月24日に発売を予定している本作は、上記に紹介した以外にも様々なテクニックが試されているとのことで、今後、発売に向けてさらにブラッシュアップが進むことになりそうだ。
その中で高原氏は、VR対応のノウハウに正解はなく、タイトル毎に最適な手法も異なってくるし、従来のVR開発ノウハウにおいて非推奨とされているものの中にも正解があることもありえるため、まずは考えるよりも試すことが大事だと語っている。
「バイオ7」のVR対応は、大型IPの完全VR化という点で業界初めての試みだ。
それがどのような形に結実するか、楽しみにしたい。
コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 4/3/PlayStation Vita向けタクティカルアクションゲーム「ベルセルク無双」の最新情報を公開した。
公開された情報は、人間と使徒の姿を併せ持つ黒犬騎士団の団長「ワイアルド」がプレイアブルキャラクターとして参戦する。
また「ボス戦」に登場する「フェムト」や「グルンベルド」などキャラクターとの戦闘シーンが公開された。
□プレイアブルキャラクターに黒犬騎士団の団長「ワイアルド」が参戦
「ワイアルド」は、人間と使徒の姿を併せ持つ、黒犬騎士団の団長。
黒犬騎士団は、ミッドランド王国の罪人で構成されていて、残忍さと恐怖で兵士たちを支配している。
「ワイアルド」は、「エンジョイ&エキサイティング」が信条で、棍棒を振り回したり、コミカルな動きをしたりと動きに豪快さがあり、使徒形態になるとさらに破天荒なアクションが特徴となっている。
■「ボス戦」キャラクター個別戦闘シーンの紹介□黒犬騎士団の団長「ワイアルド」
ワイアルドは、棍棒を振り回したりコミカルな動きをしたり、破天荒なアクションが特徴。
使徒形態になるとその奔放っぷりは更に激しさを増す。
□使徒を統べる5人の守護天使「フェムト」
フェムトは、使徒を統べる5人の守護天使「ゴッド・ハンド」の1人で、グリフィスが「鷹の団」の仲間を捧げて転生したもの。
原作では、フェムトが手をかざし、空間ごとひねり潰すような力も見せている。
□チューダー帝国の騎士「アドン」
アドンは、ミッドランド王国と百年戦争を繰り広げた、チューダー帝国の騎士。
名門コボルイッツ家の長男にして「青鯨超重装猛進撃滅騎士団」の団長を務め、戦闘中でも家の歴史や自身の技を雄弁によく語る。
原作では、大げさな名前の技が空回りすることが多いが、槍術の腕自体は侮れない。
□「紫犀聖騎士団」の団長「ボスコーン」
ボスコーンは、チューダー帝国最強と謳われる「紫犀聖騎士団」の団長。
長大な槍斧を愛用しており、原作では一騎討ちで戦ったガッツの大剣を破壊し、その技と力を見せつけている。
ドルドレイ要塞攻防戦で将軍としてチューダー軍を指揮し、ミッドランド軍を迎え撃った。
□「バーキラカ」一族の首領「シラット」
シラットは、暗殺を生業とする「バーキラカ」一族の首領。
暗殺集団として大国に雇われる身分ながら、一族が復権する機会をうかがっている。
「チャクラム」や「ウルミン」といった奇妙な武器を駆使し、変幻自在な身のこなしも脅威となっている。
□盗賊団首領(原作1巻1話で戦う使徒)
盗賊団首領は、原作の第1話に登場した使徒で、コカ城を拠点に盗賊団を率い、町の金品や人質を差し出させていた。
使徒形態は手足がある巨大な蛇の姿をしている。
尻尾を振り回す攻撃でガッツを苦しめた。
□グリフィスが率いる「新生鷹の団」の一員「グルンベルド」
グルンベルドは、肉体を得て現世に転生したグリフィスが率いる「新生鷹の団」の一員。
「炎の巨竜」の異名を持つ豪傑で、竜をイメージした甲冑をまとい、長大な戦鎚と大砲を仕込んだ盾で戦う。
使徒形態に変身すると、巨大な竜の姿となり、鋼玉の皮膚は鋼鉄以上の堅牢さを誇る。
圧倒的パワーに加え、口から吐き出される炎も脅威となっている。
Amazonで購入:ベルセルク無双 PS4ベルセルク無双 PS Vitac三浦建太郎(スタジオ我画)・白泉社/ベルセルク製作委員会
cコーエーテクモゲームス
●9月5日には初の生放送番組を配信!
コーエーテクモゲームスは、『三國志13 with パワーアップキット』をプレイステーション4、プレイステーション4、PCにて、今冬に発売することを発表した。
以下、リリースより。
−−−−−−−−−−
このたび当社は、Windows/PlayStation4/PlayStation3版『三國志13 with パワーアップキット』を今冬に発売することを決定いたしました。
『三國志13』は、「三国志」を生きた英傑のひとりになり、神算の軍師や無双の豪傑たちと、時には力を合わせ、時には競い合い、思いのままに自分だけの物語を作り上げる歴史シミュレーションゲームです。
『三國志13 with パワーアップキット』は、“さらに深まる、百花繚乱の英傑劇。
”をコンセプトとして、発売中の『三國志13』に数々の新要素を加え、英傑たちの生き様を、より深く、より自由に堪能できるように進化させた作品です。
本作は、すでに本シリーズをお楽しみいただいている方はもちろん、これを機にプレイされる方にも、心ゆくまでお楽しみいただける内容となっていますのでどうぞご期待ください。
■ゲーム概要
人間ドラマの集大成である三国志における、最高の武将プレイを表現するため、英傑たちの活躍手段を大幅に拡大する「威名(いめい)」システムを新たに加えました。
また、中国大陸における要衝をめぐる深い駆け引きが展開する戦略や、地形を駆使した采配による高い戦術性を実現した戦闘など、武将たちがゲームの中でより輝ける新要素を多数導入しました。
さらに、ファンの方々からのご要望の多かった結婚や子育てなどのイベントの拡充に加えて、三国志後期をはじめとしたシナリオの追加、シリーズ初となる「イベントエディタ」の実装なども行い、シリーズ史上最大のボリュームで、進化した「百花繚乱の英傑劇」が実現します。
■本作のパワーアップポイント
(1)「威名」で極まる、さらに奥深く、さらに自由な武将プレイ
武将として実績を積むことで獲得できる「威名」を名乗ることにより、さまざまな「できること」が開放されていきます。
私兵を率いて中華全土に武名を轟かせる「侠客」や、蓄えた私財を投じて好みの勢力に肩入れする「商人」など、在野でのプレイスタイルが大きく強化されます。
さらに、人心の掌握に長けた「軍師」や、軍勢の運用に能力を発揮する「将軍」など、いっそう多彩な活躍で、仕官後の勢力の中華統一を目指すことも可能となります。
あらゆる身分と立場において、プレイヤー自身の思い描く生き方を三国志世界に刻むことができます。
●新要素「威名」について
新要素「威名」とは、武将が天下に対して名乗る称号のようなもので、プレイヤー武将の生き様を示します。
武将の実績に応じて解禁され、新たな威名を名乗ると、その威名独自の特性を得たり、新たな行動ができるようになります。
また、「小覇王」「南蛮王」など武将固有の威名もあり、武将の個性も楽しめます。
威名には系統があり、仕官専用の威名系統や在野専用の威名系統があります。
それぞれ系統ごとにできることが異なり、同じ武将であっても威名系統や威名が異なればまったく違ったアプローチで『三國志』の世界を生き、楽しむことができます。
◆侠客系
私兵や同志を率いて、民草の味方となる義勇軍の頭領や天下を乱す賊の頭目になれます。
また、闇に潜んで武将たちを狙う刺客・暗殺者になり、歴史の裏を生きることもできます。
●威名の獲得方法、変遷について
各威名には獲得条件が設定されており、プレイヤー武将が三国志世界でどう活躍するかによって、獲得できる威名が変化します。
たとえば侠客系統であれば、無名の状態から、まず世のために働く「大侠客」になるか、世を乱す「賊徒」になるかで、その後の道が大きく変わります。
さらに賊徒になってからも私兵を集めて軍勢を動かす頭領である「賊将」になるか、武将の命を狙う「刺客」になるかという大きな分岐がある…というように、徐々に分野のスペシャリストになることも可能です。
上位の威名であるほど強力で魅力的な特性や行動が解禁されていきます。
様々な武将と絆を結んで人脈を広げ、威名ならではの経験を積むことで自身の道を極め、より特異な存在として三國志世界を思いのまま生きることができます。
●威名イベント
獲得した威名を名乗ると、威名に応じた個性的な専用コマンドを実行できます。
例えば威名「賊徒」を名乗ると、都市の金と兵糧を奪う「略奪」コマンドが実行できるようになります。
略奪コマンドを実行すると、略奪を阻止しようと他の武将から一騎討ちを挑まれることもあり、その威名ならではの展開を楽しむことができます。
また侠者として民の悩みを解決したり、時には刺客として仕事をしたり、君主から登用を持ちかけられたり、といった威名に応じたイベントが発生することがあり、三国志の世界を様々な形で体感することができます。
●武名
(2)大陸全土に拡大する「要衝」をめぐる戦略と、個性が息づく「君令」
大陸全土に存在する集落や地点を「要衝」とし、さまざまな機能をもつ「城塞」を建築することで、戦略上の要にできます。
攻め寄せてきた大軍勢を、「要衝」に布陣したより少ない兵力で防ぐ間に、別ルートからの侵攻を進めるなど、局地戦での勝敗だけではなく、勢力全体の展開を練り上げる戦略が求められるようになります。
さらに君主の戦略方針を示す「君令」の導入により、劉備の「大徳顕示」や董卓の「酒池肉林」など、君主たちの個性が強く感じられる、深い戦略場面が展開します。
●要衝・軍勢士気
本作では、『三國志13』の集落が「要衝」として表現されています。
要衝には五丈原や夷陵といった三国志の戦場として描かれた場所もあり、要衝に「城塞」と呼ばれる施設や軍勢を布陣させて備えることで、大軍勢による侵攻に対しても「要衝」で迎え撃つことで守備側が優位に立つことができます。
また、全国1枚マップの戦略性をより活かすため、行軍中に徐々に士気が減っていく「軍勢士気」も追加されています。
「軍勢士気」は軍勢ユニットの兵力の下にあるバーで表示されており、軍勢士気は進軍につれて下がり、要衝の上で待機すると回復するため、長距離行軍を行うと軍勢士気が低下し戦闘力が大幅に下がってしまいます。
そのため要衝を制圧しながら士気を上げじっくり攻めるか、軍勢士気が低下する前に一気に敵を攻めるかという軍勢運用の駆け引きが攻略のカギとなります。
(3)「軍議」と「戦術」で大きくスケールアップする英傑たちの戦い
新要素・「軍議」では、軍師たちの知謀による「戦術」を巡る論戦が展開します。
戦闘では、山岳や森林、陣といった戦場の要地に配置された「戦術地点」をいち早く確保することで、落石や伏兵などの「戦術」による、これまでにない地形を駆使した戦いが可能になります。
前作から4倍ものスケールアップを果たした戦場を、英傑たちが縦横無尽に駆ける、新たな戦いが始まります。
●軍議について
「軍議」は采配戦闘の開始前に開催される、いわば作戦会議です。
どの「戦術」を戦場に持ち込み、それをどの戦術地点に配置するかを決定・提案することができます。
軍議では、最初に総大将が参軍を任命し、参軍が戦術とそれを配置する戦術地点を決定します。
総大将自ら参軍を務めることも可能で、また戦術の選び方によっては、他の武将から反論が出て舌戦に発展することもあります。
戦術には、山岳で使用でき敵部隊の兵力や士気を下げる「落石」や、広範囲の味方部隊の士気を上昇させる「軍楽陣」など強力な効果を持つものばかりで、いずれも戦場に配置された「戦術地点」や「陣」を制圧することで使用できます。
戦術を使用することで、兵力以外にも逆転の余地が生まれるため、地形を活かした戦況の変化をより実感できるようになりました。
●戦闘画面について
すべての戦場の広さを『三國志13』から約4倍に拡大しました。
スケールアップした迫力の大戦場を体感することができます。
●攻城戦
攻城戦では、陣を守備側が占有しているため、攻撃側は戦術の使用でも、部隊の布陣でも不利を強いられます。
戦術地点を活用して敵部隊を迎撃したり、戦場が広くなったことで増えた侵攻経路から奇襲を仕掛けるなど、『三國志13』にはなかったスケール感のある攻防を楽しめます。
●野戦
野戦では、戦場の拡大や戦術地点の追加により、戦闘での選択の幅が増えています。
写真の場面だけでも、プレイヤー(孫堅軍)には、大量の敵部隊(張角軍)に対して正面から正攻法で攻めるか、画面右上の坂にある「陣」(テントっぽい赤い丸いアイコンです)を制圧し、戦術を使用することで自軍の損害を抑えながら、一気に勝利を狙うのか、という2つの選択肢があり、ユーザーの選択次第で戦況が多彩に変化します。
(4)「三國志」シリーズ史上最大のパワーアップ
結婚、子育て、災害、異民族、放浪軍など、三国志世界での臨場感を深めるイベントを大幅に拡充します。
また、三国志後期をはじめとする新シナリオや、三国志の物語を追体験しながら新要素の理解ができる英傑伝ステージを追加。
さらに「史実武将編集」や「勢力編集」といった各種編集機能に加えて、シリーズ初となる「イベントエディタ」を実装したことで、自分だけの人間ドラマを自由に創り上げることができます。
●武将スチル
パワーアップキットでは、本編の700人に加えて、新規に100名を追加します。
今回は新規に追加する武将、既存から刷新する武将を何人か紹介します。
・曹仁
字は子孝(しこう)。
魏の将で、曹操の従弟。
武芸百般に通じ、弓術、馬術を得意とした。
赤壁の戦いののちは荊州を守備する。
曹丕の代には魏の大司馬を務めた。
・曹洪
字は子廉(しれん)。
魏の将で、曹操の従弟。
曹仁とともに曹操の挙兵に参じた。
軍の中核として各地を転戦し、活躍する。
曹丕の即位後、魏の衛将軍、驃騎将軍を歴任した。
・杜氏
呂布配下・秦宜禄の妻。
秦朗の母。
のちに曹操の側室となる。
夫が使者として袁術の下へ出向くと、下ヒで留守を守る。
子の秦朗は曹操の宮中で育てられた。
・蔡ヨウ
字は伯[ロ皆](はくかい)。
後漢の学者。
隠棲中、董卓に恫喝され出仕。
しかし董卓が呂布に討たれると、厚遇され恩義を感じていた蔡ヨウは悲しんだという。
王允がこれに怒り、彼を処刑する。
・董白
董卓の孫娘。
董卓が暗殺された際、董卓の親族は老幼を問わず殺されたとある。
董卓が政権を握った際には、15歳未満でありながらも渭陽君として領地を与えられた。
・高順
呂布配下。
“陥陣営”の異名を取った武将。
徐州の攻防戦では、夏侯惇と劉備の連合軍を破る。
侯成らの裏切りによって捕らえられ、命乞いする呂布とは対照的に、潔く斬られた。
・陳宮
字は公台(こうだい)。
後漢の中牟県令。
董卓の暗殺に失敗した曹操に同行するが、曹操の非情さに呆れ決別する。
のちに呂布の謀臣となるが敗北して捕らえられ、自ら処刑を望んだ。
・呂玲綺
史実には記載が無い、架空の人物。
呂布の娘で、父親譲りの武勇を誇る。
なお、呂布には厳氏との間に娘がいた。
取り止められたが、袁術の息子との縁談があった。
■ファンの方々とのコミュニケーションをさらに厚く実施
◆公式Facebookページオープン
『三國志13』の公式Facebookを開設いたしました。
公式サイトや公式Twitterとともに、ファンの方々に喜んでいただける情報をより深く配信してまいります。
「いいね!」をした上でお楽しみください。
※『三國志13』公式Facebook アカウント
◆発表された本作に対する疑問にお答えする、第一回生放送が配信決定!
2016年9月5日(月)には、インターネット番組“『三國志13 with パワーアップキット』第一回生放送”をニコニコ生放送とYouTubeLive で配信することも決定いたしました。
発表されたばかりの本作について、プロデューサーがファンのみなさまからの質問などに早速お答えいたします。
番組ではみなさまからの質問やメッセージを8月31日(水)まで受け付けております。
詳細は本作の公式サイトをご覧ください。
■『三國志13 with パワーアップキット』インターネット番組概要
名称:『三國志13 with パワーアップキット』第一回生放送
実施日時:2016年9月5日(月)20:00〜21:00(予定)
出演者:利川哲章『三國志13 with パワーアップキット』プロデューサー
<ゲスト> 北口徒歩2分(ファミ通編集部)
<MC> 天野唯
概要:
発売を発表したばかりの『三國志13 with パワーアップキット』の魅力を、利川プロデューサーが、みなさまからの質問にお答えしながら紹介します。
本作に関する深い情報のほかに、新情報や新企画の発表もありますので、どうぞお楽しみに!
※ニコニコ生放送
※YouTube Live
■商品概要
●『三國志13 with パワーアップキット』商品概要
タイトル名:三國志13 with パワーアップキット
ジャンル:歴史シミュレーションゲーム
対応機種:Windows(Vista/7/8.1/10)/PlayStation4/PlayStation3
発売予定時期:今冬
価格:
Windows版(パッケージ版/ダウンロード版):未定
PlayStation4/PlayStation3(パッケージ版):未定
PlayStation 4/PlayStation 3(ダウンロード版):未定
プレイ人数:1人
CERO:審査予定
●『三國志13 パワーアップキット』商品概要
タイトル名:三國志13 パワーアップキット
ジャンル:歴史シミュレーションゲーム
対応機種:Windows(Vista/7/8.1/10)/PlayStation4/PlayStation3
発売予定時期:今冬
価格:
Windows版(パッケージ版/ダウンロード版):未定
PlayStation4/PlayStation 3(ダウンロード版):未定
プレイ人数:1人
CERO:審査予定
備考:プレイするためには『三國志13』本体が必要となります。
読売ジャイアンツは、コーエーテクモゲームスのタクティカルアクション『戦国無双 〜真田丸〜』とコラボレーションした入場券「戦国無双シート」を8月27日より販売します。
これは、9月27日と28日に東京ドームで開催される「読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズ」の試合の入場券で、購入者には特典として「真田幸村」と「石田三成」のどちらかの特製アクリルキーホルダーが貰えます。
なお、通常の入場券を購入しても、これらの特典は付属されません。
詳細は以下の通りです。
「戦国無双シート」
■対象試合
9月27日(火)、28日(水)巨人対中日戦(午後6時試合開始)
■「戦国無双シート」を販売
特典グッズ付きの「戦国無双シート」を上記対象試合で販売します。
ジャイアンツとコラボした戦国無双に登場する主要キャラクター、真田幸村と石田三成の「オリジナルアクリルキーホルダー」のうち、どちらかが特典に付きます。
《座席/料金》
戦国無双シートB(真田):4,500円
戦国無双シートB(石田):4,500円
戦国無双シートFC(真田):2,900円
戦国無双シートFC(石田):2,900円
戦国無双シートC(真田):2,800円
戦国無双シートC(石田):2,800円
《発売日》
<一般販売>
8月27日(土)午前11時から販売開始
《購入方法》
CLUB、G-Poチケット、チケットGIANTS(コールセンターを除く)、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケット、東京ドーム、セブンチケットで一般販売。
「戦国無双シート」は,「指定席B」、「指定席FC」、「指定席C」エリアに設置します。
購入の際は、必ず「戦国無双シート」と記載されている座席をお買い求めください。
通常の「指定席B」、「指定席FC」、「指定席C」エリアの座席を購入された場合、特典はお渡しできませんのでご注意ください。
『戦国無双 〜真田丸〜』は、PS4/PS3/PS Vitaを対象に、2016年11月23日発売予定。
価格は、PS4/PS3版が7,800円+税、PS Vita版が6,800円+税です
遊べるソフトは400本以上!
ストリーミングでプレイステーションのゲームが遊べるストリーミングサービス、PlayStation NowがWindows PCに対応することになりました。
これまではPS4やPS Vitaなど限られたデバイスからしかアクセスできなかったので、より幅広いユーザーが手軽に楽しめるようになりそうです。
DEN OF GEEK!が報じたこのニュースは、PlayStation.Blogにて発表されたもの。
必要なPCのスペックは以下の通りです。
OS:ウィンドウズ 7 (SP1)または8.1または10
CPU:3.5 GHz Intel Core i3または3.8 GHz AMD A10またはそれ以上
ハードディスク容量:300 MBかそれ以上
RAM:2GBかそれ以上
サウンドカード
USBポート
なお、接続は5Mbps以上の有線が望ましいとのことです。
そして、9月にはPCで遊ぶためのDualShock4用USBワイヤレスアダプターも発売されます。
もし、PCとMACに「PS4リモートプレイ」がインストールされていれば、その操作も可能で、お値段は24.99ドルです。
前世代のコンソールPS3だけでなく、すでにPS4をお持ちの方々も多いかと思いますが、名作も多いですし、このお手軽さとお買い求めやすさはついついほしくなりますよね。
このサービスはヨーロッパにてまず利用可能に、次いで北米となるとのこと。
日本での登場も待ち遠しいです。
image: PlayStation.Blog
source: DEN OF GEEK!, PlayStation.Blog
(岡本玄介)
マーベラスは、11月10日発売予定のプレイステーション 4/PlayStation Vita用ハイスピードサーヴァントアクション「Fate/EXTELLA(フェイト/エクステラ)」のサーヴァントプレイ動画第3弾 「エリザベート」、「呂布奉先」、「ガウェイン」を公開した。
公開された映像では、才色兼備のスーパーアイドルを自称するランサー「エリザベート」、三国志に名高い、裏切りの武将であるバーサーカー「呂布奉先」、太陽の騎士でありエクスカリバーの姉妹剣を持つセイバー「ガウェイン」のアクションを見ることができる。
□才色兼備のスーパーアイドルを自称するランサー「エリザベート」
□裏切りの武将であるバーサーカー「呂布奉先」
□太陽の騎士でありエクスカリバーの姉妹剣を持つセイバー「ガウェイン」
Amazonで購入:Fate/EXTELLA VELBER BOXFate/EXTELLA REGALIA BOX for PS 4Fate/EXTELLA PS4Fate/EXTELLA REGALIA BOX for PS VitaFate/EXTELLA PSVitacTYPE-MOON
c2016 Marvelous Inc.
ゲームクリエイター・稲船敬二氏とインティ・クリエイツがタッグを組んで生み出したアクションゲーム『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト』。
ロックオンを併用する強力な攻撃「電撃鱗」と絶対回避の「電磁結界」による爽快なゲーム性が好評を博しました。
また、ライトノベルを思わせるような濃密な設定や個性的なキャラクターに彩られた物語は、プレイに刺激を与えると共に劇的な展開がユーザーの心を揺さぶります。
そのストーリーを、フルボイスによる声優の熱演と豊かな音楽が支え、エンターテイメント性の高い一作としても高い評判を獲得しました。
さらに、「電磁結界(カゲロウ)」により、アクションゲーム初心者でもゲームが進めやすく、またハイスコアを狙う上級者向けの遊び方も同時に提案。
ひとつのゲームバランスの中で、双方のプレイを可能としたユニークなデザインも注目を集める大きな理由のひとつです。
独自性と間口の広さを合わせ持つ『ガンヴォルト』は多くのユーザーに支えられ、コンサートの開演やアニメ化プロジェクトの進行、そして続編となる『蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト 爪(ソウ)』の発売と、更なる躍進を迎えます。
今回は、続編となるDL版『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪』および、前作と『爪』をセットにしたパッケージ版となる「蒼き雷霆 ガンヴォルト ストライカーパック」の発売を記念し、シリーズが持つ魅力や『爪』でパワーアップした要素の数々を、インティ・クリエイツの開発陣に直接訊ねるインタビューを行いました。
制作の裏側からこぼれ話までたっぷりと伺いましたので、シリーズファンはもちろん、未プレイだけど『ガンヴォルト』が気になる方も、開発陣の生の声をじっくりとご覧ください。
◆『ガンヴォルト』シリーズを手がけた開発メンバーに迫る!
──それではよろしくお願いします。
まずは、読者の方々に向けて自己紹介をお願いします。
津田氏
津田氏:前作含め、ディレクターを担当している津田祥寿です。
原作というか、元ネタも担当していますね。
荒木氏:荒木宗弘です。
僕も前作から関わっているんですが、前作では主に背景を担当していました。
あと前作の開発後半に「デザインの監修をしてくれ」と言われたんですが、大詰めだったのであまり機能しませんでした(笑)。
ですがその引き続きで『爪』のデザイン監修も担当し、キャラクターデザインの畠山義崇さんとやりとりをしました。
──では『爪』では、始めからデザイン監修をされたんですね。
荒木氏
荒木氏:はい。
畠山さんから上がってきたものに対して、「これは違います」とか「世界観的にこういう形にしてください」といった指示を出させていただきました。
津田氏:シナリオやグラフィックなどの確認は、最終的に僕のところにくるようになっているんですが、「絵に関しては専任を置いたほうがいいんじゃないかな」と、前作の終盤辺りに思いまして(笑)。
それで荒木の方にお願いし、『爪』も引き続き担当してもらいました。
荒木氏:前作の時は、確認の仕方が煩雑になっていた面がありまして。
当時畠山さんは社内にいらしたんですけど、「その件は津田さんに聞いてください」みたいなたらい回しになっていて、それで「最終的には僕の方で」という話になりました。
──前作の経験を活かし、より整った形で『爪』が開発されたと。
津田氏:そうですね。
僕の方で大まかに考えたものを、荒木とシナリオ担当の田井利明で世界観的なものを構築してもらう、という形で『爪』の開発に取り掛かりました。
荒木氏:あと補足になりますが、主人公の「ガンヴォルト」(GV)のデザインだけは、前作も『爪』も、僕が担当しています。
──そうだったんですね。
では最後に山田さんお願いします。
山田氏
山田氏:サウンドプロデューサーの山田一法です。
音楽や効果音など、サウンド関連全般に携わっています。
あと音声や収録関係も自分の担当です。
音作りなどの実務は色んなメンバーで取り込んでおり、自分も音楽や効果を作ってます。
──耳に入ってくるものを総括している立場、と考えてよろしいでしょうか。
山田氏:もうひとり、川上という人間がいて、彼と二人三脚でやっているような形です。
あと音声収録に関しては、田井と一緒に演出の確認などしています。
◆「このゲーム死なない」「大丈夫?」と言われてきた『蒼き雷霆 ガンヴォルト』制作現場
──ではまず、3DSでリリースされ、Steamでの配信も行われた、前作『蒼き雷霆 ガンヴォルト』の反響についてお聞かせください。
津田氏:TwitterなどのSNSで語っていただけることもあり、ユーザーさんのコメントを見るたびに嬉しく思います。
また体験会やイベントを実施した際に、「遊びましたよ」と言ってくださる方が思っていた以上にいて驚きます。
E3のような海外のゲームショウにも、『蒼き雷霆 ガンヴォルト』を知っていただいている方がいて、なんだか新鮮な感じです(笑)。
山田氏:前作の時に、イベントを平日に行ったことがあるんです。
ほとんど告知もしていないような状態だったんですけども、すごく多くの方に集まっていただけました。
ちょっとした列ができて、警察の方から注意されたほどです(笑)。
──まさに、目に見える手応えですね。
津田氏:ほかのタイトルでも幾度もイベントを行っていたので、これくらいだろうという想定があったんですが、それを上回る人数がいらっしゃって。
それを見た時に、「ユーザーさんにちょっとは刺さったのかな」と実感しました。
実は最初椅子を並べていたんですが、(人が入らないので)全部外してイベントを行うほどで。
荒木氏:そのイベント、僕はスタッフではなく客の立場で行ったんですが、結果的に誘導役として駆りだされてしまいました(笑)。
山田氏:『ガンヴォルト』は歌もポイントになっている作品でして、コンサートなどもやらせていただきましたが、あの時のイベントがそのきっかけになりました。
すごく感触がよかったので、今後も色々とやってみようかという流れに。
──ユーザーさんの反応が、その後の広がりに繋がっていったんですか。
嬉しい流れですね。
多くのユーザーさんに支持されている『ガンヴォルト』ですが、アクションというジャンル自体は最盛期と比べるといささか縮小傾向にあります。
それでも新規IPによるアクションゲームを作ろうと決めた原動力は何なのでしょうか。
津田氏:他の人の原動力は分かりませんが、私自身は「2Dアクションならなんとか作れるかなー」という人間でして、それ以外のゲームは作れる自信がまだないんですよ(笑)。
あと私自身、2Dアクションが好きというのもあります。
TVゲームの一番面白い部分は、「リアルタイム性」だと思っているんですが、その方向性と2Dアクションの性質が非常にマッチしているスタイルだなと感じていて、作るなら2Dアクションがいいなと常日頃考えています。
加えて、言われた通りアクションゲームの全体のユーザー数というのは減ってきていますし、プレイする方の年齢層も比較的高めの方が多いんですよね。
ともすれば、オールドゲームなジャンルに取られることもありますし。
なので『ガンヴォルト』は、いかに初心者や低年齢層を開拓できるかというのを目指しました。
──ジャンルの活性化、新しい風を吹き込みたいという想いもあったんですね。
津田氏:入門的なゲームになればいいな、という想いがありまして。
アクションが得意ではない方でも最低限クリアまではできるように、「電磁結界(カゲロウ)」や「復活」というシステムを用意しました。
例えば、『スーパーマリオ』の3面くらいまでは、みんな楽しめると思うんですよ。
なので「その辺りまで進められるユーザーがクリアできるゲームを作りましょう」と開発を立ち上げ、進めていきました。
できるだけ簡単に簡単に……と。
ところがですね、社内の人間は難しいゲームが好きなので、放っておくと難易度が上がるんですよ(笑)。
「こんな難しくしないでー!」って言ってるのに、どんどん難易度が上がりまして。
──アクションの間口を拡げる考えと、手応えを求める考えがせめぎ合ったんですね(笑)。
津田氏:「復活」するとEPゲージが減らないというかなり強力な状態になるんですが、これくらいしないと(アクションが得意じゃない人は)クリアできないんじゃないかなと思って調整したんです。
「復活」のシステムを最初に考えた時は、そこまで強くするつもりはなかったんですよ、実は(笑)。
直接目には見えないんですが、こういった考えや、その結果として導入したシステムなどが、今遊んでくれている方々に刺さっているのだとしたら、本当に嬉しいですね。
山田氏:『ガンヴォルト』を作っている時、「このゲーム死なない」ってみんな言ってたんですよ。
「これでいいの?」って(笑)。
開発スタッフは、手強いアクションゲームをずっと作り続けてきたメンバーですから。
──これまで作ってきたアクションゲームとはどこか違うぞ、と。
山田氏:そうですね。
最初は「死なないゲーム」だと思っていたんですが、これは「自分で難しくしていくゲーム」だなと気付きまして。
十字キーの下を連打していれば、ほとんどの攻撃は「電磁結界」で無効化できるわけですが、いざ攻撃しようとすると相手の攻撃も当たる。
このジレンマがゲーム性なんだなと分かって、これまでの旧態然としたアクションゲームとは真逆なんだなと感じました。
──スコアを稼ごうと思ったら、「電磁結界」に頼らず自力で避けないといけませんしね。
山田氏:クリアするだけなら、「電磁結界」を使って攻撃を回避しつつ、その合間にちょっとずつダメージを与えていく。
このプレイスタイルの提案が、今までアクションゲームに手を出さなかった人たちへの間口を拡げて、裾野を拡げていったのかなと思っています。
津田氏:アクション初心者の人がクリアでき、かつ上級者の方向けのシステムも用意する。
その考えは、『ガンヴォルト』制作当初からずっと持っていました。
ただ、その考えを理解してもらうまで長かったですね(笑)。
途中までは、荒木さんとかにボロボロに言われてましたから。
荒木氏:その節はすみませんでした(笑)。
いやその、開発はそれぞれが部分部分で取り組むじゃないですか。
それらが繋がって遊べるようになったのが、『ガンヴォルト』の時は結構終盤だったんですよ。
それまで全体の形が分からなくて不安でした。
津田さんとかみんなに集まってもらって、「このゲーム大丈夫なんですか?」と聞いたりして(笑)。
ただ、繋がって遊んでみたら、それまで作ってきたゲームにはない初めての感覚があって、「このゲームすごく面白いんじゃないか!」って(笑)。
──評価が一変した、と(笑)。
荒木氏:内部で「このゲームすごく面白い」とかって、あまり言わないんですよ。
でも開発中に『ガンヴォルト』をプレイしてる時、一緒にチェックしてる人と「このゲーム、ヤバくない?」みたいな話をしてしまうほど、衝撃的でした。
その時に初めて、「こういうゲームだったんだ」と分かった瞬間でした。
──アクションゲームに慣れているほど、「電磁結界」は驚きのシステムですよね。
操作しない方が安全、という(笑)。
津田氏:子供とかにゲームをやらせてみると、やっぱりクリアできない子も多いんですよね。
そして、進まない時って、大体止まるんですよ。
穴の手前とかで。
──「どうしたらいいんだろう」みたいな戸惑いがあるんですね。
津田氏:こういう子たちのプレイを見ていると、「無敵にでもしないとクリアできないんじゃないの?」みたいに思うわけですよ(笑)。
だから、穴に落ちて死ぬというアクションゲームお馴染みの要素も、できるだけ減らしてみたんです。
ただ、「夜のビルの上に立つ主人公」というイメージも大事にしたかったので、それを表現しようと思うと、どうしても高さが必要になるんですよね。
なので『ガンヴォルト』の開発中盤くらいに「穴があるのは仕方ないよね」と、そこは考えを改めました(笑)。
──上下が反転するステージもありましたしね。
よく上に“落ち”ました(笑)。
「電磁結界」といい、印象深い仕掛けやシステムが多い作品ですよね。
山田氏:アクションゲームに慣れていると、(「電磁結界」で攻撃が回避できるなど)このゲームはなんなの? って思ってしまうんですよね、最初は。
でも実際にゲームをやってみると「あ、こういうことだったんだ」と気付かされるんですが、それまではやはりなかなかイメージできなくて。
「こんなの死なないじゃん」って(笑)。
──「電磁結界」のシステムなどを聞くと、死なないゲームだと思いますよね。
山田氏:でも死ぬんですよね、意外と(笑)。
津田氏:最終的にはいいバランスに落ち着いたのかなと思っています。
──難易設定ではなく、プレイスタイルによって難しさが変化するゲームデザインは、刺激的でしたし魅力でもありました。
津田氏:そこまではしっかり考えて作っていたんですが、クードスが1000を超えるとモルフォが歌い出すというシステムに関しては、バランス面で心残りのある部分でして。
元々は「ドキドキさせるシステムを用意したい」と考えていて、1000を超えると心臓音が鳴る、という形だったんです。
でもあるタイミングで、「クードスに歌を当てはめたら面白いのでは」と思いついて、山田に歌を一曲作ってもらいました。
その感触が想像以上によかったので、モルフォが歌うシステムという形になったんですが……プレイした方なら分かると思うんですが、クードスが1000を超え、またその状態を維持し続けるのって結構難しいんですよね。
後から加えたシステムだったので、ここのバランスだけはちょっとちぐはぐだったかなと感じています。
もう少し優しいバランスで曲が流れてもよかったのかなと。
その点を踏まえて『爪』では、スコア清算率は低いものの被弾しても減らない「アパシー」や、逆に清算率は高いものの一度の被弾で0になる「レックスレス」、3回被弾するまで維持される「ティミッド」という3つのモードを用意し、より遊びやすくしてあります。
山田氏:ご褒美を難しいところに置く、というのはゲームバランス的にやってしまいがちなんですよね。
初心者向けのアイテムを入手しづらい場所に用意する、みたいな(笑)。
それに近いことをしてしまった感覚があったので、『爪』では調整が入って安心しました。
荒木氏:前作のシステムも、あれはあれで「1000超えよう!」というモチベーションに繋がるんですけどね。
津田氏:シンプルで分かりやすいので、前作のシステムもひとつの形かなと思います。
そして『爪』では、色んなユーザーに楽しんでもらえるようにしましたので、前作と本作それぞれを出す意味がある形になったのかもしれませんね。
いきなり『爪』のシステムだと、分かりにくかったかもしれませんし。
──前作の経験や反響が、『爪』に活かされているんですね。
津田氏:前作は、アクション初心者の方と上級者の人、それぞれを意識したシステムやバランスを心がけましたが、中級者向けのシステムはあまりなかったんですよね。
なので『爪』では、そこも少し厚くしてみました。
──中級者に向けた要素を伺ってもよろしいですか?
津田氏:一例としては、「ノーマルスキル」の存在ですね。
ゲージを使わないで使用できる「ノーマルスキル」というのがGVにあるんですが、これを探す遊びなどは中間層向けかなと思っています。
ステージのあちこちを回って、見つける楽しさを味わえます。
あとアキュラで言えば、プログラムをどんどん増やせるチップを隠してあるので、それも見つけてみてください。
……ぶっちゃけて言うと『ロックマンX』ですよね(笑)。
──ぶっちゃけましたね!(笑)
津田氏:あの辺りを参考にして(笑)。
「隠しハンマー」を見つける楽しさとかは、中級者向けの遊びかなと。
上級者になると、見つけたアイテムを駆使してタイムアタックに挑む、みたいな。
前作は「簡単」と「難しい」の両立を中心にしていたので、『爪』では中間層にも向けて作ってみました。
──『爪』は、より多くの人に向けて作られた一作なんでですね。
プレイできる日が楽しみです。
◆『爪』の結末は衝撃の展開!?
──ここからは『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪』の様々な魅力についてお聞かせください。
まず物語面ですが、前作は「スメラギ」という能力者を抑圧する存在が敵でしたが、今回は能力者連合が立ちはだかります。
まったく逆の存在に立ち向かうという切り口は、ライトノベル好きな層をくすぐるなと思いました。
津田氏:前作の終わりの時に、あるキャラクターがそういう話(能力者側の結束)を少し出していたので、『爪』で戦う相手は自然な流れで決まりました。
──では『爪』の物語面に関しては、開発当初からある程度固まっていたわけですか。
津田氏:決まっていたかと言われると、ほとんど決まってない状態でした。
前作の段階で、物語面でやりたかったことは全て盛り込んでいたので。
──前作の時点でやり切っていたため、続編で何を描くのか改めて悩んだと。
津田氏:続編で何をしたらファンの人が喜んでくれるのか、頭を捻りましたね。
山田氏:何をやっても蛇足感がありそうで(笑)。
ネタ自体はあったんですけどね。
──ストーリーが固まるまで、どれくらいかかりましたか?
津田氏:開発が始まって最初の二ヶ月くらいは、物語をどうするか考えていましたね。
そんな時ふと、「これならいけるかも」というオチを思いつきまして……ネタバレになるので、そこは説明はできないんですが(笑)。
でも、蛇足ではない「続編の物語」になる手応えを感じました。
ちなみにそのオチを思いついた時、荒木さんとかは賛同してくれたんですが、一部の人間は猛反対に合いました(笑)。
──おお……それだけ衝撃的な展開なんですね。
津田氏:オチを見た時にみんながどう思うか、楽しみですし心配でもありますね(笑)。
『ガンヴォルト』シリーズは、明るいハッピーエンドではなく、どこかビターな味わいを持たせたいんです。
今回も、『ガンヴォルト』らしい、いい終わり方になっていると思います。
──それは『爪』でも引き継がれているんですね。
手応えのあるエンディング、楽しみにしています。
ちなみにゲームに落とし込んでいく中で、シナリオ面で削られた部分などはありますか?
津田氏:最初にいくらか削りましたが、それくらいですね。
山田氏:前作の時は、色々と盛り込もうとして大変だったんですよ。
そのため開発終盤で削った部分があったんです。
なので『爪』開発の時は、やりすぎないように最初から絞り込んでいました。
……ですが、最終的には盛りだくさんな内容に(笑)。
最初に整理しすぎたので、削りようがなかったんですよね。
津田氏:最後は削ぎようがなくて、大変なことになってましたから(笑)。
◆クードスの上限突破はユーザーへの挑戦状?
──それでは次に、『爪』でプレイアブルとなったアキュラについてお聞かせ下さい。
津田氏:アキュラですが、GVよりもテンポのいいアクションにしようと心がけました。
ただ作ってるうちに、アキュラがどんどんと強くなってしまい(笑)、相対的にGVが地味になってしまった時がありました。
もちろんその後、しっかり調整しましたけどね。
──敵のセブンスを使えるというアキュラの特長は、ゲームファンとしてはやはりグッと来るポイントですから、テンポよく楽しめるというのは嬉しいですね。
津田氏:まぁいわゆる「あの」システムですよね(笑)。
──まぁいわゆるそれですよね(笑)。
ちなみにGVが『爪』でパワーアップした部分は?
津田氏:基本的なシステムを継承しつつ、新しいスキルの追加や、先ほど触れたノーマルスキルの存在がGVのパワーアップ部分になります。
ノーマルスキルは、使用してもクードスが清算されないので、スコア狙いのプレイに組み込んでいくという楽しさがプラスされています。
例えばボスラッシュの時とかにノーマルスキルでとどめを刺すと、スコアがどんどん伸びていきますから。
クードスが6000や7000とか溜まっていくのは、結構快感じゃないかなと思います(笑)。
ちなみに前作では、クードスの上限が9999でしたが、『爪』ではそれ以上溜められるようになりました。
10000越えは確認しています。
──ユーザーさんがどんな数字を叩き出してくれるか、こちらも楽しみですね。
続いてはビジュアル面に関して伺いたいのですが、前作を経たことでGVの心境に大きな変化があったと思いますが、心境の変化はデザイン面にも影響していますか?
荒木氏:シナリオが出てきたのはデザインよりも後だったので、GVの成長といった部分をデザインに盛り込む意識はそれほどありませんでした。
むしろGVのデザインは「変えなくていい」と言われていたんですが、デザインした本人的には納得できてない部分もあったので、その辺りに手を入れました。
あと、「ビルの上に立つ主人公」などの、ちょっとダークな雰囲気を持たせるような形を改めて起こしたいなという気持ちもありまして、『爪』のGVをデザインしました。
全身が蒼だったので、ダークヒーローを想起してもらえるよう、ネイビー系の色も盛り込んであります。
──なるほど、そういった想いが新たな形になった新生GVなんですね。
では、今回から登場する新キャラに関して、デザイン上で意識した部分などはありますか?
荒木氏:そうですね……『爪』が出ることでシリーズ化した形になったので、前作でユーザーさんが抱いたイメージを壊さないように意識しました。
もちろん同じ事をやってもつまらないので、イメージを大事にしつつもプラスアルファを加え、より見映えが良くなるよう調整しました。
◆“シューティングゲームなイメージ”で作られていた『ガンヴォルト』の音楽、デザインのこだわりにも言及
──それでは、音楽面に関しても伺えればと思います。
『ガンヴォルト』というゲームシリーズの音楽作りに関して、重視している部分などはありますか?
山田氏:まずは「スピード感」。
そして「ノンストップ」ですね。
アクションゲームというよりも、シューティングゲームのイメージで作っています。
アクションゲームは地に足着けて進むというイメージですが、『ガンヴォルト』の場合、上手くなるほどガンガン進んで、通り過ぎてから敵を撃破する……みたいなプレイになるんですよ。
──なるほど。
確かにそのシチュエーションは、シューティングゲームに近いテイストですね。
山田氏:そういう風に遊んで欲しいところもあるので、シューティングゲームを意識した音作りをしてますね。
飛んでいる感覚を味わって欲しいというのが、コンセプトのひとつです。
あとはノンストップということで、流れを止めたくなかったんですよ。
どんどんクロスフェードで繋げていきたくて、ローテンポだろうがハイテンポだろうが全て同じクリックで曲を作っています。
──1曲1曲が完成されているのはもちろん、ステージ全体を通して大きな1曲でもあるわけですね。
山田氏:そうですね。
ステージ全体を組曲のように楽しんでもらうという試みは以前も行ったことがあるんですが、(『ガンヴォルト』で)やれたかなと思います。
ちなみに『爪』はダブル主人公です。
普通は「同じステージを異なる主人公で楽しめる」という形が一般的ですが、本作ではGVとアキュラでプレイするステージはそれぞれ異なりますし、BGMもGVの方は従来に近くて、アキュラの方はアレンジを全て変えています。
レイヴ系に近い感じですかね。
もちろんGVとアキュラでは、クードスで流れる歌も違うので、アクション性や物語だけでなく、音楽面でもひと味違うものを楽しむことができます。
「違うゲームが2本入ってる」みたいな作品にしたいなと思って頑張りました。
……何度か挫けそうになって、「それはやめようか」みたいな話も出ましたが(笑)、でもなんとか形になりました。
──GVとアキュラ、それぞれで異なるゲーム体験が楽しめるんですね。
山田氏:あともうひとつ言わせて欲しいのが、敵キャラクターについてです。
前作の敵も個性的だったんですが、『爪』では輪をかけて個性的にしすぎてしまいました(笑)。
津田氏:前作であれだけやったので、『爪』ではもっと上回らないと、みたいな感じでやってましたね(笑)。
山田氏:例えば今回、ガウリというラップのリズムを刻んで戦うキャラがいるんですが、ラッパーのACE君にガウリの台詞を全部ラップしてもらったんですよ。
それを声優さんに学んでもらって音声収録してもらいました。
あと、ニケーというロシア系のキャラがいるんですが、彼女はカタコトで喋るので、ロシア生まれのジェーニャさんをキャスティングした上で、ロシア訛りな感じで発音してもらったこともありました。
こんな感じで、表現もキャラごとに拘ったんですが、そのためクセが付きすぎてしまったかもしれません(笑)。
津田氏:ちなみにジェーニャさん、別に日本語下手じゃないですからね?(笑) 上手なのに、わざとロシア語訛りを入れて喋ってもらったんです。
──では、そういった部分もデザインに反映されているんですか?
荒木氏:んー……いや、ないですね(笑)。
そういう個性付けは田井が考えていて、デザインの段階では普通に喋る恰好いいヤツだと思ってます。
だから、声が入った時に驚きます。
「こんなヤツだったんだ!」って(笑)。
山田氏:デザインコンセプトとキャラコンセプトは、ちょっと別ですよね。
特にデザインコンセプトは……これ言っちゃっていいのかな?
荒木氏:あれですよね。
前作の時は「七つの大罪」がモチーフでしたよね。
『爪』で同じ事やるのもどうかなと思いまして、今回は「童話の女の子」をモチーフして盛り込んでみます。
キャラクター性とはちょっと違う部分ですよね。
山田氏:童話モチーフのテイストがあって、そこから転じた性格をそれぞれが持っているんです。
だから、一段階踏んだキャラクター造詣なんですよ。
──関連性があった上で、ひと味違う仕上がりになっているんですね。
山田氏:前作の時は、「七つの大罪」だったので、モチーフと性格付けがイコールに近かったんです。
なので、音楽とデザインとキャストの声がひとうのコンセプトで通っていたんですよ。
でも今回はちょっと複雑で、全体的にヒネりのある感じになっています。
出身も様々なので、音楽的にもちょっと民族色が感じられると思います。
テンジアンだとちょっと中国風だったりと。
──そういった民族的な拡がりも、前作とは違う音楽面のひとつと。
荒木氏:ちなみにキャラクターをTwitterとかで公表すると、モチーフになった童話がバレちゃったりしてますね。
バレるまでは「そうじゃないんだなー」みたいな気持ちで楽しませてもらってます(笑)。
◆『ガンヴォルト3』の構想は? 今後の展開は!?
──ここまで、『爪』でパワーアップした面をたっぷりと聞かせていただきましたが、仮に『3』を作るとしたら、これを更に超えてるのは相当大変になりそうですね。
津田氏:モルフォとかどうなるんだろうね。
荒木氏:全ては津田さん次第なところがあるので、僕は知りません(笑)。
山田氏:そもそも『3』でGVいるんですかね?
津田氏:そこもありますよね。
『爪』は『爪』で、なんだかんだありながらも物語として綺麗にまとまっているんですよ。
だから次どうするのと聞かれたら、まったく違う世界にするのもアリかもしれません。
300年後くらい先がいいんじゃないかなって僕は思います。
ただ、この話をするとみんな冷たいんですよ(笑)。
──津田さんの気持ちも分かりますし、周りの方々の反応も納得できますね(笑)。
ちなみに『爪』で実現できなかったことはありますか? それを『3』でやってみたい、みたいな。
津田氏:実現できなかったというと大げさなんですが、最初企画を立てた時に「プレイヤーキャラは3人にしよう」って言ってたんです。
でも開発に入る以前の段階で「それは無理」とハネられまして(笑)。
なのでもし『3』が出るとしたら、それも再考してみたいですね。
とはいえ、現時点では全然何もありません(笑)。
『1』はいくつか考えていたものがあって、そこから作り上げていったんですが、今回の『爪』ですら、最初はほとんど何もありませんでしたしね。
荒木氏:何も決まってないのに、ボスのデザインだけは始まってましたからね(笑)。
山田氏:ロロに和風な要素があるというのもあんまり理解してなくて、曲が出来上がった後にその話を改めて聞いたんです。
で、それを前提として聞いてみると、結構ハマってる感じだったので、「ああ、良かったな」と思いました(笑)。
津田氏:知らなかったんですか!(笑)
山田氏:作詞を担当した人がデザインから読み解いてくれたようで。
「これ、巫女デザインでしょ?」みたいな。
荒木氏:おお、そういう形で伝わっていたんですね。
デザインでモメた甲斐がありました(笑)。
山田氏:色々あったけど、最終的には収まるところに収まってくれた感じになりましたね。
──『3』も、そういう形で上手くハマってくれることを願ってます(笑)。
ちなみに続編ではなく、『爪』自体の今後の展開などはありますか?
山田氏:前作ではコンサートなどやらせていただきましたが、最初から決めていたわけではないんですよね。
前にお話した通り、イベントでの成功がきっかけとなって動き始めたわけでして。
だから『爪』の展開も、ネタやタイミング、ユーザーさんからの要望がハマった時にやれればなと考えています。
津田氏:前作関連ではアニメ化が進んでいますので、そちらも楽しみにしてもらえると嬉しいです。
今、すごくチェックしてます(笑)。
──『ガンヴォルト』『爪』ともに、今後の展開も楽しみにしています。
それでは最後になりますが、読者の方々に向けたメッセージをお願いします。
津田氏:シナリオ、アクション性、キャラクター、音楽、いずれも高いレベルでまとまった作品になりました。
特にシナリオは、“アクションゲームなのに泣けるストーリー”に挑戦しましたので。
こういうゲームはあまりないと思うので、ぜひ最後まで遊んでもらって、本当に泣けた時はTwitterに「泣けた!」と書いてもらえると嬉しいです(笑)。
ともあれ、楽しんでいただければなによりですね!
荒木氏:僕も、お話を楽しんで欲しいと思ってます。
イラストやデザインというのは、その入り口でもありますから。
そこから入った新しいユーザーさんが、物語を楽しんでくれれば幸いです。
あとユーザーさんがTwitterとかで、『ガンヴォルト』のイラストとか書いてくれてるのを見ると嬉しいですね。
結構見てたりするので(笑)。
『爪』や「ストライカーパック」をご堪能ください。
山田氏:自信作になったと思います。
『ガンヴォルト』から『爪』になったことで確実にパワーアップしてますし、前作でちゃんと終わった物語にしっかりと上乗せする形で新たなストーリーが紡がれています。
前作を遊んだ人にも気になる内容になってますし、初めて遊ぶ方は「ストライカーパック」で一気に楽しむ絶好の機会なので、『ガンヴォルト』世界にたっぷりと満喫してください。
──本日はありがとうございました!
◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
(C)INTI CREATES CO.,LTD.2016 ALL RIGHTS RESERVED.
●シリーズ2作目として再び登場
ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントは、『LEGO ニンジャゴー ニンドロイド』を、2016年11月22日に発売することを発表した。
プラットフォームはプレイステーション Vita/ニンテンドー3DS。
以下、リリースより。
−−−−−−−−−−
ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント(東京都港区 マネージングディレクター 上席執行役員 福田太一)は、『LEGO?ニンジャゴー ニンドロイド』の日本国内での発売を発表いたしました。
2016年11月22日発売予定で、プラットフォームはPlayStation?Vita / ニンテンドー3DS?を予定しております。
(※ゲーム内容はプラットフォームによって異なります)
全世界で愛され続けているレゴ ブロック。
そしてそのレゴを題材にして世界中で大ヒットしているアクションゲーム「レゴ ゲーム」シリーズ。
テレビ東京系列でも大人気の「レゴ ニンジャゴー」が、シリーズ2作目として再びゲームに戻ってきます。
過去にもレゴ ゲームを開発してきたHellbent Gamesが、「レゴ ゲーム」シリーズの開発元であるTT Gamesと協力して開発。
「レゴ ブロックで遊ぶような、ワクワクするひらめきと驚きが楽しめる」と、高い評価を獲得しているアクションゲームを、本作でもフルローカライズ日本語吹替音声付でお届けいたします。
『LEGO ニンジャゴー ニンドロイド』は、前作「LEGO ニンジャゴー ローニンの影」以前のストーリーを収録。
ニュー・ニンジャゴー・シティを舞台にウー先生の元で修行に励むニンジャたちが、特別な武器や新たなビークル、そしてスピン術を用いて、邪悪なオーバー卿とそのサイボーグ軍団「ニンドロイド」の脅威に立ち向かいます。
これからニンジャゴーを知るという人にはシリーズ導入作としてもちろん、既に前作を遊んでいる人も、ニンジャたちの過去の冒険とその固い絆を振り返る絶好の機会です。
「レゴ ゲーム」シリーズならではの謎解き、そして「レゴ ニンジャゴー」ならではのアクションがたっぷり詰まった本作。
それぞれのニンジャの特性を活かしたパンチ、キックなどの攻撃だけではなく、スピン術とのコンボ技などアクション要素が満載!さらには、アニメに登場したカイ・ファイター、ニンジャコプター、サンダー・レーダーといったクールなビークルを操縦しての敵への攻撃も可能です。
また、30以上ものアクション満載のステージレベルの他、ニュー・ニンジャゴー・シティを自由に遊べるオープンワールド型のハブエリアとして探索することもできます。
ラーメン店のオーナーからヒントやコツを教わるもよし、道場で修行をするもよし、様々な楽しいアクティビティに参加し街中を思うがままに自由に動き回ることができ、ステージクリア後のやりこみ要素もふんだんに盛り込まれています。
知育玩具レゴだからこそ提供できる安心のクオリティで、お子様にもお勧めの作品です。
本日公開の第一弾トレーラーでは、ゲーム冒頭のストーリーとともに、多彩なアクション、パズル、ビークルなど本作の魅力を凝縮してお届けいたします。
カラフルな映像とニンジャたちの華麗なバトルをお楽しみください。
ニンジャたちの過去の冒険とその固い絆を振り返るアクションアドベンチャー『LEGO ニンジャゴー ニンドロイド』にご期待ください。
・Oculus Riftのパッケージはスマートだった
今まで体験してきたHTC ViveやPS VRはヘッドセットとPS/PS4を接続するのにプロセッサーユニットが必要になります。
しかしOculus RiftはヘッドセットからそのままPCに接続できるんです。
またデザインもすっきりとしたスマート仕様。
ヘッドホンはヘッドセットの側面にくっついているので必要ありません。
これもまたスマート。
しかも音質が想像以上にいいんです。
提案:身の回りのものをスマートに済ませたい方にはOculus Riftが一番いいかもしれません。
VR内で手の動きをトラッキングしてくれる専用コントローラーが同梱されてないのが残念ですが、別売りで販売される予定です。
・ハイスペックパソコンは当たり前のように必要
はい、これは言うまでもなくVRの常識ですよね。
しかしOculus Riftが届いて「いざプレイ!」ってなった時に、編集部を見渡すと対応するPCは一つもなかったんです…。
そこで今回、ギズモード・ジャパンはある超スペックPCをDellさんから特別にお借りしました。
そうです。
ゲーミングPCでおなじみのAlienwareのVR対応デスクトップPC「Area-51」をお借りしました。
宇宙からやってきた謎の物体のようなかっこいいフォルムは、インテリアとしてもお洒落なデザインです。
実際にセッティングしてみました。
でかいです。
しかしこの物体の中には、VR体験をするのに最適化されたスペックが詰め込まれています。
提案:PCの自作なんかできない、オールインワンが欲しい、という方は、VR対応デスクトップPCをそのまま購入するのがいいでしょう。
お値段は張りますが、お手軽にVR体験ができます。
もし自分で作ったPCでうまいこと動かない…なんてことになったら絶望しかありません。
●『三國志13 with PK』の質問に答えます
コーエーテクモゲームスのシミュレーションゲーム『三國志13 with パワーアップキット』が、週刊ファミ通2016年9月8日号(2016年8月25日発売)にて発表された。
武将プレイ体験をさらに深いものにする“威名”が追加されたほか、戦略パートや戦術パートも強化。
さらに、武将エディットの機能なども加わった、まさに“パワーアップ”な内容だ。
本記事では、そんな数々の新要素についての疑問を、読者の皆さんから募集。
ここで集まった意見に対して、コーエーテクモゲームスが9月5日20時より実施予定の生放送Web番組にて、『三國志13 with パワーアップキット』の利川プロデューサーみずから答えます。
下記の記事や、発売中の週刊ファミ通を読み、ぜひとも質問をお寄せください!
※関連記事
『三國志13 with パワーアップキット』多数の新要素を搭載した決定版
『三國志13 with パワーアップキット』PS4、PS3、PCにて今冬に発売決定、公式リリースが到着
※アンケートの実施期間は、2016年8月31日(水)23:59までです。
※ご回答いただいた内容は、コーエーテクモゲームス主催の生放送Web番組や、週刊ファミ通、ファミ通.comなどで発表させていただく場合があります。
※項目の記入漏れ、文字化けその他の理由で内容が判読できないなどの場合には、ご回答を無効とさせていただく場合がありますので、ご注意ください。
トルネは、PS4、PS3、PC、PSVitaに対応したレコーダー用アプリ。
SIEのサービス「プレイステーションネットワーク」を利用することで、居住する都道府県内のサービス利用者の視聴台数、録画台数を番組別に知ることができる。
セガゲームスは、プレイステーション 4/PlayStation Vita用RPG「蒼き革命のヴァルキュリア」を2017年1月19日に発売する。
価格はPS4版が7,990円(税別)、PS Vita版が6,990円(税別)。
「蒼き革命のヴァルキュリア」は、「戦場のヴァルキュリア」などに続く「ヴァルキュリア」シリーズ最新作。
主人公たちは復讐のために、戦場のみでなく政治や経済といった各分野で活躍し、国まで巻き込む戦争を起こす。
ゲームの舞台は独特の色使いをコンセプトとした新絵画風描画シェーダー「GOUACHE(ガッシュ)」を用いて描かれており、バトルシステムには大軍での戦術的な戦いを楽しめるバトルシステム「LeGION(レギオン)」を導入するなど、新しいRPGの表現に期待がかかるゲームとなっている。
発売日の決定と同時に、初回特典・予約特典が公開され、事前登録キャンペーン等を開始した。
また、本作は9月17日より開催予定の「東京ゲームショウ 2016」にてプレイアブル出展される。
ブース来場者には「バトル体験版 Ver.2.0」をダウンロードできるプロダクトコードが配布予定となっている。
□初回特典・販売店別予約特典
初回特典として、本編の前日譚を描くフルボイス追加ストーリー「断章:ヴァナルガンド結成」のプロダクトコードが付属する。
販売店別の予約特典は以下の通り。
ビジュアル等は後日公式サイトにて公開予定。
□事前登録キャンペーン
事前登録期間:〜2017年1月18日
応募詳細ページ:http://portal.valkyria.jp/azure/cp/pre/
本作の事前登録を行なうと、発売日当日に限定「フルボイス追加ストーリー」の特典プロダクトコードがメールで配布される。
□出演キャスト公開記念Twitterキャンペーン
応募詳細ページ:http://portal.valkyria.jp/azure/cp/tw/
8月26日に公式サイトが更新され、本作のボイス出演キャストが公開された。
これを記念し、本作の公式Twitterアカウント(@valkyria_sega)をフォローし応募用ツイートをリツイートした人の中から抽選で1名に、主人公・アムレート役の小野大輔さんのサイン色紙と「蒼き革命のヴァルキュリア」のポスターがプレゼントされる。
cSEGA
8月11日にカプコンとヒューマンアカデミーは、『バイオハザード アンブレラコア』のプロデューサーである川田将央氏とゲームデザインを務めた松江一樹氏による学生向けのトークイベントを開催しました。
今回のトークイベントでは、『バイオハザード アンブレラコア』の39点という低いメタスコアや、開発者とユーザーのすれ違いを招いてしまった要因を振り返り、反省を未来のゲーム作りにどのように活かしていくかが語られました。
■『アンブレラコア』は生魚未経験者に食べさせたシメサバ?
『バイオハザード アンブレラコア』は、2016年6月23日に発売された3対3の対戦型シューターで、『バイオハザード』シリーズの世界観を活かした狭いフィールドによる短時間に凝縮されたバトルが特徴。
カバーをはじめとしたさまざまなアクション要素によって格闘ゲームのような駆け引きが楽しめるようになっています。
川田氏によると、『バイオハザード』で何か小規模で新しいことができないかと考えていた際に、『コール・オブ・デューティ―』などの大規模な作品だけでなく、多様なシューター作品が出るようになってきた市場の流れの中で、カプコンの持ち味を活かした小粒だけどエッジの効いたシューターが作れるのではないかと考えたことが、『アンブレラコア』の始まりだったと語っています。
しかし、いざ発売してみると海外メディアやユーザーからの評価は芳しくなく、PS4版のメタスコアでは100点満点中39点を記録してしまいました。
この結果について松江氏は、ユーザーが求めるもの、「バイオハザード」から想像するものとは異なるものを作ってしまったことが原因ではないか?との推察を述べました。
比喩として、自分たちが好きだけど匂いのきついシメサバを、「においがするもの」だと理解してもらわずに、シメサバどころか生魚すら食べたことのない人に提供して、「これは腐っている!」という感想を受けるのと同じだった、としています。
さて、ここからは開発背景が語られた講演内容をレポートしていきます。
■小規模タイトルとしてのゲームデザイン
ゲーム作りにおいて必要なことは「コンセプトをしっかり立てる」「ターゲットをしっかり規定する」「販売プランをしっかり組み立てる」であると松江氏。
今作は、小規模タイトルとしてがっつり遊べる対戦型シューターを低価格で提供する、大規模ゲームへのアンチテーゼかつニッチな市場へのアピール、バイオハザードの新たなチャレンジとして新規ユーザーを引き付けるユニークポイントを持たせる、ということが前提であったとのこと。
小規模タイトルとして進めるにあたり、短期間でゲームが完成するように工程の見直しが行われました。
作業の効率化のために、人の動きをそのままトレースできるモーションキャプチャーを積極的に導入、キャラクターの動作を1つ1つプログラムする手間を省き、フォトスキャンは実際の人物やプロップをそのままモデルやテクスチャとして取り込めるので、高いクオリティを維持しつつ、グラフィックをゼロから作り起こす手間が短縮されました。
また、初期に使うべき技術を選定しておき、かけるコストの効率化も行いました。
とはいえ、これらコンセプトや行程を作ることは重要ですが、「自分たちが何をしたいのか」がモノ作りの基本なのだと川田氏と松江氏は強調しています。
■高い完成度のプロトタイプができた
企画開始時、ほぼゲームデザイナーだけの少人数チームがプロトタイプの制作に取り掛かりました。
汎用性の高いUnityエンジンを用いたこともあり3カ月という短期間で完成、3対3の対戦や邪魔をするゾンビなど独自のアプローチを盛り込んだこのプロトタイプは、社内テストも順調にクリアしていきました。
上司の評価も上々だったのだそうです。
そして、このプロトタイプを叩き台にゲームの本開発がスタートしたといいます。
■ここで最初のつまずきが発生
まず、最初のつまずきは、欲を出して別の方向での模索をしてしまったことだと川田氏は説明します。
3カ月で高い完成度のプロトタイプを作れたという自負が、もっと面白くできるのでは?と思わせてしまったのです。
結果的にあまり面白くはならなかったために元に戻してしまうことになるのですが、予定されていた開発期限は変わりません。
気持ちが先走って新しいことをやろうとし過ぎたために試行錯誤に費やした分、工程ロスが発生し、短期間で完成させる小規模タイトルであるはずなのに予定が大きく崩れてしまうことになりました。
次のつまずきは、他社製のゲームエンジンであるUnityを使用していたために発生してしまいます。
当時は、カプコンの自社製ゲームエンジン「REエンジン」が開発段階であったため、スムーズにプロトタイプが作れたUnityで開発を行うことになりました。
しかし、他社製エンジンであるがために起こる、技術のすり合わせによる時間のロスや様々なトラブルも相まって、作品のクオリティアップのためではない、完成させるための期間の延長を余儀なくされます。
ただ、苦労の甲斐もあって、Unityの公式イベント「Unite 2016 Tokyo」で『アンブレラコア』を見たUnityユーザーからは、「Unityでここまでできるのか」といった称賛の声をもらえたのだそうです。
■開発者とユーザーのボタンの掛け違い
開発の遅れに伴い、エンドユーザーにゲーム内容を正しく理解してもらうための対策を十分に立てることができませんでした。
まっさらな新規タイトルではなく、『バイオハザード』とミックスさせることでシューター市場を盛り上げたいと考えていた川田氏ですが、「バイオハザードなのになぜシューターなのか?」という意見が多く寄せられることになってしまいました。
開発者の想いとユーザーがブランドに望む像にボタンの掛け違いが起きてしまったのです。
さらに川田氏いわく、『アンブレラコア』はもともとバイオハザードシリーズのスピンオフ作品として企画されたものなのだとか。
純粋なサバイバルホラーを目指す『バイオハザード7』に対し、シューティング要素をさらに特化させた『アンブレラコア』という立ち位置でした。
実際、『アンブレラコア』の時系列は『バイオハザード6』と『バイオハザード7』の間に設定されており、登場組織などは本シリーズとの繋がりを匂わせています。
しかし、様々な事情により『バイオハザード7』の発表は延期され、『アンブレラコア』のみが先行して単体で発表されることとなりました。
昨年9月に行われた「SCEJA Press Conference 2015」で大々的に発表された『アンブレラコア』ですが、その際のユーザーの声は散々なものに。
開発者側が想定していたのは、コンパクトで一風変わったシューターを『バイオハザード』の世界観で遊んでもらうというものでしたが、ナンバリングの新作を想像していたであろうユーザーの期待とは異なる物であり、反応は厳しく、一部には『バイオハザード』の名前を使っただけの作品といった声までありました。
■バイオファンに理解してもらうために
「東京ゲームショウ2015」に『アンブレラコア』を出展することになった際、開発チームはあるアプローチをとりました。
体験者に理解を深めてもらうために、松江氏を含む開発スタッフと操作を熟知したコンパニオンたちが可能な限り付き添ってゲーム内容をレクチャーするというものです。
1日に体験して貰える人数は激減しますが、丁寧な説明が幸いして参加いただいたユーザーさんからは好評でした。
ブースの狭い空間では仲間意識も強くなり、素晴らしいプレイ体験ができていたと松江氏は語ります。
手ごたえを感じた開発チームは「遊んでもらう、触れてもらう」ことが重要だと考え、体験会の開催を続けていきます。
ところが、体験会では好感触があったにも関わらず、『アンブレラコア』がいよいよ発売を迎えると、ユーザーの反応は発売前とは真逆のネガティブなもので溢れていました。
中には、生魚を食べたことがないのにシメサバを食べさせられたかのような、厳しい意見もあったと松江氏。
シメサバがどんなにDHAやEPAが豊富で脳にいいと言われても、腐っていると思われたら誰も食べないというもの。
開発チームはこうした反響に大きく肩を落とすことになりました。
そこで体験会の規模、体験して貰う人数が小さすぎたと考えた開発チームは、PS4で期間限定の体験版を展開することになります。
このアプローチによって多くのユーザーに実際にプレイしてもらい、販売の勢いを倍近くに伸ばすことができました。
ゲームを理解して貰うにも、クオリティアップの為にも、βテストをやっていればまた違っていたかもしれないと語った松江氏。
やりたくてもさまざまな要因で実施できなかったことを悔やんでいました。
また、大型タイトルと発売日が重なり、『アンブレラコア』の発売日が未発表の時点で一回、発売間近にも一回の延期を行いましたが、相手も延期になり、逃げても逃げても追ってくるという状況が発生。
また、発売当初はマッチングに問題が発生してしまったためにプレイヤーが離れてしまうというトラブルも起きました。
6月23日のリリースから8月11日までに5回のアップデートを行い、ゲームバランスを含む多くの問題の対策を素早く行ってきた開発チームですが、時すでに遅く、マイナスを挽回することはできなかったとしています。
■『アンブレラコア』の反省と未来のゲーム作り
『アンブレラコア』の反省点として川田氏の口から語られたのは、「小規模で価格が安いからという開発側のロジックは通用しない」ということ。
3990円ですら高いという声も少なくなかったのだとか。
さらに、実績の積み上げが重要なシュータージャンルで、目新しいものを小粒で、という考え自体が甘かったのだとしています。
SNSによる口コミの影響力が非常に強い現状で、『アンブレラコア』はそこに食い込むこともできませんでした。
「面白いゲームを作る」「面白いゲームであることを伝える」「面白いゲームであることを伝える手法を確立する」ことは、当たり前のようで非常に難しいといいます。
それら反省を踏まえ、川田氏と松江氏は改めて、「コンセプトをしっかり立てる」「ターゲットをしっかり規定する」「販売プランをしっかり組み立てる」ことの必要性を説明し、イベントは幕を閉じました。
トーク終了後には、Q&Aセッションや学生1人1人が両名とじっくり話ができる時間が設けられました。
■『アンブレラコア』はアップデートやDLCで今後も盛り上げていく
イベント終了後に、川田氏と松江氏から『バイオハザード アンブレラコア』のプレイヤーと、これからプレイしようと思っているユーザーへのメッセージをいただきました。
川田:同じ失敗をしないための反省として、みなさんはこんな失敗をしちゃダメだよ、という意味も込めて共有させていただきました。
『アンブレラコア』を遊んで頂いている方には、新しいコンテンツも入った無料アップデートパック(8月19日に配信済)も準備しているので、遊びやすく、面白みを増した「アンブレラコア」で一段と盛り上がってもらいたいと思います。
また、こういうのを遊んで頂きたいなという新しいDLCを出していきたいと思います。
松江: アップデートはできるものから、可能な限り早く対応してきましたし、今さらかもしれませんが、REネット(「バイオハザード」シリーズの無料サービスサイト)に開発者への質問掲示板を設けてご意見をうかがったり、初心者や中級者の方が始め易く、また上達のお手伝いにもなるようなゲームについての濃い説明も行っています。
『アンブレラコア』を購入してくださったユーザーさんにはまだまだ楽しんでもらいたいと思っていますし、興味を持った方もREネットをご覧いただいてどんなゲームなのか?理解を深めていただければ嬉しいです。
「ここでしか聞けないリアルなことが聞けたので、勉強になった」「反省点という視点での講義は初めて。
面白く聞くことができた」「コンセプトやターゲットの明確化が重要な事はもちろん、マーケティングの大切さも知ることができた」など、受講生からの好評を持って講演は幕を閉じました。
(C)2016 Human Academy Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
アトラスは、PS4/PS3向けRPG『ペルソナ5』の公式ガイドブックをゲームソフト発売同日の2016年9月15日にリリースします。
「ペルソナ5 公式ガイドブック」は、物語中盤までの解説や、ペルソナ・シャドウ・アイテムのデータなどが記載された攻略本です。
他にも「自由行動時間」や「天候」の情報を網羅したカレンダーデータが含まれているとのこと。
ページ数は256ページです。
なお、この攻略本のプロデュースは、アスキー・メディアワークスが担当しています。
同作の攻略本としては最速リリースになるので、攻略本を読みながらゲームを楽しむスタイルのプレイヤーにとって、必須アイテムになりそうですね。
「ペルソナ5 公式ガイドブック」は、株式会社KADOKAWAから出版。
価格は、1,500円+税です。
アークシステムワークスは、PS4/PS3『BLAZBLUE CENTRALFICTION(ブレイブルー セントラルフィクション)』の新たな情報を公開しています。
『BLAZBLUE CENTRALFICTION』は、2D対戦格闘ゲーム『BLAZBLUE』シリーズ最新作となるタイトルです。
本作は同名のアーケードタイトルの移植タイトルとなっており、新規プレイアブルキャラクターとして「Es(エス)」が追加されるほか、アーケード版では謎に包まれていた“真実”が明らかになります。
今回は、新たなプレイアブルキャラクター「マイ=ナツメ」の参戦が決定し、ネットワークモードの情報も公開。
なお、本作の公式サイトでは、「マイ=ナツメ」役を演じる早見沙織さんのキャストコメント、「ブレイブルー リミックスハート」作画担当でマンガ家のスメラギさんからのメッセージとイラストが公開されています。
◆新キャラクター情報
■「マイ=ナツメ」
「ごめんね。
とても危険な賭けかもしれないけど今はこれしか方法が思いつかない!」
・身長:162cm
・体重:51kg
・誕生日:4月4日
・血液型:A
・出身地:第三階層都市・イワス
・趣味:不思議な生物の鑑賞。
・好きなもの:爬虫類(特にカメレオン)
・嫌いなもの:酸っぱいもの(が嫌いだった)
・ドライブ名:朱弾(ガリアスフィラ)=アウトシール
・CV:早見沙織
十二宗家「ハヅキ家」の嫡男であり、ノエル達とは士官学校時代のクラスメイト。
とある魔道書の暴走事故により、身体が女性のものへと変質してしまったが、様々な葛藤を経た末、現在では女性としての自分を前向きに受け入れている。
大切な友人を護るため、発掘兵装「朱弾=アウトシール」を携え、その危機へと駆けつけた。
■ストーリー
暗躍するマッドサイエンティスト「レリウス」。
大切な仲間を「観察対象」と言い放つ男に対し、マイは闘志を剥き出しにします。
統制機構を裏切ったという濡れ衣を着せられた親友「ノエル」を、危険人物「ハザマ」から守ろうと立ち向かうマイ。
仲間のため、真っ直ぐな信念の元に行動します。
マイの体術を持ってしてもハザマには太刀打ちできません。
絶体絶命のピンチに陥った彼女たちの前に、ある人物が現れます。
●原作コミックについて
マイは漫画作品「ブレイブルー リミックスハート」のオリジナルヒロインとして初登場しました。
本作では、ノエルやツバキ、マコトらが在籍していたころの士官学校を舞台に、彼女たちと過ごす貴重な学生時代が描かれています(全4巻で発売中)。
なお、現在は雑誌「ドラゴンエイジ」で続編にあたる「ブレイブルー ヴァヴリアブルハート』が連載中です。
◆「マイ=ナツメ」のプレイスタイル
■専用コンビネーション:ヴァリアブルアーツ
マイは、リボルバーアクションのほか、専用のコンビネーションである「ヴァリアブルハーツ」を使用できます。
リボルバーアクションとの違いは空振りでも派生可能という点と、2発目以降が専用の攻撃に変化する点です。
■ドライブ:朱弾(ガリアスフィラ)=アウトシール
ドライブ能力「朱弾=アウトシール」は、マイの持つ槍を構えて、飛び道具として投げるドライブ。
構え中に、レバー操作で最初に投げる角度を変化させることができます。
さらに、投げたあとにもう一度Dボタンを押すことで槍が方向転換し、相手をサーチして飛んでいきます。
■必殺技:刹梛(せつな)
●派生技:姫百璃(ひめゆり)
●派生技:姫百璃・斗李(ひめゆり・とり)
■必殺技:月華(げっか)
●派生技:須寿蘭(すずらん)
●派生技:須寿蘭・斗李(すずらん・とり)
低い体勢から相手との間合いを詰める「刹梛」、ムーンサルトのような動きが特徴的な「月華」。
ダッシュや回避手段として単独でも使えるだけでなく、発動中にボタン操作で突進必殺技へと派生します。
■ディストーションドライブ:断空崩蕾花(だんくうほうらいか)
鮮やかな花びらを舞い散らせながら相手を天高く突き上げ、一気に地面へと叩きつける大技。
相手のダウンを奪うことができます。
■ディストーションドライブ:六花嵐桜閃(りっからんおうせん)
華麗な身のこなしで相手に強烈な一突きを喰らわせる技です。
■エクシードアクセル:桜花爛刃(おうからんじん)
オーバードライブ中に発動できるエクシードアクセルで「桜花爛刃」。
◆ゲームモード
本作の「ネットワークモード」は更にパワーアップ。
「オンラインロビー」ではゲームセンターのように、不特定多数のプレイヤーと交流することが可能。
また、自分の分身「アバター」を操りアクションをすることも。
なお、ロビーでは「アバター」と「アクセサリ」「家具」を入手できます。
「ランクマッチ」は世界中のプレイヤーと規定のルールで対戦するモード。
マッチング待ち中にも一部のオフラインモードで遊ぶことができます。
プレイヤーのプロフィールが記載された「D-Code」。
「D-Code」にはプロフィールのほか、ネットワークモードでの勝利数や勝率など様々な戦績も記録されています。
なお、自動更新される情報以外にもアイコン・プレート・アバター・よくプレイする時間帯・称号・一言メッセージなどを設定できます。
「プレイヤーマッチ」では「対戦&観戦」、「全員乱戦」、「リプレイ鑑賞」など、プレイスタイルにあったルームタイプを選べます。
また、「オンラインロビー」で入手した家具で、マイルームを自慢の部屋にリフォームするのもプレイヤーマッチの醍醐味とのこと。
1度対戦したことのあるプレイヤーを「グッドプレイヤー」「バッドプレイヤー」に分けてリストに登録することも可能。
「ライバル設定」を行えば、常にライバルの動向をチェックできます。
◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
PS4/PS3『BLAZBLUE CENTRALFICTION』は2016年10月6日発売予定。
価格は以下のようになります。
・通常版:6,800円(税別)
・DL版:5,800円(税別)
・限定版(Limited Box):9,800円(税別)
(C) ARC SYSTEM WORKS
●購入特典やキャンペーン情報など一挙公開!
セガゲームスは、プレイステーション4、プレイステーション Vita用ソフト『蒼き革命のヴァルキュリア』を2017年1月19日(木)に発売することを決定した。
さらに、購入特典や各種キャンペーン情報、“東京ゲームショウ2016”出展情報などを公開している。
以下、リリースより。
−−−−−−−−−−
株式会社セガゲームス コンシューマ・オンライン カンパニーは、新作RPG『蒼き革命のヴァルキュリア』の発売日を2017年1月19日(木)に決定いたしました。
プラットフォームは既発表のPlayStation4に加え、PlayStation Vitaにも対応。
多角的に描かれる戦火での人間ドラマや戦場を体感できる戦術的なバトルシステム、絵画風のグラフィック表現など、“ヴァルキュリア”プロジェクトの新たな挑戦作品となる本作にどうぞご期待ください。
今回の発売日決定に伴い、購入特典や各種キャンペーン情報、TGS 出展情報などを一挙公開。
また、このタイミングで公式WEBサイトもリニューアルオープンしております。
各情報の詳細は公式サイトにて掲載しておりますので、ぜひ公式サイトでご確認ください。
公式サイト:http://portal.valkyria.jp/azure/(⇒こちら)
○初回特典・販売店別予約特典が決定!
○事前登録やTwitterフォローによる各種キャンペーンを実施!
○東京ゲームショウ2016にプレイアブル出展決定!
■初回特典・販売店別予約特典が決定!
本作の初回版には、本編の前日譚を描くフルボイス追加ストーリーDLC「断章:ヴァナルガンド結成」プロダクトコードを封入。
主人公アムレートが所属するアンチ・ヴァルキュリア部隊“ヴァナルガンド”がいかに結成されたのか、ぜひこちらの断章でお楽しみください。
販売店別オリジナル予約特典を実施します。
対象の店舗にて本作をご予約いただいた方に、キャラクタービジュアルを使用したアイテム等、店舗オリジナルの予約特典を先着でプレゼントいたします。
アイテムデザインは決まり次第、下記の公式サイトページ等で公開していきますので、今後の情報にご期待ください。
★URL:http://portal.valkyria.jp/azure/guide/(⇒こちら)
◇販売店別特典内容
[アニメイト全店]
オリジナルピンバッジ 3 個セット
[Amazon]
・装備品「ラグナイト(Amazon.co.jp 特殊仕様)」プロダクトコード
・装備品交換アイテム「ラグナイトのかけら 30 個」プロダクトコード
[あみあみ]
オリジナルアクリルマルチスタンド
[いまじん / いまじんWEB ショップ(注1)]
オリジナル大型布ポスター
[ゲーマーズ全店]
オリジナルB2 タペストリー
[ゲオ]
アイテム未定
[セガストア(注2)]
蒼き革命のヴァルキュリアDX パック
[ソフマップドットコム]
タカヤマトシアキ描き下ろし
オリジナルB2 タペストリー
[トレーダー3号店]
清原紘描き下ろし
オリジナルB2 タペストリー
[PlayStation Store(ダウンロード版)]
・装備品「ラグナイト(ダウンロード版予約特典特殊仕様)」
・装備品交換アイテム「ラグナイトのかけら 30 個」
[WonderGOO ゲーム取扱店及び、WonderGOO 楽天市場店]
清原紘描き下ろし
オリジナルB2 タペストリー
注1:布ポスターパック 販売分/販売方法はお取り扱い店舗までご確認ください。
注2:「DXパック」はゲームソフトのほか、「A3 タペストリーアムレート&ブリュンヒルデ」「ヴァナルガンド部隊章マグカップ」「アクリルキーホルダー5 種セット」がセットになった限定版です。
販売価格につきましては、セガストアにてご確認をお願いいたします。
※ご予約時に各店舗にて特典の有無を必ずご確認ください。
※各店舗ともに特典数量には限りがございます。
無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。
※特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引渡し時にお渡しいたします。
※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。
※特典内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。
■事前登録やTwitter フォローによる各種キャンペーンを実施!
『蒼き革命のヴァルキュリア』のソフト発売前に事前登録していただいた方には、特典プロダクトコードを発売日当日にメールにてお届けします。
◆事前登録限定フルボイス追加ストーリーDLC プロダクトコード
登録期間は、2017年1月18日(水)まで。
応募方法などの詳細は、下記の公式サイトよりご確認ください。
★URL:http://portal.valkyria.jp/azure/cp/pre/(⇒こちら)
本日更新の公式サイトや特報映像にて、『蒼き革命のヴァルキュリア』のボイス出演キャストを公開しました。
これを記念して、ヴァルキュリアプロジェクト公式Twitterアカウント(@valkyria_sega)をフォローいただき、応募用ツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で1名様に、主人公アムレート役の小野大輔さんのサイン色紙と『蒼き革命のヴァルキュリア』のポスターをセットでプレゼントするキャンペーンを実施します。
応募方法などの詳細は、下記の公式サイトよりご確認ください。
★URL:http://portal.valkyria.jp/azure/cp/tw/(⇒こちら)
■東京ゲームショウ2016 にプレイアブル出展決定!
2016年9月15日(木)〜9月18日(日)まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2016」(一般公開日は17日・18日)にPlayStation4版のプレイアブル出展が決定。
本作のバトルをいち早く体験できるとともに、最新映像の公開や、試遊体験者およびコーナー来場者には、「バトル体験版Ver.2.0」をダウンロードできるプロダクトコードのプレゼントを予定しています。
ぜひご来場ください。
※バトル体験版Ver.2.0 は10月上旬より上記の配布プロダクトコード所持者を対象に先行ダウンロード配信を行います。
配信日詳細は後日公開させていただきます。
また、「バトル体験版Ver.1.0」所持者は、「バトル体験版Ver.2.0」を本プロダクトコードなしでプレイ可能です。
※本プロダクトコードは、試遊体験者、並びに事前登録キャンペーン応募者を対象に配布します。
※「バトル体験版Ver.2.0」はPlayStation4版です。
■公式BLOG「陣中日誌」も更新!
公式サイトで展開している公式BLOG「陣中日誌」の第11 回を公開しました。
この陣中日誌は、「アンチ・ヴァルキュリア部隊」、通称「ヴァナルガンド」に所属する部隊員の「ヘレナ・アンデルセン」と「ブルム・トマソン」による公式BLOG です。
今回のお題はということで、本日のさまざまな発表にあわせて、ヘレナとブルムからもご挨拶という内容。
普段とはちょっと違う(?)ヘレナの行動は、彼女なりにこのプロジェクトに関わる者の思いを代弁しているのであります。
詳しくは、ブログでご確認ください!
公式ブログ:http://portal.valkyria.jp/azure/blog/(⇒こちら)
<『蒼き革命のヴァルキュリア』概要>
“ヴァルキュリア”プロジェクト完全新作RPG始動! 聖暦1853年、“死神”「ヴァルキュリア」を擁する帝国との戦争を主導し、救国の英雄として活躍した5人の若者たち。
彼らは戦後、復讐という私怨で国家を戦争に導いた“大罪人”として処刑された。
後の歴史は問う。
彼らは英雄か、それとも罪人か――。
豪華スタッフ&キャスト陣による重厚な物語が、レギュラーRPGながら戦術的なバトルシステム「LeGION(レギオン)」と絵画風のグラフィック表現「GOUACHE(ガッシュ)」で鮮烈に描き出される!
蒼き革命のヴァルキュリア
メーカー:セガゲームス
対応機種:PlayStation Vita / プレイステーション4
発売日:2017年1月19日発売予定
価格:プレイステーション4版:7990円[税別](ダウンロード版も同額)、プレイステーション Vita版:6990円[税別](ダウンロード版も同額)
ジャンル:RPG