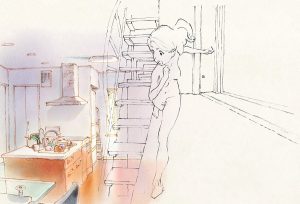世界初のフルデジタルOVA『青の6号』を生み出した前田真宏が語るアニメの進化と未来
–前田さんは世界初のフルデジタルOVA『青の6号』(1998年)を手がけられておられますが、そこへ至った経緯はどのようなものだったのでしょうか?
前田: 当時、すごくゲームが勃興期で最初のPlayStationがでた頃でした。
アニメーターとかもそっちの業界に鞍替えした人がたくさんいたんですね。
一番有名なのでは、小田部(羊一)さんという日本アニメーションで『ハイジ』や『母をたずねて三千里』を手がけていた方が任天堂に行ってしまわれたりとか。
僕の知り合いでもけっこうゲーム業界に行ってしまう人がたくさんいて、そういう仕事をされるようになったんですね。
一番決定的だったのは『マクロス(『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』)』というアニメのゲームをやったんですよ。
アニメーションの監修に板野一郎さん(※マクロスシリーズなどの立体的超高速戦闘アクション、通称「板野サーカス」で有名なアニメーター)にも入っていただいて、これが格好いい感じにできて、基本的には『青の6号』のコンセプトはここである程度できてるんです。
–ということは、この時点でセル画と3DCGを一緒にまぜるという……
前田: そうです。
カットで割るにせよ、合成するにせよ方法論に落とし込めるんじゃないかというのがなんとなく見えて、これで長編も作れたら面白いんじゃないかという話になって、そこから『青の6号』という企画が浮上してきて、1本30分ぐらいの尺は短いですけど全部デジタルプロセスだけで作ったんです。
–当時、見たときは3DCGとセルアニメが一緒にあると違和感を感じたのですが、再見すると、全然普通に見られて面白かったです。
見ているとあっという間に慣れてくるというか……
前田: (違和感について)散々言われました。
当時のスタッフのデジタルの人たちは、みんな結構経歴が面白くて秘書をやっていましたという人や、メインでCGをやってくれたのが鈴木朗さんという方で、もともとは実写で特殊メイクをされていた方。
ガレージキットの原型師とか、いろんな雑多な職種から人を集めてチームを作ったんですけど、そういうチームですから逆に言うと本当に右も左も分からないというトコロからの出発で、だから1話ができるまでの助走にすごく時間がかかっています。
2話ができて3話ができてだんだんやることがはっきりしてくる。
これが問題点だったねっていうのをある程度現場でカバーしながら良くしていったっていうのがあり、見ていて慣れるというのはそういうことかなと思います。
–今、3DCGが当たり前になってくると昔ほど違和感はないとも思ったのですが。
前田: 最初はすごい気持ち悪いとか、ラッシュを見てコレはホントに商品になるの?という空気はすごいあったんですけど(笑)、僕は強引に「いや、人間の方が柔軟だから、人間の方がすぐ慣れるから」って特に根拠のない話をしていました(笑)。
–やっぱり反響っていうのは結構大きかったのではないですか?
前田: 「なんだこれは!」って、批判もいっぱいされましたけれど、逆に面白いって言ってくれる人もいて、無理してやって良かったなって思いましたね。