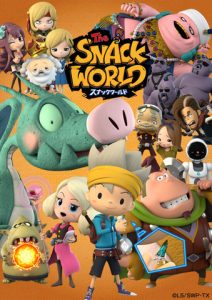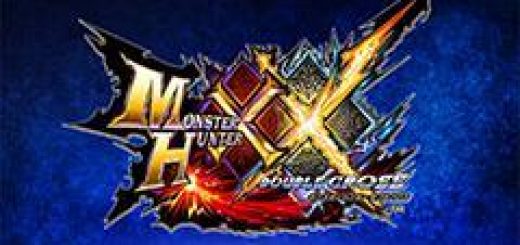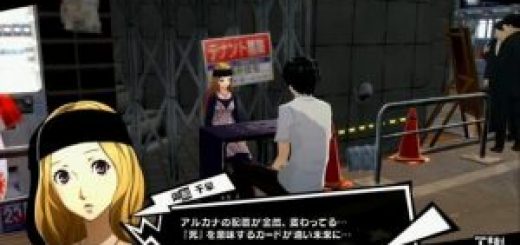ポケモンGOの隠れたルーツ「Field Trip」を知っていますか?
「ポケモンGO」の人気は衰えません。
米企業の業績発表ラッシュとなった今週も、米Appleのティム・クックCEO、米Facebookのマーク・ザッカーバーグCEO、米Googleのスンダー・ピチャイCEOがそれぞれ、業績発表後の電話会見でこのゲームについてコメントするほど盛り上がっています。
ポケモンGO誕生のきっかけは、Googleが2014年のエイプリルフールネタに発表した「Googleマップポケモンチャレンジ」だったという話は結構有名です。
それでは、任天堂に話を持ち掛けてポケモンGOの開発を行った米Niantic(ナイアンティック)のジョン・ハンケCEOとはどういう人物で、いつからこの「外を歩き回る+AR(拡張現実)技術」というゲームを作ろうと思ったのでしょうか。
ハンケさんのLinkedInによると、テキサス大学卒業後、カリフォルニア大学バークリー校でMBAを取ってから、1996年に3DO(松下電器がかつて販売したゲーム機のライセンス供給元!)へ入社し、2年席を置いた後、2つばかり企業を立ち上げました。
その2つ目の企業であるKeyholeが2004年にGoogleへ買収されて、Googleの人になったという経緯です。
このKeyholeという会社は、衛星+航空撮影で集めた画像を地図情報としてデータベース化し、企業や一般ユーザーに販売していました。
そうです、これこそがGoogle Earthのオリジナルです。
ハンケさんはどうやら、ゲームと地図が好きみたいですね(実はCIAのエージェントなんじゃないかという、Ingressユーザーなら妙に納得するうわさもありますが、どうでしょう)。
そんなわけで、Google入りしてからもしばらくは、Google Earth、Google Maps、ストリートビューなどを担当する副社長を務めていました。
Googleでは「こういうことやりたい!」という社内ベンチャーが(少なくとも当時は)奨励されていたので、ハンケさんはARの何かをやりたいと願い出て、2011年に社内ベンチャーのNiantic Labsを立ち上げました。
Niantic Labsでは2012年11月に、AR対応の位置情報ゲーム「Ingress」をリリースしました。
でも実はその数カ月前に、もう1つアプリをリリースしています。
知る人ぞ知る「Field Trip」です。
今でもデモ動画にじーんときて記事を書いたのを覚えています(今でも自分の2代前のAndroid端末にこのアプリが入っています)。
仕事が忙しくてろくに外を歩かないようなちょっと疲れた感じのビジネスマンが、ふと窓の外を見ると、そこには双眼鏡を下げた少年が……。
誘われるようにして一緒に街の探検を始めるというストーリーが、デモ動画では流れます。
このField Tripは、GPSをオンにして街を歩き、登録されている街の名所やショップに近づくとプッシュ通知が表示され、ヘッドフォンをしていればその場所の解説もしてくれるという、当時は画期的なアプリでした(ほとんど話題にならなかったけど)。
これも当時はめずらしいクラウドソーシングで、ユーザーは自分で名所旧跡を登録できました。
ARアプリではないですが、デモ動画の紹介はまるでARです。
リリース時期からみて、Niantic LabsはField TripとIngressをほぼ同時に開発していたのだと思いますが、Ingressの人気が高まったので、そちらにシフトしちゃったようです。
Google Glassと組み合わせれば、これはこれで(Glassともども)もう少し人気が出たかもしれないのに残念でなりません。
その後、Niantic LabsはGoogleからスピンアウトし、Nianticになりました(Googleは今もNianticに出資しており、ポケモンGOのインフラはGoogleのものだそうです)。
ハンケさんは最近いろんなところで、「ポケモンGOは人々に街に出て歩いて、人と出会ってほしいから作った」と語っていますが、その思いはField Tripのころから一貫していたんですね。
ちなみにこのField Trip、2015年5月からアップデートされていませんが、まだGoogle Playからダウンロードできます。
久しぶりに起動してみたら、近所のおしゃれ住宅が登録されていました(登録したのは建築家さん)。
ポケモンGOの「ポケストップ」は今のところ一般ユーザーが登録申請できませんが、Field Tripの「カード」は今でもステップを踏めば登録できるみたいです。
ソニーは2016年7月29日、2017年3月期(2016年度)第1四半期の決算を発表した。
第1四半期の業績は、売上高は前年同期比10.8%減の1兆6132億円、営業利益は同42.0%減の562億円、税引き前利益は同58.9%減の570億円、四半期純利益は同74.3%減の212億円と減収減益の結果となった。
セグメント別では、「プレイステーション4(PS4)」関連のハード、ソフトが好調な他、ネットワークサービスも順調に成長を続けているゲーム&ネットワークサービス部門が大きく増収増益となった他、構造改革を進めているモバイル・コミュニケーション部門が黒字転換したことなどが好材料となったが、その他部門は軒並み苦戦。
為替の影響や熊本地震の影響などで半導体部門などが影響を受けた。
ソニー 代表執行役副社長 兼 CFO 吉田憲一郎氏は「半導体の国内での開発費が上がっていることや、ゲーム事業の本社を米国に移したことからドル円での為替影響度が変わっている。
ドルは1円高くなると営業利益でプラス35億円の影響度、ユーロは1円高くなるとマイナス50億円の影響度となる」と述べている。
連結業績見込みは、5月時点の予想比に対し5.1%下方修正したものの利益については前回予想比を据え置いた。
ただ、セグメント別では、熊本地震の影響を受けた半導体部門で売上高、利益ともに下方修正している他、今回譲渡を発表した電池事業を含むコンポーネント事業も売上高、利益ともに下方修正している。
なお、村田製作所への譲渡に伴う関連費用などは今回の決算には計上していない※)。
※)関連記事:ソニーが村田製作所に電池事業を売却――一般消費者向け製品は維持
●電池事業の敗因は製品力の問題
電池事業を村田製作所に譲渡するに至った理由について、吉田氏は「直近の赤字が続いている状況については、主力であったスマートフォン向けのバッテリーにおいて大手顧客の製品に入れず大きく影響を受けたことがある」と述べた。
ソニーはスマホ向けのリチウムイオン電池が電池事業の主力で、さらにここから電動工具向けなどに用途を拡大する方針を示していた。
ただ、主力だったアップルのiPhone用電池で受注が取れなくなり、収益の主軸が崩れたことにより、事業継続が難しくなったということがいえる。
スマートフォン向けではソニーはイメージセンサーで高いシェアを得ており、同じ販路を通じた販売戦略などをとることもできたが「実際に同じ販路で提案するケースもあったが、製品力では強みを発揮していたイメージセンサーと異なり、容量や充電速度など機能や製品力の面で受注をとることができなかったという経緯がある。
こうした製品力の面で力をつけるには開発投資が必要になる。
電子部品大手である村田製作所は、豊富な技術と人材を保有しており、電池事業を譲渡することで技術面や販路面でもシナジーを発揮できると考えた」と吉田氏は譲渡の理由について述べている。
夏休みに入ってすぐの7月22日、ポケモンGOの配信が始まり、多くの親は子供のスマホ漬けを心配したことでしょう。
野村総合研究所上席コンサルタントの北俊一さんがそんな親御さん向けに、スマホと上手に付き合えるアプリ「集中モード」を紹介します。
◇設定時間中は他のアプリ利用を防ぐ機能
夏休みがやってきた。
子どもにスマホを持たせている親としては、スマホの画面ばかり見ていないで、今しかできない体験をしてほしいと思う。
だから、このタイミングで「ポケモンGO」を開始した任天堂が恨めしい。
といっても、「だめ」と言ったところで親が夢中になっているのだから説得力はない。
「スマホ依存症の子どもは、親も依存症」という説があるが、認めざるを得ない。
とはいえ、自分の子どもをスマホ依存にはしたくない、依存症から脱却させたい。
小学生ならキッズケータイや、フィルタリングソフト、ペアレンタルコントロールソフトなどで、親が子どものスマホ利用を強制的に制限することは有効だ。
しかし中学生にもなると、親や学校の先生が上から押しつけてもうまくいかない。
では、子どもが自主的にスマホと上手に付き合えるようにするにはどうすればよいか。
そんな悩みに真正面から取り組んだアプリがある。
NTTドコモは7月12日、「集中モード」というAndroidアプリのお試し版をリリースした。
自分でスケジュールを設定すると、指定した時間に通知が来て、自らボタンを押すことでスマホが「集中モード」に切り替わり、LINEなどのSNSやポケモンGOなど、他のアプリが使えなくなる。
またアプリからの通知もブロックされる。
電話の着信と、緊急地震速報などを通知するエリアメールは制限対象外だ。
ドコモは2015年秋、子供向けに新しい価値を提供するためのプロジェクトチームを発足させた。
アプリ開発担当者によると、チームが中高生30人に1対1のインタビューをしたところ、60%の中高生が「やりたいことがあるのに、スマホの誘惑に負けてしまう」と回答した。
「特に試験前は、スマホが気にならないように親にスマホを預けたり、目の届かないところに置いたりする」「スマホを触っていて、そろそろ勉強しなきゃ、あと10分でやめようと思っても、気がついたら夜中の2時……そこから焦って取り組む」
このような声が聞こえ、中高生自身がスマホの使いすぎを問題だと感じ、葛藤している姿が浮き彫りになった。
◇自主的にスマホから離れる時間を作れる
また、チームは中高生の親80人にも1対1インタビューをした。
すると、「自分の子供がスマホ依存症になることは心配だが、子供のスマホ利用をコントロールすることは避けたい」という声が多く聞かれた。
このような親子の意見を繰り返し聞き、子供が自主的にスマホ依存症を解決することを支援するアプリ開発に着手したという。
その後も多くの中高生にインタビューし、繰り返しコンセプトを検証、改善して、16年5月からはβ版アプリを約50人の中高生に実生活で使ってもらった。
そこでさらにサービス内容やユーザー・インターフェース(UI)を改善し、いよいよお試し版リリースとなった。
アプリはAndorid版のみ対応で、残念ながらiOSでは利用できないが、ドコモ以外のキャリアでも利用できる。
Andoridスマホ持つ中高生のお父さん、お母さん。
この夏を有意義なものとするため、お子さんにこのアプリの利用を勧めてみてはいかがだろうか。
そして、使った感想、もっとこうなれば良いのに、という声を、ぜひドコモにフィードバックしてほしい。
今後、他社からも似た機能を持つアプリがリリースされ、互いに競争することで、全国の中高生たちがスマホと適切な距離を保てるようになることを、高校1年生の娘を持つ父親として切に願っている。
さらに Screen Rant に語ったところによると、彼が考えていた主人公はレッドと呼ばれている赤毛の少年。
彼の母親はかつて若くして成功を収めたポケモントレーナーだったが、所属していたポケモンバトルのチームから捨てられ、そのことがきっかけでレッドはポケモンを憎んでおり、ポケモントレーナーになることにも全く興味を持っていなかったが……というストーリーだったという。
「ものすごいエモーショナルで本当にクールな映画になるはずだった。
存在しないのが悲しいよ」と続け、傷心のあまりスマホゲーム「Pokemon GO」に手を出せていないとも語っていた。
(編集部・市川遥)
ハードウェア性能の限界に挑んだ初期の頃から、現実と見間違うほどのクオリティーを誇る最近のものまで、常に私たちの心を揺さぶり、楽しませ続けくれるゲーム。
主要なジャンルのひとつであるスポーツゲームは、様々な形で五輪と関わってきた。
両者はどのように交わり、どのように発展してきたのか。
ゲーム専門誌「週刊ファミ通」の編集長とデスクに、自身の体験とともに聞いた。
懐かしの定規プレーを再現・高橋名人のレアショット…五輪TVゲーム年代記
◇
■林克彦・編集長(42)
――業界全体にとって、スポーツゲームはどういう位置付けにあるのですか
家庭用ゲームが登場した初期の頃からスポーツゲームはとても人気が高く、ひとつのジャンルとして確立しています。
また、人の記憶に鮮明に残る、というのも特徴のひとつ。
たとえば野球ゲーム。
あの頃に子どもだった人なら、誰もが遊んだ記憶があると思います。
――オリンピックとの関係はどうでしょう
オリンピックといえば、世界中を巻き込む一大イベント。
私の子どものころは、学校で先生が授業中にテレビ中継を見せてくれて、クラスのみんなで応援した、そんな記憶すらあります。
そういった世の中の盛り上がりに、ゲームの世界も当然、無関係でいられるはずはありません。
そんな中でゲームとオリンピックを結びつけるきっかけとなり、みんなの記憶に残っているソフトとしては、やはり「ハイパーオリンピック」(コナミ、1985年)が挙げられると思います。
とにかくボタンを連打して速く走るといった単純明快なおもしろさは、まさにスポーツの原点。
今振り返ってみても、当時の子どもたちが夢中になるのも十分理解できます。
――あの頃のゲームならではの特徴というと、どんなことがありますか
あの時代のゲームを語る上で欠かせないのは、当時の時代背景への理解です。
今とは異なり、ライセンスや許諾といったものへの考え方で、あの時代特有の「ユルさ」というようなものがありました。
もちろん、これはゲーム業界に限ったことではありませんが。
今では考えられないことではありますが、その一方で、それはあの時代の良さでもありました。
そういった社会全体の「ユルさ」のおかげでたくさんのゲームが発売され、子どもたちを通じてオリンピックのムードを盛り上げることに貢献したという部分があるのも事実です。
野球ゲームなど他のスポーツゲームも同じような状況にありました。
そんな時代背景があったからこそ、先ほどの「ハイパーオリンピック」のような数々の名作が生まれ、私たちの記憶に残ったのです。
そうでなければ、あれだけたくさんのゲームが発売され、スポーツゲームというジャンルそのものが盛り上がることもなかったと思います。
――その後、時代が進み、ハードウェアの性能も大きく進歩しました
先ほど指摘したライセンスに対する考え方も世の中全体で大きく変わり、ゲーム業界もその流れに従った結果、確かにオリンピックに関係するゲームの数は減ってしまいました。
しかし、ハードウェアの進歩に加え、ゲーム制作者の努力もあってスポーツゲームそのものの奥深さや幅が広がり、多様な楽しみ方ができるようになりました。
スポーツの原点のおもしろさとして「単純明快」ということを指摘しましたが、今のゲームの魅力はそこにとどまりません。
実際にプレーヤーが動かすゲーム内の登場人物は、それぞれのキャラクターによって特徴付けがはっきりしており、ゲーム内で結果を出すためには単なるキーやボタン操作だけでなく、工夫や戦略といったものが欠かせません。
決められたルールの中で何をするべきか、プレーヤーが考えさせられる部分が以前のゲームに比べると飛躍的に増えています。
ただ、「遊び」としての根源的な部分は、実は変わっていません。
今も昔も、ゲームをするプレーヤーにとって最大の関心事は「そのゲームをどれだけ極められるか」ということ。
そこに情熱を注いだ分だけ、記憶にも残るんだろうと思います。
その根源的な欲求を、いかにテレビゲームの世界に転換できるかが、おもしろさにつながるゲームとしての勝負どころ。
かつては8ビットの世界で実現していたものが、今は実物と見まごうばかりのCGになりましたが、本質は同じだと思います。
――リオオリンピックを前に、公式ゲームも発売され始めました
最近のオリンピックの公式ゲームとして、最も注目を集めているのはやはり「マリオ&ソニック」シリーズ(任天堂・セガ、2007年〜)でしょう。
オリンピックという世界的イベントに対し、同じように世界中で人気があり、日本を代表するキャラクターであるマリオとソニックがタッグを組んだというのは、とてもいい試みだと思います。
そしてその結果として、この2大キャラクターをひとつの画面で同時に見ることができ、しかも関連する数多くのキャラクターも同じゲーム上でそろうという、ゲーム業界からすれば革新的なことが実現しました。
このワクワクする感じは、ひとりのゲームファンとしても素直にうれしいです。
――スポーツやオリンピックのゲームについて、ご自身の個人的な経験はいかがですか
子どものころにも様々なゲームをやっていたのですが、個人的にハマったスポーツゲームとしては、セガサターンの「デカスリート」(セガ、1996年)を挙げたいと思います。
当時は20代前半で、すでにファミ通編集部で働いていたのですが、仕事が終わった後に会社に残り、同僚とそれこそ翌朝まで腕を競い合いました。
気の合う仲間とゲームをやり込むのは、年齢がいくつになっても楽しいものです。
そして、その仲間に勝ちたい、一位になりたいという情熱も子どもの頃と同じ。
「コソ練(仲間に隠れてコッソリ練習すること)」もやっていましたし。
――子どもだけでなく、そうやって大人もハマってしまうスポーツゲームの魅力は、どういったところにあるのでしょうか
ストイックに究めようと思えば、ひとりでどこまででもやり込める一方、大勢でガヤガヤとプレーしても盛り上がる、その両方の楽しさが同時に存在するのがスポーツゲームだと思います。
(1)練習を繰り返して上達すると
(2)その技をみんなに見せたくなり
(3)ゲームが終わった後も話をしたくなる
そういった一連の流れが、スポーツゲームの魅力につながっているんだと思います。
――オリンピックやスポーツのゲームは、これからどんな方向に向かっていくと思いますか
ゲームの世界では今、ゲームの大会や競技をスポーツとして捉える「eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)」という考え方が広がっています。
世界的に見ると米国や韓国が先行していて、日本でも少しずつ浸透している状況です。
スポーツをゲームで実現するのではなく、ゲームをすること自体がスポーツであるというこの動きは、東京オリンピックがある2020年にはさらに広がっているでしょう。
私たちもメディアとして、何らかの企画を考えたいと思っているところです。
もう一つはVR(仮想現実)をゲームに採り入れる動き。
いわゆる「酔い」の問題など課題もありますが、技術の進歩も著しく、可能性を感じます。
ゲームは基本的に自分の手を動かすものですが、最近では人のプレーをみるという楽しみ方も動画サイトなどを通じて広がっています。
VRの発展は、そういった「ゲームを『する』のではなく『みる』」という楽しみ方に、新しい魅力を提供できる可能性もあるのではないでしょうか。
◇
■菊地祐一・デスク(41)
――スポーツゲームはなぜ、我々を引きつけるのでしょう
操作自体はシンプルであるにもかかわらず、ちょっとしたタイミングの違いで結果に大きな違いが出るスポーツゲームは、やり込みがいがあるジャンルのひとつで、無限の楽しみ方があると思います。
また、ゲームを楽しんでいるうちに、そのスポーツのルールや奥深さを理解できるというメリットも見逃せません。
それはオリンピックでも同じ。
普段あまりなじみのない競技でも、事前にゲームで親しんでおいたことで、観戦の楽しみが何倍にもなったという経験は、多くの人にあると思います。
――ご自身ではどんな思い出がありますか
編集長も挙げていた「ハイパーオリンピック」は、私もよくプレーしました。
ただ、私の場合はファミコンよりも、むしろゲームセンターでやり込んでいた記憶があります。
当時はまだ家庭用ゲームのハードの限界もあり、時代の最先端を走っていたのはゲームセンターにあるアーケードゲーム。
ハイパーオリンピックに関しても、ゲームセンターではファミコンで発売される2年前から遊ぶことができました。
当時はまだ小学校の低学年でしたが、ゲームセンターに通ってよくプレーしました。
当時流行した「定規を利用したボタン連打」もゲームセンターで覚えたと記憶しています。
この方法を使うと、走る速さのレベルゲージは振り切れてしまうため、好結果を出すカギはジャンプするタイミングのみ。
よりシビアさが求められ、まさにオリンピックに出場するアスリートのような気持ちになって遊んでいたことを覚えています。
――あの情熱の源は何だったんでしょうか?
今はゲーム以外にも様々な娯楽があふれていますが、あの頃のエンターテインメントはゲームが支配的でした。
そのなかで「明日は友達に勝つんだ」という気持ちが自然にあふれ、私たちを突き動かしていたのではないでしょうか。
(聞き手・田之畑仁)
ゲームはスマートフォンとニンテンドー3DS向けに2017年4月から配信・発売される。
マンガは今冬から「月刊コロコロコミック」で連載を始める予定。