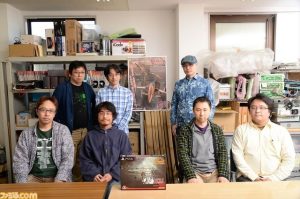『バトルガレッガ Rev.2016』発売記念ロングインタビュー エムツー初のパブリッシング作として度を超えた熱意が注ぎ込まれたタイトルは、こうして生まれた!
文・取材:ライター 馬波レイ、撮影:カメラマン 堀内剛
●エムツー ショットトリガーズ第一弾として開発!
1996年にエイティングよりアーケード用に生まれ、いまなおファンにプレイし続けられている縦スクロールシューティングゲーム『バトルガレッガ』。
その伝説的なゲームが、2016年12月15日プレイステーション 4用タイトル『バトルガレッガ Rev.2016』としてエムツーから発売された。
“エムツー ショットトリガーズ”のブランド第一弾として初の自社パブリッシング作品である本作は、いかにして形作られていったのか。
このインタビューでは“移植を超えた移植”が生まれるまでの過程や秘話を開発スタッフにたっぷりと語っていただいた。
参加者の人数が多く、また役割も多岐にわたるため、会話がやや入り組んでいる部分もあるが、スタッフどうしがそれだけ有機的に仕事を重ねていったことの証拠。
また、この手のインタビューではカットする雑談めいた部分もあえて残している。
そのざっくばらんさから、エムツーという会社のメンバーが、どのようにゲームを捉え、考え、制作しているかまでが伝われば幸いである。
気鋭の開発スタジオが満を持してパブリッシャー参入! エムツーが仕掛ける“エムツー ショット トリガーズ”という新たな挑戦
■ゲームを丸裸にする“M2 ガジェット”はこうして作られた
――本日はよろしくお願いします。
まずは皆さんの今回の役割をおきかせいただけますでしょうか?
長野エムツー ショットトリガーズのシリーズディレクターを担当しています。
裏ですべてを操っています。
一部では“堀井の上司”とも呼ばれています(笑)。
冬野タイトルディレクターです。
開発前半はひたすら『バトルガレッガ』をプレイしながら「こういうものがプレイヤーに望まれているのではないか」という仕様の洗い出しを、後半にはひたすら公式サイトやパッケージなどで使われるビジュアルを作成していました。
長野冬野はこれまで二回やったイベントのオーガナイズも久保田といっしょにやっているんです。
ほかに、限定版の構成案を考えたりして、大活躍でした。
久保田プランナーとして参加しましたが、アシスタントディレクターという役割を途中から自分で作りました(笑)。
担当は、UI絡みの仕様策定全般、動画作成やイベント系の仕込みもやっていましたね。
長野前半は『バトルガレッガ』の完成度を高めるために、オリジナルと『Rev.2016』の速度を動画で比較したりとめちゃくちゃがんばってくれました。
福井原作プログラムの解析をメインに、プレイモードのチューニング、サウンドコアの改善、サウンドデータコンバータの構築(M2PCM対応ほか)を担当しています。
春日“M2PCM”でRev.2016 perfect editionを鳴らすための改造および、そのほかサウンド周りの作曲以外のもろもろをやっています。
並木もともとアーケード版のオリジナルコンポーザーであり、今作ではサウンドディレクターとして基本サウンドに関わる作業をしました。
河内プロジェクトマネージャーを担当していまして、限定版の制作進行を含めて、パブリッシング業務全般を受け持ちました。
堀井プロデューサーです。
お金や時間を確保したり、やりたいことを言って却下されたりしました(笑)。
これから先もやりたいことを言って、どんどんやっていきたいと思います。
――以前のインタビューでは、ゲーム本体は動いていましたが、まだ追加要素が入っていない素の状態でしたので、それ以後の実制作でのエピソードをお聞かせいただけたらと思います。
まずは、ユーザーのあいだでもすでに話題になっている“M2 ガジェット”ですが、そもそもどのように作成されていったのでしょう?
長野企画の初期段階で「こういう機能が欲しい」というのを洗いだして、できる/できない/難しいといったように振り分けていきました。
冬野ただ、仕様書を切る時間がなかったので、いきなりM2 ガジェットのUIを組んでしまうという荒業を使ったんです。
まずはガワありきで、中身に関しては解析の作業を進めながら細かく仕込み直してもらうというプロセスでした。
福井ですので、時間的な問題で泣く泣くカットしたM2 ガジェットもあります。
冬野たとえば最初はボスのHPは“できない”部類だったんです。
アイデア段階ではパーツ単位でのHPを表示させたいという要望だったのですが、それをするには時間が足りないということで一度は引っ込めました。
でもいつの間にか「パーツは無理でも、ボス本体なら出せます」ということになっていて。
(一同笑い)
長野そういうキャッチボールは開発中盤では多かったですね。
プログラマー班から「これが出せるようになったのでデザインを足してくれませんか」といったように。
冬野久保田のほうで水面下でM2 ガジェットの仕様をかなり細かく作ってもらっていたのですが、本来ゲームにはない仕様を付け足すというゼロから1を生み出す仕事には凄いカロリーが必要になる。
そのため、社内で誰も仕様策定に手を挙げなかったんです。
けっきょく締め切りまでの猶予がなくなってしまったので、「じゃあ僕がやります」と手を上げて。
それでゼロが1になったので、そこに肉付けをしてもらって完成したということです。
――M2 ガジェットのデザイン制作で苦労された点は?
冬野画面の中央にあるゲーム本体と、その左右にあるM2 ガジェットのUIをどうつなぐのが理想形なのかがわからず、しばらく悩んでいた時期がありました。
ふつうのフォントであったり、高解像度のUIを構築すべきなのかと。
それが、あるときテストプレイヤーから「ゲームと関係ないフォントが画面に入っていると嘘っぽい」という言葉をもらって、そこでゲーム中のフォントやパーツを引用して構築するという突破口が生まれました。
長野基本仕様は久保田のほうで策定をして、そこに冬野がデザインをあてはめていったという形です。
――発表時にはM2 ガジェットをユーザーが自由に配置できるとのことでしたが?
長野今回は開発時間が足りずにM2 ガジェット単位でのオン/オフの切り替えのみとなっています。
今後は置き換えられる仕様にしようと思っています。
冬野最終的にはM2 ガジェットを自由に配置できるエディターを搭載する予定ですが、それは今後のDLCで対応したいと思います。
■原作のプログラムを徹底解析したからこそ見えたもの
――ゲームランクやボスのHPといった本来表には出ていないパラメーターを視覚化するというのがM2 ガジェットの大きなウリになっているかと思うのですが、そうしたパラメーターの目星はどうやってつけたのでしょう?
福井最初の段階では実行形式のプログラムしかなかったので、まったく手がかりがない状態でした。
そのために原作のプログラム解析が必要だったんです。
作業は苦戦の連続でしたが、冬野が策定したM2 ガジェットの中身(数値)を出すというゴール、そこにたどり着く喜びは格別でしたね。
長野中でもHP表示はテストプレイヤーから「これが見られるとゲームの難易度や稼ぎかたが変わってくる」とすごく好評でした。
――開発途中で原作のソースコードが発掘されたそうですが、どのタイミングだったのでしょう?
福井すでに解析がほぼ終わったあとでした(笑)。
とはいえ、解析したパラメーターとの答え合わせができたのと、最後の追い込みには役立ちました。
やっぱりソースコードを見ると、プログラムの全体像がイメージできるようになるんです。
それまでは実行形式のプログラムしかありませんから、まるで暗闇の中を手探りするかのように「このレジスターはこのパラメーターだろうな」と当たりをつけていく作業だったんです。
長野でもハードルもあったんだよね?
福井変数名が暗号になっていたんです。
略語と略語をくっつけていて作られていたりして、名付けた本人は読めるんだけど、ほかの人が読めない。
その解読時間がまず必要だったんです。
読むのは一苦労でしたが書いた本人にとっては合理的ですし、読んでいるうちにプログラマーの意図も見えてきましたね。
――完成したプログラムを通じて製作者とコミュニケーションを取るというか。
すごいことになっていたのですね。
福井時には立ちはだかる壁となり、時には先を照らす明かりとなって。
久保田人知れず電子の海で大冒険をしていたわけですね(笑)。
春日サウンドでも同様のことがあったんです。
サウンドのソースでは変数名に一般的な単語が使われていたので、まだ助かりました(笑)。
福井『バトルガレッガ』の基板は、ゲームはMC68000、サウンドはZ80と別々のCPUで動作していて、プログラムを書いている方が違うんです。
春日原作に関わった並木がいたので、福井よりは多少楽だったかもしれません。
たとえば、効果音を鳴らす仕組みとして、ゲーム側から1フレームごとに効果音を鳴らせというリクエストが来ても、連続で鳴らないようにする“間引きテーブル”という仕様があるとか。
並木アーケード版開発当時、そういう仕様が必要だと自分が考えてプログラマーに言って、用意してもらったものなんです。
福井『Rev.2016』では、BGMを新たに“Rev.2016 perfect edition”として作り直しているのですが、それを実現するにあたっても、間引きテーブルの情報も必須だったんですね。
堀井アーケードからすると2代目プログラム担当って感じだよね。
あとはPCMのチャンネルを16に増やしたりしたから、処理的な負荷があっただろうしね。
福井今回仮想チップとして“M2PCM”を社内で設計して基板に追加したんですが、それに対応するプログラムを春日が再構築していったわけです。
春日開発の初期でストリームで音を鳴らす必要があるという仕様決めがあったときに、どの段階で鳴らすのかという問題があって、ゲーム内のサウンドに関しては、けっきょくZ80ですべてをまかなうことにしたんです。
長野ちょっと補足すると、エミュレーターで動作しているZ80で動かすのも、上位層のプレイステーション4の実行プログラムで動かすのも、工数的にはいっしょなんです。
新しいPCMを載せてやったほうが間違いがない。
それに、メインプログラマーの作業がかなり詰まっていたので、だったら春日くんががんばればどうにかなるだろう、と(笑)。
――エムツー名物の“がんばれば”でしたか(笑)。
春日社内での人的リソース管理ゲームみたいになっていましたね(笑)。
堀井実質的な話で言えば、その作業は8月の終わりくらいに行っているんですよ。
12月発売のゲームなのに。
河内プロジェクトマネージャーとしては絶対止めたかったです(笑)。
長野話をM2PCMに戻すと、エミュレーター系は別の担当プログラマーがいるのですが、その人も優秀で、一週間程度でプログラムを完成してくれました。
並木は当初「こんなの無理だよ!」レベルの仕様を要求してきたのですが、それがほぼ実現されましたからね。
並木実装する前に僕がM2PCMと、それを使ったリニューアルBGMの制作を提案したんです。
長野「これができたらエムツーっぽいよね」と言っていたものが、ほぼすべて実現できたのは我々にそれだけのスキルがあるからだと再確認できたのは大きかったですね。
春日(ボソリと)どれも綱渡りでしたけどね。
(一同笑い)
――スタッフそれぞれが、自分の受け持った部分をしっかりと仕上げたからこそなし得たのだと。
並木「ストリーム再生をどうしよう」とサウンド周りの仕様決めで社内が混沌としていたときに、自分がM2PCMというアイデアをひらめいて、10分くらいで提案書にまとめてプレゼンし、それから設計仕様を書いたんです。
この設計の仮想音源チップを搭載できれば、ストリーム再生も、自分が手掛けるリニューアルBGMも再生可能となるし、なおかつセールスポイントにもなる。
任天堂の宮本茂さんが「アイデアというのは複数の問題をいっぺんに解決することだ」とおっしゃっていたんですが、まさにそのとおりでしたね。
我ながら名案でした。
■スーパーイージーモードは“シューティング教習所”!?
――追加要素についてお伺いします。
まずはスーパーイージーモードとプレミアムモードについて。
久保田基本コンセプトは冬野のほうでモードの草案を作って、福井からは(解析した結果から)どういう改造ができるかという声を聞きながら、オプション項目を増やしていきました。
そのオプション項目をいくつか束ねたものがスーパーイージーとなっています。
プレミアムモードは「別物を作ろう」ということで、それこそマスターアップ直前まで手を加えまくっていきました。
ある意味福井の暴走の成果ですね(笑)。
福井ギリギリまでテストプレイヤーと議論と検証を続けて、意見を取り入れたりもしました。
――では、オプション項目がめちゃめちゃ細かく用意されているということなんですね。
久保田そうです。
オプション項目はカスタムモードにすることで設定可能なのですが、設定次第では、スーパーイージーモードよりもさらに簡単にすることもできます。
各モードはランキングで個別の集計となります。
アーケードモード、スーパーイージーモード、プレミアムモードと、カスタムモード用のランキングになります。
カスタムモードではどんなオプション設定でもオーケーなので、闇鍋みたいなランキングになると思います。
前出の3モードは1周エンドなので、カスタムランキングの上位は2周が占めると思います。
長野アーケード版の隠し要素であるステージエディットやスペシャルコースも、カスタム扱いになります。
――なるほど。
では、プレミアムモードはどんな仕上がりなのでしょう?
冬野すでに『バトルガレッガ』ではない“なにか”ですね。
(一同笑い)
冬野開発中盤に「こんなことができたらいいな」という草案を用意したのですが、その後に限定版やポスターのビジュアル制作にかかりきりになってしまったので、調整に関わることができなくなってしまったんです。
長野スーパーイージーは、おもに自分が、プレミアムは福井と久保田、テストプレイヤーとで調整をしました。
プレミアムは、クリアーをするだけなら楽しいけど(点数)稼ぎをしようとすると難しいテイストになっています。
福井スーパーイージーはかなり冒険をしていて、一般的な家庭用シューティングと比べても、かなり親しみやすい難度になっています。
「シューティングゲームって難しいから」と敬遠されている方でも十分にクリアーできるものになっていると思います。
久保田やっぱり“『バトルガレッガ』=難しい”というイメージを持たれてしまっているので、そこを払拭しないと、という使命感から用意しました。
長野ゲームの世界観や音楽を楽しみたいけど、難しくて先に進めなかった人でも、達成感を感じつつ最終ステージまでを楽しめるという味付け。
慣れてない人でも楽しめます。
自分もそうなんですけど、中級者の方ならアーケードのスコアラーの真似をしながら気持ちよく稼ぎができます。
――以前のインタビューで堀井さんが“ガレッガ養成ギプス”にしたいとおっしゃっていましたが、入り口としての機能が用意できたということですか。
堀井そうですね。
スーパーイージーは、シューティングを初めてプレイする人の入り口〜つぎのステップへ進むためのモノとなりました。
福井シューティングのチューンをするにあたって一番難しいのがそこで、ゲーム初心者にとってはちょうどよくても、中級者以上にとっては簡単すぎる場合もある。
今回はなるべく簡単なほうに幅を広げたというところです。
ある意味スーパーイージーモードは、シューティングゲーム養成の……。
堀井(遮って)そう、シューティングゲーム教習所!
――シューティング教習所!
堀井そのスーパーイージーという難度でゲームのルールを理解して、避けたり撃ったりをしながらスリルをちゃんと味わって、(シューティングゲーム的快感)脳汁がちゃんと出ているわけですよ。
そのため、アーケードで6面を超えられるような人がプレイすると「なんじゃこりゃ」となる。
福井社長の言葉を借りるなら、“シューティング教習所”として楽しくシューティングを遊ぶための基礎教養を学んで欲しいという意図ですよね。
堀井それを『バトルガレッガ』でやるのはどうかっていう部分もあるでしょうけど、やれる!やれるんです(笑)。
久保田ユーザーさんにとっては半信半疑な部分もあると思いますが、やってみると「ああ、なるほど」と感じてもらえると思います。
長野ほかのインタビューでも言っていますが、単にランクを下げるだけではスーパーイージーにはならないんです。
そこで福井が敵の弾を間引いたり硬さを変えたりといったチューニングを行っているんです。
久保田出現テーブルには手を加えていないんですが、敵はかなり柔らかくなっていて、ザコ敵は基本ショット1発で倒せます。
小さな戦車が意外に硬い、みたいなのが『バトルガレッガ』の辛いところなので。
――難度を下げすぎたみたいなこともあったり?
長野ボスのHPが少なすぎてすぐ倒せてしまうケースもありましたね。
福井そこも苦労がありまして、硬さの解析をボス1体1体に対して行っているんです。
原作のボスはランクに応じてHPが変化するのですが、スーパーイージーやプレミアムでは「一番おもしろい硬さはどこか」を探した上での固定値なんです。
長野「これだと柔らかすぎて稼げない」なんて言っていたね。
久保田テストプレイヤーのDBSさんは喜んでやってくださったのですが、社員でもない方をド深夜まで付き合わせてましたからね。
まさに(『ガレッガ』)警察24時(笑)。
堀井夜中の3時すぎまでやっていたよね。
福井最終的にはスーパーイージーは、ふだんシューティングはあまりプレイしないサウンドの春日がノーコンティニュークリアーできるレベルになりました。
春日さっきも話に出た、上級者の真似ができるというのが気持ちいいですよ。
スペシャルウエポンがすぐに貯まるから、2面の鳥を焼き放題だったり。
堀井勲章の吸着があるのもラクなんだよね〜。
長野自機が勲章に近づくと、吸い込んでくれるんですよ。
ただ、それに慣れてしまうとアーケードモードがヘタになってしまう。
春日『バトルガレッガ』って敵を倒す、弾を避ける以外に、勲章を逃さず取ることも攻略要素なので、考えることがひとつ減る。
福井スーパーイージーは“人をダメにする『バトルガレッガ』”ですね(笑)。
ほかにも1面のボスについている通称“ドリーム砲台”は、弾速が早すぎて初心者はたいてい死んでしまう。
そこで解析をして速度を落として“ゆっくりドリーム砲台”にしました。
久保田ブラックハートのワインダー弾もそうですね。
福井ワインダーの角度変化をゆっくりにして、見てから避けられるようにしています。
冬野原作を知っている人は自分から弾に当たりに行ってしまう(笑)。
――初見殺しも甚だしいワインダーですが、スーパーイージーなら「小足見てから昇竜余裕でした」なプロ気分を味わえるぞと(笑)。
長野『バトルガレッガ』だからここまで掘り下げられたんだと思います。
福井関連した話だと、敵が放つ弾の間引きにも苦労しましたね。
長野最初はみっともない形だったけど、福井が一生懸命直してくれましたね。
福井最初は弾が1発撃たれるごとに1発を間引くという単純な手法を取っていたんです。
ただそれだと、扇形に放たれる“WAY弾”が片側だけしかでないような、みっともない見た目になってしまったんです。
ですので、WAY弾そのものの発射方式の解析までしたのですが、そこから先にまたハードルがあって、専用の処理をもっている敵がいくつかいたりして泣かされました(笑)。
長野WAY弾が片側にだけ出たり、360度に放たれる弾がカットされたバームクーヘン状になっていたりすると、みっともない以上にゲーム性も変わってきちゃいますからね。
そこを可能な限り潰していったということです。
――テストプレイはどれくらいの頻度で行なっていたのでしょう?
長野基本的には“作っては直し”なので、ほぼ毎日です。
スーパーイージーに関しては、あまり上手じゃない社内の人間を連れてきてプレイさせたりしてました。
冬野最初は「『バトルガレッガ』はこういうゲームです」というセオリーを説明するんですけど、一様に苦い顔をしていたんですよね。
でも、テストプレイをくり返していくうちに何も言わずに攻略してくれるので「みんな成長したなあ」と(笑)。
久保田終盤になると開発スタッフどうしで“ガレッガコミュニティ”が出来上がってましたよね。
福井並木も最後にプレミアムの調整に関わってくれたんですが、「難度カーブがまだ甘い!」と言われました。
並木サウンドのチェックを兼ねてテストプレイはずっとやっていて、新規追加モードをプレイできる状況にあったので、自然な感じでアドバイスをしていましたね。
「サウンド担当なのに?」と思われるかもしれませんが、もともとはオリジナルの開発者でもありますので。
久保田『バトルガレッガ』って、「じつはこうするのが正解だった」というのをあとで知ることが多いゲームなんです。
とくに今回M2 ガジェットでゲームの内部情報が視覚化されたことで、自分のプレイが客観視できるようになった。
長野正解が狭くないのがまたいいよね。
自分から正解を狭めて考えていた人でも、「ここまで苦労しなくてもいいんだ」と思い直すケースも生まれる。
福井自分なりのクリアーの仕方が明らかになるということですね。
――M2 ガジェットの構想を聞いたときの第一印象は「そんなことをしていいの!?」だったのですが、結果としてより深くゲームを知るためのツールとして、しっかりと成立できたようですね。
もちろんそれは、これまで原作の『バトルガレッガ』攻略に心血を注いできたプレイヤーの努力があったからでしょうけど、発売から20年という年月を経て、また新しいアプローチで楽しめるようになったというのは、すごいことだと思います。
堀井ハードに余力ができたことも大きかったですね。
原作の基板を動かした上で、さらにガジェットなんかも追加できる。
プレミアムモードに関しては、あえてまだ黙っている部分もあるんですが、これまで話した部分だと、ステージの順番を変えていてランクは固定です。
並木ステージ順は、12月10日に開催したイベント“出撃!ガレッガ警察24時〜年末大捜査SP〜”でDJプレイした曲順がヒントになっています。
久保田それは気づかなかったー!“ガレッガ警察”の映像は、スーパースィープ様のYou Tubeアカウントにて公開されておりますので、再訪していただければと思います。
個人的には“ガレッガおしゃれ談義”が聞けたのがよかったと思います。
世界観が作り込まれているゲームということもあって、スコアとは関係なく、いかにカッコイイプレイで魅せるかという。
――フィギュアスケートの技術点と芸術点のような(笑)。
『バトルガレッガ』は警察があったりおしゃれだったりと、どれだけやりこまれているんだというエピソードです。
福井リプレイ機能もこだわったんですよ。
プレイステーション4版は自分のプレイを録画できて、1/60秒単位でコマ送りができますので、おしゃれなプレイを録画した後、“ここを見て欲しい”という部分を再生して、ぜひシェア機能でSNS投稿していただきたいです。
■突然のロケテ! パズルのようなスケジュール管理
――秋葉原のゲームセンタHeyで、ロケーションテストを2回にわたって行われましたが、これはどのような経緯できまったのでしょう?
長野堀井の「やりたい!」からだよね。
堀井発売前の露出が欲しかったんですよ。
ありがたいことに発表から発売までファミ通さんを始めさまざまな媒体で記事にしていただいていたんですが、ユーザーさんに向けた“もうひと押し”が欲しいと思っていたんです。
だったら、いまあるモノをゲームセンターに置かせてもらえれば、フィードバックもあってWin-Winじゃね? と思ったんです。
長野俺は「どこにそんな時間があるんだよ」って止めたけどね。
――テストに出すための手直し作業が必要になりますもんね。
堀井そうなんです。
デベロッパーあるあるでいうと「ショウに出展するバージョン制作に1ヵ月取られたけど、締め切りは変わらないじゃん!」というヤツ。
長野でも堀井は、こっちが知らないうちにHeyさんにコンタクトを取っていて、しょうがないから俺もついていったんですよ。
そしたら先方さんがもうノリノリで、やる前提になっていたんです。
堀井長野の言うことも当然で、すでに原作の『バトルガレッガ』が稼動しているHeyさんで、もうひとつ『バトルガレッガ』を置けるものなのかと。
ただ、僕としては「両方の『バトルガレッガ』を遊び比べたくなるはず」といってなんとか説得して。
久保田Heyさんは「配信もやりますよ!」、「ポスターも作りましょう!」とノリノリでしたね。
長野と、やらざるを得ない状況になったので、プログラマーをひとり拝み倒して手伝ってもらったり、筐体に組み込むための助っ人を調達したりと、突貫工事で仕上げました。
そのため、ロケテストが始まってからも数回アップデートをしているんです。
堀井当初は週末だけの3日で終わらそうと思っていたけど、延長となったからね。
冬野僕はポスター用ビジュアルの作業があったので、最初のロケテはいけませんでした。
――その話が出たところで、新規ビジュアルについてお聞きしていきます。
前半はディレクション作業をして、後半はビジュアル制作をされていた。
冬野さんはグラフィックデザイナーとして以外にも、イラストレーターとして活躍をされていますが。
冬野『バトルガレッガ』のビジュアルを手掛けるのは初めてでしたが、機体の数が多かったのがたいへんでしたね。
しかも3DCGを作るための三面図とかがあるわけではないので、わからない部分は設定画やイラスト、ドット絵から想像して制作を進めました。
幸いにもオリジナルのドッターさんと知り合いだったので、「こういうニュアンスでどうかな?」とTwitterで進捗を報告しながら進めていました。
基本的にはツッコミが入らなかったので、大きくニュアンスを外していないんじゃないかな。
長野原作のドッターさんにも評判がいいですよね。
冬野最初は自分から「社員に3DCGができる人間がいるんだから、穴埋めくらいのビジュアルなら作りますよ?」と進言したんですけど、気がついたらほぼ専任になっていました。
長野限定版を作ることになってからビジュアルは必須になっていましたね。
冬野機体モデルそのものは春くらいから準備を初めていて、完成一歩手前の状態でまで出来ていたんです。
ただパッケージやポスターのビジュアルとして使うとなると、データを整えたりレンダリングをしたりといった仕上げの作業が必要になる。
それが、8月の頭2週間でM2 ガジェットの外枠を作る作業に没頭していたので、まったく止まっていたんですね。
長野公式サイトのディザービジュアルとして4号機を公開しましたけど、その段階ではほかの機体は未完成だったんです。
冬野唯一完成している4号機のビジュアルをティザーや販促告知に使い回しつつ、裏では1号機、3号機を作っていました。
限定版に入っているポストカードのビジュアルは各機体とボスが対決している構図なんですが、両方が揃っていないと制作ができない。
印刷の締め切りなどを含めて制作行程がパズルのようで、どこか一手間違えたら破綻していましたね。
ボスの一部は外部のCGモデラーさんにも手伝っていただきました。
――となるとパッケージのビジュアルが完成したのは……。
冬野ゲームのマスターアップ付近でしたね。
いろいろなところで使われる絵になったので間に合ってよかったですが、完成直前までは寿命が縮む思いでした(笑)。
でも、自分が遊んでいたゲームを仕事としてここまでガッツリ手掛けたのは初めてだったので、充実感はありました。
ただ『魔法大作戦』機体とかは作っていませんからね……。
全員おお、作るんだ!
長野今後の『バトルガレッガ』の展開にあわせていろいろ展開できるといいね。
冬野自分の機体の壁紙とか欲しいじゃないですか。
まだモデルを作ってないボスもいますし。
■初めてのパブリッシング、初めての限定版
――エムツーさんとしてはパブリッシャー参入作品にして、最初から限定版を制作することになったわけですが。
河内まずパブリッシャーとしてのゼロからのスタートでしたから、ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア(SIEJA)さんにどうやって連絡を取ったらいいんだ、というところからのスタートでした。
最初にお話をしにいったのが、去年の11月くらいでしたでしょうか。
一番困ったのが、限定版の話がでたときで、ダウンロード専売のゲームに物理コンテンツがついた商品構成が、前例がかなり少ないとのことだったんです。
こちらが知らないのも相まってたいへんドタバタしましたが、SIEJAの担当者さんに手助けいただいたおかげで完成しました。
堀井いろんなエピソードを話してから結論にいこうぜー。
河内あまりにエピソードが多すぎるので、全部話すときりがないかなと(照れ笑い)。
限定版の物品を制作していただいたメーカーさんにも非常に親身にご対応をしていただいて……さっきから何度か奇跡という単語が出ていますけど、限定版はまさに“奇跡の詰め合わせ”といったところでございます。
(一同笑い)
河内プロジェクトマネージャーとしてはゲームの制作進行が本業なのですが、開発に手練のメンバーがそろっているので、スケジュール管理は非常に楽をさせていただきました。
限定版の制作があまりにたいへんで、そちらに意識が向いてなかったのかもしれませんが(笑)。
ブックレットにせよ、紙の厚さを重さで示すことすら知らないところからのスタートでしたから。
ただ、冬野と長野を中心に企画をした商品構成から、ひとつもかけることなく完成できたことはうれしいですね。
堀井河内は「絶対ヤバイです!」とみんなを早めの締め切りで急かしつつ、それを使い潰してなお足が出るというところでした。
――(ブックレットをめくりながら)これはちょっとすごいですね。
同じゲームメディアに関わる人間として、ここまで凝ったことができることを羨ましく思います。
久保田並木のインタビューでは当時どんな音楽を聞いていたかの資料まで掲載されていますからね。
並木がどんな思考で『バトルガレッガ』の楽曲を作っていたかがわかると思います。
河内スコアラーさんへのインタビューもいい話満載ですし、なにより初公開の絵コンテがすごいです。
久保田紙に敵の出現位置や演出などが時間軸にそって描かれているんですけど、ゲームで忠実に再現されていて。
――仕様書はともかく、絵コンテという形式は珍しいですね。
堀井なくはないんですけど、作っていくうちに変わってしまうことがほとんどなんですよ。
『ガンスターヒーローズ』でも絵コンテはあったんですけど、ゲームを作る前に描いたものかどうかはわからなかった。
並木当時のライジングは絵コンテありが主流でしたね。
――絵コンテがあったことは楽曲にどう影響したのでしょう?
並木たとえばオープニング曲は、画面ができるより先に絵コンテだけで書きました。
全員ええーーっ、すごい!
並木僕らにとってはそれが当たり前なんです。
――絵コンテを書かれた方の頭の中では、ほぼほぼゲームが動いているんですね。
並木そういうことです。
微調整はしますけど、我々制作チームとしては、絵コンテで情報が共有されていました。
これまで発言したことはないかもしれませんが、『バトルガレッガ』のBGMって初めのころは紙の絵だけを見て作っていましたから。
久保田完成形を知っているから、逆に絵コンテどおりでビックリしました。
並木メーカーによっては仕様書、設計書ありきで作っていくことはありましたね。
企画職が動かないと、グラフィックもプログラムも動かないという、プロフェッショナルどうしのチームワークが行われている現場を見てきました。
ゲームによっては、仕様書段階でキャラクターの動きのフレーム数が書いてある場合がありますね。
堀井それ、一度だけ見たことがあって、ウエストンさんがそうでしたね。
これで作れるんですか? と驚いていたら「だってROMに焼いて試すよりラクだから」とおっしゃっていて、職人の凄みを感じましたね。
――“Rev.2016 perfect edition”として生まれ変わった楽曲を収録した、サウンドトラックCDについてお伺いします。
並木楽曲は、FM音源とM2PCMというふたつの音源で作られているのですが、どちらもデジタルデータから直接収録したいと考えたんです。
PCMは元がデジタルデータなので問題ないんですけど、FM音源は実際に本物のチップを鳴らして、それをデジタル収録したかった。
できるだけ“ホンモノの音”をお届けしたかったんです。
そこで、G.I.M.I.CというFM音源の出力ボードを制作している方たちに技術協力をいただいてデジタル録音をしました。
曲順といった収録内容も自分で決めているので、すべて作曲者の意思が反映されたモノとなっています。
長野一般的なサントラCDって2ループなんですけど、このCDだと3ループですからね。
CDの容量ギリギリの67分まで使っている。
並木ジャケットや盤面のデザインも社内デザイナーの手を借りて、自分が表現したい形を実現してもらっています。
それに、ライナーノーツでは1曲ずつにひとことコメントを載せているので、『ガレッガ』の曲を作曲者がどういう考え・目的で作ったかを知りたい方は、それを読んでもらえればバッチリですので。
――当時を思い返しながらですか。
並木そうですね。
今回の作業をやっていると、20年前の自分といまの自分が繋がっちゃうときがあるんです。
別人になっている部分もあれば、根っこの部分はいっしょなんだなと思って。
今回のスタッフで“過去の自分と対面”したのは自分だけなので、その思いが共有できないことがなかなかしんどかったです。
限定版の特典の中のひとつという気持ちではなく、『ガレッガ』ファンに自分ができる最高のお礼という気持ちで制作しましたので。
――いや、すごくわかります。
だって製品版のごとく帯が付いているんですよ! 「20年ぶりの着弾!」ってのが非常に心に響きます。
並木キャッチコピーも半分自分で書いていますからね。
自作自演CDです(笑)。
――今日はお話を聞けば聞くほどに知らない、それだけ魂が込められているのを感じているのと同時に、これだけ遊び込まれているゲームって幸せだろうなと思います。
プレイヤーと作り手の情熱が、ここに来て『Rev.2016』があったことで再集結する。
並木原作に関わった人間としては、20年前に自分たちチームがベストを尽くして作ったものを、新しい形で、しかも当時の資料を含めた形でお届けできることは懐かしくもあるし、当時の自分たちの伝えたかったことを受け止めてもらえるのは幸せだと思います。
――まさに『Rev.2016』というのにふさわしい完成度になったわけですね。
長野ファンがいっぱいいるのが本当にありがたいですね。
■つながっていくエムツー ショットトリガーズという物語
――すでにたっぷりとお話を伺いましたが、みんなが気になっている、エムツー ショットトリガーズのこの先についてお聞きかせください。
堀井まず、『弾銃フィーバロン』はガンガン進んでいるところです。
そして、版権がまとまりそうなものが1社あります。
さらにアプローチをかけているのがもう1社あるので、いい形でまとまればいいなと思っています。
『超連射68K』については、いつでもオッケーだと思うので数に入れていません!
――『弾銃フィーバロン』の発売日はいつごろになりそうでしょうか。
堀井『バトルガレッガ』に負けず劣らずの物量を突っ込んでいるので、「冬、それとも春?」みたいな状況になっています。
これまで『ガレッガ』の情報を追ってくださった方からすると「どれだけ自分でハードル上げているんだYO!」と思うかもしれませんが、それはこれからも続きます。
みなさんがビックリするネタも用意していますので! おもしろいものができあがったときは、またお披露目の機会を設けますので、期待していてください。
今度は『弾銃フィーバロン』好きな久保田がディレクターです!
久保田引き続き全力でいきますので、続報をお待ちください!
堀井『バトルガレッガ』の経験もあるので、今度は大丈夫ですよ。
第3弾以降も矢継ぎ早とはいいませんけど、順次リリースしていきます。
――『バトルガレッガ』でかなり上がったハードルをどうやって超えていくのかという心配は、正直ちょっとあります。
久保田ユーザーもそう思っている方が多くて、なぜか弊社の心配までしてくださる方までいたりするんです。
その不安を払拭して期待を超えるものを出せるよう、全力で取り組みます。
――では最後に、本日参加された皆さんからひとことずつ、読者へのメッセージをいただけますでしょうか。
長野やっと発売日を迎えることができました。
『バトルガレッガ』が好きな人に支えられてうまくいっているので、ありがたいところです。
いろいろ仕掛けたことが全部うまくいって話題に挙がり、いい感じで発売日を迎えられたので、今後ともエムツー ショットトリガーズをよろしくお願いします。
冬野今年『バトルガレッガ』を攻略して実際にクリアーするところまでやったので、ガチで遊ぶ楽しさをわかっているんですけど、初心者でシューティングが不得意という方も興味を持ってくださっているんです。
そういった方のための導線としてスーパーイージーモード、プレイせずともランキングといったコミュニティー機能も用意しました。
すでに購入していただいた皆さんには、ぜひ『ガレッガ』に参加して、使い倒していただきたいと思っています。
久保田今回はアシスタントディレクターという形で、こんなに大きな仕事に関わらせてもらってここまで来ました。
今日お話したディレクション以外にも、動画制作やイベントといった自分の得意分野である能力をさまざまなケースで発揮することが出来るところまでたどり着けました。
つぎの『弾銃フィーバロン』ではディレクターですので、さらに気を引き締めてがんばっていきたいと思います。
――エムツー ショットトリガーズはある意味、久保田さんの成長物語でもある、と。
堀井30代後半になってゲーム屋に転職してきたもんね。
やめとけって言っていたのに。
久保田福井も自分も、ほぼ同時期にSEから転向してきたんですよ。
基本的にショットトリガーズってエムツー所属歴が浅いスタッフが多いんです。
今後もこのフレッシュなメンバーでがんばっていきます!
長野若くないけどな(笑)。
福井自分も40歳を過ぎてからの転職でしたが(笑)、皆さんの力添えもあって100%以上の仕事ができて嬉しく思っています。
『バトルガレッガ』もそうですが、エムツー ショットトリガーズは、シューティングゲームが三度の飯より好きな連中が寄ってたかって作っています。
このジャンルならではのおもしろさを、たくさんの人に楽しんでいただけたらなと思います。
並木さっき特典サントラの話で言い忘れましたが、最終トラックの18曲目にラスボス曲のリミックストラックが入っているんですけど、これは曲がループするごとにキーが1個ずつ上がっていくという仕組みなんです。
それを延々と続けていくとどうなるかというと、どんどん音がおかしくなっていって、音源レジスタに与える数値が上限値を超え下限に戻り、最終的に最初に戻ってくるんですね。
それに要する時間は、4時間かかるんです。
(一同笑い)
並木その4時間分を全部録音してから音的に“おいしいところ”を選り抜いて、それをリミックスしたんです。
作曲者が意図しないところで、音程から音色から元の曲の原型を留めないくらい攻撃的な音になっていますので、ふつうの『バトルガレッガ』では楽しめない部分をサントラで楽しんでもらいたいです。
堀井バカだよね!そこまでやるんだって。
しかもサントラ制作時は疲労困憊なはずなのに、気がつけばボーナストラックまで入っている。
拍手するしかない。
春日今回は自分が担当したZ80でストリームデータが鳴っています。
外から見えはしませんが、フェードイン/アウトなどをしているところで、チップの息吹を感じてもらえたらうれしいです。
エミュレーションですけど、実チップで動作するのと変わらない作業をしているので。
今後のシリーズでもサウンド方面でおもしろい仕事ができたらと思うので、期待してください。
河内長年の夢であるエムツーから家庭用ゲームソフトを出すというところにたどり着けました。
これも関係各位のご助力、数々の奇跡、そしてお客様の熱意とご支援があってのことです。
皆様への恩返しというとおこがましいかもしれませんが、これからもよいものをお届けできるようがんばっていきます。
堀井ようやく自社パブです。
これまでエムツーはゲームの移植をたくさん手掛けてきましたが、こちらがやりたくても版元さんの判断でできないものがたくさんありました。
でもここからはもう違います。
自分たちが責任を持てる範囲であれば、なんでもできる。
俺や長野さんが言い出したバカなことも全部!
――バカありきなことは、今日のインタビューでかなり理解できたと思います。
ちなみに、発売前にここまで盛り上がるとは予想できましたか?
堀井正直『バトルガレッガ』も手を上げたはいいけど、蓋を開けるまでは「商売になるの?」という意見は内外で多かった。
ですが、これからは覚悟を決めさえすれば自分たちが作ったものを世に問うことができるようになりました。
それが奇しくも会社設立から25年。
非常に嬉しく思うし、綱渡りなのか薄氷を踏む状況を楽しんでいきたいと思うので、みなさん応援よろしくお願いします。
(綱を渡っているのに脇の下をくすぐってくるじゃないですかー! の声が)