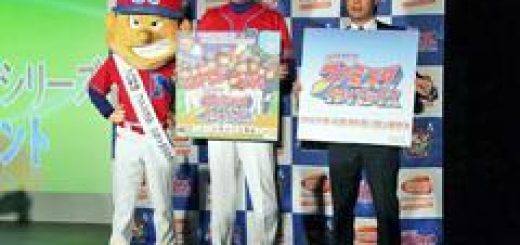“LUMINOUS STUDIO PRO”での新たな取り組みも公開! 『ファイナルファンタジーXV』開発の教訓が詰まった田畑端ディレクターのセッション
文・取材・撮影:編集部 メタボIKEDA
●『FFXV』開発の裏側が語られた貴重なセッション
2017年2月27日〜3月3日(現地時間)、アメリカ・サンフランシスコ モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターの技術交流を目的とした世界最大規模のセッション、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2017が開催。
開催3日目となる3月1日、『ファイナルファンタジーXV』(以下、『FFXV』のディレクター・田畑 端(たばた はじめ)氏(以下、田畑氏)による’Final Fantasy’: A Challenger Once Againと題されたセッションが行われた。
この講演は、2016年11月29日に発売されたPS4/Xbox Oneソフト『FFXV』(スクウェア・エニックス)のチームが、ソフト開発の際に取り組んだ多面的なアプローチについて、田畑氏が解説するもの。
セッションの最後には、現在、開発チームが取り組んでいることの断片も紹介された。
●少年時代の経験から得たチームで戦うことの大切さ
セッションの冒頭で説明されたのは、田畑氏の少年時代のエピソード。
なぜこの話が導入部分にあったのかというと、その後に語られる『FFXV』開発チームの思想に深く完成するからだ。
少年時代の田畑氏は、競技スキーの選手であり、大会で活躍するほどの腕前だったという。
そんな中、ある大会で勝ったらゲームを買ってもらう約束を親としていたという田畑少年は、その大会であっさりと負けてしまう。
「たまたま対戦相手がすごかっただけ」と自分を納得させようとするが、田畑氏に勝利した選手は、つぎの試合で負け、そこで勝利した選手もまた、つぎの大会で負けるという光景を目撃する。
「11歳にして、世界には上には上がいることを学び、そこで一度、挫折しました」と語る田畑氏。
この経験は、田畑氏がゲーム制作をするうえで、「個人の戦いよりも、チームで戦うこと」と強く意識するようになったきっかけとのことだ。
そんな田畑氏だが、『FFXV』の開発を振り返ると、成功体験というよりは、「正直に言って、自分の中では反省や、失敗から得られた教訓のほうがずっと多い」とのこと。
本セッションは、おもにこの教訓の部分を会場のゲーム開発者向けに語り掛ける内容となった。
●『ファイナルファンタジー』シリーズを“挑戦者”に戻すということ
つぎに田畑氏は、『ファイナルファンタジー』というシリーズ名に込められた想いについて語った。
それは“これが最後だと思ってプロジェクトに取り組むこと”だという。
今回結果が出なかったら、つぎはない。
ラストチャンスだと。
田畑氏が『FFXV』のディレクターに就任した直後、各販売地域のセールス担当者にソフトの販売予測をしてもらったところ、すべての地域の予想本数を足しても500万本に届かず、非常に厳しい結果だったという。
この予想は、従来のターン性バトルをガラッとアクションベースに変えるといった遊びかたの変化や、『FF』シリーズのブランド力がさまざまな理由によって低下しているということが理由として挙げられた。
これに対して田畑氏は、「あえて最低限の販売本数を600万本に設定した」とのこと。
その理由は、「最低限のセールス目標を軽々と越えられるようにするためには、いったい何を成さなければいけないのか、それを徹底的に考えて、それを妥協なく実行する。
そういうことが現在の『ファイナルファンタジー』には必要だ」と考えたからだという。
確かに、長い歴史を持つシリーズだけに思い切った施策が取りにくくなっており、状況を打開するためにはそうした覚悟が必要だったのだろう。
●目標を明確にすることが“本当の仲間”を得ることに繋がる
『FFXV』のプロジェクトをマッキンリー登山に例えた田畑氏。
そもそもそんな高い山に登ったことがないので、当初は途方に暮れていたという。
「いったいどんな装備で、どんなルートで、どんなプランで登ればいいのかまったく見当が付かなかった」と田畑氏。
ただ、最低600万本というゴールを明確に決めたことで、田畑氏といっしょに困難な取り組みに挑戦してくれる本当の仲間がたくさんできたことが、自体を打開するきっかけになった。
仕事をする上での仲間とは、その仕事のゴールに向かってともに道のりを歩み、ともに喜びを分かちあったり、ともに苦しんだりできるメンバーであることを実感したという。
その仲間たちと仕事をするために田畑氏が作ったのが、”第2ビジネス・ディビジョン”(以下、DB2)だ。
セッションの聴衆に向け、「何かに取り組むときは、ぜったいにこれを実現させるという明確なゴールを定めてみてほしい」と語り掛ける田畑氏。
「はっきりしないことも無理やり具体化し、誰かに伝えられる目標にすることで、その目標に向けていっしょに取り組める本当の仲間を見つけることができる」と、この考えかたの有用性を説いた。
●“強みの集合体”としての開発チーム
つぎに語られたのは、開発チームの能力を引き出す方法について。
“マッキンリー並み”の巨大な山を攻略するためには、それなりの技術や知識、装備が必要になる。
それまで田畑氏が登ってきた“3000メートル級の山”の登りかたは、いったんすべてアップデートすることにしたという。
そこで田畑氏が重要視したのは、より強力なチーム作りだ。
そのコンセプトは、“強みの集合体”。
田畑氏は、開発スタッフのひとりにひとりに、各々がやってみたいことや、強みと感じていることを丁寧に聞いていったという。
これは、自分の苦手なことで勝負をするのではなく、それぞれの強み、得意分野でチームに貢献するような体制作りをするためだ。
イメージは、プロスポーツチームのような、強くて柔軟性のある組織。
個々の個性を尊重し、強みを組み合わせて、チーム全員に重要な役割があるようにすること。
それによってチームのパフォーマンスをベストに保つことを心掛けたという。
「実際に我々は、多くの開発のマイルストーンに違うフォーメーションで挑み、たくさんの成果を上げることができた」と、当時を述懐する田畑氏。
「皆さんは自分のやりたいことをチームの仲間とかリーダーに伝えていますか?」と問いつつ、「もしも、現在の自分のパフォーマンスに満足できていない人がいるとしたら、この方法を試してみてほしい」と勧めていた。
「イメージ通りの活躍できていない理由は、個人の能力の問題ではなくて、仕組みの問題かもしれない」という考えかたは、巨大なゲームプロジェクトのみならず、さまざまな規模、分野のプロジェクトで活かせるように思われる。
ともかく、田畑氏のこのチーム強化策は見事に効果を発揮。
『FFXV』開発チームは非常に高いパフォーマンスを出せるようになったという。
『FFXV』開発当初、チームのメンバーが感じていたオープンワールドに対する高い壁も、この方法によって突破したそうだ。
●困難な仕事に臨む際、忘れてはならないもの
2015年の3月。
『FFXV』チームは、初の体験デモとなる『FFXV エピソード・ダスカ』を開発。
本作の発売を待ち望むユーザーに向けて配信した。
このデモを作った目的は、もちろんマーケティング的な意味合いもあったが、同時に開発チームにとっても、はっきりとした目的があったという。
『FFXV』のコアシステムは、1日のサイクルにある。
この、昼間から夜のサイクルをきちんとゲームの基本システムに据え、その周辺のさまざまなゲームシステムが機能するかを確かめることが、その目的のひとつだったという。
基本サイクルが機能するかどうかを確かめるためには、最低でも『FFXV エピソード・ダスカ』程度のロケーションが必要で、その中でコンバートができ、キャンプができ、キャラクターを成長させられるストーリーを整えた結果が、あのデモ版だという。
『FFXV エピソード・ダスカ』に関して、キャラクターに対する好き嫌いはユーザーによってさまざまだったものの、ゲームデザインについては、おおむね好評を得る結果に。
ところが、開発チームは実際には非常に厳しい現実に直面したという。
このデモ版の制作によって、いろいろな技術検証がクリアーになり、あとどのくらいの分量のものを作ればゲームが完成するのかが明確になったが、その反面、登山の例でいうと、山頂までの道のりの3合目程度までしか到達できていなかったことに気が付いてしまったためだ。
デモ版には仕様の半分程度までが組み込まれていたので、この時点でチームとしては道のりの中盤までは来ている感触があったようだが、実際にはまったく足りていなかった。
完成までに必要な物量が絶望的に多く、本当にそれを乗り越えられるのか、チーム全体が不安な状態に陥ってしまう。
それまで勢いよく進んでいたチームもその勢いを失い、スタッフのあいだには疲労と不安と焦燥が蔓延。
2015年の夏から秋に掛けては、チームのパフォーマンスがひどく低下し、思うように開発が進まない事態になったとのこと。
これを打開するきっかけは、意外と言えば意外なところにあった。
ずばり、“家族”である。
田畑氏によると、「ある日、僕が仕事に出かけようとすると、当時6歳になる僕の娘がギュッと抱き着いてきたんですね。
そして、非常にさみしそうな顔で、パパはいつまで忙しいの?と聞いてきたんです」という。
これに対して「まだしばらく忙しい」と答えた田畑氏。
その後、なんと娘さんが笑顔の田畑氏の顔を描いた絵をプレゼントしてくれたというのだ。
田畑氏は、この行動に親として身につまされ、家族に掛けていた迷惑を顧みて、ショックを受けたという。
この状況を打開するために、田畑氏は開発メンバーたちとミーティングを行い、独自の“ファミリーデイ”の開催を決める。
目的は、崩れてしまった仕事と家庭のバランスを正常に戻すこと。
そして、ずっと心配をかけ続けた家族にしっかりと感謝を伝えること。
サポートの体制をより明確にし、お互いに安心して仕事ができる状況を作る狙いがあったという。
手作りで家族をもてなす準備をする開発スタッフたち。
前述の通り、この時期は楽観的な雰囲気ではなかったが、一度立ち止まって自分たちの仕事や目指すものを家族に知ってもらうための準備を進めていった。
“DB2”には、250人以上のスタッフがおり、その家族を呼ぶとなると、かなりの数となった。
なかには子どもを持っているスタッフも多いので、なんと開発中だった『FFXV』を子ども向けにカスタマイズし、子どもたちが遊べるようにするといった企画も用意したとのこと。
開発スタッフは、自分の家族たちに向け、いつもの仕事席で、いつも使っているPCを使い、自分の仕事の内容を説明。
この“ファミリーデイ”の実施によって、開発スタッフの家族は仕事についての理解が深まり、とても安心感を得て、もてなした側の開発スタッフたちも、自分の素晴らしさを再認識。
これによって開発チームは活力を取り戻したという。
田畑氏によると、「より強いチームを作るためには、開発スタッフの職場における配置を適切にデザインするだけでなく、家族も含めたもうちょっと大きな枠組みで仕事に取り組む体制をデザインをしなければ、本当に強いチームにならない」と感じたという。
●大きな挑戦の結果は?
開発の後半、世界各地で行った『FFXV』のイベントは大盛況。
目標に対する確かな手ごたえを感じていたという田畑氏。
ただ、ソフト発売直前にも、大きなピンチが待っていた。
多くの読者は、『FFXV』の発売日が2か月延期されたことを想像するかもしれないが、意外にもピンチとはそのことではないという。
マスターが完成し、デイワンパッチも完成した後に訪れた大ピンチとは、“フラゲとネタバレ”。
「ソフトの世界同時発売の経験がなかったので、フラゲを防止するノウハウが絶対的に不足していた」と、当時を振り返る田畑氏。
「フラゲしても個人で楽しむぶんには大きな問題ではないかもしれない」とする田畑氏だが、問題となるのは、ソフトの発売を楽しみにしている人たちに対して悪意を感じるようなネタバレの拡散行為だ。
『FFXV』チームのもとには、多くのファンから、そうしたネタバレ行為に関する苦情の声が寄せられたという。
関係者と話し合った田畑氏は、ネタバレを見たくないユーザーに対して注意喚起をし、悪質なネタバレ行為に対しては強い態度で臨む意思表示を行った。
これによって悪質なネタバレ行為はだいぶ沈静化したが、「その反面、代償として僕個人に対する批判や、ゲームに対する批判が過熱して、プロモーションに悪影響を及ぼしてしまいました」と当時の状況を説明していた。
しかし、「ここから得た教訓もたくさんあった」とする田畑氏。
もしも今度、同じような状況に直面した場合はどうするべきかを考えることもあるという。
田畑氏は、「ネタバレを取り締まって、何とかそれを無くしていく方向ではないことを考えるかもしれないです。
たとえば、ネタバレをする人たちには情報拡散力がすごくあります。
声も大きい。
だから、そういう人たちと一緒に発売を盛り上げられるような、ちょっと新しいプロモーションを考えたりして、こうした問題を解決できないものか、というふうに考える気がします」と自身の考えを語った。
前述のファミリーデイのように、大規模なプロジェクトの場合、ピンチのときにはそれを克服して逆にチャンスに変えるような大胆な発想が必要だというのだ。
ゲームの開発には、いろいろな問題が発生するのはもはや常識で、規模が大きくなればなるほど、問題の根が深かったり、難解だったり、複雑だったりする。
田畑氏は、「僕が『FFXV』で得たとても大きな教訓は、“ピンチはチャンスに変える”ということ」だったと、開発の途上で得た経験を総括した。
幾多の危機を経て、『FFXV』を完成させた開発チーム。
ソフトは発売1か月にして、最低限の目標として定めていた600万本のセールスを突破した。
“これがヒットしなかったら、これで終わり”、“次はない”という状況を乗り越えた田畑氏は、これによって「次はあるのかな」と期待しているという。
「僕にとっての『FFXV』は決してサクセスストーリーではない」とする田畑氏。
しかし、勇気と覚悟をもって本気で挑戦しないと到達できない領域のゴールというものがあるということは、今作の開発を通じて非常によく理解できたという。
「そういう高い領域を知ったので、僕らは『FFXV』の挑戦をまだまだ続けますし、当然、新しい挑戦もそうした高い領域のゴールに向かってやっていくことになる」と語り、セッションのまとめとした。
●『FFXV』チームがNVIDIAと取り組む新領域のチャレンジ
セッションの最後には、『FFXV』の今後を示唆するデモも公開された。
これまで『FFXV』チームが手掛けてきたものを短くまとめた映像の最後に、現在進行形の施策が少しだけ盛り込まれていたのだ。
なお、この映像には、“THE JOURNEY OF LUMINOUS STUDIO PRO”といった文言が登場。
“LUMINOUS STUDIO”(ルミナス・スタジオ)とは『FFXV』に使われているゲームエンジンだが、新バージョンとなる“LUMINOUS STUDIO PRO”によって新たな取り組みが始まっていることを伺わせる内容だった。
田畑氏によると、「いま僕らはプロシージャルとAI、そして破壊の3つに関して、重点的な取り組みしています。
NVIDIAのゲームワークスチームと技術を融合し、いろいろな挑戦をしています」と、いま取り組んでいる施策を解説。
画面を分割してモンスターと戦っているシーンは、モンスターの戦闘アルゴリズムをディープラーニングしている実験で、プレイヤーの戦闘パターンを解析して、そのプレイヤーを上回る戦いかたをしてくるといったテストのようだ。
このように『FFXV』チームがすでに新たに目指すゴールを提示。
それがとても新しい挑戦であることを強調して、セッションの閉幕となった。