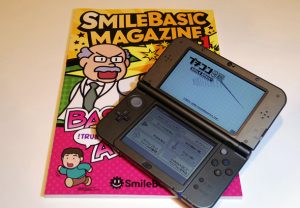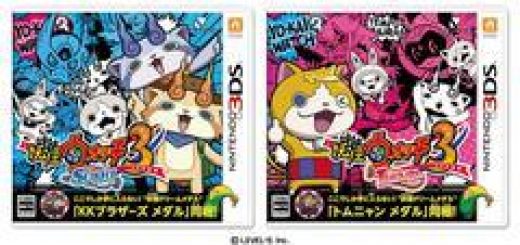なぜ今? 「SMILEBASIC MAGAZINE」の発刊で復活した読者投稿型プログラム雑誌とは
SMILEBASIC MAGAZINEは任天堂ゲーム機専門誌「ニンテンドードリーム(通称ニンドリ)」を発行するアンビットが手がけたプチコン専門誌。
書店では販売されず、Amazonもしくはアンビット通販サイトでしか入手できないという、ちょっと特殊な流通形態である。
A4版フルカラー106ページのうち、90%近くが第3回プチコン大喜利入賞作8作品のプログラムリストで占められる「プログラム投稿型雑誌」だ。
●80年代に生まれたプログラム投稿型雑誌
近年ではすっかり見ることのなくなったプログラム投稿型雑誌だが、その誕生と最盛期は1980年代にまでさかのぼる。
1980年代から90年代前半ごろまで、国内のパソコンはMSXを除くと規格が統一されておらず、各メーカー、各機種で異なるアーキテクチャを採用していた。
そのため、ほとんどのプログラムは特定の機種専用であり、同じメーカーであっても異なるシリーズには異なるプログラムを用意しなければならなかった。
今となっては独自仕様は淘汰されるように思えるかもしれないが、当時は他機種との違いこそが存在意義であり、各機種には群雄割拠の覇者となるべく「尖った」仕様が求められるという一面もあった。
だが、そんな中でもほとんどの機種に共通する特徴があった。
それが標準搭載されたBASICインタプリタの存在だ。
多くの機種ではマシンを立ち上げるとそのまま、BASICプログラムを入力するエディタ画面になる。
シェル(コマンドプロンプト)の代わりもBASICで、命令を直接実行させることでファイルの一覧を表示したり、プログラムをロードしたり、実行したりするようになっていた。
これは、今の環境に照らせば起動と同時に開発環境がフルスクリーンで立ち上がるようなものだ。
当時のパソコンでは取扱説明書にプログラミング入門や、BASICリファレンスマニュアルが付属している機種も多く、パソコンを使うこととプログラムを作ることはかなり近い意味を持っていた。
プログラムを組まないユーザーのことを「ロードランナー(プログラムのLOAD(読み込み)とRUN(実行)しかしない人)」と揶揄(やゆ)することがあったくらいだ。
とはいうものの、言葉巧みに親にパソコンを買ってもらった当時の小中学生の多くが考えていたことは「ゲームがやりたい」、これに尽きる。
しかし、ゲームソフトを買うお金はない。
パソコンまでは「勉強に役立つから」とかなんとか謎理論で押し切って親に買ってもらえても、さすがにゲームソフトでは言い訳が立たない。
パソコンなら何百種類ものゲームができる、とマイコン大百科(ケイブンシャ)にも書いてあったのに、プログラムがなければただの箱だ。
そうしたパソコン少年たちの福音となったのがプログラム投稿型雑誌の代表である、マイコンBASICマガジンだった。
●出版社・投稿者・読者で作るコミュニティ
数百円で手に入る月刊誌「マイコンBASICマガジン」は読者から広くパソコンのプログラム(多くはゲーム)を募集し、それをプログラムリストのまま掲載していた。
雑誌を購入した読者はそれを自分自身で打ち込み、採用された投稿者にはいくらかの原稿料が入る。
マイコンBASICマガジンには互換性のない多くの機種、それら一つ一つに対して1本ないし2本のBASICプログラムリストが掲載されていた。
同じBASICでも機種によって「方言」があり、やはり機種が違えば同じプログラムは動かないことが多かったからだ。
ゲームソフトを買うお金のない小中学生たちはそれを自分のパソコンやショップの展示パソコンに1行ずつ入力したものだった。
そうして、ゲームを楽しみたい一心でタッチタイピングを身につけ、小学生には難しいLOCATEやRANDOMIZEといった単語を覚えていった。
だが、たいていの場合は打ち間違いや抜けがあり、ほとんど一発では動かない。
単純な打ち間違いによるシンタックスエラー(文法エラー)などであれば修正する場所は簡単に見つかるものの、もっと手強いタイプミスもある。
文法としては正しくても、XとYを取り違えたために上下/左右に動くはずのキャラクタが下にだけは動かなかったり、壁をすり抜けてしまったり、突然「Out of Range」と表示されてゲームが停止したり。
エラーメッセージが英語だから分からない、などと投げてしまうとプログラムをイチから見直さなければならないため、必死にエラーメッセージの意味を理解し、なにがまずくてそういうエラーが出るのかを突き止めていく。
エラーの原因が分からず、とりあえずエラーが出るところを削除するという荒っぽい対応をする読者もいた。
その結果、エラーは出なくなっても別のところで問題になることもある。
例えば、スコアを増やすところでエラーが出て止まるため、そこの行を丸々削除したら今度はラウンドクリアができなくなった、というようなものだ。
こういったエラーを経験しながら、初心者はプログラムの意味を理解し、そして改造を加えていくようになる。
まずは変数を変更して残機数を増やし、自機衝突ルーチンをコメントアウトして無敵に。
さらには面構成データを書き換えてオリジナルの面を作成したり、発射した弾が画面から消えるまで次の弾が撃てないゲームを改造し、連射ができるようにするなどだ。
そのころにはプログラムの文法だけでなく、ゲームの基本的なアルゴリズムや組み方まで一通り身についてしまう。
しかし、タイピングの速度が上がり、デバッグテクニックが身についてくると、1カ月に1、2本のプログラムリストでは物足りなくなってくる。
自分が持っていない機種のゲームが面白そうだったりすると、今度は他機種用プログラムの移植を始める。
そうしてそのプログラムを投稿し、いつしか読者から投稿者へ、移植作品からオリジナル作品へとステップアップしていく。
一つの雑誌の中でプログラマとしてのキャリアパスが完成しているのだ。
だが、時代は変わった。
PCのOSはBASICからMS-DOS、そしてWindowsへと移り、プログラミングは専門性の高いアクティビティの一つとなった。
BASICの実行環境も標準ではなくなり、「わかる!動かせる!プログラムが組める雑誌」をうたったマイコンBASICマガジンも2003年には休刊となってしまう。
●プチコン登場
プログラミング言語としてのBASICは廃れたわけではなかった。
1991年〜1998年にはマイクロソフトからVisual Basicが販売されている。
もっとも、それまでのBASICの特徴である行番号を廃止し、スコープの概念など、構造化プログラミングの機能を多く取り入れたもので、旧来のBASICとは大きく異なるものだった。
その文法はVBScriptやVisutal Basic .NET、Excelなどで動作するVisual Basic for Applicationにも引き継がれている。
しかし、ゲームが買えないからWindowsのVisual Basicでゲームを作る、という人はかなり少数派だろう。
いい意味でも悪い意味でもパソコンは道具となり、その一方で携帯ゲーム機も高性能化が進んだ。
ゲームで育った世代が親になり、ゲームがしたければ素直にパソコンの数分の1の値段のゲーム機を買えばよい、という環境になったのだ。
そうして「ゲームがしたいけれど、ゲーム機は買ってもらえないからパソコンで自分で作る」という子どももほとんどいなくなった。
ところが、2011年3月にスマイルブームからニンテンドーDSi用のBASIC環境「プチコン」が登場した。
プチコンは行番号の代わりにラベルを使用するなどの相違はあるものの、極めてクラシックなBASICに近い文法を実現している。
プチコンは息の長いヒット作となり、翌年2012年にはバージョンアップ版の「プチコンmkII」、そしてニンテンドー3DS専用として新コアで生まれ変わった「プチコン3号」と順調に版を重ねた。
プチコン3号と上位互換のあるWii U用「プチコンBIG」も発売が予定されている。
プチコンのバージョンアップと並行して、スマイルブームとアンビットはプチコンを楽しむためのコンテンツやコミュニティ作りを積極的に進めていった。
公式ガイドブック、公式ガイドムック、公式活用テクニックといった書籍のほか、ニンテンドードリーム「こんにちはプチコン3号通信」、日経ソフトウェア「プチコン3号でミニゲームを作ろう」といった紙媒体雑誌による定期的な情報発信。
そして2015年10月には東京でプチコンファンミーティングを開催している。
さらにプログラムコンテスト「プチコン大喜利」を開催。
第3回の優秀作品34本は「プチコンマガジン創刊号」に収録され、新作1本+実行環境とともに2015年7月に300円で発売されている。
このプログラムコンテストと優秀作品の販売、というのもまたパソコン黎明(れいめい)期、80年代に見られた風景だ。
プログラムコンテストで有名なのはエニックス(現スクウェア・エニックス)主催のものだろう。
特に1982年開催の第1回のインパクトは大きかった。
入賞者には森田将棋の故森田和郎氏、ドラクエの中村光一氏、堀井雄二氏など、有名プログラマが名を連ねている。
当時はプログラマ自らゲームをデザインし、絵を描き、音楽をつけることが多く、作品は個人のものだった。
しかし、パソコンの表現力が向上してくるにつれ、その上のコンテンツの質も高いものが求められるようになり、次第に分業化が進んでいった。
ニンテンドー3DSをプラットフォームとするプチコン3号も豊かな表現力を持つが、あらかじめ多くの汎用的なグラフィックや音楽、サウンドが収録することで、一人でもゲームを作ることができるようになっている。
こうして見ていくと、プチコンがヒットした原因には「ニンテンドー3DS上で自作プログラムが動かせる」というだけでなく、そのまわりの環境も含めて「あのころ」を再現していることもあるのではないだろうか、と思える。
そう考えると、ニンテンドーDSi/3DSというプラットフォーム自体、レトロPCとの相似性が意外と大きいことに気づかされる。
「立ち上げたらBASICだけの画面」「ゲームがしたいけれど買えないから自分で作る」「これ一つあればいくらでも(ただで)ゲームができる」という、まさしく「あの頃」の環境だ。
Windows用プチコンではこうはならなかったかもしれない。
そして、プラットフォーム、コンテスト、作品販売――ここまでそろえば80年代ゲームプログラミング環境最後のピースである「プログラム投稿雑誌」が登場するのは必然だったとも言える。
●SMILEBASIC MAGAZINE刊行までの道のり
SMILEBASIC MAGAZINE誕生のきっかけは2012年3月のことだった。
Twitterで電子版のプログラムマガジンのことに触れたアンビットさあにん@山本直人氏に、ちょうどプチコン3号の開発をスタートさせたばかりのスマイルブーム小林貴樹氏が反応、3年越しで「プチコンマガジン」として実現を果たした。
しかし、このときの話はデジタルマガジンだけでは終わらなかった。
山本氏にとってSMILEBASIC MAGAZINEは「公式ガイドブックや『ニンテンドードリーム』の記事などを経て、最終形としてやりたかったもの」だという。
マガジンとついているものの、形態としては書籍となり、広告は入らない(雑誌であってもスマイルブームと自社広告しか期待できないという事情はあるが)。
部数は1000部未満と非常に少なく、制作は企画・編集・DTPデザイン・ライターへの依頼まで、山本氏が一人ですべてを担当。
流通が限定的であるのもそのためだ。
そこまでして山本氏が発刊にこぎつけた目的は「発刊する」こと自体、それと「プログラムリストの復活」だ。
監修のスマイルブームもこだわった点はやはり、80年代のパソコン雑誌のイメージだという。
ただ、想定外だったのはプログラムリストの長さだった。
30年前と比べると、プラットフォームの性能・表現力だけでなく、読者(プレイヤー)の目も、投稿者の実力も格段に向上していたのだ。
SMILEBASIC MAGAZINE掲載プログラムリストは1画面プログラムである「くさかり(kuni氏作)」、218行にまとめた「とびだせ!3Dチキンレース(てっく氏作)」を除くと、どれもかなりの大作である。
大喜利大賞の「FM2K(ゆのみ氏作)」で1781行、最長の「Shooting Life 2014(葛城コニミル氏作)」に至っては3507行、21ページに渡って延々とプログラムリストが続く。
マイコンBASICマガジンでは1作品あたり2ページ〜4ページ程度だったので、かなりボリュームが大きくなっていることが分かる。
しかも、多くの作品は別にグラフィックデータが必要であり、リストをすべて打ち込んでもそのまま遊ぶことはできない。
だが、各プログラムには公開キーが掲載されており、これをプチコン3号のメニューから入力するとスマイルブームのサーバからプログラムやデータ一式がダウンロードできるようになっている。
所要時間はわずか数分。
長大なプログラムリストを入力する必要はない。
ならば、プログラムリストを掲載する意味はなんなのだろうか。
それは「自分の遊んでいるものがどうやって動いているのか」という回答のため、と山本氏は話す。
ゲームソフトが高度化するとともにブラックボックス化していき、開発者というものが見えなくなっている。
その中身を見ることで開発者の苦労や、どうやって動いているのか、学ぶことが多いのではないかと。
山本氏はこれを「映画を見てから原作を読む」ということになぞらえている。
SMILEBASIC MAGAZINEに掲載されたプログラムリストを見ると、綺麗にインデントをつけていたり、変数に大文字・小文字を混在させるなどモダンなスタイルがあるかと思えば、ENDIFを使わずにすべてマルチステートメントでTHEN節にまとめてしまうクラシックスタイルもある。
難易度を変える改造ができる部分にあらかじめ「コラ!」とコメントが入っていたり、ゲームをプレイするだけでは分からない作者の一面が見えてくるのも面白い。
●SMILEBASIC MAGAZINEの向かう先は?
SMILEBASIC MAGAZINEは次号の発行も予定されている。
タイミングとしてはWii U用プチコンである「プチコンBIG」の発売に合わせる形になるようだ。
創刊1号が「発刊する」「プログラムリストを復活させる」という目的があったのに対し、それをすでに果たした2号以降ではもう少し「遊ぶ」というベクトルが増える見込みだ。
読者投稿型プログラミング雑誌は制作側だけでなく、投稿者も作り手となる。
語りたい人、受け止めたい人、遊びたい人のバランスをうまく取るため、ゲームを作るための講座のようなものや、投稿者の作品の紹介記事、攻略記事を掲載することも考えているそうだ。
次号は「第4回大喜利」受賞作品を中心にした構成になると予想されるが、投稿は「プチコン投稿ポスト」で随時受け付けている。
これは公開キーを登録することで、SMILEBASIC MAGAZINE、プチコンマガジン、単体発売への投稿になるというもの。
投稿できる数や期間に制限はないので、自信作ができたら投稿してみてはいかがだろうか。
(C) Ambit 2016(C) BANDAI NAMCO Entertainment Inc.(C) 2016 SmileBoom Co,Ltd. All Rights Reserved.