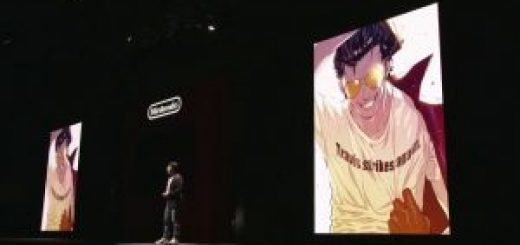ソフトバンクのARM買収は正しい選択か?
日本では3連休最終日だった7月20日の月曜日、ソフトバンクグループが英ARMを買収するというニュースが駆け巡った。
買収額は約240億ポンド、日本円で約3.3兆円という日本企業による企業買収では過去最大の規模になる。
iPhoneやAndroidスマホに幅広く使われているARMの技術
ソフトバンクグループは、日本のガンホー・オンライン・エンターテイメント、フィンランドのSupercellといったモバイルゲーム企業や、中国の電子商取引会社アリババ・グループの株売却などで2兆円近い資金を調達しており、その行き先がどこになるのかと話題になっていた。
もともと手元資金として2兆円を超える現金を保有していたうえ、株式売却による現金も近く振り込まれる。
追加1兆円の資金をみずほ銀行から調達するが、これも売却株式の代金が振り込まれるまでのつなぎ融資との説明だ。
3.3兆円という巨額の買収資金は完全に自腹。
ARMは(買収金額ほどの)大きな売り上げや利益を出しているわけではないが、近年は継続して黒字を続けている。
今後もARMの売り上げは継続的に伸びていくだろう。
巨額融資ではあるものの、のれん代の大幅減損に追い込まれる、といった事態は起きないと予想される。
ソフトバンクグループの孫正義社長は「投資の目的はIoTがもたらす非常に重要なチャンスをつかむことにある」と明言している。
IoTとはご存じの通り、Internet of Thingsの略で「モノのインターネット」と呼ばれるジャンルだが、テクノロジー分野に詳しい人たちの間でも「3兆円を超える資金のARM投入が、本当に正しいことなのか」と疑問の声が出ている。
だが現代社会には、普遍的にネットワークデバイスが存在し、使用者が知らないところで多様なコンピュータが動作している。
そうした中にあって、ARMの強みは「普遍的に存在する」プロセッサの権利を保有していることだ。
普遍的な存在であるという事実は、iPhoneを含む大多数のスマートフォンにおけるARMの採用率といったところを越えて大きな意味を持っている。
「われわれが現代社会において、ARMが存在しない空間に存在することは極めて難しい」と言えるほど、ARMは普及している。
これこそが、ARMの価値だろう。
もちろん、孫正義氏の真意は分からない。
しかし、ソフトバンクグループは株主総会の中で、(Pepperのような)スマートロボットとIoTの数が爆発的に増えると予測し、AI(人工知能)とともに集中的な投資を行うことを表明済みだ。
同社は1人あたり1000台を越えるIoTデバイス、世界人口より多くのスマートロボットが2040年には使われていると予想している。
そんなIoT時代の新しい市場環境において、ARMの持つ知財が極めて重要であるという仮説のもとに、筆者が思うことを書いてみたい。
●ARMとはどんな会社なのか
ご存じの方には釈迦に説法だが、ARMというマイクロプロセッサ(CPU)は、Acorn Computers(エイコーン・コンピュータ)という、かつて英国に存在したパーソナルコンピュータメーカーが開発したものだ。
当初は6502というApple IIにも使われたCPUを代替する目的でつくられた。
その後、AppleやVLSI Technologyが出資し、1990年にCPU開発会社として創業したのが現在のARM Holdingsの源流となる会社である。
詳細な経緯は省くが、ARMが今日まで生き残っているのは、複雑性を徹底的に排除したためだ。
それゆえに当初、性能を出すことができずにパーソナルコンピュータ向けプロセッサとしては成功しなかったが、組み込み向けとして大成した。
今日のARMはより複雑で、性能を高められるデザインになったが、その主な用途から常に消費電力あたりに得られる性能を高めることが重視されている。
また、ARMは自社でプロセッサを開発、生産、販売するのではなく、プロセッサのデザイン(設計)のライセンス販売に事業をフォーカス。
さらにはアーキテクチャライセンスと呼ばれる、ソフトウェア互換性を保持しながら独自の改良を加えることを許すライセンスを他半導体メーカーなどに与えるなど、柔軟なビジネスモデルも採用している。
このため、さまざまな領域で多様な性能、多様な機能を持つプロセッサに採用され、アプリケーションプロセッサとして機能統合が進む中で好んで使われるようになった。
その結果、iPhoneやiPad、Android搭載のスマートフォンやタブレットのほとんどに、ARMがライセンスするCPUコアが組み込まれている。
少々回りくどい言い方だったかもしれないが、同じように組み込みに向いたRISC型プロセッサの中でも、特にコンパクトな設計で自社設計の統合プロセッサに使いやすかったことで、結果的にスマートフォンやタブレット……すなわち、今日使われているパーソナルコンピュータ(PCではなく、個人にひも付いたコンピュータという意味)がARM色で染まったということだ。
しかし、これはあくまでARMプロセッサが社会の中に顕在化している一例にすぎない。
冒頭でも述べたように、ARMが設計したプロセッサは世の中に普遍的に存在しているからだ。
しかも、半導体業界の巨人であるIntelが普及を目指した省電力プロセッサのAtomが、2016年春に新規製品の開発を断念。
徐々に撤退を始めているという背景もある。
ARMは世代を重ねるごとに、互換性を維持しながら性能や機能を強化してきた。
現在では、そのままPCで使えるほどパワフルなものもあるが、一方で目に見えない、使用者がそれをコンピュータだと知らずに使っているようなな組み込み用途にも採用されている。
ARMはプロセッサの生産と販売を行っているのではなく、あくまでデザインを販売しているからだ。
例えば、ニンテンドー3DSなど現在世界で販売されているポータブルゲーム機の大多数にもARMプロセッサが使われている。
そして現在、ARMが提供している設計や命令セットは多様だ。
中でも組み込み用のCortex-Mシリーズは、小さなリモコンやウェアラブルデバイスにも入り込んでいる。
例えば、PlayStation 4のゲームコントローラーの中にもARMアーキテクチャは存在している。
●なぜARMをソフトバンクが買収するのか
そんなARMをなぜソフトバンクグループが買収するのか。
なにしろ3兆円を超える買収である。
ARMの純資産は約1600億円しかない。
すなわち、その企業価値のほとんどは「のれん代」としての評価ということになる。
ARMがその価値を失えば、ソフトバンクは巨額ののれん代を償却せねばならなくなる(もちろん、そんなことにはならないと考えているから買収したのだろう)。
ソフトバンクグループが現業とのシナジーを期待できないとしたら、3.3兆円(株式時価総額が約2.3兆円に対して1兆円を上乗せしている)もの資金は純投資ということになる。
本当にその投資した資金を回収できるのか、と疑問に思うのは当然だろう。
いくら黒字続きの企業とはいえ、投資回収には気の遠くなるような時間がかかるように思える。
しかし、過去のソフトバンクグループによる大型買収を振り返ってみると、その多くは本業とのシナジーが直接的には見えにくいものが多かった。
本業とのシナジーを感じさせる大型買収は、恐らく米Sprintぐらいではないだろうか。
孫氏は、経営者よりも投資家に近い人物イメージを個人的に持っている。
同じような印象を持っている読者も少なくないだろう。
では今回の買収に関して、単なる博打(ばくち)なのかと言えば、そうは思えない。
なぜなら、これまで孫氏は投資において抜群の実績を挙げてきたからだ。
ベンチャー投資に限れば、約4000億円を投資し、10兆6000億円もの成果を得ている。
このような成果を上げている背景には、上場後のソフトバンクグループがシリコンバレーの投資家やIT企業経営者などのコミュニティーに溶け込んでいるという指摘が、以前からされてきた。
「あれはいいね」あるいは「この技術は将来を変える」といった話は、シリコンバレーのコミュニティーにいれば耳にすることもあるが、孫氏には逐一そうした情報やオファー、プレゼンテーションの類が入っている。
そうライバル企業の経営者がうらやんでいたことを思い出すが、ITトレンドに関して生の意見が聞こえてくるところに、孫氏の強みがあるのだろう。
孫氏はARM買収に関して、あらゆるものがネットワーク化される社会で、各デバイスの中にARMの技術が入り込んでいくこと、さらにネットワーク事業やセキュリティ技術などに投資をしてきたソフトバンクの持つ資産が、あらゆる場所で普遍的にネットワークデバイスが存在する未来のコンピューティング環境において、ARMの技術と交わってより大きな価値を生み出すことを説いた。
●IoTの時代が到来するということは?
ここでIoTの時代が到来するということは、一体どういうことなのかを考えてみたい。
恐らく、「IoTが普遍的に存在する世界」におけるARMの役割をどのように考えるかによって、今回の買収に対する感じ方が大きく異なる。
それはARMが設計したプロセッサコアが、まるで空気のように当たり前に存在し、何らかの形でネットワーク、あるいはスマートフォンなどのネットワークへのゲートウェイとの接続口を持つようになるということである。
孫氏は「97〜98%のスマートフォンで、ARMの設計したプロセッサが使われている」と話したが、IntelのAtom撤退が進めばほぼ100%になるだろう。
しかし、これはあくまでも「世間一般に分かりやすい数字」として出されたものだ。
だが(現時点では巨額と言われるものの)、「将来はARMに出した3兆円超の資金が小さく思えるほどARMの事業は大きくなる」と孫氏は説明した。
コンピュータはもちろん、一般にコンピュータと認識されていないちょっとした機器なども含め、ありとあらゆるデバイスにARMが入っていく。
モバイルと光の両方でネットワーク企業を持つソフトバンクグループが、ネットワークインフラとセキュリティ技術を用いてIoT時代を支えるという考えには、一定の納得感を感じる人も多いだろう。
だが、それでも筆者はこの買収劇の先に経済合理性があるとは思えない。
世の中はこれからIoTの時代に入っていき、ARMの設計するプロセッサコアは数え切れないほどの場所に入っていくだろう。
しかし、それはあくまでもARMのプロセッサにすぎない。
IoT同士がコミュニケーションし、インターネットの各種サービスにつながるのが当たり前の時代になっていくだろうが、ネットワークコミュニケーションにおいてCPUの互換性にどこまでの影響力があるだろうか。
むしろ、ネットワークの中における主役は、OS(基本ソフト)やアプリケーションごとのプロトコルの実装にあるのではないだろうか。
マイクロプロセッサはOSやアプリケーションが動作する基盤ではあるが、コミュニケーションの基盤ではない。
●方向性は正しくとも、買収戦略が正しいわけではない?
ソフトバンクグループによるARM買収の話を聞いて真っ先に思い付いたのは、1996年にまだ小さかったソフトバンクが米Kingston Technologyというメモリモジュールメーカーを買収したときの話だ(1999年にソフトバンクはKingston株を売却した)。
このときもたっぷりと株価にプレミアムを乗せて買収した。
創業者オーナーは全社員に向けて歓びのメッセージとともに(買収で得た巨額の利益を分配するため)、ボーナスを全社員に支給するとメールしたことがニュースになったほどだ。
筆者がこのときのことを思い出した理由は、「方向性は正しくとも、買収戦略が正しいわけではない」という典型的な事例だったからだ。
孫氏は質の高い情報源との連絡網の中で、適切な投資先を見つけてきたが、今回は狙いすぎて失敗ではないかと思えるのだ。
Kingstonという企業は日本ではマイナーだったが、PCやプリンタの増設メモリでは最大手の1社だった。
一方、コンピューティング技術の進歩は要求メモリ量の増加を促し、当時のDRAM(メモリの一種)売り上げは上昇の一途をたどっていた。
当時、Kingstonの買収を進めた役員と話をしたことがあったが、半導体生産という意味でのメモリ事業のトレンドと、B2C、B2Bに限らずメモリモジュールの販売トレンドとは同じではないということが、いまひとつ理解されていない印象を受けた。
メモリモジュールのビジネスは、今は完全に下火になってしまったが、デスクトップPCが主流でプリンタにも増設メモリが用意されていた当時、必要なメモリ容量の急増からニーズ拡大が見込まれていた。
実際、1995年ぐらいは16MBのメモリ容量がぜいたくと言われていたのに対して、2016年現在は16GB(すなわち1024倍)のメモリ容量でも普通とされている。
孫氏の見立ては正しかったことになる。
孫氏は、業界のメガトレンドを読みながら次の事業を模索するのが得意な人物だ。
ブロードバンドインターネットの時代を加速させつつ、電子商取引やネットメディアの企業に投資を行った。
そうした時代の流れを読むのは得意だが、ディテールに関してはよく知っている部分と、情報が不足している領域が明確に分かれているように思う。
まだソフトバンクが小さかった頃と比較するのはアンフェアかもしれないが、業界トレンドに近そうでいて、全く異なる立ち位置のKingstonを買収したときと同じように、今回も「投資先分野の選択は正しい」と言える。
今後、世の中にあるさまざまなものがインターネットに直接的、間接的につながっていくだろう。
爆発的にIoT関連商品や技術は伸びていくはずだ。
孫氏が話すように「将来、振り返ると安いと言える買い物」になるだろう、IoT関連企業はいくつもあるはずだ。
しかし、その投資先としてARMが本当に正しいのか。
孫氏は、直観的に将来のビジョンが見えているのかもしれないが、そこには決して小さくはない疑問符が残る。
ARMは成長を続けるだろう。
しかし、3兆円を超える投資に見合う成果を引き出せるかどうか、確実なビジョンは恐らくない。
そんな中にあって、ソフトバンクグループは次世代に向けて、大きな賭けに打って出た。
[本田雅一,ITmedia]