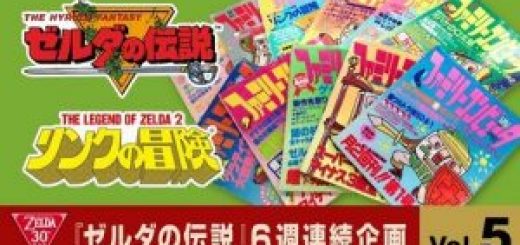話題のPS VR、シネマティックモードなどのAV機能を発売前に体験してみた
10月13日に発売されるPlayStation 4向けのHMD「PlayStation VR」(PS VR)。
発売に先駆け、6月16日から東京・名古屋・大阪・福岡のソニーストアで体験コーナーが用意されているほか、今後も一部販売店で順次、体験会の開催が予定されている。
実際に、PS VRでどのような体験ができるのか、マスコミ向けの体験会に参加してみた。
ゲーム関連は僚誌GAME Watchに任せ、AV Watchではシアターライクな体験ができるシネマティックモードなどを中心にレポートする。
■品切れ店続出のPS VR
発売前のPS VRだが、予約受付は6月18日からスタート。
だが、多くの通販サイトや量販店で、すぐに初回受付が終了するほどの人気となっている。
ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)マーケティングコミュニケーション部の会田覚氏は品切れ状態に陳謝した上で、「PS VRに対する皆様の反響は非常に大きく、我々としてもできるだけそれにお応えしようと準備をしてきましたが、それを超えるご好評をいただいている」状態だと語る。
しかし、PS VR自体は限定商品ではなく、今後も継続的に生産・販売されていく製品でもある。
SIEでも、「予約再開に向けた準備が整い次第、PlayStation公式サイトやPS VRの『プレミアムメールマガジン』で案内する」としている。
今後もこうしたオフィシャル情報をチェックしていきたい。
■PS VRの基本と、それを楽しむために必要なもの
PS VRはPlayStation 4(PS4)と組み合わせて、VR体験ができるデバイスだ。
つまり、PS VR単体では動作せず、必ずPS4も必要となる。
また、ユーザーの頭や、手にしたコントローラーがある位置をPS4が把握するため、それを認識するための「PlayStation Camera」もゲームプレイなどでは必要となる。
対象年齢は12歳以上。
製品には2種類あり、PS VR単品版(CUHJ-16000)は44,980円。
VRヘッドセット、プロセッサーユニット、VRヘッドセット接続ケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル、ステレオヘッドフォン(イヤーピース一式)、電源ケーブル、ACアダプタが同梱されている。
「PlayStation VR PlayStation Camera同梱版」(CUHJ-16001)は49,980円。
前述の単品版に加え、PlayStation Cameraを追加したものだ。
PlayStation Cameraは発売中の周辺機器でもあるため、既に持っているという人は、PS VR単品版を選ぶ形になる。
ヘッドセットには、1,920×1,080ドット/5.7型の有機ELディスプレイを搭載。
左右の目にそれぞれに960×1,080ドットの映像を表示し、3D立体視ができる。
リフレッシュレートは120Hz/90Hz。
視野角は約100度。
3軸ジャイロ、3軸加速度で構成する6軸検出システムで、装着者の頭の動きを検出。
さらに、テレビの近くに設置したPlayStation Cameraでも装着者の動きを検出するため、その目印となる青いLEDライトも9箇所に搭載されている。
いずれも楕円形で、これもライトとカメラの距離などを詳しく計測するための工夫だ。
頭部に被ると3D空間がプレイヤーを取り囲み、頭部の動きや位置に合わせて映像が360度全方向にリアルタイムに変化。
3Dオーディオ技術も採用され、仮想空間内の音響も連動して変化。
ワイヤレスコントローラーのDUALSHOCK 4やPlayStation Moveモーションコントローラを使って、仮想空間内の探検や、仮想キャラクターとの交流などが楽しめる。
PS4とヘッドセットの間には、プロセッサーユニットを挟むように接続する。
ユニットにはHDMI入力、2系統のHDMI、AUX端子、USBなどを備えている。
HDMI出力が2系統あるのは、1系統がテレビ向けに60pの映像を出力するためのもの、もう1系統はヘッドセットに出力するもので、前述のとおりヘッドセット向けには120Hz/90Hzの映像が出力される。
PS VRのサウンドはテレビのスピーカーだけでなく、ヘッドフォンで聴く事もできるが、その際に、頭部の動きに合わせて変化するバーチャルサラウンドサウンドが楽しめる。
その変換処理も、プロセッサーユニットの役割だ。
ヘッドセットとプロセッサーユニット間のケーブルにはリモコンが備えられており、ボリュームボタンなどを装備。
そのリモコン側面にステレオミニの出力端子があり、手持ちのヘッドフォンをここに接続する形となる。
■装着はよりシンプルに
PS VRが「Project Morpheus」というコードネームで呼ばれていた頃からAV Watchでは何度も取り上げてきたが、その都度ハードウェアも進化を重ねており、今回体験したのはハード的にはほぼ製品版と言えるもの。
重量バランスも考慮され、フロントヘビーを解消。
長時間装着しても疲れにくくなっているという。
レンズの中心と、目の中心を合わせるように装着。
フロント底面にあるボタンを押すと、フロント部分と目の間の距離を自在に調整できる。
位置が決まったら、後頭部にくるバンド部分のダイヤルをまわすとシッカリ固定されるという流れ。
シンプルでわかりやすいので、慣れれば瞬時に装着できるだろう。
光が入りやすい目の下の部分の空間には、柔らかい素材の遮光パーツが取り付けられており、これがピッタリと顔に当たるとほぼ真っ暗な環境が得られる。
逆に、自分の手元を確認したい時などは、遮光パーツをピラッとめくったり、フロント部分を目から離すと現実視界が確保できる。
ゲームや動画鑑賞中に、手元のお菓子に手をのばすなんて時には便利だろう。
ヘッドフォンを装着する場合は、PS VRを取り付けた後で、普通のヘッドフォンとして耳に装着するという流れだ。
■ホームシアター気分で動画再生
ゲーム機の周辺機器であるため、ゲーム用途がメインとなるが、AV Watchとしては動画鑑賞機能に注目だ。
PS VRには、動画をホームシアターのように表示する「シネマティックモード」が搭載されている。
要するに、PS VRを純粋なヘッドマウントディスプレイとして使うためのモードだ。
仮想空間に表示されるスクリーンのサイズは、「2.5m先に最大226インチ」と表現されているが、実際に装着してみると、確かに真っ暗な世界に、見上げるほど巨大なスクリーンが現れる。
体感的には、大規模な映画館の前から4、5列目で見上げているような感覚だ。
視界の中にスクリーンが収まりきらず、端を見るために、少しだけ顔を左右に向ける必要があるほどのサイズ感だ。
それだけに、Blu-rayの映画を再生すると迫力がある。
ソニー・ピクチャーズエンタテインメントから6月8日にBlu-ray/DVDが発売された「ザ・ウォーク ブルーレイ」(4,743円)を再生。
1974年、当時世界一の高さを誇ったワールド・トレード・センターで、命綱無しの綱渡りに挑んだ実在の男、フィリップ・プティを描いた作品だが、脚がすくむようなビルの高さが、大スクリーンで視界を覆われるように表示されると一層強調されるようだ。
なお、スクリーンのサイズは小(117インチ相当)/中(同163インチ)/大(226インチ)の3段階から調整でき、これまでは“大”を選んでいた。
これを“中”にすると、ちょうどスクリーンが視界ギリギリに収まり、映画館の中央の席で鑑賞しているような感覚になる。
大迫力という意味では“大”も良いが、個人的には“中”が観やすいと感じる。
また、“大”ではスクリーンの端を見るために、首を動かしたり、眼球をギョロッと横に向ける必要があるのだが、その際に、接眼レンズの端で発生する歪みや、レンズの色収差が気になってくる。
“中”であれば、そんなレンズの端まで目を向けなくてもコンテンツが視界にまるごと入るため、画質的な面でも利点があると感じる。
いずれのモードでも、暗い空間で映像だけ没入して鑑賞する形になるため、テレビ表示と比べて、臨場感が大幅にアップするのは確実だ。
目の前にディスプレイを配置したシンプルなHMDと、PS VRが大きく異なる点は、仮想的なスクリーンが自分の前方に浮いているように見える事だ。
普通のHMDは、横を向いても、後ろを向いても、目の前にディスプレイがついてくる。
しかし、PS VRは前方にとどまり、横や後ろを向くと、目の前は真っ暗になる。
これが、本当に映画館で首を動かしているような感覚を演出してくれる。
また、常に目の前に映像がついてまわるような、わずらわしさというか、圧迫感にも繋がらない。
なお、Blu-rayや動画コンテンツの再生において、PS VRと接続したから何かの機能が利用できなくなるなどの制限は今のところ無いという。
また、Blu-rayや動画ファイルだけでなく、NetflixやHuluで配信している動画や、PS4のゲームも、同様にシネマティックモードで表示できる。
さらに、リコーのTHETAで撮影したような、正距円筒図法を用いてた全天球写真の表示も可能。
ユーザー自身が撮影した全天全周動画・静止画を再生する事も可能だ。
南国のビーチで撮影した写真を見ると、単純に「綺麗な写真を見ている」感覚に加え、頭上の青空や、足元の砂浜なども見渡せるため、その場にいる感覚がプラスされ、深呼吸したくなるような開放感を感じる。
ゲーム系のコンテンツと比べ、顔を近づけたら、パラソルとの距離が近くなるようなインタラクティブ性には弱いが、写真鑑賞の新たな可能性は感じさせてくれる。
これらもPS4のメディアプレーヤー機能を利用して再生する。
メディアプレーヤーには今後のアップデートにより、VR表示モードが追加される。
■VRでも酔いにくい?
首を動かしながら体験するVRでは、気分が悪くなる、通称“VR酔い”が不安だという人もいるだろう。
しかし、今回映画や静止画、ゲームを1時間以上体験しても、特にそのような感覚は残らなかった。
ディスプレイがOLED(有機EL)であり、リフレッシュレートも最大120Hzと高速であるため、映像にキレがあるためだと考えていたが、SIEによればそれに加え“ディレイ”にもこだわった結果だという。
例えば、“自動車に酔いやすい人でも、自分で運転すると酔いにくい”という現象がある。
これは、右に曲がる、左に曲がるなど、これから先がどうなるかを自分で把握した上で、視界もそのように変化するためだという。
VRの場合、首を横に降ると横の映像が見えるようになるが、センサーが動きを検出し、それに合わせた映像を表示するまでには遅延が生じる。
その遅延が大きくなると、横を向いたつもりなのに、視界が横を向いていない状態になり、“VR酔い”につながるとされている。
PS VRではそのディレイの低減を追求。
酔いやすくなるとされる0.02秒のディレイを超え、最終的には0.018秒を実現したという。
実際に装着して首を素早く動かしても、視界が遅れる感覚はほとんど無く、それが次第に映像を見ているという気持ちを薄れさせ、“ゲームの中にいる”というリアルな感覚に寄与しているようだ。
文・取材:編集部 コンタカオ
●サンドボックスゲームが盛んな海外でどのような評価を受けるのか?
北米および欧州で『DRAGON QUEST BUILDERS』というタイトルで2016年10月発売が決定した、スクウェア・エニックスのプレイステーション4、プレイステーション3、プレイステーション Vita向けソフト『ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよ』。
サンドボックスタイプのモノづくり要素と『ドラゴンクエスト』(以下、『DQ』)ならではのRPG要素を組み合わせた“ブロックメイクRPG”として、日本ではスマッシュヒットを記録した本作は、サンドボックスゲームが盛んな海外でどのような評価を受けるのか。
E3期間中は取材がぎっしり詰まっていたというプロデューサーの藤本則義氏、アシスタントプロデューサーの白石琢磨氏に話を聞いた!
●海外のユーザーにも新鮮に映ったブロックメイクRPG
――だいぶ取材を受けていらっしゃるようですが、反応はいかがですか?
藤本日本で『DQビルダーズ』を立ち上げたときには、「サンドボックスってどんなゲーム?」というところから説明することが多かったのですが、海外はサンドボックスゲームが人気で、しっかりとした土台があります。
なので、サンドボックスとRPGが融合したゲームはイメージしやすかったようです。
海外メディアの方からは「これは新しいジャンルだ」と、期待されている印象を受けました。
白石反応はかなりよかったですね。
『DQ』シリーズもコンスタントにローカライズ版を出すことに対して、安心感だけではなく期待も持っていただいているのかなと思います。
――ニンテンドー3DS版の『DQVII』が、北米でも発売(北米では『Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past』というタイトルで2016年9月に発売)されます。
藤本(ローカライズの希望は)つねにいただいていて、「できるだけ早いタイミングで出してほしい」と言われているんです。
そもそも『DQVII』はあまりにもテキストが多くて、海外版を出す予定はなかったんです。
でも、ファンの方々から強い要望をいただいて、発売できるようになりました。
『DQビルダーズ』はナンバリングタイトルほどのテキスト量ではないので、あまり間を置かずに出せますね(笑)。
――海外では本作のようなグラフィックのサンドボックスゲームって、あまりないですよね。
藤本そうなんですよね。
そこは、海外のユーザーさんにも新鮮に映っているようで、キレイなオブジェクトでモノづくりをしてみたい、そこに乗っかるストーリーも体験してみたいと思っていただけているようです。
白石毛色は違えど、やはりサンドボックスは人気のジャンルなので、私たちが頻繁にアピールしているストーリーといったRPG要素もポジティブに捉えられている印象を受けます。
――とはいえ、『DQI』をベースにしたストーリーは海外では知らないプレイヤーも多いのでは?
白石たしかに知識がない方も多いでしょうし、海外のメディアからも「『DQI』を知らなくても大丈夫なの?」と聞かれました。
ただ、あくまで『DQI』は物語の背景です。
コアなファンは「あ、これは!?」とニヤリとしながら楽しめるでしょうし、初めてプレイする方でもひとつのお話として完結しているので、「まったく不自由なく楽しめますよ」と、しっかりお伝えしています。
藤本日本でも、『マインクラフト』はプレイしたことはあるけれど『DQビルダーズ』が初めて遊んだ『DQ』シリーズだというお子さんが多かったんです。
彼らは『DQI』のことは全然知りませんが、ストーリーは楽しんでくれました。
それと同じ感覚で、海外の人も遊んでくれるのかな、と。
――『DQ』とサンドボックスの親和性はどこにあると感じていますか?
藤本ブロックで世界を作ることと『DQ』の組み合わせは、『マインクラフト』を見たときから抜群にいいと思っていました。
もともと『DQI』は2Dの方眼紙で作られていたので、モノづくりをしながらのRPGは組み合わもきっとうまくいくだろうという感覚はありました。
白石実際に日本で発売して、日本のユーザーの皆さんからも自分たちが思っていたとおりの感想をいただいたので、『DQ』とサンドボックス型のゲームを組み合わせるのは正しい選択だったと思っています。
「サンドボックスは何をすればいいのかわからない」というユーザーに、丁寧に説明するために『DQ』の要素はつながりやすかったのではないでしょうか。
藤本説明という意味では、チュートリアルをやらされている感じはなく、ストーリーに沿っていつの間にかスキルを身につけられるのが、『DQビルダーズ』でうまくできたところです。
白石だいぶうまくなりましたもんね(笑)。
藤本僕はモノづくりが下手だったのですが、いつの間にか何でも作れるようになりました。
「ちょっとセンスあるんじゃないの?」って、勘違いしてしまうほどで(笑)。
――きちんと上達が感じられますよね。
白石ステージごとに区切られているのもよかった。
第2章では、第1章で得た知見を活かして街を作ることができるので、自分がステップアップしていると肌で感じられると思いますから。
――海外版で仕様を変えている部分はありますか?
藤本特にはありません。
ブロックを置く感覚もそのままです。
国内で行ったアップデートがすべて反映されているので、直下にブロックを置けるようにもなっています。
――『DQ』は言葉の柔らかさが特徴的ですが、ローカライズするうえで言葉も意識されるものでしょうか?
藤本そこがもっとも『DQ』のローカライズで難しいところですね。
『DQVIII』より前までは直訳していて、堀井さん(堀井雄二氏)の描いた「ただのしかばねのようだ」といったユーモアとか、メラのような日本語の擬音を活かしたネーミングは伝わりにくかったと思います。
でも、『DQVIII』以降は、時間をかけてグロッサリー(用語集)を考え直しました。
その蓄積を持ったローカライズチームを、リメイク版も含めてずっとシリーズで使っていて、『DQビルダーズ』も担当してもらいました。
本作では『DQ』のあたたかみは出せていると思います。
●今後の『DQビルダーズ』はどうなる?
――国内と海外での評価で違いはありますか?
白石E3 2016に先駆けて開催された“Judges Day”で初めてプレイした海外メディアの方々も多かったのですが、想像していたよりも高い評価をいただけました。
それが、今回のノミネートにつながったと思います。
なかには、昨年の東京ゲームショウでプレイして、このE3でもプレイして「だいぶ変わっているね!」と言ってくれた方もいました(笑)。
藤本日本で、ほかのサンドボックスゲームに馴染めなかった人もRPG感覚で楽しめますと言い続けてきましたが、アメリカでは「ほかのサンドボックスゲームを何度もプレイしている人にこそ、『DQビルダーズ』をプレイしてほしい」という論調が多かったですね。
白石国内版と唯一違うのが、海外版は最初のチュートリアルを減らしているんです。
それでも、おそらくサンドボックスタイプのゲームに慣れているので、さくさくと進んで設計図まで到達されていましたね。
――実際にプレイしたら違うものだと理解されたのでしょう。
藤本建物を作っただけで終わらず、村人からリアクションがあって、それがストーリーや街の防御に影響したりするところが、ほかのサンドボックスにはないゲーム性ですからね。
キレイなグラフィックへの評価もかなり高かったです。
――日本のプレイヤーは実用的な建物を作る方が多い印象ですが、きっと海外ではまったく違う観点でモノづくりをされる方がいると思います。
白石実際にどのようなモノ作りを見せてくれるのか、楽しみですね。
――E3 2016ではVRが大きな目玉となっていますが、VRへの対応は?
藤本まったく検討をしないということはありませんが、技術的に乗り越えなくてはいけない壁があるので、すぐに結果を出すのは難しいですね。
親和性という意味では、VRのヘッドセットを長時間装着するのはたいへんなので、もしやるのであれば、1回15分で終わるような違うゲーム性のものになると思います。
――気の早い話ですが、次回作はいかがでしょうか……?
白石『DQVII』のローカライズも難しかったのですが、ファンの方々からの熱い要望があって実現しました。
それと同じく、続編についても皆さんからの熱い思いが届いていると……いいなあ(笑)。