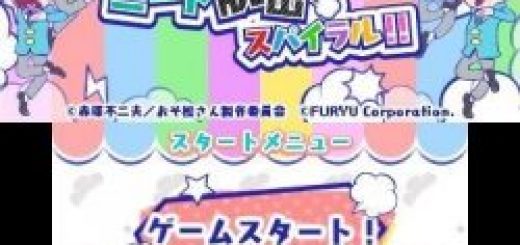映画『マトリックス』が未来のVR イベント「VR産業革命」第1回開催、gumi國光氏ら登壇
映画『マトリックス(The Matrix)』は1999年に公開された、現実と仮想世界の双方にまたがったストーリー。
人気俳優のキアヌ・リーブスが物語の主人公である「ネオ」を演じたことでも注目を集めた。
モチーフとなった仮想現実(VR)が今、にわかに注目を集めており、その究極形がVRの最新動向を紹介する全6回のイベント「VR産業革命」(dots. [ドッツ]主催)で登場した。
第1回は6月29日、東京・渋谷のイベントスペース「dots.」で開かれ、約110人が参加した。
「シリーズ VR産業革命」には、gumi の國光宏尚社長やUEIの清水亮社長兼CEO、先進的な取り組みをするベンチャーやスタートアップを支援するアクセラレータープログラムをVRに特化して行う「RIVER」を立ち上げたTipatat Chennavasin氏、東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻で教鞭を執る稲見昌彦教授も駆け付け、VRの現状を紹介する講演や、VRの未来を創造するパネルディスカッションを実施。
その中で、 VR/ARの発展する先には「映画『マトリックス』のような世界が来る」との見通しを語った。
■VRは映画『マトリックス』の様な仮想世界を生み出すのか?
「メタバース」と聞いてピンとくるだろうか?ITやネットに詳しい人であれば、すぐに思い当たるかもしれない。
インターネット上などに時空間を仮構して、その中に自分の分身となるキャラクター(アバターとも言う)を作り出して、操作。
仮想世界では、探検したり、ビジネスをしてお金を稼いだりするなど、まるで現実にいるかのように過ごすことができる。
VRが実現するかもしれない究極のカタチはまさに、「メタバース」に端的に現れているという。
もう少し解説しよう。
2000年代にはかつて、米国のカリフォルニア州・サンフランシスコに本社を置くリンデンラボがインターネット上に作り出した仮想世界「セカンドライフ」が注目されたが、まさにあれがメタバースだ。
仮想世界の中には、独自のお金が流通していた。
「リンデンドル」と名付けられた架空の通貨はセカンドライフの中で、創作物を売ったり買ったりする電子通貨のようなもの。
ドルなど実際の通貨との交換もできる。
つまり、仮想世界「セカンドライフの中にも「経済」があるという寸法だ。
同様のVRを活用した仮想世界(メタバース)が未来には作り出されるかもしれない。
それが参加者らが提示したVRの未来像だ。
VRは現在、ソニー がプレイステーション(PS)4と接続するためのヘッドマウントディスプレイ「PSVR」の秋発売を計画するなど、ゲームを中心に展開しているところだ。
他方で、もちろんゲーム以外へのVRの応用も構想されており、VR映像の視聴やテーマパークやアーケードゲームといったエンターテインメント、医療関係者向けの訓練機器などさまざまな用途が想定される。
その一つに数えられるのが、没入型のメタバースだ。
VRの究極の未来はこの、いわば「VRメタバース」であろう。
Chennavasin氏は「VR産業革命」での講演で、「VRが発展していけば本当に映画のマトリックスのような世界が来る」と言及。
「メタバースの分野は幅広く、第一歩とする会社がいくつかある。
それが次の世代の『セカンドライフ』になるのではないか」(Chennavasin氏)とした。
同氏の講演に引き続き、gumiの國光社長やUEIの清水社長、東京大学大学院の稲見教授も交えて行ったパネルディスカッションでも、VRを使ったメタバースの可能性について議論。
清水社長は「マインクラフトのようなローポリゴンで、自由度の高いもののほうが『セカンドライフ』のような作り込まれたメタバースよりも受けやすいのではないか。
マイクロソフトがマインクラフトを買収したのはそこをにらんでいるのではないか」などと語った。
■VRは「メディアの未来」を拓く
VR/ARについては、仮想世界に没入するための機器として、頭に装着するゴーグル型画面であるヘッドマウントディスプレイ(HMD)がようやく市場に投入されるなど注目を集めてきた。
その一つが10月発売予定のソニーのPSVRで、先立って発売された米Oculus Riftも大きな存在感を示すHMDとなっている。
Channavasin氏はVRの現状について「VRの技術はまだモバイルフォンのボットレーフォンの時代に過ぎない。
ビジュアル的なディスプレイが進化し、タッチ機能も出てくるのではないか。
今後は匂いや味を体感させられるかもしれない。
思考についても、インプットという点で、脳派を使うことも必要になっていくだろう」と、長期的な見通しを語った。
同氏はさらにVRの現状について解説。
「VRは新たな技術ではなく、メディアとして人間の感覚を錯覚させ、より没入させられる媒体」だとした上で、伝統的にはフィルムやコンピュータなどはAVを体験できるがVRは奥行きやアタマのモーションを追跡することも可能だとした。
さらに、伝統的には、フラットのTV、スクリーンに投影されたものをみることができる。
また「3Dテレビについては、やはりポップアップされたものを見られるが、これはまだスクリーンの枠が存在する」が、「VRについてはスクリーンの枠がなく、2Dから進化し、没入型の体験を出来る」(Chennavasin氏)。
つまり、視覚、オーディオを用いてその場にいる感覚にさせられる違いがあるというのだ。
■VRの、HMDに加わる幅広いビジネス機会
またVRは新たな成長をもたらすテーマとしてももちろん、注目を集めている。
ビジネスにおける可能性もさらに、「VR産業革命」の講演から探ってみよう。
もちろん、頭に装着するゴーグル型画面であるヘッドマウントディスプレイ(HMD)がようやく市場に投入され、市場関係者からの期待も高まっているとみられる。
消費者もソニーのPSVR、Oculus Riftでの新感覚の体験を心待ちにしているところだろう。
Chennavasin氏の講演によれば、VRに関わるビジネス機会は、HMDや入力機器などハードウェアから、VRのエンターテインメント、ドキュメンタリーコンテンツまで幅広いという。
さまざまなVR体験を実現するために、手にもってVR内での動きを操作するスティック型のコントローラーなどの入力装置から、3Dの映像の編集製作用のソフトウェアなどだ。
ほかにも、音楽配信プラットフォームとなるiTunesやSpotifyと同様にVRの映像などコンテンツの提供者と、ユーザーをつなぐ機能も必要とされるという。
ほかにも、VRのための映像を撮影するためのカメラなど、撮影機器ももちろん必要。
バリューチェーン全体を構想すれば、ビジネス機会も幅広く、大きな潜在力を秘めていそうだ。
イベント「VR産業革命」は全6回で、次回は8月ごろに、「VRと介護」をテーマに行われる予定だ。
(ZUU online 編集部)