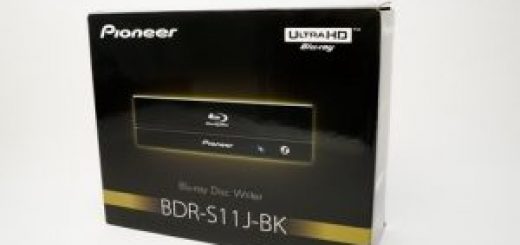開放と融合の力示す「ポケモンGO」ブーム=韓国
代表的避暑地の江原道(カンウォンド)の束草(ソクチョ)が早めのかき入れ時を迎えているという。
日本のゲーム会社の任天堂が米国のオーグメンテッド・リアリティ(拡張現実、AR)企業ナイオンティクとともに開発した「ポケモンGO」というゲームのおかげだ。
このゲームは「ピカチュウ」などの『ポケットモンスター』のキャラクターたちを携帯電話の位置情報システム(GPS)を利用して探して集める内容だ。
今月7日、米国やオーストラリアなどで発売されたが、加入者数と利用時間が空前絶後のスピードで増えている。
最近5〜6年間、力を発揮できなかった任天堂の株価も先週1週間、75.9%急騰した。
「ポケモンGO」ブームは、開放と融合という4次産業革命の傾向をよく示している。
長い間、世界最高のゲーム会社として君臨してきた任天堂は、ソフトウェアとハードウェアのいずれも「自分のもの」だけにこだわってきた。
「スーパーマリオ」のようなゲームを「ゲームボーイ」や「Wii(ウィー)」のような専用ゲーム機で楽しむことができるようにした。
しかし、「ポケモンGO」はこのような閉鎖性を脱し、アンドロイドやアップルの携帯電話で楽しむことができるようにした。
以前のように自社のゲーム機に固執したとしたら、このような成功は期待することが難しかっただろう。
「ポケモンGO」は、実は複雑なゲームではない。
携帯電話で仮想のキャラクターを探す一種の宝探しである。
それでも話題を集めているのはキャラクターのパワーとGPSという情報通信(IT)技術がよく調和しているためだ。
1990年代後半にTVで『ポケットモンスター』を見て携帯電話を体の一部のように受け入れて生きてきた20〜30代の若い世代にとって魅力的であるのは当然だ。
新しくて大掛りな新技術であることが必ずしも新しい価値を生み出せるわけではない。
もどかしいのは韓国の現実だ。
韓国には「ミッキーマウス」や「ポケットモンスター」のような世界的なキャラクターはない。
「ポロロ」が成功したというが、幼児用キャラクターにとどまっているだけだ。
政府も企業も重厚長大産業中心のハードウェアマインドからまだ抜け出せずにいる。
規制も同様だ。
地図を海外に持ち出せないという法規のせいで全国のほとんどの地域で「ポケモンGO」ゲームができない。
シャットダウン制のようにゲームを有害物質扱いする規制も多い。
開放と融合がスローガンのみにとどまっているだけだ。
これでは「クリエイティブ・コリア」は不可能だ。