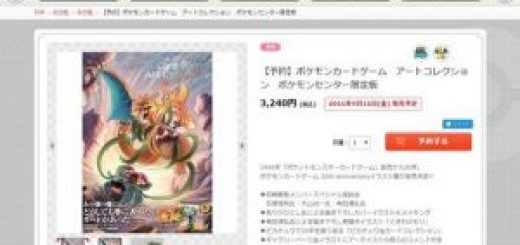なぜPlayStation VRは素晴らしいのか 「ワクワクの魔法」が消えない極上のVR体験
ガジェットを買う際に決め手となるのは何だろうか? スマートフォンのように、ある程度世の中に広まっているものの場合、「できない」「遅い」「使いにくい」といった、今抱えている不満を解消できるという点を重視する場合が多いだろう。
一方、まだ定番が出ていない未知のジャンルでは、「ワクワクできそうだから」「何か面白そうだから」という気持ちからその製品を手に取るはずだ。
VRヘッドマウントディスプレイはまさに黎明(れいめい)期で、この10月13日にソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation VR」(以下、PS VR)が発売を迎えた。
そして実物を「お迎え」してじっくり触れば触るほど、その「ワクワク」の期待感に応えてくれる素晴らしい製品ということも実感できた。
そもそもVRは何がスゴいのか、PS VRはどんな経緯をたどって発売を迎えたのかという話と合わせて、インプレッションをお届けしよう。
●約2年半前の発表から、ようやく発売
読者の中には、2016年は「VR元年」と呼ばれていることを知っている人も多いはず。
Facebook傘下であるOculus VRの「Oculus Rift」、ValveとHTCが協業して生まれた「HTC Vive」、そして今回のPS VRと、高性能なVRヘッドマウントディスプレイが相次いで一般販売を迎える年になるため、元年というわけだ。
ヘッドマウントディスプレイといえば以前より市販されていたが、かぶると正面に巨大なスクリーンが現れるタイプがほとんどだ。
それがVR対応になることで、まず視界が覆われるうえ、頭を上下/左右に動かすと途切れなく映像が続くという体験を実現した。
端的にいえば、どこを見ても世界があって「映像の中に入った」感覚を生み出してくれる。
この点が新しい。
さらにリアルの位置を反映してくれるポジショントラッキング技術が、バーチャル空間にいる感覚を高めてくれる。
部屋の定位置に置いたセンサーなどを基準にすることで、ユーザーが体を動かすと、その動かした分だけ視界が変化する。
例えば、小物に頭を近づけてじっくり見たり、正面にいる人物の右側や左側に回り込むことが可能だ。
一歩進んで、手の再現も実現している。
モーションコントローラーを両手に持つことで、バーチャル空間に手を出現させ、アイテムをつかんで投げたり、剣を振ったり、銃を撃ったりといった操作が可能だ。
今までコントローラーやマウスといった機器でちまちま入力していたものが、自分の体で直感的に指示できるようになった。
昨今のVRが流行り始める以前でも、同じような体験は数百万円、数千万円をかければ実現できた。
そして現在は、量産されて安価になったスマートフォンのディスプレイパネルやセンサーを利用することで、数万円、数十万円と文字通りケタ違いの安さでも、質の高いVR体験を両立できる。
価格が安くなれば、今まで興味があっても買わなかった人たちが手に取るケースも増えてくる。
ここ数年のVR業界では、ガジェットファンだけでなくソフト開発者も多く飛びついてきた。
コンテンツ制作についてもハードルが下がっており、「Unity」や「Unreal Engine 4」といった優れたゲームエンジンが無料で使えるようになっている。
実写の360度動画撮影でも、アクションカメラを複数台組み合わせる方式が生み出されて非常に安価になった。
ハードとソフトの両面で劇的に状況が変化し、「VR元年」が叫ばれる今の「コンシューマー向けVR」のムーブメントを生み出しているわけだ。
そんな激動の時代において、PS VRは2014年3月のゲーム開発者向けイベント「GDC 2014」で開発コード名「Project Morpheus」として初めて存在が明らかになった。
その後、ゲーム系イベントに出展を重ね、2015年9月の東京ゲームショウでは正式名称をお披露目し、さらに2016年6月には発売日と価格を発表した、というのがこれまでの流れだ。
開発機は誰でも入手できるわけではなく、約2年半イベントや体験会といった限られた機会でしか触れなかったため、2014年からずっと取材してきた筆者も、今こうして届いた製品パッケージを眺めて「ようやく好きなだけ遊べる」という気持ちだ。
●練りに練られたセットアップのガイド
さて、VRの特徴とPS VR発売に至るまでの背景を踏まえた上で冒頭の話に戻るが、ガジェットをいろいろ買って来た方々なら、購入前の期待が引き起こす「ワクワクの魔法」は、意外と簡単に解けてしまうこともご存じのはず。
人間、新しいものの導入は誰しも億劫だ。
実際に触ってみたら意外とセットアップが面倒だったり、うたっていた性能ほど効果が感じられなかったり、最初はよかったけど意外と使い道がなかったりと、随所にあるハードルが超えられずに気持ちがなえていき、いつのまにか使わなくなってしまうことも多い。
VRヘッドマウントディスプレイは大半の人にとってまさに未知の存在で、この時点でハードルが高い。
しかしPS VRが素晴らしいのは、そうした新しいものを少しでも手軽に扱えるように配慮している点。
一番、「考えられてる」と感動したのは>PANORAの記事でも書いたが、セットアップにおけるケーブルの接続だ。
PS VRは、主にヘッドマウントディスプレイとプロセッサーユニットに分かれている。
ヘッドマウントディスプレイとプロセッサーユニットは専用の2股ケーブル、プロセッサーユニットとPS4はHDMIとUSBでそれぞれ接続する形だ。
ここにプロセッサーユニットとPS4には電源ケーブル、PS4にはPS CameraへのUSBとテレビへのHDMI、ヘッドマウントディスプレイの途中にあるリモコンにはヘッドフォン……とさらにケーブルが加わる。
ほかにもワイヤレスコントローラーの「DUALSHOCK4」や、両手に持つ「PlayStation Moveモーションコントーラー」も、初期設定時にUSBケーブルでPS4につなぐ必要があったりして、この文章を見るだけでも面倒くささが漂ってきているはずだ。
そこをPS VRでは、何重もの工夫で面倒さを軽減しようと試みている。
まずRPGの宝箱にも似た内箱をパカっと開くと、いきなりA4サイズのクイックスタートガイドが現れる。
電子機器にありがちな、何重にも折りたたまれたA3用紙に小さいフォントで手順を解説するのではなく、イラストを大きく使い1ページに1手順という迷いようがない説明の仕方でガイドしてくれる。
さらに主要なケーブルに1〜4の番号を振って、名称ではなく数字でも分かるようにしている。
似たサイズの端子が隣り合っている場合、「△○」「×□」というPlayStationのコントローラーでおなじみのマークをオスメス両方の端子に振ってあったり、端子内部を白黒で分けていたりと、視覚的に判断つきやすいようにしているのも親切だ。
その後のセットアップも基本的に画面の指示に従って進めていけば完了する。
筆者的には、まったく取扱説明書を開くことなく、ネットの情報も検索することなく、アプリの購入まで1〜1時間半ほどで完了することができた。
「設定で疲れた〜。
じゃああとは明日で」という感じではなく、そのまま遊べる気力が十分に残っていた……のは発売日のモチベーションのせいかもしれないが。
当たり前の話だが、自由にマウスカーソルを動かせるPCとは異なり、コントローラーの十字キーを動かしたところにしかカーソルが行かないのも面倒くささを減らすことに貢献してくれると感じた。
ウィンドウもマルチウィンドウでなかったり、ゲームが置かれた階層も浅かったりと、細かいところでサクサク操作していけるのはコンソールならではだろう。
●繰り返し遊びたくなる強いコンテンツ
そうしたセットアップのあとに、長時間遊ぶための要素が後押ししてくれる。
まずハードウェアの装着感のよさだ。
他の競合は、顔面にヘッドマウントディスプレイをあててバンドなどを絞めて固定する方式が多い。
一方、PS VRでは頭に通したリングを絞めて額と首の後ろで固定し、そこにぶら下がったヘッドマウントディスプレイを前後してピントを合わせるため、顔面への圧迫感が少ない。
もっとも、顔面に密着させた方が頭を振ったときにずれにくいため、激しく動き回るコンテンツには向いているのだが、圧迫感が少ない方が長時間つけていても蒸れにくい。
この辺はトレードオフだろう。
肝心のコンテンツも本当に作り込まれていて、長時間遊べるものばかりだ。
ローンチタイトルを見ても、SIE自身がリリースしている「The Playroom VR」や「PlayStation VR Worlds」、「RIGS」、バンダイナムコエンターテインメントの「サマーレッスン:宮本ひかり セブンデイズルーム」や「アイドルマスター シンデレラガールズ ビューイングレボリューション」、セガゲームスの「初音ミク VRフューチャーライブ」、エンハンス・ゲームズの「Rez Infinite」など、独占作品がずらりと並んでいる。
各コンテンツについて細かく書き出すと本当に長くなるので割愛するが、いずれもデモのように一回遊べば終わりというわけではなく、何度も遊びたくなる仕掛けが随所に盛り込まれている。
PS4のキャッチコピーではないが、「できないことが、できるって、最高だ。
」と感じさせてくれるものばかりだ。
VRコンテンツの制作手法は日進月歩で進化していて、Oculus RiftやHTC Viveが登場した3、4月からわずか半年でも、VR酔いを感じさせない移動方法や、バーチャル空間で効果的な演出などで大きな違いが出てきている。
ライバルのリリースに半年ほど遅れをとったPS VRだが、その間に力を蓄えて質の高いコンテンツを一気にリリースしたことで、体験した人に「VRって……スゴい!」という大きなインパクトを与え、「ちょっとこれ面白いからうちに来て遊んでみてよ」とさらなる口コミの輪を広げてくれそうだ。
●単体で大画面テレビとしても使える
長時間遊べるという話以外にも、用途が広いのもいいところだろう。
VRは一人で遊ぶものと思われがちだが、誰かと一緒に楽しんでもコミュニケーションツールとして役立ってくれる。
PS VRにはソーシャルスクリーン機能が用意されており、体験中のゲーム画面をテレビ側にも表示してくれる。
人がVRヘッドマウントディスプレイをかぶってあちらの世界で奮闘している姿は、そもそも周囲で見ていて興味深いものだが、さらに見ている場所もリアルタイムでわかるのだ。
複数人で交代しながら遊べば、会話が弾むこと間違いなしだ。
ほかにも先にあげた「The Playroom VR」はパーティーゲームで、1人がヘッドマウントディスプレイを、最大4人が1台のテレビと4台のDUALSHOCK4コントローラーを使って、同じゲームをバーチャル/リアルの双方で遊べる。
大画面テレビとしての使い道も用意されている。
PS VRでは旧来のヘッドマウントディスプレイのように目の前に巨大なスクリーンを表示させて、VRではないPS4ゲームを遊んだり、BD/DVDを再生することが可能だ。
ネットでは、PS4アーケードアーカイブスで配信されている「ダライアス」で遊ぶと、3画面を使ったアーケードを再現できるということが話題になっている。
BD/DVDでは、DUALSHOCK4の「OPTION」ボタンを押すとスクリーン位置を再調整できるので、ごろ寝でダラダラと映像を楽しむことも可能だ。
あまり知られていないことかもしれないが、テレビなしでPS VR単体でも動作することも見逃せない。
一人暮らしだったり、リビング以外の自室にも大画面テレビが欲しいという人は、PS 4とPS VRのほうがコンパクトで済むだろう。
長々と書いて来たが、こうした細かい積み重ねが、PS VRで初めてVRに接した人々にさらなる魔法をかけて、バーチャル世界の虜にしていったに違いない。
もちろん世の中に完璧なものがないように、気になる点がないわけではない。
例えば、ざっと思ったのは以下のような項目だ。
・ホーム画面が360度表示でない(VRなのにもったいない!)
・ホーム画面がポジショントラッキングされない(近づいて拡大、離れて縮小表示されない)
・DUALSHOCK4やPS Moveが常時VR内に表示されない(持ち替え時にHMDを前にずらすか手探りすることになる)
・ViveやRiftに比べてポジショントラッキングがややずれやすい?(まだ使用時間が10数時間レベルなので要検証)
・長時間遊べるがゆえレンズや鼻パッドの汚れが目立ちやすい(仕方ない! ふけばいい!)
・そもそも入手できない(待つしか!)
しかし、「ここが改善されたらもっと使うのに」ではなく、しっかりした屋台骨があったうえで「ここが改善されたらさらに完璧になるのに」といった気持ちだ。
2016年10月13日を境に、VRの歴史はついにコンシューマーという領域に大きく踏み込んだことになる。
PCでいえば1995年のWindows 95、インターネットでいえばYahoo! BB、スマートフォンでいえばiPhone 3Gといったように、このPS VRがVRの普及に一層弾みをつけることは間違いない。
ガジェットファンならこの最初の盛り上がりを体験しておかないのはもったいないので、まだ触っていない方は、次回以降の出荷の際には是が非でも入手して体験すべきだ。
●著者紹介:広田 稔
VRジャーナリスト、株式会社パノラプロ代表、VRおじさん。
コンシューマーVRのほか、アップル、niconico、初音ミクなどが専門分野。
VRにハマりすぎて360度カメラを使ったVRジャーナリズムを志し、2013年に日本にVRを広めるために専門Webメディア「PANORA」を設立。
「VRまつり」や「Tokyo VR Meetup」(Tokyo VR Startupsとの共催)などのVR系イベントも手がけている