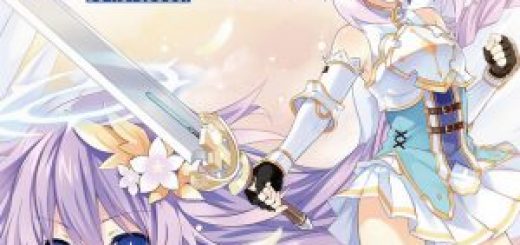大航海時代の「世界地図」作成に励む「Neo ATLAS 1469」をプレイ!
プレーヤーはひとりの貿易商人となり、探検と冒険を繰り返しながら「世界地図」の完成を目指すPlayStation Vita(以下、PSVita)用ゲーム「Neo ATLAS 1469」。
ゲームの舞台は大航海時代直前のポルトガル。
当然、この時代には「Google Earth」はもちろん、正確な地球儀も地図も存在しない。
そんな時代に生きたひとりの貿易商の、「世界の姿」を明らかにする大事業を体験できるゲームだ。
こう聞くと、30代以上の読者は「あれ?聞いたことがあるぞ」と思うかもしれない。
実はこのゲーム、1998年に第1作目が発売されて大ヒットを記録した名作「Neo ATLAS」シリーズの最新作。
前作はプレイステーション 2で発売された「Neo ATLAS 3」だったので、実に16年ぶりの新作となる。
当時、特定層のゲーマーの心を激しくアツくさせたこのゲーム。
かく言う筆者もそのひとり。
寝る間も惜しんで世界中の海を航海&大冒険しまくっていたわけで、「まさかいまのご時世に『Neo ATLAS』シリーズの新作を遊べるなんて!」と大興奮ですよ!
しかも新作は、シリーズのなかでも特に人気の高かった「Neo ATLAS 2」のシステムをベースとして開発された。
地図の拡大/縮小をタッチスクリーンのピンチイン/ピンチアウトで操作できるようになったり、スクリーンをタップするだけで探検や貿易の指示を行なえたりと、PS Vitaならではの進化を遂げたのだ。
さっそく新作の紹介……といきたいところだが、まずはまずはアンダー30の読者諸君のために「Neo ATLAS」シリーズを軽くおさらいしてみよう!
■プレイがプレイを呼ぶ「Neo ATLAS」スパイラル!
「Neo ATLAS」シリーズの基本的なゲームシステムは、シリーズによって微妙な変更点はあるものの、大きくは以下の3つのパートを繰り返しながら世界地図の完成を目指してゲームを進めていく。
まず、ひとつめは「探検航海」パート。
雇った提督に未知の海域を探検航海させ、世界の姿を少しずつ明らかにしていく、いわば「Neo ATLAS」のメインとなる部分だ。
目指すは世界地図の完成なのだが、序盤の世界地図はヨーロッパや地中海の周辺以外、雲に覆われて未確定となっている。
その雲に覆われた領域に向けて提督を派遣すると、帰港した提督から「こんな地形だったよ」と報告され、その結果、調査が完了したエリアが世界地図に書き込まれていく。
ゲームの大きな目的は世界の未確定領域をゼロにすることだ。
ふたつめは「貿易」パート。
これは雇った提督に支払う賃金や、探検船団の編成に必要となるカネを稼ぐために行なう。
いつの時代も「世のなかカネ」なのだ。
新たに発見した土地で「コショウ」や「絹糸」などの産物を見つけたら、貿易を行なうために航路で結んでいく。
これらの産物はただ売買するだけでなく、複数の産物を組み合わせた「加工品」になる場合もある。
世界の大部分が謎に包まれている時代、大儲けのチャンスはどこに転がっているかわからない。
このパートだけでもかなり遊びごたえのある「貿易シミュレーション」となっている。
そして最後は「クエスト」パート。
世界地図が広がっていくに従って、洞窟や遺跡などといった何かありそうな「調査対象」や、ふわふわと浮かぶ「風の噂」を発見できることがある。
これらを発見して調査を行なうと、「秘宝探索」や「海賊との因縁の戦い」、「世界の謎」などのエピソードを進められる。
これはまるでアドベンチャーゲームのよう。
地図とにらめっこしたり、ときに頭をヒネったりしながら進めていく。
クエスト達成の報酬は、お金やアイテムだけじゃなく、ときには新たな提督が仲間になったり、所有できる探検船団や貿易航路の数が増えたりと、重要なクエストも盛りだくさん。
「Neo ATLAS」シリーズの主なシステムは以上。
これらのパートが互いに影響し合って、プレーヤーは冒険と航海の世界に引き込まれていく。
探検船団によって報告された土地では新たな発見があり、発見から始まるクエストを進めるためには、さらなる探検が必要になることも。
そして、探検船団の維持には資金が必要なので、新たな産物を探しに探検航路を拡充しなければならない……とまぁ、こんな感じでプレイがさらなるプレイを呼び、気付くと寝食を忘れて「Neo ATLAS」の世界に没頭してしまうキケンなゲームなのだ!
■「Neo ATLAS」の世界は「信じる」と「信じない」で創造されていく
ゲームの流れを理解してもらったところで、ここでは「Neo ATLAS」ならではのユニークなゲームシステムを紹介しよう。
「地図を作る」という地味な目的が、なぜこんなに楽しいのかを理解してもらえるハズ!
ゲームに限ったハナシではないが、ある選択に迫られたときに人間は「YES」か「NO」で答えるだろう。
「Neo ATLAS」の世界では、このYESとNOの選択肢が「信じる」と「信じない」になっている。
前述したように、探検航海に派遣した提督が帰港すると、「南の方にこんな島と大陸があったデース」といった報告を受けるのだが、このときプレーヤーは、提督の報告を「信じる」か「信じない」かを選択できる。
「信じる」と選択すれば、提督の報告通りに地図上に地形が書き込まれ、「信じない」と選択すれば、地図にはなにも書き込まれない。
当然、ずっと「信じない」を選択し続けると、いつまで経っても世界地図は完成しない。
反対にすべて「信じる」を選択すれば、比較的短時間で世界地図が描かれていくが、それが果たしてどんな形の地図になるのかは、まったく想像もつかない。
「信じる」と「信じない」の選択を迫られるのは、探検航海のときだけではない。
世界各地で聞いた数々の「風の噂」や、「建設物」などを発見したときも「信じる」か「信じない」で答えることになる。
例えば「伝説の金属オリハルコンって本当に存在してたの?」や「ジパングって本当に黄金の国?」、「◯◯には◯◯な生き物がいるって噂だけど本当?」などと、ロマンチックな疑問を投げかけられることもある。
ここでも「信じる」と答えれば世界の事実になるし、「信じない」を選べば世界から消える。
オリハルコンの存在を「信じる」プレーヤーの世界では、いつかきっと世界のどこかで伝説のオリハルコンを発見できるかもしれないが、「信じない」プレーヤーの世界ではどれだけ時間をかけても決して発見されないだろう。
同様に、ジパングが黄金の国だと信じるプレーヤーの世界では、黄金がザクザク産出されるジパングが現われる(かもしれない!)が、信じないプレーヤーには単なる極東の島国になるかもしれない。
貴重な産物や伝説の遺跡、謎の生物、不思議なアイテム、それらの存在理由はただひとつ。
プレーヤーがその存在を「信じる」から。
ただそれだけ。
「信じる」力は強いのだ!
■ついに、新作「Neo ATLAS 1469」の世界を冒険してみた!!
前置きが長くなったが、実際に新作「Neo ATLAS 1469」のプレイリポートに出港! とはいえ自由度の高いこのゲーム、本稿は僕の一例なので悪しからず。
ゲームを始め、しばらくはチュートリアルに沿ってプレイ。
筆者のような「Neo ATLAS」シリーズ体験者でも、「こんなことあったなぁ」などと懐かしい想い出が蘇ります。
そしてゲームのイロハをある程度覚えたところで、プレーヤーにポルトガル王からの勅命が下される。
その最初の目標は「30年以内にジパングにたどり着く」こと。
「あれれ? なんだかいままでと違うぞ……?」
前作までの第一目標だった「20年以内の喜望峰到達」が、今作では「30年以内にジパング到達」へと変更されたみたい。
うーん、これは何か意味があるのかなぁ……と考えていたら、「ややこしいことは考えないで、最初っから西回り航路でジパングを目指してもいいんじゃよ?」という声なき声が聞こえてきた。
プレーヤーの商会所属の提督のなかでもっとも理系の提督「ペレス」は、最初からずっと西回り航路を大プッシュしてくるし!
商会の執事「ミゲル」が勧める「東回り航路」(喜望峰発見→インド経由)と、理系提督「ペレス」が推す未知の「西回り航路」。
どちらでジパングを目指したらいいのか、なんだかいままでにない流れ。
コレが新生「Neo ATLAS 1469」なのか!
■ひとまずは東回りでジパングを目指す
「西回り航路を推されてるのかなぁ」と気になりながらも、まずはやっぱり従来のシリーズ通りに東回り航路を進むことに。
ペレスごめん!僕はミゲルを信じるよ。
ということで、東回り航路を推し進めようとしたのだが、ここで最初の関門となるのが喜望峰。
スムーズに通過しておきたいところではあるが、ゲーム開始直後は編成できる探検船団の数も少なく、手元の資金も心許ない。
おまけに資金調達のための貿易航路も少ない現状。
それならばまず、小さな利益をコツコツと積み重ねていこう。
少しずつ、少しずつ、貿易船を往復させて小銭を稼ぎ、探検船団を派遣し、地図に書き込んでいく。
その先にきっと貴重な産物が見つかるはず。
何ごとも「千里の道も一歩から」だよね。
どちらかというと数学よりも地理の方が得意だったと言えなくもないレベルの筆者でも、現実の世界地図のカタチぐらいは知っている。
しかし「そろそろアフリカ大陸の南端じゃないかな?」と思っている地点までたどり着いても、提督はいつまでも南へ伸びる海岸線を報告してくる。
このまま「信じる」を繰り返していたら、アフリカ大陸が南極まで到達してしまう……なんてこともあり得る。
そんなことになったらジパングに行けないじゃん。
もう、東回り航路は控えめに言って絶望的。
「Neo ATLAS」シリーズを遊んできたプレーヤーなら1度は提督の言葉をすべて信じる「縛りプレイ」なんて遊び方をしたことがあるはず。
でも、そんな特殊なプレイをしているのでなければ、ここは理想的なアフリカ南端の海岸線が報告されるまで提督の報告をひたすら「信じない」ことで、東回り航路を取りやすいアフリカ南端を形にしたいところ。
もちろん、そんな簡単にはいかないんだけど……。
■アフリカ大陸をぐるっと周って海岸線を攻めろ!
アラビア半島とアフリカ東北部に挟まれた湾、紅海。
現実には北のスエズ運河と南のバブエルマンデブ海峡によって地中海とインド洋とにつながる細い海域なのだが、このゲームのプレイ開始時には、インド洋につながるはずの南側の海岸線は未確定地域となっている。
紅海に面したアラビア半島の港では「ルビー」を産出しており、価値の高いルビーはもうぜひとも貿易したい気持ちでイッパイなのだが、未確定地域を通す航路は組めないため、最初は貿易ができない状態だった。
この時代は地中海と海をつなぐスエズ運河のような便利なモノは建設できないので、アラビア半島で産出されるルビーを外海に運ぶためには、紅海南部をうまくインド洋につなげなければならない。
とはいえ、ここもまたなかなか上手くいってくれない。
紅海はすぐに陸に閉ざされた湖を形作ってしまうのだ。
これが本当に歯がゆくて仕方がない! 「うんうん、それもまた世界地図だね」と思えるような大人の寛容さがあるなら話は別だけど、ルビーと指輪を貿易航路で結ぶことで生まれる加工品「ルビーの指輪」で一儲けしたい僕は、何度も何度もやり直すのだ。
そう、この追い求める理想があるからこそ生まれる歯がゆさこそ、本作ならではのクセになるポイントなんだよなぁ。
今回は「ルビーの指輪」を狙ったが、ルビーに限らず、ダイヤモンドやサファイアといった宝石しかり、コショウや絹糸、さらには空飛ぶパイナップルだったり、未知の世界には多くの貴重な産物が眠っている。
しかし、仮にそれらを発見したとしても、港が内陸の湖なので貿易できない……なんてこともよくある話。
とにかくこのゲームでは外海に港がない以上は貿易航路を結べないのだ。
だからこそ貿易のための海岸線の作成に必死になってしまう。
そう、すべてはカネのために!
世界の姿を100%明らかにする、そのためには金がいる。
金を稼ぐためには価値の高い産物が必須。
貿易に理想的な海岸線を作るために何度も船団を派遣する。
船団派遣には金がかかる。
金を稼ぐためには価値の高い産物が……(以下略)。
何度でも言おう。
これが「Neo ATLAS」スパイラルなのだ。
■気づくと世界地図作成よりも本気になっている「カネ稼ぎ」
先も述べたように、この世界で運河を建設することはできない。
そりゃその通り。
スエズ運河だって開通したのは19世紀だし、現実世界で南北アメリカ大陸を結ぶパナマ地峡は、運河が開通する20世紀まで大西洋と太平洋の間に横たわり続けてた。
ゲーム内でも地峡の存在はわずらわしい! 本当にジャマ!! ゲーム開始時点から地中海沿岸諸国とアジアの間にスエズ地峡が存在する以上、アフリカ大陸南端を迂回する航路を強いられるのはしょうがないので、せめて大西洋と太平洋をスムーズに結ぶために南北アメリカは分断しておきたい。
「パナマ地峡なんて存在しないんだ!」と信じる強い心が、パナマ地峡のない世界の可能性を具象化させ、現実のものにした瞬間だ。
そうしてパナマ海峡ができ上がり、極東地域と西ヨーロッパを結ぶ、2大洋を横断する「夢の航路」が目の前に現われた。
世界の形さえ変えてしまうのも、すべてはカネのため……いやいや、効率の良い貿易のため。
なんだか手段と目的が逆転しちゃってるけども。
さて、この「Neo ATLAS」の貿易で考えなければいけないのが、「産物の生産量」と「利益」の間のジレンマだ。
当たり前の話だが、1回の航海で運べる荷物が多いほど、そして1回の航海にかかる日数が短いほど、その貿易航路の利益は大きくなる。
運行できる貿易航路の枠に限りがある以上、よりたくさんの荷物を運べる船で、なおかつ高速で航行できる船で、効率的に大稼ぎ! といきたいのが心情というもの。
しかし、産物には年間の産出量があり、それを上回る速度で貿易していたらいつかは産物の在庫がゼロになる。
ゲームが進み、能力の高い船を使えるようになればなるほど、効率的な儲けと引き換えに、短時間で在庫を枯らしてしまいかねないのだ。
在庫がゼロになると、当然船は何も運べないワケで、それでは利益もゼロになる。
後に残るのは貿易船の維持費だけ。
それすなわち赤字ということ。
産物が枯れてしまった航路はさっさと廃止して、新たな航路を結ぶのが得策……なのだが、その貿易によって産まれた加工品をさらに貿易していた場合、少し困ったことになる。
大もとの航路を廃止すると、その加工品を利用した二次貿易航路もひきづられるように廃止になってしまうのだ。
加工品は価値が高く、大きな利益を上げてくれることが多い。
こっちは廃止したくないのに廃止せざるを得ない。
そんな悲しい現実に直面することもある。
加工品を産むための航路は、積載量も少なく維持費も安い船で結んで、在庫を枯らさないように少しずつ貿易する方法もあるが、それでは利率の低い航路になってしまう。
限りある貴重な貿易航路のひと枠を、そんな使い方で埋めてしまって良いのかどうか。
なんとも悩ましい所だが、あえてそういった航路を用意するのも確かに戦略。
嗚呼、商売って本当に難しい。
ちなみに筆者は、大量輸送による利益追求主義で、現地の在庫がなくなり次第さっさと見切りをつける焼畑商法が大好き。
現実だったら大迷惑なタイプだ!
■大航海時代の厄介モノ「海賊」
得意の焼畑商法で荒稼ぎする筆者だが、全て順風満帆というワケにはいかないのである。
世界を股にかける貿易商会の前に現われる最大の厄介モノ「海賊」。
英語で言うとパイレーツ。
「だっちゅ〜の♪」な巨乳のお姉さんならこちらも大歓迎なのだが、ホンモノの海賊はまったく歓迎できない。
(海賊と聞いて某人気海賊マンガよりも巨乳お姉さんが出てしまうのが「Neo ATLAS」リアルタイム世代なのだ!)
ひとたび貿易航路のあいだに入り込まれたら、その貿易船の積荷は奪われてしまい、まったく利益があげられなくなってしまう。
カネがなくなるとプレーヤーの貿易商会は破産。
つまりはゲームオーバー。
そんな悲しい結末だけは避けたいところ。
運行する貿易航路の数が増えるほど海賊に襲われる機会も増えるわけで、いくつもの航路が海賊の被害にあっているなんてザラ。
このままでは大赤字の予感。
ツライ!
貿易のジャマをする悪い海賊たちを黙って見過ごすわけにはいかないので、こんなときは雇った提督たちに海賊退治の任務を与える。
提督と海賊の戦闘のルールは実にシンプル。
提督の能力値と船の戦闘力に、アイテムの補正値を足した「総合戦闘力」が、対象の海賊を上回っていたら勝利だ。
とはいえ、この海賊、とにかく次から次へと湧いてくる。
言い方は悪いけど害虫レベル。
駆除しても駆除しても追いつかないのだ。
せっかく結んだ貿易航路を何度も荒らされるともう、怒りを通り越して最っ高にイライラしちゃうんだよな!
ここはひとつ、健全な精神状態でゲームするためにも、最大5枠を編成できる探検船団のうち2枠、最低でも1枠は海賊駆除専門で活用していきたい。
筆者のオススメとしては「アフリカ大陸東岸からアジア、オセアニア」までの担当と、「南北アメリカ大陸周辺からヨーロッパ、アフリカ大陸西岸」までの担当に分けて海賊退治へ派遣する方法。
モグラ叩き感覚で効率よく海賊を退治できて、ストレス解消にも最適なのだ!
■無限の可能性を秘めた世界を思うがままに創造せよ!
「Neo ATLAS」シリーズの最新作「Neo ATLAS 1469」を、シリーズとしての魅力のおさらいと、実際に遊んだ筆者のプレイリポートで紹介したが、あとは皆さんの手で体験してもらいたい。
ゲームのなかの世界は無限の可能性を有していて、観察し「信じる」ことが世界を収束させていく。
「信じる」と「信じない」の選択は、無限のパラレルワールドが重なり合って揺らぐ世界を、たったひとつの揺らぎようのない世界に収束させていく作業である!(ドンッ)
まるでSF小説のような言い回しだが、他のゲームでは決して味わえないこの感覚、クセになること間違いなし。
長々と語ってきたが、プレイが次のプレイを呼ぶ「探検航海」と「貿易」、「クエスト」の3つのパートのオモシロさはもちろん、プレイの数だけ無限に世界を創り出す「信じる」と「信じない」の選択肢が「Neo ATLAS」シリーズの最大の特徴。
そしてでき上がった世界は、自分だけのオンリーワンの世界だ。
ときには地図をぼんやりと眺めるもよし、簡単にはコンプリートできない膨大な量のクエストを進めるもよし、地図を拡大して見ないと見つからない隠された宝箱を探すもよし。
自分だけの世界を愛でながら、時間の許す限り永遠に遊び続けられるゲームが「Neo ATLAS」の醍醐味なのだ。
シリーズ伝統のゲームシステムのオモシロさと、PS Vitaというハードで実現した新たな操作感が見事に融合した「Neo ATLAS 1469」で、あなたはいったいどんな世界を「信じる」のか!?
THE ATLAS:cARTDINK
Neo ATLAS:cFlipFlop
Neo ATLAS 1469:c2016 STUDIOARTDINK / ARTDINK