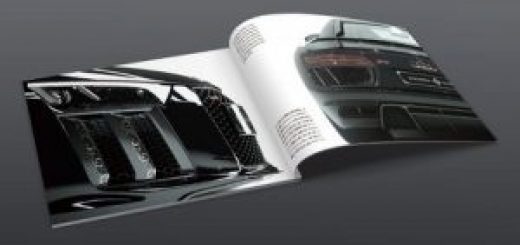映像は誰のもの?――麻倉怜士の「デジタルトップ10」(後編)
2016年のデジタル業界を総括する「デジタルトップ10」。
後編はトップ3と番外編2の発表だ。
驚くべきことに、今回のトピックは全てビジュアルで占められた。
世界のビジュアルシーンの最先端を常に走ってきた麻倉怜士氏は2016年をどのようにみたのか……え、番外編はガッカリ賞ですか?
2016年の第1位はこの製品!
●ガッカリ賞:ソニー「PlayStation 4 Pro」
麻倉氏:今回は新機軸として、2つ目の番外編に「ガッカリ賞」を入れました。
鈍色に輝くザンネンな評価を得てしまったのはソニーの「PlayStation 4 Pro」(以下、PS4 Pro)です。
今までプレステは同一世代では、サイクルの半ばに小型化や廉価版といったディフュージョン的なマイナーチェンジを行ってきました。
ですが互換性に関わる大規模な“アップグレード”は、ソフト製作にも問題が出るということで避けてきました。
今回はその禁を破り、PS4 Proをデビューさせたのです。
初代プレイステーションは光学ディスク化してメディアのコストを劇的に下げました。
PS2はDVD化し、汎用プレーヤー機能を付けることで単なるゲーム機からAV機器としての役割も持たせました。
PS3はHDとなり、Blu-ray DiscとHD-DVDとの「第4次ビデオ戦争」に対して強力に援護射撃し、ゲーム+BD再生としてホームシアター環境での一角を担いました。
そしてPS4は、メディアは変わらず内部をブラッシュアップしてゲームの処理速度を向上させたのです。
――PlayStationシリーズは4になってから大きく方針転換をしましたが、正直何だかなあという感じですね……それで“がっかりポイント”はどこでしょう?
麻倉氏:PS4 ProはPS4が2013年末に出て3年弱というタイミングで、フォーマット的なモデルチェンジまでは至りません。
では、なぜ今回あえてアップグレードしたかというと、これは間違いなくメディア情況が4K化したからに他ならず、それに加えてHDRという新機軸も出てきたからです。
常に最先端メディアを採用してきたという今までの流れからいっても、今回のアップグレードは本来であれば当然Blu-rayも4Kになるだろうということで、当たり前のようにUltra HD Blu-rayが採用されると見られていました。
が、ふたを開けてみるとゲームはしっかり4K+HDR化を果たしたにも関わらず、Blu-ray Discは従来の2K規格のもので、期待値が高まっていたAVコミュニティーでは盛大にズッコケたというのが顛末です。
2K世代で標準的なディスクメディアとなっているBDは、専用プレーヤーだけでなくPS3で楽しんでいるという人がとても多いです。
BDプレーヤーとしてのPS3を見てみると、コントローラーの操作性は良好、クロスメディアバーというユーザーインタフェースは直感的で、機材自体も“スーパーコンピューター・オン・チップ”といわれたCELLの強力な処理能力を用いるため、非常にハイパワーで快適に動作します。
よって“ホームシアターにプレステ”という選択は定番となっていた。
そのホームシアターが4K化するとなると、当然メディアも4K化するわけですが、プレステも当然この流れに乗ると思ったらそうはいかなかったのです。
何故かという疑問に対しては“世界的にディスクからOTTへ”という流れが言い訳としてはあります。
つまり、OTT(Over The Top)であるNetflixやAmazonプライムなら自由に4K +HDRを観ることができる、と。
確かにその通りではありますが、でもその機能はテレビも当たり前のように内蔵するという時代になってきました。
そうなると専用端末であるセットトップボックスはもはや不要で、わざわざ導入してもらう差別化にならないのです。
――4K化の流れにおけるプレステ側の言い訳自体が、自身の存在理由を否定しているということになりますね。
工夫次第で広がるさまざまな可能性をコストカットを理由に否定し、ゲームのみに特化させるという。
この流れはPS4から提唱されていますが、PS4 Proになってそれが先鋭化したといえるでしょう
麻倉氏:ハード的に見てPS4 ProはHEVCのデコーダーなど必要なものはだいたい積んでいるので、UHD BDに対応するにはBlu-rayの3層対応ドライブさえあれば対応できてしまいます。
ソニーはそれをしなかったわけですが、逆の選択を取ったのがパナソニックです。
パナソニックがいち早くUHD BDプレーヤー(レコーダー)を出せたのは、光学ドライブを自製していたからなんです。
一般的に新ドライブと既存のシステムの互換性を取るのはなかなか難しく、検証に時間がかかるのですが、実はパナソニックは前々から3層対応のドライブを搭載しており、規格が固まってチップができればすぐにでもUHD BDに対応できるという強みがありました。
先にも述べた通り、今回のPS4 Proはマイナーチェンジです。
この状況に対する私の答えはズバリ「PS4 Pro IIを出そう」(笑)
――なんだかノリが「ファイナルファンタジー X-2(テン・ツー)」みたいになってますねぇ(笑)
麻倉氏:「OTTなんてことをいうならゲームだってクラウド化でダウンロードができる時代だし、そもそも面倒な検証をしてまでコストのかかるディスクはいらない」となるところですが、実際のところ大メーカーが何年もかけて作るゲームはとてもダウンロードに耐えられず、Blu-rayの容量がなければやってられません。
デリバリーメディアとしてはやはりディスク、そうであるならばそこは是非メディアの片輪である最新ディスクフォーマットに対応を、となるのです。
それも本当に4K/HDR信号を入れるとなると、まさにUHD BDが必要になります。
よって“PS4 Pro II”か、あるいはいっそ“PS5”を望みたいところです。
――確かに現在の回線環境で100GBのゲームをダウンロードなんてのは、PCゲーマーが顔をしかめる“ギガパッチ”と呼ばれる大容量バグ修正ファイルのダウンロードが、裸足で逃げ出す悪夢ですよ……
麻倉氏:初代PSが1994年、PS2が2000年、PS3が2006年、PS4が2013年と、今まではだいたい6年周期できました、となれば次は2019年になるかといいたいところですが、技術革新の速度が速まっており、2019年には8Kをやらないといけないためそうはならないでしょう。
そんな時に8Kのデリバリーメディアとして133GB止まりのUHD BDなんていっているようでは、とてもお話にならないのです。
次世代機に4Kメディアというのは当然のように読めることですが、そんな当たり前の事はもうちょっと前からやってほしかったというのが私の意見です。
今までがそうであったようにプレステには新メディアの牽引役であってもらいたいし、それを実行し続けていた久夛良木健氏が居ればこんなことにはならなかったでしょう。
――「Xbox One」やPC版とマルチリリースをする大型タイトルも増えている今、ソニーがゲームをやる意味というのをもう一度考え直すべきなんでしょう。
プレステの出発点自体が元々スーパーファミコンの光学メディア拡張システムで、遊びの領域をゲームからマルチメディアへ拡げるというものでした。
個人的には今一度プレステの原点に立ち返り、ホームメディアの中枢という久夛良木さんの構想を評価し直してもらいたいと願ってやみません。
●第3位:HDR(ハイダイナミックレンジ)
麻倉氏:第6位にランクインしたUHD BDは、単純な解像度向上だけではなくHDRとの合わせ技で真価が発揮されるとしてきましたが、HDRは何もUHD BDだけのものではありません。
むしろこちらが映像メディアに革新的価値を与えているということで、今年の第3位にはHDRがランクイン。
今回のカウントダウンではどこにこだわるというではなく、ドルビービジョン、HDR10、HLG、あるいはNetflix、ひかりTVなどなどのHDRに関わる動向をまとめて取り上げたいと思います。
――当代における映像技術革新の台風の目と呼ぶに相応しいHDRですが、具体的にはどのような技術なのでしょう?
麻倉氏:真っ黒から真っ白までの幅(ダイナミックレンジ)を拡張して、今までトんでいた明部や潰れていた暗部の表現を拡げるという技術がHDR(ハイダイナミックレンジ)です。
HDRを一番初めに見たのは2012年のCESで、シャープやTCLのブースでひっそり展示されていた時は「なんか明るいな」程度の印象でした。
明るさに関する提案は以前からあり、元を辿れば2008年のソニーのBRABIA「XR1」とシャープのAQUOS 「XS1」に搭載された、今日の液晶テレビで「ローカルディミング」と呼ばれる直下型LEDバックライトのエリア制御技術へ行き当たります。
シャープは当時まだLEDが3原色独立していたという利点を生かして、明るさのみならず色までもバックライト制御で積極的にエンハンスしていました。
一方のソニーではローカルディミングで使用しない余剰電力を使って明部のバックライトをブーストしていましたが、明部のブーストというこの発想はブラウン管時代にまでさらに遡ることができます。
この時の弱点としては、元々のデータが白飛びしていたり黒潰れしたりしていると、いくら制御をかけても色は出てこないということでしょう。
今のHDRはそうではなく、初めから広いDレンジで撮っておきます。
SDR時代の制御とは違って物理的なカラーボリュームが増え、特に明るい部分で白トビせずに色が出てくるのです。
これまでスペック的な画質向上として、解像度を上げることで精細感に関する情報量は増えていましたが、色に関しては増えていませんでした。
むしろ減っていました。
そういう意味で私はHDRの駆け出しからずっと見ている訳ですが、今はどこへ行ってもHDRな状態で、まさかここまで注目を集めるとは思わなかったですね。
映像でHDRを初めに提唱したのはドルビービジョンです。
が、初期のドルビービションはマスターモニター「パルサー」につながる直下型LEDバックライトのモニターシステムそのものを指す言葉であり、これは大失敗でした。
つまり今日のドルビービジョンの様なエコシステムの技術ではなく、単にディスプレイで白を延ばすものだったのです。
2008年から同様の技術を民生品に投入してきた日本のメーカーから見ると、とっくに通った後の道を見せられて「何を今更」でした。
そこでドルビーは日本を飛び越して中国メーカーへ売り込みをかけてみたのですが、今ほど革新的ではなかった当時の中国メーカーにとって、ドルビーの技術はあまりに高級で引く手がありませんでした。
考えてみればラボ創立最初期のドルビーノイズリダクションから、ドルビーはコーデック技術のエンド・トゥ・エンド・ソリューションでのライセンスで身を立ててきました。
初期のドルビービジョンのあり方はドルビーの土俵じゃないのです。
そこで一旦仕切り直し、今日のエコシステムに落ち着くこととなりました。
――HDRというと、写真の世界ではかなり以前から用いられてきた技術ですが、動画と静止画では違いがあるのですか?
麻倉氏:ドルビービジョンは元々広い輝度と色域で記録しておき、それを伝送帯域に収めるために上手く処理しようという考え方です。
動画におけるHDRは基本的にこの情報圧縮という考え方で、複数の露出レベルの画像を合成してDレンジを拡張する静止画とは根本的に発想が違います。
なぜ、こんな手間が必要になるのかというと、映像制作では入り口と出口の情報許容量が全く別のレベルだからなんです。
最新の撮影機材16bitデータ、14stop記録が標準となっており、ソニー「F65」などのRAW信号は16bitとなっています。
ですがBlu-rayやOTTといった流通メディアへ落とし込む過程で、16bitデータでは帯域がパンクしてしまって送れないという技術的な壁が存在します。
そこでドルビーでは、リアリティを感じるのにどの程度明るさ情報量が必要かという実験をしました。
さまざまな人種の被験者に、冬山のスキーや羽毛といった階調がある絵を視てもらい、どの程度の明るさまでならリアリティを感じるかを聞くというものです。
その結果90%以上の被験者がリアリティを感じるとした値は1万nitsという数字を弾き出しました。
しかし1万nitsもの明るさを実現するにはもの凄くbit数が必要です。
何せ従来のBlu-ray Didcでは100nitsを8bitへ押し込めていたのに、その100倍を要求された訳ですから。
帯域的にはやはり16bit要るとなりますが、現在の技術ではそんな膨大な帯域は確保できません。
――フルHDだとしても数Gbps、4Kともなれば数10Gbpsオーダーを“安定的に”確保しないといけない訳ですからね、確かに現実的とは言い難いです。
麻倉氏:そこで人間の錯覚を研究して圧縮・アジャストできる情報量を探求した結果に出てきたのがPQカーブです。
PQとはPerceptual(パースペプチュアル:知覚的) Quantizer(クァンタイザー:量子化器) の頭文字で、ざっくり意訳すると認識可能なビット数まで削るという意味になります。
16bitを削る際には暗部、つまり低域だとバレやすいけど、明部つまり高域は意外と騙せるぞという話です。
そのため情報量を低域に偏らせた方が自然に感じ、その偏差カーブがPQカーブという訳です。
――何だか「高音や小音量は気付かれにくいから削って軽くしようぜ」という、MP3なんかと同じ発想に見えます。
ということは、さらに技術革新が進むと、削る必要さえなくなってRAWへ向かうかもしれません
麻倉氏:オーディオで辿った道ですから、ビジュアルでも遠い未来には有り得ます。
ですがとりあえず未来の話は置いておいて。
PQカーブの考え方が元になって業界団体で標準化された10bitへの落とし込み規格が、UHD BDで採用された「HDR 10」です。
対してドルビービジョンは12bitで、ダイナミックメタデータという可変的な予備情報を持っています。
コンテンツをテレビなどへ映す時には圧縮した情報を解凍する換算式(メタデータ)が必要で、HDR 10はこのメタデータが単一コンテンツに1つなのに対して、ドルビービジョンは刻々と移り変わってゆきます。
一方、放送にもHDRを適応できないかとして開発されたのがHybrid Log-Gamma(HLG)です。
これは圧縮する際の情報偏差を、低域は従来のガンマカーブ、高域は対数(Log)カーブにするとした規格です。
各種HDR技術はこういった経過を辿ってきました。
これまで画質改善に対するアプローチというと解像度の向上でしたが、ここへきて色を増やすHDRが画質改善の切り札的存在になりました。
解像度向上プラスHDRで、人の目が感じる生々しいリアリティを飛躍的に向上させることができる、そういう意味で今年はHDRに注目しました。
UHD BDはもちろんのこと、最近ではOTTやIPTVでのHDR採用が盛んです。
Netflixが6月にリリースした芥川賞作品原作の「火花」は9月からHDR化して話題になりました。
実は製作途中でHDR化が決まった本作ですが、大元が16bitのRAWで撮られているため、そこからHDRへグレーディングし直しができたそうです。
この火花でHDRとSDRを比べた際に一番良く分かるのは、朝焼けの海岸を走るシーンです。
役者がシルエットになり、SDRでは太陽が白くトんでしまうところが、HDRでは太陽がトばずに色がちゃんと出ます。
雲に朱い光が当たって全体が朱く染まり、それが海にも反射するという一連の朝日のドラマも情緒豊かに捉えられており、単に明るくピカピカしているのではなく、光を潤沢に取り入れて表現に生かすことで、ドラマの世界観を映像として饒舌に語っています。
そういった点からHDRを世界観を構築するドラマツルギー(物語を創るおやくそく)のひとつの有力な武器として使っているのです。
――これまで利便性至上主義で「画質なんて2の次3の次」だったOTTがHDRで映像に表現を求め始めたというのが、実に興味深い展開です。
映像が物語に寄り添った深化を見せるというのも、ビジュアルラバーとして喜ばしいですね
麻倉氏:一方のIPTV、NTTぷららが展開しているひかりTVは、ドルビービジョン、HLG、HDR10という3つのHDR規格を世界で唯一そろえたサービスです。
11月に行われた野球日本代表“侍ジャパン”の強化試合でHLGの伝送実験が行われ、現場で見ているような生々しい色使いが見ることが出来ました。
HDRの3つを比較する機会もありましたね。
オートバイで大ジャンプをするという映像で、背後から強烈なライトが当たる逆光の絵でしたが、例えばHDR10では光の輪が若干曖昧にほわっとするところ、12bitのドルビービジョンでは光源とフレアの識別がしっかりできるという違いが見られました。
肉眼で見たらおそらく光源があってフレアが出ているという感じになると想像できますが、そういった映像にとても近いものだったと思います。
これからHDRは盛んになり、テレビをはじめとした対応製品はさらに増えます。
6位のUHD BDで今年は”UHD BD元年”としましが、HDRの本サービスが続々登場ということで同時に”HDR元年”でもあるのです。
今後2020年の東京オリンピックを見据えたリアリティー向上のための画質改善へ明確な筋道がこれで立ったといえるでしょう。
●第2位:ソニー「VPL-VW5000」
――ビジュアルにまつわる話題が続いていますが、次もビジュアルの話題ですね?
麻倉氏:今度はプロジェクターの話をしましょう。
第2位はソニーの超弩級機「VPL-VW5000」がランクインです。
麻倉氏:今年は間違いなくプロジェクターの当たり年です。
フォーマットが変わると機材も全取っかえとなり、それに伴って新製品が盛んになりますが、特に2Kから4Kに移行して何が大きくなるかというと、ズバリ画面が大きくなります。
2Kなら50インチくらいが限界で、60インチや70インチともなるとちょっと甘くなってくるのは否めません。
では4Kで本領発揮するサイズはとなると、さらに大きくなります。
液晶テレビも100インチが出る今の時代、さらに大きな画面が可能なプロジェクターこそ4Kの恩恵を受けるのです。
しかし、困ったことに家庭用プロジェクターには画質改善の切り札であるHDRに関するフォーマットがありません。
テレビのような規格が定められていないため、逆にプロジェクターメーカーが既存のHDRフォーマットにどう対応するかが腕の見せ所となるのです。
その意味でVPL-VW5000は4KとHDRを上手く突いた史上初の製品です。
超弩級プロジェクターと表現するに相応しく、価格も800万円と超弩級です。
――トヨタのクラウンを買ってもまだオツリが来るヨ〜(白目)
麻倉氏:私のシアターで今稼働しているのは「VPL-VW1100ES」という従来の4Kリファレンスモデルです。
これを4K+HDR時代にどうブラッシュアップするかという問いに対して、新たなリファレンスを作ったのがVPL-VW5000です。
インプレッションとして、VW1100ESはバランスが良くナチュラルでスッキリして細部再現も良い。
ですが、VW5000の後で見直すとやはりその差は歴然。
VW1100ESは明るさが1800ルーメンなのに対して、VW5000はまさに5000ルーメン、この明るさから来る精細さ、光の持つ精細な意味合いが凄いですね。
ソニーのプロジェクターで言うと、「VPL-VW535」という4Kの新製品。
こちらの価格はVW5000のおよそ10分の1と、比較的買いやすい(?)モデルですが、これは非常にハイパワーな画調です。
コントラストの両端を持ち上げたドンシャリ的なくっきりハッキリの映像で、むしろ強調感を上手く使って明確さを演出しています。
対してVW5000は恐ろしいまでのナチュラルさです。
あざといところは全くなく、細部まで目が行き届いて、階調の多さに驚かされます。
まずSDRのリファレンスとしてよく使っている「サウンド・オブ・ミュージック」はどうでしょう。
Dレンジが非常に広く、黒の沈みと白のノビが良いですね。
ただこれは強調感があるというのではなく、あるべきところにあるべきものがあり、それが特に奥行方向に出て、マリア先生や子ども達や草原などが明瞭明確に並んでいます。
色の階調も非常に高く、細やかな一体感を感じます。
1つ不思議に思ったのは、VPL-VW5000がキリキリした絵ではなく、ちょっと優しい絵ということです。
それも強靭にして優しいというアンビバレントが見られます。
単に強いだけ、あるいは単に優しいだけというのではない、自然界の相反する概念が上手くバランスを取っているというのが、おそらくホンモノの絵なんだろうと思うのですが、そういう感覚がします。
色の階調感や粒子感、あるいは輪郭感など、繊細でありながらバランスが良く、3管式プロジェクターが今あればこんな感じかと思いました。
これはレーザー発光のプロジェクターで、色は青色レーザーに蛍光体を当てて3原色を作っています。
対して3管式はまさに蛍光体発光。
電子ビームとレーザー光という違いはありますが、この色は3原色のうち最もカラーボリュームが薄い青をベースにして、色の85%ほどを蛍光体で出しているからこそ出るのではないでしょうか。
もしこれが3原色ともレーザー発光なら、色は純色に近くなってくっきりしますが、きっともっとギラギラした絵になるだろうと思われます。
そうではなくしっとり感というか滑らかというか。
ツルツルしているのではなく細かい粒子が高密度に敷き詰められているなだらかさ。
そんなアナログ感が大変魅力的です。
――ソニーの映像はカリカリのモニター調が基本というイメージがあるので、確かにこれは意外です。
ところでVW1100ESからの最大の更新点であるHDRはどうでしょうか?
麻倉氏:VW5000ではHDRを再生するために最初から高輝度で出し、暗くなる部分を後から抑えこむというアプローチを取っています。
ローカルディミングでコントラスト比を向上させてきた昨今の液晶テレビとは逆の手法です。
レーザーはユニットの寿命は長く、光の立ち上がりが速い、加えてVW5000は絞りが無段階で瞬時に変化します。
プロジェクターにおいてコントラストを上げるのに絞り制御は必須ですが、従来の機械式絞りには追随速度に限度があります。
ですがVW5000はフレーム単位で完璧に制御するという強みを持っています。
もう1つ面白いのはHDRに対する考えです。
最初のHDR対応プロジェクターである「VPL-VW515」に見られたソニーの考え方は、ズバリディレクターズインテンション尊重主義。
PQカーブで作られたコンテンツはPQカーブを忠実に再現するという姿勢だったのですが、絶対値で表現されるPQカーブをそのまま表現しようとすると、例えば3000nitsが上限のコンテンツであれば規格上限値である1万nitsの3分の1のため、プロジェクターの出力も3分の1しか出せません。
今回はHDRコントラストというモードを入れて50%まではリニアに変換し、それ以上は最高輝度を保ちつつPQカーブをグラフ上で移動させることで白の階調をなるべく出すという仕掛けを採用して現状に即した対応に変えました。
もともと5000ルーメンもある明るさに加えて、この新しいHDRに対する考え方がよく効いています。
そんなソニー渾身の1台ですが、惜しむらくはガンマ設定がなくなってしまったことでしょう。
今までは1から10までのガンマカーブを自由に選べていて、私は黒の階調を出す「ガンマ7」の設定がお気に入りでした。
少々黒浮きになる分明るさを落としてやると上手く対応できたのですが。
――うーん、一方でユーザーフレンドリーになりながら、もう一方でクリエイター主義になる。
何だかチグハグな感じがしますね……
麻倉氏:こういった自由なガンマ設定は重要ではないかと私は強く感じますね。
コンテンツにあるものをそのまま出すというのがソニーの基本的な姿勢ですが、それに対してユーザーが操作できる面を増やし、もう少し柔軟な対応ができるとさらにより良い体験ができますね。
もっともソニーの言い分も分からなくはないのです。
というのも、ソニーはソニー・ピクチャーズを持っており、ハリウッドから「俺達が作った絵が出てこない」という文句に晒され続けてきました。
再生側でどうにでも変えられるのではなく、クリエイターとしてはディレクターズインテンションをしっかりと視聴者に受け取ってほしいというのがハリウッドの考えです。
ソニーはそういうコミュニティも持っているため、そういった考えに対して共感もする訳です。
年始のCESで出てきた「ULTRA HD PREMIUM」規格というのは、クリエイター側のこういう思想を体現したものといえるでしょう(ソニーはサポートしていませんが)。
それはそれとして、視聴者側にもそれぞれ好みの画調はあるから、個人的にはやっぱりある程度自由な範囲がほしいですね。
●第1位:JVC DLA-Z1
――さて、カウントダウンもいよいよ大詰めです。
麻倉怜士的、2016年最大のニュースは何でしょう?
麻倉氏:ズバリ、JVCケンウッドの新世代4K HDRプロジェクター「DLA-Z1」です!
――おっと、2位に続いてまたまたプロジェクターですね?
麻倉氏:ソニーも大変素晴らしいですが、こちらは別の意味で素晴らしいのです。
ちなみにブランド名はJVCですが、ワタシ的には“ビクター”という響きのほうがずっとしっくり来るので、以降はビクターで通させてもらいます。
ランプユニットは明るさ3000ルーメン、光源には48個のレーザーを用いており、それを蛍光体に当てて色を作るというもので、システムとしては先程のソニー「VPL-VW5000」とよく似ています。
ところが、出て来る絵が全く違うというのが凄いです。
ビクターの絵の魅力というのは、ソースに対してまさにビクター的としか言い様のないヒューマンなフレーバーを与えることで、さらにビビットになって感動が高まるという部分にあります。
HDR以前からDレンジは広く、黒にキチッとしたベースがあり、その上に階調が細かく乗って中間調の色が大変リッチで白も良くノビていました。
そこへ今回はさらにHDRがきた訳です。
ビクターの画作りをしている人は徹底的にこだわる映像哲学の担い手で、ここ10年間のビクターのホームシアター用プロジェクターの歴史は紛うことなく彼が作りました。
テクノロジー的に見ると、従来の2Kデバイスを半画素分だけ斜めにずらして疑似的に4Kを表現するという「e-shiftテクノロジー」から、この度ついにリアル4Kに進化しました。
今までのe-shiftでは見た目の解像感を上げようとするとどうしても強調型となってしまい、弊害としてノイズも出ていました。
特にごちゃごちゃしたところがパンをしながら動くと、画質的にもごちゃごちゃしてしまいました。
そういった問題点をいかに抑え込みながら絵作りするかという、手かせ足かせをはめられた状態で頑張ってきたのですが、今回はそういった拘束から開放されて、全く自由に広大な画質環境の中で自分の絵を作れるとなりました。
そんな中で出てきたのがZ1の絵なのです。
いってみれば手かせ足かせとなっていた”大リーグボール養成ギブス”が遂に外れたのです。
――なるほど、ほんとうの意味で「ビクターの4K」がようやく顕現した訳ですね。
これは確かに大きく注目すべきです
麻倉氏:同じコンテンツを見ても「これだけの情報が入っていたのか」「こんな描き込みがされていたのか」ということがよく分かります。
完全に“オーディオビジュアルあるある”ですが、同じコンテンツから得られる違った感動を求めて、我々AVファンはさまよい歩く訳です。
古いものからも新鮮な感動を得られるという意味で、今回のZ1は正しくビシュアル趣味です。
私が思うに、ビクターの凄さはグロッシー、つやっぽい、濡れているというところです。
逆に位置するドライな絵というのは、くっきりシャッキリでキリリとしているけど、何だか情緒感がないというもの。
ビクターは凄くシャキッとしてしっかりした安定感や粒子感を保ちつつも、そこに得も言われぬツヤ感やグロッシーなものがあり、絵が実にすべらかです。
ソニーは論理的にすべらかなのに対して、ビクターは感情的にすべらかというべきでしょか。
このZ1、4Kが良いのはもちろんのこと、2Kのアップコンバートがたいへん素晴らしいです。
ビクターのプロジェクターには従来からマルチプルピクセルコントロール(MPC)という優秀なアプコン用超解像技術がありましたが、今回のMPCはどちらかというと4K入力のためのものになりました。
とは言えやはりこのアプコンは素晴らしいですね。
ホームシアター専門店のアバックが毎年開催している恒例の大商談会イベントで、定番のサウンド・オブ・ミュージックを最初に上映したのですが、目の肥えた参加者から「おおっ」というどよめきがあがりました。
マリア先生の肌の細かい立体感や自然な奥行き感が機械的に出るのではなく、情緒的・人間的で暖かな情感があり、なおかつ峻厳な解像度もあります。
――アバックの商談会イベントでどよめきがあがるというのはなかなかすごいことですよ。
何せ既にシアター環境があって、次の獲物を虎視眈々と狙う猛者達が集う場所ですから。
“明らかに凄い”というレベルでないと参加者をうならせることはできません
麻倉氏:色の階調感と色の出方にも驚きですよ。
お気に入りソースである「音楽・夢くらぶ」の松田聖子さん(NHK、2004年放送)は基本的にオーバードライブして白トビが多々あるのですが、今回はそこに中間調があって色の違いが何とも滑らかです。
表現が良くない場合、肌に色の段差であるバンディングが出てしまって暗部と明部に分かれてしまいますが、コレで見るとスコットランドの丘陵地帯を思わせる実になだらかな地平が続き、徐々に変化する中で色の階調感がすごく出ます。
同じピンクであってもちょっと赤っぽかったり薄かったりと、これまで見たことのない階調感です。
ここだけの小話、実は以前のモデルに「聖子ちゃんモード」を作ったことがあるんです。
――えっ、「聖子ちゃんモード」……?
麻倉氏:というのも、量販店ではなく専門店で購入した人への特別サービスで。
これと「きみに読む物語」チャプター11の赤が一番リアルに見られる画調設定というのをやったんです。
――すごい、他に全く使い道のない超絶限定モードですね
麻倉氏:若干ピンクに行くような魅力が出るように私が絵を作ったんですが、これはナチュラルというモードに入っていて、最初は特別モードだったんですが今でも半分くらいは入っています。
そんなこともあって、以前やったアバックのシュートアウトイベントで聖子ちゃんをかけると、ビクターだけが異様に光輝いていたりしました(笑)
とにかく、リアル4Kの上に階調が乗っているということのすごさ、違いがまざまざと分かります。
4Kもさることながら、HDRのイコライジングもすごいですよ。
先程のソニーはガンマ調整を許さなかったですが、Z1はなんと暗部・中間部・明部の3帯域に分割して非常に細かくイコライズすることが出来ます。
HDRに対するトリートメントが可能です。
――それはすごいですね、ソニーとは正反対の姿勢だ
麻倉氏:一口にHDRといっても、「パシフィック・リム」は凄く明るいし、「るろうに剣心」は凄く暗い。
こんなに違うのに一緒の値でいいのか?という疑問も当然湧いてくる訳です。
先にも述べた通りHDRに関してはディレクターズインテンションが過度に主張されてきましたが、行き過ぎたディレクターズインテンション信奉に対して、今ユーザーズインテンションの揺り戻し効果が出てきており、その1つの流れがビクターです。
そのビクターのHDRに対する考え方というのも、画質の哲学者が作った非常に使いやすいものなんです。
元々ある映像からさらに魅力を引き出すことが可能なプロジェクター、それがZ1ですね。
――何というか、徹頭徹尾人間に寄り添ったモデルだと感じます。
文学論に作者を神として物語を読み解く作家論か、読者が読み取った物語で世界を語る作品論かという論争があるのですが、まさにソニーとビクターがぴったり当てはまると感じました
麻倉氏:例えば「LUCY」、肌のリアルな凹凸感や油性分の妖しい輝きなど、非常に官能的でエモーショナルな表現です。
e-Shiftの時は細部でMPCによって強引に強調するようなところがありましたが、ネイティブ4Kでは非常にナチュラルで、だからこそにじみ出るすごさがあります。
特に今回は60mmから100mmにレンズサイズをアップしており、本質的に自然さを追求した凄い精細感が、全画面に渡って出ています。
いうなればこれは理想の映像を自らの手で創ることができるプロジェクターです。
私のシアターのリファレンスになる可能性大の、素晴らしい映像美が誕生しました。