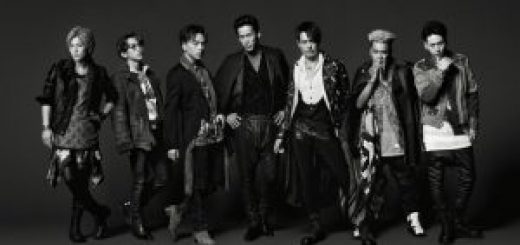「Nintendo Switch」は分解や修理が容易、放熱に配慮した設計–iFixitのレポート
任天堂の据え置き型新ゲーム機「Nintendo Switch」(ニンテンドースイッチ)が3月3日に発売された。
当然iFixitはSwitchをすぐに入手し、分解レポートを公開した。
分解作業の大半を標準的なドライバで進めることが可能で、接着部も無理なく分離できた。
ほとんどの部品が交換可能で、バッテリや画面、デジタイザも交換して修理しやすい構造だという。
また、熱分散と放熱に配慮した設計になっていた。
「Repairability Score」(修理容易性スコア)は、10段階評価で8(10が最も修理しやすいことを表す)とした。
画面の搭載された本体を開封するには特殊な形状のネジを緩める必要はあるものの、対応するドライバさえあれば簡単に開けられる。
開くと、放熱性を考慮した金属の保護板が全面を覆っていた。
microSDカードのスロットは容易に交換可能。
金属板を外すと、バッテリ、ヒートパイプ、放熱グリス、ファンなどが現れ「コンピュータのようだ」(iFixit)。
金属板には小さな突起が多数設けられており、構造的に安定を確保するだけでなく、ヒートシンクからの熱を効率よく伝えて分散し、背面ケースの特定部分が熱くなるのを防ぐための工夫だという。
ヒートパイプとファンは、一般的なプラスのドライバで簡単に取り外せた。
バッテリの取り外しも、接着されていたものの容易。
容量は16Wh。
「Nintendo 3DS」などと違ってユーザーによる交換は想定していないが、任天堂から有料の交換プログラムが提供される予定だそうだ。
その後の分解もプラスのドライバで進められ、マザーボード、画面およびデジタイザ、バックライト、スピーカなどに分かれる。
マザーボードに実装されていた主なチップは以下のとおり。
CPU:NVIDIA ODNX02-A2(Tegra X1ベースのSoCと推測される)
RAM:Samsung K4F6E304HB-MGCH 2GB LPDDR4 DRAM×2
無線LAN(Wi-Fi)/Bluetooth SoC:Broadcom BCM4356
デジタイザと画面は融着されておらず、接着剤を温めて柔らかくすることで簡単に分離できた。
交換も可能な構造だ。
LCDモジュールも簡単に外せた。
本体などの左右に装着するコントローラ「Joy-Con」も、分解が容易。
バッテリ交換が可能な構造で、バッテリの容量は1.9Wh。
BluetoothトランシーバはBroadcom BCM20734。
NFCリーダICと思われるチップ「STMicroelectronics NFCBEA 812006 33」が搭載されていた。
最後に、本体を接続するドックの基板は以下のとおり。
任天堂Switchを分解していく様子(出典:iFixit)