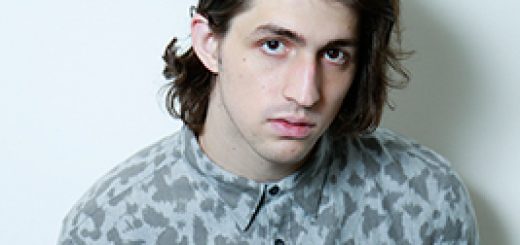知っていますか? ブームを支えた「ポケモンカード」
「ポケモンGO」が大ヒットしています。
位置情報を使ったゲームは「Ingress」をはじめとしてこれまでもさまざまに存在していましたが、多くの人にとって“初めての位置情報ゲーム”であることでしょう。
「ポケットモンスター」(以下、ポケモン)というIPは、他の分野に関しても多くの人の「初めて」となっています。
その中でも代表的なものは「カードゲーム」です。
●世界を広げたポケモンカード
ポケモンはゲームボーイ用のゲームとして生まれた作品ですが、かなり早い段階でメディアミックス展開を盛んに行っていました。
アニメや漫画、グッズ展開……その一環で生まれたのが「ポケットモンスターカードゲーム(以下、ポケモンカード)」。
ゲーム発売後から約半年、1996年10月20日でした。
このポケモンカードは、全てカラーで、ポケモンやトレーナー(ポケモンとともに旅をする人間キャラクター)が印刷されています。
カードにはポケモンが1匹ずつ描かれていて、名前や特殊能力、技や弱点などが詳しく表示されています。
ラインアップは、「スターターパック」と呼ばれる60枚セットと、「拡張パック」という10枚入りのパック。
その中にカードがランダムに封入されていて、めったに手に入らない「レアカード」や光る特殊印刷が施してある「キラカード」があります。
このカードは、単純に「好きなポケモン」や「かっこいいポケモン」などを集めてもよし。
こういった楽しみは昭和に流行した「プロ野球カード」と似ています。
ポケモンカードが新しかったのは、集める楽しさだけではなく、戦う楽しさがあったこと。
詳細なバトルのルールが決められていて、カードを使った対戦ゲームを楽しめるもよし……となっています。
こうしたゲームのバトル要素は、米国で誕生して欧米やアジアでも人気を博したTCG(トレーディングカードゲーム)「マジック・ザ・ギャザリング」のゲーム性を踏まえています。
ポケモンカードはゲームの世界を広げるのにも一役買っていました。
初代のソフト「ポケモン」は、ゲームボーイのソフト。
まだゲームボーイカラーは出ていなかったので白黒です(カラー対応ソフトの「ポケットモンスター金/銀」の発売は1999年)。
しかもドット絵なので、1匹1匹のモンスターの絵はきれいではありません。
しかし、ポケモンカードはフルカラー!アニメの放送は97年4月なので、アニメよりも先にポケモンの世界をカラーで楽しめるのは、ポケモンカードでした。
98年に発売されたポケモンビジネス研究会『ポケモンの秘密』(小学館文庫)には、当時行われたアンケートで「ゲームボーイで遊んだ子どもは、ほとんど例外なくカードもやっている」という結果が掲載されています。
ポケモンカードが発売されたおかげで、ポケモンファンが拡大し、ポケモンが身近な存在になっていたのです。
●「ランダム封入」はなんと手作業!?
当初、販売を担当していたのはメディアファクトリー(現在はポケモンに販売が移行)。
当時の取締役だった香山哲さんが「マジック・ザ・ギャザリングのようなカードゲームを日本で展開できないか」と考えていたところに、「ポケモン」というゲームを開発していることを知りました。
ゲーム発売前の95年から計画し、カード担当の営業がわずか4人しかいない中で、販路を広げていったのです。
カードの製作は任天堂の関連工場が担当。
カードのクオリティーにこだわり、トランプのトップメーカーだった同社のノウハウが生きています。
紙は高級なもので、表面にはトランプ並みのコーティングが。
そして4隅は「子どもがケガをしないように」という配慮から、丸くカットされています。
当時の任天堂には“カード印刷のノウハウ”はありましたが、“ランダムにパッケージするノウハウ”はありませんでした。
第1段で発売された69種類のポケモンカード、26種類のトレーナーカード、7種類のエネルギーカードをランダムに封入しなければなりません。
同じ構成のパックができないように、印刷したものを裁断して、シャッフルし、一列ごとに交互に入れる――ということを、なんと手作業で行っていたのだとか。
売り上げが爆発的に伸びたことで、さすがに人手が足りなくなっていきます。
97年9月にコンピュータ制御で組み合わせをコントロールして、同じカードが出ないようにできました。
●大人もハマったポケモンカード
カードはパッケージ販売以外にも、他メディア展開の販促効果も期待されるようになりました。
通常は手に入らないレアなカードを、『コロコロコミック』(小学館)などの雑誌の付録に付けたり、カードゲームの公式大会参加者への特典として渡したりしていたのです。
こうしたポケモンカードの戦略は、その後のTCGにも生かされていきます。
ポケモンカードの次に日本で大きなブームになったのは「遊戯王デュエルモンスターズ」(1999年発売)。
このカードゲームは『少年ジャンプ』(集英社)に連載していた『遊戯王』を原案として、「マジック・ザ・ギャザリング」を参考に作られたゲームですが、こちらもさまざまなメディアミックスの販促として使われました。
ポケモンカードは、小学生でもルールを把握すればじゅうぶん遊べるようなもの。
やり込めば大人でもハマってしまう戦略性を持っていました。
ソフトを補完するために生まれたゲームでしたが、「ゲームやアニメを卒業した層のハマる受け口」としても機能していたのです。
事実、アイティメディアの新卒社員(22歳)も、ゲームを積極的にプレイしていたのは小学生時代ながら、ポケモンカードゲームにドハマリしたのは中学生のころ。
才能を発揮し、公式全国大会のベスト8に残ったそうです(ただし、大会上位優勝者に渡される特別なポケモンカードは、会場前に居座っていたワルい大人にダマされて売ってしまったとのこと)。
ポケモンというIP(知的財産)の強さは「ポケモンGO」のスタート以降盛んに言われていることですが、ゲームだけではなく、さまざまな方向性で展開していたからこその強さだと、ポケモンカード1つをとっても見ることができるでしょう。