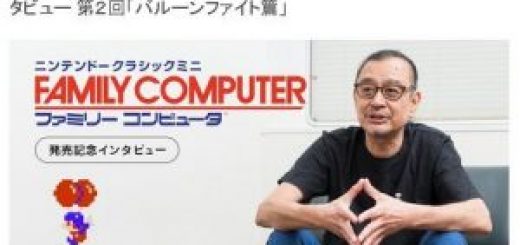新作『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』ついにお披露目! 自由度溢れる本作を青沼英二氏のプレゼン&プレイインプレッションで詳細リポート
文・取材:編集部 世界三大三代川
●すべてが生まれ変わったOpen Airの世界
2016年6月14日〜16日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスにて世界最大のゲーム見本市、E3(エレクトロニック・エンターテインメント・エキスポ)2016が開催。
任天堂は、NX(コードネーム)でも発売が予定されているWii U用ソフト『ゼルダの伝説ブレス オブ ザ ワイルド』(英語名:『The Legend of Zelda Breath of The Wild』)のプレゼンテーション&試遊会を行った。
プレゼンテーションには、『ゼルダの伝説』シリーズのプロデューサー・青沼英二氏を始め、ローカライズスタッフなどが登壇。
生まれ変わった『ゼルダの伝説』の何が新しくなったのか、その魅力を、映像とWii Uによる実機プレイを交えながら説明した。
すでに公開されている映像からでも十分に伝わるだろうが、プレゼンテーション、そして実際にプレイすることでわかる、“当たり前を見直した”『ゼルダ』の新しさを感じてほしい。
『ゼルダの伝説ブレス オブ ザ ワイルド』は、2014年のE3で発表されたタイトル。
当初は、Wii U用ソフトとして発表されたが、二度の発売延期発表を経て、現在は2017年にWii U版とNX版を同時発売することを発表している。
最大の特徴は、とにかく広大な世界。
ゲーム業界では一般的なオープンワールドという呼称は使わず、本作で採用しているアートスタイルや、自由に壮大な世界を探索できるゲーム性、それに合わせて制作された音楽から“Open Air(オープンエアー)”という用語で説明が行われている。
なお、グラフィックは、リアルでもセル画調のアニメーションでもない独特のグラフィックで、淡い色使いながら、ほかにない独特の世界を作り上げている。
プレゼンテーションは、トレーラーからスタート。
アクションなどの各要素については後述するとして、映像だけで見られた要素を、考察を交えて解説していく。
映像には、さまざまなシチュエーションが登場。
ヤシの木が生えた南国風の場所や、鉱山のような荒野、巨大なスタルキッド(『ゼルダの伝説 ムジュラの仮面』のスタルキータ?)のようなガイコツが歩く後ろ姿が見える山、そして、『ゼルダ』らしい草原が映し出される。
ほかにも、オルディン大橋のような石橋、雪山、砂漠、高い塔など、広大な世界にはいろいろなシチュエーションがあるようだ。
各地をリンクみずからの足で踏破するのはもちろん、高い山や塔を上ったり、野生の馬を捕まえて駆け回ったりということもできる様子。
まさに、描かれる世界のすべてが舞台になるというわけだ。
そして、ストーリー的に気になるのは、英語版ロゴに描かれた錆びたマスターソード。
映像の最後には、森の中で錆びたまま台座に刺さっていたが、これは長いあいだ持ち主が現れていないことを示しているのか……?
今回のサブタイトル『ブレス オブ ザ ワイルド』(Breath of The Wild)は、これまでのシリーズのサブタイトルとは異なる傾向のもの。
このタイトルについて青沼氏は、「いままではアイテム名やキャラクター名などをサブタイトルにしていましたが、今回はこの世界が主役というイメージ」と語る。
“Open Air(日本語では、野外などと訳されることが多い)”というキーワードで紹介される本作の世界には、前述のようにさまざまなシチュエーションがあるほか、ランドマークとなる塔や城が多く、各地には野生の動物が暮らしていたり、魔物たちが隊形を組んで徘徊していたりと、青沼氏が“主役”と称するだけの要素が入っている様子。
本作の広大な世界は、「『ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス』の約12倍の広さと言われている」(青沼氏)。
これだけの世界を用意した理由として、青沼氏は「ルートが決まっている世界にしたくなくて、100人がいたら100人が違う遊びかたができるようにしたかった」と理由を語る。
そんな世界を構築した青沼氏は、本作を表すOpen Airというキーワードを考えたとき、すぐに音楽のことが浮かんだそうだ。
「(本作は)決められたルートに従って遊ぶのではなく、自由に遊べる。
そうなると、“コースを決めて、この曲を流して盛り上げよう”という仕組みが取れないんですよね。
だから、この世界の自然の音に近く、融合する音楽にしないといけないと思って。
トレーラーも、冒頭にピアノのシンプルな音が鳴りましたが、ああいった自然の環境音にピアノが融合したような音にしています。
ピアノの音は、人の内面に語りかける響きを持っていると思うんです。
プレイしているときは自然の環境音のように感じているけど、プレイヤーが目的を持って動いたときに、ピアノの音が響いたりと、音楽がプレイヤーの行動と偶然にマッチして驚くようなことがある。
音楽もそんな自由度、Open Airになったということです」(青沼氏)。
今回のアクションの特徴として、任意にジャンプができる、ジャンプボタン(Xボタン)が搭載された。
『ゼルダの伝説』シリーズでは、地面の切れ間へ走っていくと、リンクが自然と跳ぶオートジャンプがデフォルトだったが(『ゼルダの伝説 夢をみる島』では、ジャンプができる“ロック鳥の羽根”というアイテムがあった)、任意にジャンプをし、崖や塔、遺跡の壁といった場所へしがみついてそのまま自在に上れるようになったのだ(ジャンプをせず地面からジリジリ上っていくことも可能)。
また、ジャンプ中に攻撃ボタンを押せば、従来にもあったアタック攻撃に近い、ジャンプ攻撃もできる。
崖や壁をどんどん上れると言っても無限ではなく、上っているあいだは『ゼルダの伝説 スカイウォードソード』にもあった“がんばりゲージ”が消費される。
がんばりゲージは、ダッシュ時などにも消費され、すべて使い果たすと、リンクが息切れを起こして、しばらく動きが遅くなってしまう。
『スカイウォードソード』同様に、使い切る前に回復し、再びダッシュ&上るというのをくり返すのがいいだろう。
ちなみに、がんばりゲージは試練の祠(詳細は後述)で手に入るアイテムで増加させられるという。
映像などでは、通常の緑色のがんばりゲージに加え、横に黄色いゲージが表示されている場面もあった。
小高い丘や大木などを上った場合、“パラセール”というアイテムを持っていれば、ゆっくりと飛んで落ちていくアクションが楽しめる(『ゼルダの伝説 風のタクト』のデクの葉、『スカイウォードソード』のパラショールのようなイメージ)。
非常に高い場所で景色を一望しつつゆっくりと落下し、つぎの目標を決めるという醍醐味は、本作ならではだ。
そんな魅力を青沼氏は、「高いところから自由に降りていくのも、Open Airにふさわしいと思っている」と語る。
ちなみに、記者がプレイしたデータではパラセールを持っていなかったのだが、それでも高所から飛び降りた場合、ものすごい勢いで地面に叩きつけられ、そのままゲームオーバーとなった。
そりゃそうだ。
草を斬って、ハートやルピーを回収するのは『ゼルダの伝説』シリーズのおなじみの要素だが、今回は、広大な土地に無数に生えている草を斬ってもハートなどは出ないという。
「今回、草を斬ってもハートなどは出てきません。
では、どうやってライフを回復するのかと言うと、今回のリンクはものを食べる。
狩りをしてそれを食べたり、狩りで手に入った材料を組み合わせて料理をするんです」(青沼氏)。
フィールドにはいくつか焚き火などが点在しており、その側には石でできた鍋があって、それを使って手に入った材料を調理していくのだ(木の棒を使って火を移したり、木と鉱石で火を起こしたりもできる様子)。
食材としては、木々に実っているリンゴなどの果物や、根もとに生えているキノコ、そして、フィールドを歩いているイノシシなどを倒したときに手に入る肉などが確認できた。
メニュー画面のアイテム欄でそれらを選べば、そのまま食べることもできるし、HOLD(抱える)を選べば、食材を持ち運ぶこともできる。
鍋の側で食材を持っていれば、鍋に投げ入れて、自然と調理がスタート。
一定時間で自動的に調理が終わって、おいしそうな料理ができあがる。
一方、焚き火などに食材を投げ入れれば直火のソテーもできる。
とはいえ、こちらは食材に火が通ったかを自分で確認しなければいけないようだ。
記者は、イノシシの肉がいい塩梅のステーキになるまで焼いたが、そのまま置いておけば焦げすぎた肉になってしまうのかもしれない。
なお、食材単体を食べるよりは、調理したものを食べたほうが、ハートの回復量が増えるほか、がんばりゲージが回復するものなど、さまざまな効果が得られるようだ。
さらに、「材料によっては料理じゃなく、薬ができることもあります。
今回のリンクは、こうやってものを食べないと回復できないので、サバイバル生活のようなイメージがありますね」(青沼氏)と語る。
リンクの武器と言えば、マスターソード。
『ブレス オブ ザ ワイルド』の英語版ロゴにもマスターソードが描かれているが、今回のリンクはいろいろな武器を使って戦う。
というのも、今回の武器はある程度使っていると壊れてしまうのだ。
そのぶん、剣や槍、斧を拾ったり、敵を倒して敵の棍棒などの武器を奪ったりできる。
武器ごとにモーションが違うのはもちろん、斧を使えば、大木を倒して谷を渡ったりといった、謎解きにも活用可能。
なお、リンクは盾も装備でき、敵が攻撃する瞬間に盾で弾けば、敵をひるませて倒しやすくできる(『トワイライトプリンセス』や『スカイウォードソード』の盾アタックに近い)。
広大な世界では、敵もただ徘徊をしているのではなく、生活をしているという。
なかには、陣形を取って、指揮をするもの、見張りをするものと役割分担ができているものも。
後ろで指揮を取っているようなリーダーを狙うもよし、こっそりと見張りを倒して各個撃破するという戦法も取れる。
ちなみに、左アナログスティックを押し込むと、リンクは腰を落としたステルス状態になる。
この状態で近づけば敵に気づかれにくいうえ、敵の背後から不意打ちで敵を倒すこともできるのだ。
このときの参考になるのが、画面右下に表示されている、音量を波形表示したもの。
大きな音を立てれば波形が大きく揺れるため、この波形の波をなるべく小さく留めて、不意打ちを食らわすのが理想になる。
また、敵とのバトルは、武器だけでなく、地形を活かしたアイデアも重要になる。
丘の上から大きな岩を落としてそのままぶつけたり、側にある蜂の巣を弓矢で落として蜂に敵を攻撃させたり、敵陣にある火薬樽に火の矢を放ち大爆発を起こしたりと、その場にあるものをうまく使って戦っていく遊びは、『ゼルダ』らしい閃きが活用できる場面でもあるだろう。
プレゼン中のプレイでは、何気ない岩に近づいたところで、岩どうしが合体し、大きな敵になるバトルも見られた。
非常に強く、一撃を食らっただけでやられてしまったのだが、青沼氏は「画面中央に敵の体力ゲージがありましたが、ものすごく長いですよね。
この敵は、すごくタフだと思います。
E3バージョンでも遊んでもらえますが、なかなか倒せないと思います」と語るように、非常に強力な敵があちこちに点在しているようだ。
ちなみに、この岩の敵は背中にある異なる色の岩が弱点のようだった。
とはいえ、そこを攻撃するだけで倒せそうな相手ではなかったが……。
本作では、小型のタブレット端末のような“シーカースレート”を使って、マップ画面を表示できる。
今回のE3バージョンのマップ画面には、宝箱の位置、敵の集落の位置、ランドマークなどが表示されている。
また、マップの特定の場所を指定すれば、リンクは青い光になってワープが可能だ(いわゆるファストトラベル)。
地名としては、ハイリア山、ハイリア川などが確認できたが……。
そのほか、シーカースレートを使えば、遠くの景色をズームしたり(望遠鏡のような使いかた)、目的地に光の柱を立てて目印にしたりといったこともできる。
マップに表示されるもののひとつに、“試練の祠”がある(英語版ではシュラインと呼んでいた)。
「『ゼルダ』と言えばダンジョンですが、今回はいままでと違うものとして、試練の祠と呼んでいるものがあります。
ダンジョンのようにフィールドから入っていくものですが、構造が違うもので、勇者を鍛える役割を持つ場所。
試練の祠の中のパズルを解いてゴールまでたどり着くと、ハートやがんばりゲージを増加させることができます」(青沼氏)。
今回のプレゼンで挑んだのは、“Bomb Trial”という名の試練の祠で、その名の通り、爆弾を活用した謎解きが多く用意されている場所だった。
試練の祠自体はそこまで大きくないが、ゴールにたどり着くまでは複雑な構造になっており、ゴールにはミイラになっている人(名前は“ja baji”だった)からスピリットオーブが手渡されていた。
青沼氏いわく、「シュラインというのは、100種類以上があって、攻略に順番はありません。
解けなかった場合、外に出てもワープできるので、すぐにもう一度挑戦してもらえる。
また、このシュラインとは別に、従来型のボスが存在するダンジョンも存在します。
それも、いままでと違うんですが、その情報はもうちょっと先に取っておこうかなと」とのこと。
ちなみに、爆弾を使った際、ゲージが表示されていた。
おそらくそのゲージが回復するまで、つぎの爆弾が使えないという、『ゼルダの伝説 神々のトライフォース2』でアイテムを使う際に必要ながんばりゲージに近いものだと思われる。
だが、弓矢の矢は従来のように数量で管理されていたため、アイテムによって数量管理なのか、ゲージ管理なのかが異なるようだ。
なお、E3版は通常の試練の祠よりも見つけやすくなっているとのこと。
ちなみに、プレゼンでは試練の祠の側に地中に埋まったガーディアンという敵がいて、リンクが近づくとレーザーを発射してきた。
この敵は、2014年の本作のデビュートレーラーで、リンクを猛スピードで追いかけながらレーザーを発射してきたあいつ。
どうやら試練の祠の側など、各地にいるようだ。
プレゼンの最後に公開されたのは、『トワイライトプリンセス HD』のウルフリンクamiibo。
このamiiboを使えば、本作と連動するということは発表されていたが、その連動内容は、『ブレス オブ ザ ワイルド』にウルフリンクamiiboをかざせば、ウルフリンクがゲーム内に登場するということだった。
また、ウルフリンクのライフは、『トワイライトプリンセス HD』でamiiboに保存したデータと連動するという。
「『ブレス オブ ザ ワイルド』はひとりで旅をしているが、これがあれば相棒が手に入ります。
新作が出る前にウルフリンクを育てて挑んでほしいですね」(青沼氏)。
なお、ウルフリンクがやられてしまうと、つぎに呼び出せるのは実時間で24時間後になるそうだ。
また、『ブレス オブ ザ ワイルド』のamiiboも3種類発売される。
そのうち2種類はリンクのもので、ひとつは弓矢を構えたもの、もうひとつはフードを被って馬に乗っている姿。
「いままでもamiiboをたくさん作りましたが、いちばんハイディティールじゃないかなと、僕は思っています(笑)」(青沼氏)。
また、最後のamiiboは、ガーディアンのamiibo。
これは触手のような手足の部分が可動式になっているという、初の可動式amiiboだ。
amiiboを紹介し、プレゼンは終了。
最後に青沼氏は、「新しい『ゼルダ』が作れたなと思っているんですが、遊んで実感していただけないと意味がない。
ぜひ体験してください」と結んだ。
●すべてを試したくなる、遊びが詰まった世界を体験!
各要素を詳細にお伝えしてきたが、ここからは実際に実機プレイで遊んだ感想を交え、本作のさらなる要素を紹介していきたい。
プレイができたのは、自由に世界を動き回るモード15分、そして、ストーリーの序盤を体験できるモード20分だ。
どちらも、自由度に溢れて困るというよりも、好きなことがなんでもできるので、やりたいことが多すぎてあっという間に時間が過ぎていってしまった印象だった。
その中で確かめられたことを中心にお届けしていく。
本作のプレイ感覚は、がんばりゲージの存在もあって、シリーズの中では『スカイウォードソード』に近い。
ただし、広大な世界を旅している感覚は、初めて『時のオカリナ』に触れたときのような印象だ。
コキリの森を抜け、初めてハイラル平原に飛び出したような、目の前に広がる大地。
しかし、『時のオカリナ』と異なるのは、遠くに山、大地だけでなく、塔や城、建物など、いろいろなオブジェクトが見えること。
プレイを初めて、ちょっと歩きまわるだけでも、敵の集落を見つけたり、料理ができる焚き火があったり、斧などの武器が落ちていたり、岩の下にコログ族(見た目は『風のタクト』のようだった)が隠れているのを見つけたりと、世界がただ広いだけではなく、あちこちが遊び場になる、『ゼルダ』らしい遊びの詰まった世界になっていることを実感できる。
あちこち歩き回っていると、イノシシのような動物を発見。
激しく動きまわっているが、弓矢を構えて(弓矢の狙いはスティック、もしくはジャイロ)攻撃。
一撃では倒せず、2発目の攻撃で倒した瞬間、敵は肉のアイテムへと生まれ変わった。
その後、近場に焚き火と石鍋があったため、石鍋で調理開始。
肉とキノコを鍋に入れると、カチャカチャとリズミカルな音を立てながら、石鍋の中を材料が跳ねまわって、おいしそうな料理へと生まれ変わった。
ハート3つ程度とあまり回復量は多くなかったが、手軽に作れるため回復にはあまり困らなそうだ。
ちなみに調理で薬ができたとき、とくに空き瓶を持っていなくても持ち運びができたのだが、今回は空き瓶はないのだろうか?
続いて、見張り台に立つ敵(シリーズでおなじみの、ボコブリンのような見た目)を発見。
台のまわりにも同様の敵が数体いる。
まずは、台の上の敵を倒そうと、弓矢を構え、いざ攻撃……するも、距離が遠かったのか矢は失速。
もう一度敵との距離を測ろうと、タブレットのようなシーカースレートを使って敵を観察すると、敵をマーキングし、体力のような数値が現れた。
体力が数値化されるのは、『ゼルダ』シリーズ史上初ではないだろうか(ほかにもあったらごめんなさい)。
改めて弓矢で敵を射ると、見事に撃破できた。
のだが、その音を聞きつけたのか側にいた敵が駆けつけ連戦に。
難なく倒せたが、まったく気づかれずにすべての敵を倒すのには慣れが必要そうだ。
なお、映像では、戦闘中に一瞬スローモーションのようになり、特別な動きで攻撃をする、『トワイライトプリンセス』の奥義のようなシーンもあった。
条件などは不明だが、武器ごとに奥義があったら、さらに楽しそうだ。
序盤のストーリーが楽しめるモードでは、水が浸されている台座のような場所で眠るリンクが、「Open your Eyes」と呼びかけられ目覚めるところからスタート。
シーカー族のマークが描かれたタブレットのようなシーカースレートを手に入れ、暗い洞窟から抜け出すと広大な大地が眼前に広がる。
ちなみに、起きたばかりのリンクはパンツ一丁の姿で、宝箱にある洋服(上下)を手に入れて着ることで、冒険者のような姿に。
なお、洋服には防御力の概念のほか、寒さを防ぐといった効果もあり、映像では鎧を着ているリンクの姿も見られた。
外に出ると、廃墟のような建物の近くに杖を持ったおじさんがいた。
カンテラを持っているが、『時のオカリナ』などに登場したダンペイさんとは異なる様子。
ストーリーの語り部のような、『スカイウォードソード』で言う、最初に出会うおばあさんに近いものを感じたが……?そのおじさんや、冒頭に聞こえた天の声(ハイリアの女神だろうか)の言葉から察するに、今回の冒険の舞台は、ハイラル王国が崩壊して100年後の世界。
“Calamity Ganon”という敵が、世界を滅ぼした後に再び力を蓄え、その力が世に出るのも間近という状況のようだ。
リンクはそんな100年のあいだ眠りについていたという。
ちなみに、側にあった廃墟のような建物は、崩壊した時の神殿。
中には、ハイリアの女神像らしきものがあり、目の前で“祈る”アクションが使えた。
ハイリア王国の崩壊から100年後。
そして、『風のタクト』に出たようなコログ族の姿(ちなみに、コログ族は世界各地にいるようで、スタルチュラのように探す楽しみがありそう)から想像するに、ハイラルの時系列的には後半に位置する内容なのかもしれない。
地図に導かれるまま、岩山の中にある謎のくぼみにシーカースレートをかざすと、突如、大きな塔が隆起を始める。
しかも、その場所だけでなく、世界中のあちこちに塔がそびえ立ったようだ。
これによって、現在リンクがいるリージョン地域のマップがシーカースレートに記録される。
どうやら、各地の塔を訪れることが、当面の目的になりそうだ。
塔から降りると、さっき出会ったおじさんが呼びかけてくる。
塔の隆起で世界中の異変を感じ取ったようだ。
そんなおじさんがこの場所にやって来るのに使っていたのが、パラセール。
これで、このアイテムが手に入る……と思いきや、おじさんは「目の前にある祠の中の宝物を持ってきてくれば交換してやる」と言い出してくる。
この流れで試練の祠に挑戦かーと、祠を目指して、目の前にある谷のあいだに溜まった深い水を泳いでいると、徐々にがんばりゲージが減っていく……!急いで渡らなきゃと水中ダッシュ(早く泳ぐ)を使ったら、ゲージがさらに一気に減少。
結果、溺れてゲームオーバーになったところで、時間が来て、試遊は終了となってしまった。
トータルで40分くらいという、試遊にしてはそれなりに長い時間をプレイしたのだが、それでも時間はぜんぜん足りず。
できることが多いこともあって、あっという間に時間が来てしまった。
試練の祠にも行きたかったし、もっと敵との戦闘も楽しみたかったし、遠くに見える山を登ってみたかった。
製品版も、こんな気持ちで、つぎつぎとやりたいことが出てくるのかもしれない。
●今回のリンクは右利き!いろいろな謎を開発者に聞く
記事の最後に、開発者へ向けて行われたQ&Aセッションをお届けしよう。
いろいろと興味深い話題が多く、早く、青沼氏にインタビューをしたいという思いに駆られる。
回答者は青沼氏を中心に、現地スタッフやローカライズスタッフの方も答えていた。
Q今回のディレクターは?
A『スカイウォードソード』の藤林(藤林秀麿氏)が担当しています。
チームの人数がとても多いんですが、彼を中心にとりまとめてやっています。
Qリンクは100年眠っていたと言うが、シリーズの時系列ではどこに組み込まれるのか?
A今年のE3では、この世界の話題を中心にお話させていただいて、この世界で何ができるのか、今回はリンクがどんなことができるのかを説明させていただいているので、ネタバレ回避も含めて、ストーリー、キャラクターについての話は控えさせていただきます。
そういったお話はまた改めて。
時系列についてヒントだけ。
シーカースレートというアイテムがありますが、このアイテムについているマークは、『時のオカリナ』のシーカー族のマークなんですね。
それで、100年後というお話だとどうなるかを考えていただければと思います。
Q昼と夜のサイクルはどれくらいの時間で変わるのか?
A現実世界の1分がゲームでの1時間です。
24分でゲーム内では1日が経過します。
Q開発を始めたときに何がきっかけだったのか。
最初のアイデアにはどれだけ近づいているのか。
A『スカイウォードソード』を作ったときに、広大な空を作って、空からいろいろなエリアに降り立つものにしました。
かなり大きな世界を描いたつもりだったんですが、ファンの方からは「そのあいだの世界を知りたい」、「あいだのエリアに行けないのはなんで?」という意見をいただいたんです。
『ゼルダ』を遊んでくださる方は、そういう探究心が強いんだろうなと改めて感じ、そういうところを作りたいなと思って作り始めています。
だから、パラセールを使って高いところから降りるというのは、『スカイウォードソード』の進化系というイメージですね。
どこにでも上っていけて、スッと降りられるという感覚を仕上げていくのにとても時間がかかったんですが、本日、皆さんにプレイしていただいているのを見たところ、皆さんにサクサクと遊んでいただけていたようなので、思い描いたものができていると思います。
Qウルフリンクamiibo以外のamiibo対応は?
Aお楽しみに、とさせてください。
Qすごく広い世界ですが、広く感じさせないくらい遊びが詰まっているように感じた。
この密度ですべての世界が構築されているのか、今回のE3版のエリアは密集度が高いのか。
また、全世界のファンが気になっていると思うのだが、今回のリンクが右利きなのはなぜか?
AE3で遊んでもらっているところは、物語の冒頭であり、短時間でいろいろなところが見えるように、わかりやすくレイアウトされています。
そのさらに外のエリアは、もっと高いところから降りたり、馬に乗ったりと、移動に関してももっといろいろな要素ができるぶん、密度感は外とは若干異なると思います。
あと、試練の祠の話をしましたが、今回体験できるところでは目に見える場所に試練の祠がありますが、外のエリアでは隠されたものもあって、そこにどうやってたどり着くのかといった遊びもあるので、ご期待ください。
密度の違いはあるけれど、ストーリーだけを進めようとしても、その道中でいろいろなものを発見して、あれをやってみよう、これをやってみようと、いろいろな経験ができると思います。
あと、リンクの右利きに関してですが、リンクがどちらで剣を振るかというのは、操作方法を決めるときに決定するんですが、今回は、Wii U GamePadでボタンを押して剣を振るということで、剣のボタンが右側にあるため、右利きにしています。
Qゲーム中では、天の声などにボイスがあったが、ほかのキャラクターもしゃべるのか?
A結論から言いますと、製品版を楽しみにしてください。
ボイスもあればテキストもあるように、今後もそうなるのではないのかなと。
QNX版に関してですが、Wii U版と違う点は?
ANX版はWii U版と同じ体験がしてもらえるようになっています。
それ以上は言えません。
Qこのゲームでは、Wii U PROコントローラーは使えるのか?
Aはい。
Wii U PROコントローラーでもプレイできます。
Q昼と夜の概念があるが、昼と夜の違いは何か?音の波形を表示しているが、あれを活用する要素は多くあるのか?
A夜になると敵が寝ちゃったり、夜じゃないと出てこない敵がいます。
あと、敵をやっつけるのに、夜になって寝るのを待つといいといったことがあります。
そのときに重要になるのが、音のゲージ。
クラウチングしてゆっくり近づくと、あのゲージが波打たないので、そのまま不意打ちで倒せます。
もちろん昼にも不意打ちはできますが。
あと、料理で音を消す薬なども作れます。
ちなみに、すべての敵が夜に眠っているというわけではないです。
Qサブタイトルで自然を表す用語として、ネイチャーではなく、ワイルドを使った理由は?
Aサバイバルという話がありましたが、本作では大自然の中でリンクはものを食べながら、敵と戦いながら生きていかなくてはいけない。
大自然の中でも、荒野といったイメージが近いので、ワイルドという言葉を使いました。
マップのスタンプなどで表示された場所だと、特定の材料、武器などが手に入りますが、武器が手に入るとか、自然の中で取りに行かなければいけないという要素があります。
今回体験していただいたのはゲームの冒頭ですので、穏やかな環境になっているかもしれませんが、自然溢れる環境もあります。
個人的には自然に散歩に行くのではなく、野生に冒険に出るイメージですね。
お見せした中で、ガーディアンという敵が出てきましたが、今回は動きまわりませんでした。
でも、あの敵は本来はレーザーを撃ちながら追いかけてくる怖い敵で、先のエリアでは走って追いかけてきたりします。
製品版でワイルドになっているところを体験いただけると思いますね。
あと、音楽にもつながっているところがあって、ふつうに歩きまわっていると穏やかな音楽が鳴っているのが、音楽が変わるとプレイヤーの中にも恐怖感が生まれると思います。
以上で、プレゼンテーションと試遊会は終了。
最後に、E3の任天堂ブースの『ゼルダ』部分を見学させてもらった。
『ブレス オブ ザ ワイルド』の世界をそのまま再現したようなブースは、試練の祠に入るところから始まり、その奥にリンクやガーディアン、ボコブリンなどの巨大フィギュアが設置された、広大な世界(ブース)に入っていくことになる。
地面も芝のようになっており、歩く場所によって音が鳴るという。
朽ち果てた時の神殿なども再現されており、ブースだけでも力の入れようが伝わってくる。
ついに詳細がお披露目された『ゼルダの伝説ブレス オブ ザ ワイルド』。
あまりに広大で、かつ、多くの要素が入っていると思われるため、その全貌はつかめない。
しかし、プレゼンや試遊で片鱗に触れただけでも、大きく変わったことはわかる。
かつて、『時のオカリナ』を初めてプレイしたとき、初の3D『ゼルダ』という変化に戸惑いつつも、謎解きに頭を悩ませる感覚や、冒険をしているプレイ感に、“ゼルダらしさ”を感じたのを覚えている。
『ブレス オブ ザ ワイルド』も、戸惑いは覚えつつも、いろいろなことを試したくなる楽しさや、やってみたら謎解きにつながっていく発見などは、まさに“ゼルダらしさ”が感じられる。
『ゼルダ』シリーズ最高峰のタイトルになるか。
発売は2017年だが、早く触れてみたいと思う気持ちが止められないくらい楽しみだ。
ゼルダの伝説ブレス オブ ザ ワイルド
メーカー:任天堂
対応機種:Wii U
発売日:2017年
価格:価格未定