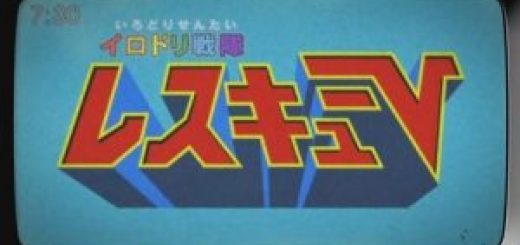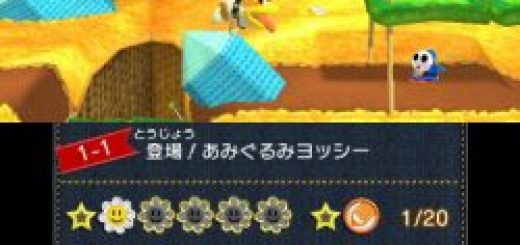SIEJAプレジデント・盛田厚氏インタビュー―キッズからハイエンドユーザーまで全方向に攻めるプレイステーション
2013年に発売され、3回目の年末商戦を迎えるPlayStation 4(以下、PS4)。
PS4 Pro、新型PS4、PlayStation VR(以下、PS VR)とファミリーが増え、多彩な新作ラインナップも投入されて大きな盛り上がりを見せています。
東京ゲームショウ 2016にあわせて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア(SIEJA)プレジデント盛田厚氏への合同インタビューが行われました。
◆PS Vitaと『Minecraft』でキッズ層に広げられた
――E3と違い、東京ゲームショウではPlayStation Vita(以下、PS Vita)が数多く展示されていて、安心しました。
まずは今後のPS Vitaの展開から教えてください。
盛田:よくご存じだと思いますが、去年PS Vitaはすごく大きなことを達成しました。
PS Vitaと『Minecraft』のおかげで、子ども達にプレイステーションフォーマットをすごく拡大させられました。
2年間くらいかけて地道にやってきて、100万本のセールスを達成できました。
ただ、イベントをやって子ども達にアンケートをとると、まだPS Vitaや『Minecraft』を持っていない人たちがいます。
単純計算でPS Vitaと『Minecraft』が今の倍くらい売れてもおかしくありません。
そのためPS Vitaと『Minecraft』のキャラバンは年末商戦も含めて、まだまだ続けていきます。
『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』も含めて、キッズ層へのアプローチは重要な施策の一つだと思っています。
――「PS Vita 2」の予定はありますか?
盛田:ノーコメントです(笑)
――先日のカンファレンスで子ども向けのキャラクターを創出するというお話もありましたが、それもキッズ層アプローチの一環ですか?
盛田:キッズ層アプローチをやりたいと、2年前に着任したときからずっと思っていました。
子供の頃の習慣は非常に重要です。
子供の「コントローラー離れ」が進んでいるのではないかと感じていて、テコ入れしたかったんです。
十分とは言えませんが、PS Vitaでキッズ層をかなり拡大できました。
次は子ども達に愛されるようなキャラクターを自ら作り上げることで、さらに推進していきたいですね。
ソニーグループにはさまざまな会社があるので、グループ全体で連携して、ゲームだけではなく、もっとおもしろいことに挑戦していきたいと思っています。
――具体的にはどのような計画が?
盛田:現時点ではお話できることはありませんが、来年くらいには何かお話できるのではと思っています。
アニメ、音楽、もちろんゲーム…できればこれらが連動していけるといいですね。
「言うは易く行うは難し」なので、がんばらなければいけないところです。
◆PS4 Proと新型PS4が担う役割
――すそ野を広げるという意味ですか?
盛田:プレイステーションのユーザー層を全方位で広げていきたい、そのための活動の一環という意味ですね。
今回「PS4 Pro」「新型PS4」を投入するのも、その一つです。
日本でもこの年末商戦に向けて、ユーザーさんが待ち望んでいたタイトルが、ほぼ出そろうのではないかと思います。
このタイミングで新型PS4をマジックプライスで出すことができる、そんな風に考えています。
ここで購入を待っていた人たちに、一気に拡大させていきたいですね。
――なるほど。
盛田:また、これまでプレイステーションはライフサイクルが長かったんですが、これに対してPCやスマートフォンは1年ごとにバージョンアップしています。
これまでのライフサイクルではPS4はまだ中間地点です。
しかし、このタイミングでハイエンドモデルを出すことで、よりハイエンドなゲーム環境を求める人々に対して、買い換えも含めて、プレイステーションをもっと楽しんでもらうことに挑戦したいと思っています。
これがPS4 Proの役割です。
――PS4 Proはどれくらい日本のユーザーに受け入れられると思いますか?
盛田:台数は言えませんが、PS4をすでに遊んでいて、さらにハイエンドを望まれている人。
それからPCゲーマー。
4Kテレビを所有している人、または購入を予定されている人がターゲットです。
――同じことは「よりハイエンドなゲームプラットフォームを求めている」ゲーム開発者にも当てはまるのでしょうか?
盛田:そうですね。
PS4 Proによって、よりクオリティの高いゲームを作ることが可能になると思います。
――では数年後、さらにすごいPS4が出たりするんでしょうか?「PS4 Pro II」だとか。
盛田:もちろん、ハードのスペックアップについては、社内で常に議論がありますので、検討はしなければいけませんが、今はPS4 Proに全力投球ですね。
――先日「PlayStation Now」がPCでも対応されて、スマートデバイス市場に向けて新たにフォワードワークスも立ち上げられましたが、御社にとってPCやスマートデバイスはどのような存在になりますか?
盛田:ゲームというエンタテインメントでは同じですので、プレイステーション、あるいはゲームを生業にしている企業として、市場が大きいところはやったほうがいいという考えはあります。
PS Nowによって非PS4ユーザーにもプレイステーション体験を広げていけるでしょう。
フォワードワークスについても、スマートフォンという、日本で非常にたくさんのユーザーさんがいる分野に対して、我々のノウハウでゲームを提供していける…そんな考えで設立しました。
――プレイステーションを幹にして周辺に広げていくというイメージですか?
盛田:そうですね。
ゲームが楽しいのは、最高の体験が提供できるから。
つまり「できないことができるから楽しい」んだと思います。
これはコンソールゲームならではの楽しさです。
最高の楽しさを提供していくのがプレイステーションだというのは忘れてはいけないと思っています。
◆PS4は「遊んで楽しい、見て楽しい」
――PS4が発表された時、「PS4体験」とでもいうようなコンセプトムービーを作られたと思います。
大学生がPS4でeSports的な大会を主催して、その様子がスマートフォンで広がって、世界中の人たちが大会を応援したり、視聴して楽しんだりといった内容のものです。
盛田:はい。
――年末商戦に向けて、PS VRが出ます。
PS4 Proも新型PS4も出ます。
こんな風にデバイスの種類は増えています。
しかし、あのコンセプトムービーが示していたような、ライフスタイルの変革といった点では、まだ道半ばかなと思うのですが、いかがでしょうか?
盛田:そういう意味で言うと、やりたいことはまだずっと先にあります。
いかに新しい楽しみを創り出して、それらを連結させていくかということだと思いますので、そのためのベースとしてPS4があり、PlayStation祭があり、ということだと思います。
まずはみんなが戦う場、楽しむ場をつくっていく必要がありますので、強い人たち、上手い人たちが戦う場から、みんなが気楽に楽しめる場、それから子ども達が何かを作り上げて発表して、そこからコミュニケーションを広げていける、そんな場を作っていきたいですね。
――なるほど。
盛田:それから、もう一つ重要なのは、それを「見て楽しめる」ようにするということです。
せっかくYoutubeなどを通して、子ども達も動画を見て楽しんでいるので、そこをうまくつなげていって、「対戦を見て楽しむ」「みんなで応援して楽しむ」「日本代表を応援する」「国や地域ごとに対戦する」といったように、インターネットの良さを活かして、いろんなボーダーを超えていければと思います。
それを今は、まずはPlayStation祭を通して、日本で進めているところです。
その先にいろんな連携があると思います。
すべてを弊社が押し付けると、なかなかうまくいきませんから、まずは少しずつ場を作ることだと思います。
――夏に開催したPlayStation祭の手応えはいかがでしたか?
盛田:もともと我々はいろいろなイベントをやってきました。
それらを単発のもので終わらせずに、連続して行うことで、最終的に大きなものに作り上げられるのではないか。
そんな思いでPlayStation祭をやっています。
夏に開催したのもその一つです。
実際、イベントとしてはかなり盛り上がりました。
子ども達の創造性はすごくて、『Minecraft』でさまざまな作品が完成しました。
今後も「単発で盛り上げていくこと」「それらをつなげていくこと」「見て楽しいということ」。
これらの連結を考えていきたいですね。
――とはいえ、子供さんたちはスマートフォンを触りたいというのも、事実だとは思います。
フォワードワークスは今後どのような取り組みを進めていくのでしょうか?
盛田:まだ公表できませんが、せっかく我々のノウハウを活かして、スマートフォンでゲームを作るからには、精一杯良いものを作りたいですね。
オリジナルゲームも移植作も含めて、いろいろなやり方があるかと思います。
◆VRで楽しいことは、できるだけVRで実現していきたい
――スポーツのネット配信DAZN(ダ・ゾーン)で、日本に先駆けて海外でPS4とPS3むけに対応アプリの配信が始まりました。
今後DAZNをPS VRで展開されるような考えはありますか?
盛田:今そのような予定はありませんが、VRにはさまざまな可能性がありますから、VRで楽しいことは、できるだけVRで実現していきたいですね。
――PS VRでもゲーム以外のコンテンツがかなり充実してきています。
盛田:はい、そこはすごく重要だと思っています。
ゲームの楽しさを伝えることは絶対必要だとしても、プレイステーションを全家庭に普及させていくうえで、VRのような技術はすごく向いていると思っています。
いろいろなコンテンツがPS VRに来てくれるように、また提供できるように、努力していきたいですね。
――盛田さんが2年前に就任された時にはまだ「Project Morpheus」と呼ばれていたものが、いよいよ発売になります。
この2年間を振り返っていかがですか?
盛田:たしかにハードウェアもソフトウェアも、2年前と比べればずいぶん改善されました。
みんな「よくここまで来たなあ」と思っているのではないでしょうか。
もっとも、VRの市場自体はまだまだ小さいじゃないですか。
特にPS VRはこれから発売ですので、我々としてはこれからがんばります。
――PS VRの国内予約が非常に順調ですが、当初から想定されていましたか?
盛田:思っていた以上に好調ですね。
――いつ頃になったら普通に買えるようになりますか?
盛田:これも予測が難しいのですが、もちろん我々も努力していきたいと思っています。
我々はPS VRが非常に大きな可能性を秘めた商品だと思っています。
今年何台売れたから良かったという話ではなくて、買っていただいたお客様が満足していただける、もっと遊びたくなる、他人に自慢したくなる、そういった状況をいかに作り上げていけるかがポイントです。
そのため来年以降がすごく重要で、そのためにはハードウェアのクオリティも、コンテンツも、できる限りフォローしていく必要があります。
それらが積み重なって、市場が広がるのだと思います。
――PS4 ProとPS VRを組み合わせると、さらにリッチな体験ができるとのことですが、両者のセット商品などは考えられていますか?
盛田:どのような販売方法が良いかは、常に考えていかないといけませんが、まだこの段階でお話できることはないですね。
でも、ハイエンドなユーザーさんであれば、そうしたニーズもあると思いますので、頭に入れておきます。
◆デバイスは増えても軸足は変わらない
――PS4、PS4 Pro、新型PS4、PS VR、そしてPS Vitaとハードウェアが増えて、全方位的に拡大していますが、今後のプレイステーションビジネスの展望はどうなりますか?
盛田:デバイスの数では増えていますが、各々が異なる役割を持っていますので、全体で「プレイステーション」を拡大していきたいと思っています。
繰り返しになりますが、PS Proでハイエンド指向の方に満足していただきたい。
新型PS4で、これまで購入を迷っていた人にも楽しんでいただきたい。
PS Vitaで子供層にも浸透させていきたい。
PS VRでゲームの世界を広げていきたい。
口で言うほど簡単ではありませんが、我々としては、そうなるように努力していきます。
日米金融政策イベントを前に売り買い交錯となる中、やや買い戻しが優勢となっている。
日経平均株価は小幅高の一方、東証株価指数(TOPIX)はしっかり。
トヨタが反発し、アルプス、ソニー、キーエンスは高い。
三菱商、ブリヂストン、JALが買われ、ソフトバンクG、東電力HDは堅調。
任天堂が値を上げ、ディーエヌエーは大幅高。
三菱UFJ、第一生命が締まり、花王、武田はしっかり。
半面、スズキが下押し、Vテク、キヤノンは弱含み。
三井不、リクルートHD、JR東海、アステラス薬が売られ、ファーストリテは大幅安。
スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズの“ジョーカー”シリーズ最新作、3DS用RPG「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル」を2017年2月9日に発売する。
価格は、パッケージ版、ダウンロード版ともに5,250円(税別)。
発売決定の発表に合わせてティザーサイトがオープンした。
本作は、「ドラゴンクエスト」のモンスターたちを仲間にして育成・配合していく「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3(以下DQM ジョーカー3)」をベースに、新シナリオを追加したタイトル。
これまでの“ジョーカー”シリーズのキャラクターたちも多数登場し、冒険を繰り広げる。
また、完全オリジナルのモンスターをはじめ、前作「DQM ジョーカー3」では登場しなかった人気モンスターたちも参戦する。
インターネット通信などの通信機能を使用したプレーヤー同士の対戦では、自分だけのパーティでさらに白熱したバトルを楽しむことができるうえ、「DQM ジョーカー3」のセーブデータがあれば、集めたモンスターのデータを引き継ぐことも可能となっている。
(C)2016 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.(C)SUGIYAMA KOBO