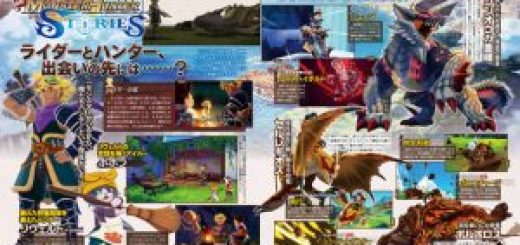NAS業界に海外からの新たな刺客 TerraMaster「F2-220」
国内での新たなNASの選択肢として、最近、ちらほらと名前を見かけるようになってきたブランドが「TerraMaster」だ。
ホームユーザー向けながら、高い性能を誇る2ベイNAS「F2-220」を実際に試してみた。
■まだまだまだ発展途上
結論から先に言えば、TerraMasterのF2-220は、まだまだ、否、まだまだまだ発展途上の製品だ。
そこら中で見かける「アプリ」ボタンが「Apply」の日本語訳であることに気づくまでしばらく時間がかかったほど、翻訳の精度は甘いし、フォントも簡体字が多用されており読みにくい。
仮想環境の実装やアプリケーションサーバー化が進む最近のNASと比べると、アプリとして提供される拡張機能の数も少ないし、それぞれの機能の完成度もさほど高くない。
販路は今のところAmazon.co.jpのみだし、日本語でのオンラインフォーラムやヘビーユーザーのレポートなどもあまり期待できない。
では、選択肢として検討する余地がないのか?と言われると、決してそうはならない。
なぜなら、コストパフォーマンスが抜群に高いからだ。
以下の表は、本コラム執筆時点、Amazon.co.jpで2万円以下で購入可能なディスクレスのNASのスペックだ。
※実売価格はAmazon.co.jpの2016年11月9日時点の価格
今や定番となりつつあるSynologyやQNAPの2ベイエントリーモデルと同様に2万円以下の格帯に位置するF2-220だが、スペックとしてはAtom系とは言え、2.41GHzのIntel製Dual Core CPUを搭載しているうえ、メモリも512MBが多い家庭向けのエントリーモデルとしては異例の2GBを搭載。
組み立て式の製品が中心となるなか、フロントアクセス可能なホットスワップ対応のHDDベイを備えるほか、筐体もアルミを採用するなど、クラスを超えたハードウェアスペックを備えている。
ちなみに、同じCPUを搭載するQNAPのTS-251(メモリは1GB)の実売価格は5万2824円(2016年11月9日時点)。
多機能さではQNAPとはまだ勝負にならないが、同等の処理性能を持つNASが2万円以下で手に入るのだから、驚きではある。
ファイル共有、バックアップというNAS本来の処理以外にこだわらないというのであれば、発展途上の機能面に納得したうえで、あえて本製品を選ぶというのも一つの選択と言えそうだ。
■アルミならではの高い質感と実用性
それでは、製品をチェックしていこう。
本体はアルミと樹脂を組み合わせたシルバーのシンプルなデザインで、サイズも幅119×高さ133×奥行227mmと比較的コンパクトに仕上がっている。
低価格なエントリーモデルのNASの場合、本体は樹脂製であることが多いが、本製品は側面部分にアルミが採用されている。
デザイン的な高級感も感じられるが、放熱に有利という実益もある。
実際、一週間ほど連続稼働させてみたが、すっかり寒くなった今の季節であることを考慮しても、本体温度が22〜23℃前後で安定。
アイドル状態では、背面のファンが停止し(ステータス画面では10rpmと表示されるが停止)、ほぼ無音といっていい状態にまでなる。
ベンチマークテストで100%近いCPU負荷をかけても、温度の上昇は1〜2度ほどとわずかで、CrystalDiskMarkをアイドル状態から2〜3周させたくらいでは、ファンは止まったままで、微動だにしない。
これには、だいぶ驚いた。
組み合わせるHDD(今回はWDRed 4TB)次第ではあるが、かなり優秀な筐体であることをうかがわせる。
できれば夏場に実際にテストしてみたかったところだ。
■セットアップ
セットアップは、改善の余地はあるが、比較的簡単だ。
HDDの装着は、トレイを引き出してねじ止めするだけと簡単で、ねじを回すためのドライバーも付属しているので準備には苦労しない。
ただし、同梱の簡易マニュアルの記載に従って、セットアップ用のWebページにアクセスすると、なぜかイタリア語で表示されてしまい、まったく何をすればいいのかがわからない。
せめて英語にしてくれれば何とかなるのだが……。
よくわからないままページを進めていくと、写真と画面から、どうやらユーティリティをダウンロードすればいいことがわかったので、PC向けのユーティリティをダウンロードしてインストール。
こちらはきちんと日本語でセットアップされた。
ユーティリティさえインストールできれば、あとは簡単だ。
画面表示に従ってネットワーク上のNASを検索、設定画面にアクセスしてHDDの初期化とOS(TOS)のインストールを実行すればいい。
なお、F2-220は2ベイのNASとなるため、基本的にRAID1での構成となる。
シングルディスク構成やRAID0なども使えるが、大切なデータの保存先であることを考えると標準のRAID1のまま構成するといいだろう。
セットアップが完了すると、ブラウザ経由でTOSと呼ばれる独自のGUI画面にアクセス可能になる。
デスクトップを模したUIは、しっかり今時のNASという印象だが、やはりフォントと翻訳はかなり気になるところ。
前述した「Apply=アプリ」も気になるが、「Public」共有フォルダーをわざわざ日本語で「公共ディレクトリ」と翻訳しなくてもよさそうなものだ。
「アプリケーション」で、アプリを追加するための画面に「もう取り付けます」と表示されているのは、おそらくダウンロード済みのアプリを起動可能にする意味だと思われるが、とにかくところどこで「ん?」と思わせられる。
機能面では、Samba、Macファイルサービス、NFSのファイル共有に加え、Webサーバーを利用可能。
ユーザーとグループを作成して、一般的なファイル共有が可能になっている。
ホームユーザーの利用を想定しているため、Active Directory(AD)との連携などはできない。
パフォーマンスを考えるとビジネス利用も不可能ではないだけに、このあたりはサポートしてほしかった印象だ。
このほか、外部からのアクセスも可能になっている。
tnas.onlineという独自の中間サーバーを経由する方式とDynamic DNSを利用する方式の2種類があるが、tnas.onlineがアカウントとパスワードを登録するだけで利用できるため手軽だろう。
ただし、基本的にサポートされるのはブラウザ経由でのアクセスのみであり、スマートフォン向けのアプリは提供されない(tnas.onlineはアプリのダウンロードを推奨するメッセージが表示されるがアプリが見当たらない)。
このため、スマートフォンでのユーザビリティとしては、あまり良好とは言えない。
また、「ファイル管理」アプリを利用することで、NAS上のファイルを共有するためのURLを自動生成することも可能だ。
NASでは一般的な機能なのだが、なぜかURLが「192.168.1.22」などのローカルIPアドレスで生成されてしまう。
内部のユーザーとわざわざURL指定でファイル共有することは考えにくく、通常は外部ユーザーとの共有に利用するための機能だ。
Dynamic DNSを登録する機能があるのだから、そのアドレスで生成するのが筋だ。
この点は非常に疑問が残る。
■アプリもまだまだ
F2-220はアプリを追加することで、機能を拡張可能だが、これらの機能もまだ発展途上だ。
評価時点では、SVNサーバー、Javaバーチャルマシンなどの開発環境、Clam AVアンチウイルス、PTダウンロード、iTunesサーバー、Dropbox Sync、メールサーバー、Plex Media Server、MySQLサーバー、マルチメディアサーバー(DLNA)が利用可能となっていた。
とりあえずマルチメディアサーバーをインストールしてみたが、若干、相性がありそうだ。
ビデオカメラで撮影したMP4の動画の再生を試してみたところ、PS3では問題なく再生できたものの、SONY製のテレビ(BRAVIA KDL-23W600)では再生に失敗してしまった(SynologyのNASでは再生可能)。
同じくアプリとして提供されているPlexもDLNAメディアサーバーとして使えるが、こちらはPS3、BRABIAともにエラーでメディアの参照ができなかった。
メディア系の機能は、ホームユーザー向けのNASとしては必須ともいえる機能なので、このあたりに相性問題があるなると、購入を躊躇するユーザーも少なくないだろう。
しばらく使ってみた印象としては、どうも検証が足りないように思える。
先のローカルIPの件にしろ、DLNAの相性の件にしろ、もう少し、実環境でのテストを繰り返し、煮詰めていかないとユーザーの信頼を得るのは難しいだろう。
■パフォーマンスは良好
最後に、パフォーマンスについて触れておこう。
以下は有線LANで接続したPCから、CrystalDiskMark 5.1.2を実行した際の値だ。
リード、ライトともにシーケンシャルで100MB/sを超えており、さすがにCPUパワーとメモリの余裕を感じさせる。
ここまでパフォーマンスが出るなら、LANポートを2系統用意しLAGで使えるようにしてくれれば、翻訳や多機能さとは関係のない、ファイル共有やバックアップといった基本中の基本の用途での素性の良さが発揮できるのに……、と残念に思える。
正直な印象として、多機能さという部分で、今からSynologyやQNAPのNASに追いつくのは至難の業と思える。
であれば、放熱性に優れたケースとクラスを超えたCPU性能、それでいて低価格であるというコストパフォーマンスの良さを前面に押し出した方がいいのではないかと思える。
本コラムで以前に同社のDASを取り上げたことがあったが、目指すのはその延長線上であり、アプリケーションサーバーやプラットフォーム化しつつある先行勢ではないと思える。
この点が、もっと明確に表に出るようになれば、きっと、それを理解してくれるユーザーからの支持を得ることができるだろう。