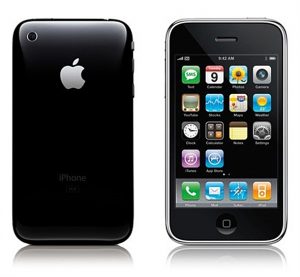ポケモンGOとサン・ムーンに見る「脱落させない」ゲームの作り方
「ポケットモンスター 赤・緑」が発売された1996年、私は小学生だった。
さすがに小学生の頃というと記憶がおぼろげになっているが、通信ケーブルの所持がとても重要だったことは今でも覚えている。
赤緑の20年後に発売された「ポケットモンスター サン・ムーン」も、発売前に予約して初日からプレイしている。
実は前作の「ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア」は序盤で飽きてやめてしまったのだが、今回は学生時代に比べて少なくなった遊び時間をほぼサン・ムーンに費やして一気にクリアしてしまった。
時間の少ない社会人でも飽きずにクリアできた、というのは「Pokemon GO」でポケモン熱が再燃しているのもあるが、サン・ムーンがこれまでのポケモンシリーズに比べて大きくゲーム設計を変えたのが何よりも大きな要因だと考えている。
端的に言えば、プレーヤーを「脱落させない」ゲーム作りになった。
そう思う点を下にいくつか挙げてみよう。
ネタバレは極力しない方針だが、ゲーム内容に触れるのでその点了承した上で読んでほしい。
・ライバルがこちらにとって相性の良い御三家ポケモンを選んでくれる
赤・緑では主人公がゼニガメを選べばライバルはフシギダネ、フシギダネを選べばヒトカゲ、と主人公のポケモンにとって相性の悪いポケモンをライバルが選んでいたが、今作ではそれが逆転している。
主人公がみずタイプを選べばライバルはほのおタイプ、ほのおタイプを選べばくさタイプ、と主人公にとって有利なポケモンを選ぶようになった。
これによって最初のライバルとのバトルは簡単に勝てるようになった。
(もっとも、この変更は「ポケットモンスター X・Y」からの仕様だ)
・ひでんマシンがなくなった(わざ自体はある)
マップを攻略していく上で必要不可欠だったのが「ひでんマシン」だ。
木を切るには「いあいぎり」、海を進むには「なみのり」などのひでん技を手持ちのポケモンに覚えさせておく必要があった。
どうくつに入ってみたが「かいりき」を使えるポケモンを連れてこなくてすごすご帰る、という経験がある人もいるだろう。
サン・ムーンではポケモンがなみのりを覚えていても海は進めず、そらをとぶを覚えていても他の街に飛べない。
ではどうやってマップを攻略していくかというと、「ライドギア」という道具から登録されたポケモンを呼び出し、ポケモンの背中に乗って海や空を渡るのだ。
なので今までのようにひでん技を覚えさせた、いわゆる「ひでん要員」を手持ちに加えずによくなった。
今までのひでん技は、サン・ムーンではわざマシンの1つとなっている。
・次の目的地がマップ上で常に表示されている
今作では3DSの下画面に常にマップが表示されている。
このマップ機能が従来より親切になっており、ストーリーを進める上でとても便利だ。
マップ上には主人公の現在地と次の目的地が常に表示されており、「あれ、次何したらいいんだっけ?」となることもなくストーリーを進めていくことができる。
・バトル中、自分のポケモンのわざと相手ポケモンとの相性が表示される
相手のポケモンのタイプを知らなくても割りとなんとかなるようになった。
相手のポケモンと対面して技を選ぶときに、技の下に「こうかばつぐん」「こうかあり」「いまひとつ」「こうかなし」と技の相性が表示されるようになった。
・個体値厳選、努力値振りが簡単に
ポケモンバトルをがっつりやる人にとってこの変更は大きい。
簡単に説明するとこれらはHPやこうげきなどのステータスを決定する要素で、個体値は個体ごとの固有の値、努力値は野生のポケモンとのバトルなどで後から振り分けを決められる値だ。
個体値の厳選には高個体値のメタモンを用意することで、目的のポケモンのタマゴを量産し良い個体を選んでいくというのが通例なのだが、高個体値のメタモンを見つけるのがこれまではかなり難しかった。
ところが、今作では野生のポケモンが「仲間を呼ぶ」ようになり、野生で出たメタモンとのバトル中に仲間を呼ばせまくることで高個体値のメタモンを確実に捕まえられるのだ。
また、努力値を特定のステータスに振っていくには同じ種類のポケモンだけを何度も倒す必要があったが、今作では「ポケリゾート」というところに1日程度預けておくだけで1つのステータスへの努力値振りが完了するようになった。
●やりこみ要素まで多くのユーザーを連れ込むゲーム設計
これらの変更を見渡すと、「間口を広くし、やりこみ要素まで誰でも到達できる」ということを意識してゲーム設計がなされたのだと思う。
現在のポケモンシリーズのやりこみ要素は、図鑑の完成もあるがやはりバトルだろう。
ここ数年のポケモンのゲーム要素で何が一番流行っているかと言えば「レーティングバトル」だ。
これはインターネットを通して世界中のプレーヤーと対戦をし、勝てば勝つほどレート上位に上がり、負ければレートが下がっていく。
そこには個体値の厳選はもちろんのこと、わざや戦術も洗練してきたプレーヤーたちがひしめき合っている。
このレーティングバトルの魅力に取りつかれたプレーヤーは寝ても覚めてもバトル環境の考察に明け暮れることになるのだが、ここに至るまでに必要な個体値厳選の手間やタイプ相性の把握など、やることが大変でその前にゲームを辞めてしまうプレーヤーも少なくなかったのではないだろうか。
その視点からサン・ムーンのゲーム設計を見返すと、まずはスムーズにストーリーをクリアしてもらい、個体値厳選などのコストも下げることでより多くのユーザーをレーティングバトルに誘おうという意図があるように思う。
以前は不正に改造された高個体値ポケモンが横行することもあったが、改造なしで簡単に厳選できるようにすることでそういった不正のメリットを相対的に下げるという意味もあるのだろう。
懐古的なことを言うと、ストーリー攻略にかかる手間やタイプ相性の知識など、そういった煩雑な部分まで含めてポケモンであったなあとも思うのだが、スムーズに攻略できるようになったのは新規ユーザー・ライトユーザーにとってはうれしいことだ。
私がスムーズにクリアできたのもそのおかげであるし。
ポケモンGOも、ゲームシステムを単純にしたことにはまず多くのユーザーにプレイしてほしい意図があったと開発元が明かしている。
まずは分かりやすく、多くのユーザーに、という思想はサン・ムーンとポケモンGOに共通しているといえる。
サン・ムーンは初めてポケモンをプレイする人にも、久しぶりにポケモンをプレイする人にも広くおすすめできるゲームだ。
ポケモンGOからポケモン熱が再燃していたら是非プレイしてみてほしい。
キャズム理論がいま、大きく進化している。
経営コンサルタントのジェフリー・ムーアがキャズム理論を提唱したのは1991年だ。
当時インターネットはまだ普及しておらず、状況は今と大きく変わっていた。
25年の時を経て、このキャズム理論が大きく進化を遂げている。
そして最新キャズム理論は、日本市場を再び大きく成長させる可能性を秘めている。
筆者は、キャズム理論に基づいて企業の変革を支援しているキャズム・インスティチュートが都内で行ったセミナーに参加した。
さらにこの団体でマネージング・ディレクターを務めるマイケル・エックハート氏と意見交換をした。
そこで得られたエッセンスを皆さんと共有したい。
●この25年間で、何が変わったか?
1991年にキャズム理論が提唱されて25年、大きく変わったことが3つある。
1つ目は、市場や顧客の変化が数倍速くなったことだ。
例えば企業向け携帯電話は、2010年代前半までブラックベリーの独壇場だった。
しかしわずか2〜3年で急速にアップルやサムソンに代替えされていった。
かつては競争優位性を確立した企業は、10年間は高収益ビジネスを持続できた。
しかしいまや競争優位性は2〜3年程度しか継続しない。
持続的競争優位性の時代は終焉(しゅうえん)し、一時的な競争優位性を常に継続して獲得し続けることが必要になっている。
だから常に顧客や市場の変化に対応して変革できる体制が求められているのだ。
2つ目は、顧客がますます力を持つようになったことだ。
例えばインターネット登場前は、最安値の商品を買うためにはいろいろな店を回る必要があった。
今では価格比較サイトで、市場の最安値はすぐ分かる。
企業の不祥事もすぐに表に出てしまう。
かつては顧客よりも企業のほうが知識を持っていたが、ネットが隅々まで行き渡った現代、顧客は何でも知っている時代になった。
昔から顧客を騙(だま)すという行為は商売倫理上の問題があった。
しかし現代では、そもそも顧客を騙すことは不可能な時代になったのだ。
3つ目は、1990年代からクラウド、VR+AR、モバイル、アナリティックス、AI、ソーシャル、IOT、ビッグデータといった新しいデジタルテクノロジーが次々と登場し、ビジネスのあり方を大きく変えているということだ。
この20年間、グーグル、アップル、アマゾン、アリババ、サムソンなどは、これらのデジタルテクノロジーを十二分に生かし、世界で躍進し大企業に成長した。
日本でも、ソーシャルを活用したソニーのプレイステーション、最近では任天堂ポケモンGOのような成功事例もいくつかある。
しかしかつて世界を席巻した1990年代までの日本企業の輝きと比べると、寂しさは否めない。
日本企業の多くは、デジタルテクノロジーの恩恵をビジネスに生かし切れていないのである。
●3ステップで考える最新キャズム理論
このような状況に追い詰められると、企業はこのように考えがちだ。
「それではデジタルテクノロジーを主役に据えて考えるようにしよう。
まずは技術に詳しい人材をそろえて、徹底的にデジタル技術を理解した上で、ビジネスを立ち上げよう」
残念ながら、この方法ではビジネスは立ち上げられない。
デジタルテクノロジーはあくまで手段だからだ。
重要なのは、デジタルテクノロジーを生かして、新しい顧客を生みだし、事業を創造することだ。
ここで役立つのが最新キャズム理論なのだ。
最新キャズム理論では、自社の新事業が市場でどのような状況にあり、どこに焦点を絞り、どのように支配していくかを考えていく。
具体的には、次の3ステップの問いに答えながら進めていく。
・ステップ1:“Where?” 今、自社商品は技術市場モデル(TMM: Technology Market Model)のどこにいるか?
・ステップ2:“Which?” どこにフォーカスするか?
・ステップ3:“How?” ビジネスを刈り取るためにどうするか?
そして市場の圧倒的シェアを獲得し、市場を支配する。
個別に見ていこう。
●ステップ1:“Where?” 今、自社商品は技術市場モデル(TMM)のどこにいるか?
最初に考えるべきは、自社商品の技術が、市場ではどのような普及状況にあるのか、ということだ。
ポイントは、自社商品の視点ではなく、あくまで市場の視点で考える、ことである。
例えば、電気自動車・テスラのケースで考えてみよう。
テスラのターゲット市場をカリフォルニア州シリコンバレーとして考えると、既に充電ステーションも充実しており、消費者にとっては現実的な選択肢になりつつある。
つまりキャズムを超えようとしている段階だ。
しかしターゲット市場を米国の他の地域として考えると、充電ステーションはそこまで普及していないので初期市場にとどまっている。
ターゲット市場を日本として考えると、そもそも充電ステーションをこれからつくろうとしているので初期市場に入ろうとしている段階だ。
このように、市場でどのような状況にあるのかを考える際に使うのが、技術市場モデル(TMM: Technology Market Model)だ。
連載第1回で紹介した「イノベーター理論」では、普及段階に応じてユーザーをイノベーター、アーリーアドプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードに分類して考えた。
TMMもこれに近い形で市場を分類して考える。
市場での商品の普及段階により、顧客の行動は異なるし、必要なビジネスの対応も変わってくる。
ここを見誤ると失敗してしまうのだ。
例えば2014年、アマゾンは新しいスマホ「Fire Phone」を発売した。
アマゾンにとってFire Phoneは新商品だ。
そこでアマゾンはさまざまな新機能を搭載してアピールした。
しかしこの時期、スマホは既に広く世に普及しており成熟市場になっていた。
目新しい機能だけで選ぶ顧客は既に少数派だったのだ。
2015年、アマゾンはFire Phoneの販売を打ち切ることになった。
本来ならば、2014年時点でスマホは成熟市場なのだから、目新しい新機能ではなく、既存のスマホ顧客が乗り換えやすい施策を考えるべきだったのだ。
このように、最初の段階で、自社の商品やサービスがターゲットとする市場の中でどのような普及状況になるのかを理解することが必要だ。
●ステップ2:”Which” どこにフォーカスするか?
目指す市場の状況がどうなっているかが分かったら、その次に「どこにフォーカスするか」、つまり顧客の絞り込みを考える。
ここで事例を紹介したい。
1990年に創業したドキュメンタムという文書管理システムを提供する会社がある(現在、ドキュメンタムは買収されてデルEMCの一部門になっている)。
当時、文書管理システム市場は成長していた。
この会社も創業後の数年間は、多くの応用分野で文書管理システムを提供していた。
しかし幅広く手を広げたにも関わらず、売り上げは伸び悩んでいた。
そこで思い切って75分野まで広げた応用分野を思い切って2分野に絞り込んだ。
その1つが、製薬会社の新薬認可申請業務だ。
私たちはつい「こんなニッチな分野に絞り込んでしまって、本当に儲(もう)かるのか?」と思ってしまうが、実は顧客はとても困っていたのだ。
新薬認可申請業務では、申請書類だけで25〜50万ページに及び、この書類をつくるために膨大なデータを調べる必要があった。
申請書類をつくるだけで、1日100万ドルという膨大なコストと、数ヶ月間もの時間がかかってしまう。
申請が遅くなる分、その期間の貴重な新薬の特許収入を失ってしまう。
顧客の痛みは極めて大きく、製薬会社の担当重役は「この業務がより簡単・迅速にできれば、ある程度のお金がかかってもぜひやりたい」と考えていた。
そこでドキュメンタムは「1年間、新薬認可申請業務に徹底的に取り組む」と腹を据えて、1社の顧客に集中して問題解決を図り、大きな成果を挙げた。
その後、製薬業界トップ40社中30社がドキュメンタムのシステムを使うようになった。
そして同様の文書管理のコストと時間の課題を持つ企業は他業界にもいた。
その後ドキュメンタムは装置産業、製造業、金融業といったさまざまな業界に広がり、一気にキャズムを超えた。
後日、ドキュメンタムのCEOはメディアのインタビューで「75分野から2分野に絞り込むのは、リスクがあったのでは?」と聞かれ、こう答えた。
「確かに75分野から2分野に絞り込むのはリスクが大きかった。
しかしもっと大きなリスクがある。
75分野のまま、絞り込まないことだ」
根回し・コンセンサスによる折衷案を重視し、既に手をつけている分野からの撤退が苦手な日本企業にとっては、耳が痛い話かもしれない。
このドキュメンタムの事例から学べることは、顧客を絞り込む上でもっとも重要なのは「顧客の痛み」、言い換えれば「顧客がそれを買わなければならない差し迫った理由」である、ということだ。
顧客の痛みを理解し、解決することが必要だ。
もう1つ、別の視点がある。
多くの企業で、まず市場規模や成長性を考えて市場を選ぶ、という間違いを犯している。
市場規模や成長性を無視してよいわけではないが、実際にはさほど重要ではない。
市場サイズや成長性は、マーケットアナリストがさまざまな仮定を積み重ねて算出している予測だからだ。
私たちがそれらの仮定をすべて把握しているわけではない。
他人が考えた予測よりも、自分が目の前にいる顧客で検証した「顧客の痛み」という現実を信じるべきだ。
●ステップ3:”How?” ビジネスを刈り取るためにどうするか?
フォーカスすべき市場を決めたら、キャズムを超えて、市場を着実に刈り取る戦略を立てる。
キャズム・インスティチュートではツールキットとして、戦略を立てるための9つの質問とその詳細なガイドを用意している。
エックハート氏は、「もしこの9つのすべての質問に答えられないのであれば、それはあなたは戦略を持っていない、ということだ」と手厳しい。
あなたがいま取り組んでいる事業でこれらに答えられるか、ぜひ考えてみていただきたい。
●日本企業で、最新キャズム理論は活用できるか?
ここまで最新キャズム理論の概要を簡単に紹介してきた。
さて、この方法論を御社でそのまま取り込むことはできるだろうか?
「現実には難しそうだ……」と感じる人も多いはずだ。
そこで次回は、この最新キャズム理論を取り入れる上で、日本企業の課題と解決策について考えてみたい。
(永井孝尚)