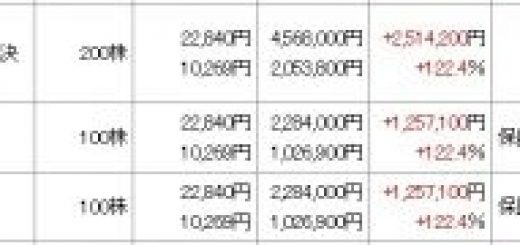時間帯による画面変更や大規模なリアルイベントを検討? 貴重な開発資料も飛び出した『ポケモンGO』セッション
●『ポケモンGO』開発の裏側が明らかに!
2017年2月27日〜3月3日(現地時間)、アメリカ・サンフランシスコ モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターの技術交流を目的とした世界最大規模のセッション、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2017が開催。
開催2日目となる2月28日、『ポケモンGO』のインタラクション&ビジュアルデザインを手掛けるディレクター、Dennis Hwang氏(以下、ホワン氏)が登壇し、“’Pokemon GO’ & Designing Interactive Games for the Real World”(現実世界とつながるインタラクティブゲームをデザインするということ)と題されたセッションが行われた。
●開発側も想定外だった『ポケモンGO』ムーブメント
セッションの冒頭では、改めてNiantic,Inc.の成り立ちと、『ポケモンGO』開発に至るまでの流れが解説された。
現在、『ポケモンGO』の開発・運営を手掛けるNiantic,Inc.(ナイアンティック社)は、2011年にGoogleのスタートアップ“Niantic Labs”として設立。
2015年には独立することになるのだが、当時はまだ全体で30人程度の小さな会社だったという。
同社は2013年12月にはスマートフォンの位置情報を新たなゲームの遊びへと昇華させた『Ingress』をリリース。
そのわずか数年後には『ポケモンGO』を生み出すに至るわけだが、ごく少人数の開発会社でしかなかったということは、やや意外に感じられるかもしれない。
さて、『ポケモンGO』の開発についてだが、これはNiantic Labsに対して任天堂、ポケモン、そしてGoogleが出資する形で進められた。
ホワン氏によると、「Nianticは、人とモバイル端末との関係を変えることを目的とした会社」であるという。
セッションで、「親がスマホいじっていて、子どもが親に遊んでくれとせがむような姿を変えたい。
なぜなら、スマホにはセンサーもあるし音もモニターもいいし、GPSもあるし、CPUもパワフルなのだから!」とファング氏は語る。
“理想的な親子の在りかた”を声高に説くのではなく、デジタルデバイスをうまく利用して、自然に変革させようという発想は、いかにも“Niantic的”。
Niantic Labsが持つこうした企業風土と、位置情報分野での高度な技術が、任天堂やポケモンといった、ワールドワイドにIPを展開する企業を引き付けたのだろう。
その後、Niantic Labsは2015年10月にgoogleから独立し、Niantic,Inc.に。
2016年7月には『ポケモンGO』をリリースすることになるが、そのころの騒動はまだ皆さんの記憶に新しいところだろう。
『ポケモンGO』がリリースされるやいなや、米国サンフランシスコや、豪州シドニーなど、世界各地で、『ポケモンGO』の“ツアー”のような群衆が生まれ、誰の目にもわかる巨大ムーブメントとなった。
ホワン氏によると、当時、Niantic,Inc.本社は「うわーっ!」と驚く感じだったという。
誰かが公園で「ポケモン!」と叫ぶと、まわりが「イエーイ!」と反応するような空気が醸成され、このムーブメントを仕掛けた当事者たちですら、「これはただごとではない」と感じていたというのだ。
データトラフィックは、リリース前にNiantic,Inc.側が想定していたものを遥かに越え、“最悪のケース”として想定しいたトラフィックのさらに50倍にも到達。
『ポケモンGO』の現在までのダウンロード数は6億5千万回以上、2016年7月のリリースから同年12月までにプレイヤーが歩いた総距離は87億キロメートル以上、さらに、同期間でプレイヤーが捕まえたポケモンの総数は880億匹以上と、いくつかの驚嘆すべき数字をたたき出したのだ。
『ポケモンGO』がリリースされたとき、一般にメイントピックとして注目されたのは、ポケモンを捕まえる際にスマートフォンのカメラを利用する“AR(現実拡張)”だった。
ホワン氏は、「これはラッキーなタイミングだったと思う。
HohoLensやMagin Leapが世に知られるようになったころだったから。
ただ、“ARの開発は実験室で起きているんじゃない、もう現場にあるんだ”というのがジョン(注:Niantic,Inc. CEO ジョン・ハンケ氏)の考えだった」と当時を振り返った。
確かに、GPSなどを使って現実世界とつながるという意味では、ARは地図や移動ナビシステムのような分野ではとっくに実用化されていたし、当のNiantic,Inc.自身がそのジャンルの成功例として、『Ingress』を運営していたのだから、この発言は当然のことと言えるだろう。
ちなみに、『Ingress』は、プレイヤーたちがふたつの陣営に分かれて争うゲームデザインになっており、作品の雰囲気もスパイ活動やSF的なノリで演出されている。
また、どちらかというと世界中に散らばる“エナジー”をパックマンのように拾っていく、ARG(代替現実ゲーム)的な側面が強い。
ホワン氏によると、『Ingress』開発の際に目指していたものは、「人々の習慣を少しでも変えてみよう」ということだったという。
たとえば、毎日の通勤ルートを少し変えてみたり、ずっと部屋に座っているんじゃなくて、外を歩いてもらいたい、運動してもらいたいと。
「これで僕たちは、位置情報ゲームの可能性を確信した。
収集要素や他者との交流といったこれまでのゲームメカニクスを使って、『Ingress』を作り上げた」と語るホワン氏。
なお、『Ingress』では、いまでも毎年、世界中で何千人単位を集めてのイベントが行われている。
タイトルに対するプレイヤーの熱量も高く、たとえば陣営のシンボルをタトゥーとして体に入れる人が現れたり(開発チームでは「やばい、これはもうロゴを変えられないぞ」と話されていたという)、『Ingress』をプレイするために運動量が増え、減量に成功する人が現れるほどだ。
ARゲームが現実世界に変化を与えた『Ingress』の成功は、Niantic,Inc.の開発チームにとって、このジャンルのゲームが新しい社会的交流を促し、地元や見知らぬ地の探検と新たな魅力の発見に有用であることを確信するきっかけになったという。
●そして『ポケモンGO』の開発が始まった
セッションでは、『ポケモンGO』には最初から明確なアイデアがあったことが紹介された。
『Ingress』とは異なり、「たくさんいる“エージェント”のひとり」ではなく、「自分が主人公」と感じられるものにして、多くのデモグラフィック(性別・年齢)に受け入れられるようにしたかったとのことだ。
なお、ゲームを開発していく上で、大きな問題となったことは、カメラによるARを使うことにしたことで生じる“Cognitive dissonance”(認知的不協和)を解決すること。
これは、たとえば、温かいビーチで美しい雪山の映像を見たときのような感覚のことで、現実世界と拡張現実世界のあいだで矛盾する認知が生じると、人は不快感を覚えるというものだ。
『ポケモンGO』では、この問題を解決することが難しい課題だったという。
また、最初はGoogle Street viewで見える景色にポケモンを表示するテストが行われたそうだが、景色とポケモンを合わせるのは簡単ではなかったとのこと。
それというのも、どういう環境がスマホの画面に表示されるのかを認識しないままだと、ピカチュウの表示が大きすぎて巨大怪獣に見えてしまったり、逆に小さくなりすぎたりすることがあるからだ。
なお、ポケモンを捕まえるアクションついては、Unityが得意なテクニカルアーティストがプロトタイプを手掛けたという。
さまざまな要素を調整した結果、我々が知る形に落ち着いた『ポケモンGO』。
ホワン氏によると、「できあがった形は最先端ARではないけれど、没入感やゲーム体験としては素晴らしいものになったので、“これで行こう”という決断になった」という。
マップデザイン自体にも、完成に至るまでは紆余曲折があったらしい。
ホワン氏によると、初期のマップはかなりポップな雰囲気だったが、その後、機能性を重視したところ、今度は冷たい感じに。
最終的には、ポケモンの世界観に合うようにテクスチャの見えかたなどの調整を重ねていったという。
また、開発途中には、マップに木や芝生、あるいは鳥などを出してみたこともあったそうだが、これは見た目としてはリッチになる反面、「現実と大きく違う」ために、やはり前述の認知的不協和を引き起こしてしまい、最終的に現在の(緑などはテクスチャで表示するのみに留める)抽象的なスタイルに集約されていったようだ。
さらに、ホワン氏は、「(マップ表示画面も、ポケモン捕獲画面も)時間帯に応じて明るさを変えるという案もあったけれど、結局は実装できなかった。
没入感を高める上でとても良かったのだけれど。
なにせチームの規模が小さかったので、日の傾きによって(朝・昼・夕方・夜)ポケモンたちのライティングを調整し切るまで手が回らなかった」と説明。
時間帯によって画面表示を変化させる仕様を考えていたことが明かされた。
●主人公キャラのアバターについて
さて、『ポケモンGO』プレイ中には長時間にわって目にすることになる主人公キャラのアバターだが、開発チームの方針としては、なるべく抽象的にしたかったとのこと。
一時期は「リアルな人型は避けようか?」という議論もあり、ただ円形のアイコンが動くだけのカーナビのようなアバターも検討されていた。
ただし、この案のアバターは見た目が洗練されていないように見えることから不採用に。
その後、さらにいろいろなアイデアが検討されるうちに現在の形になり、そこに衣装のカスタマイズ要素が追加することに。
このカスタマイズ要素に関しても、開発チームが小規模だったことや、モバイル向けというハード面での制約もあったので、技術的にもアートの面でも工夫する必要があったようだ。
●各ポケモンのアートディレクションについて
「ポケモンは歴史が長いIP(知的財産)だけど、自由にやらせてもらえたのは大変ありがたかった」と語るホワン氏。
『ポケモンGO』の命とも言えるポケモンのアートディレクションについては、現実世界にポケモンを登場させるということもあるので、その状況で生き生きとした姿になるように調整を重ねたそうだ。
うまくゲームデザインに落とし込むために、コンセプトアーティストが膨大な試案を出し、シェーダーやライティングをたくさん試し、現在のような姿になったという。
ホワン氏によると、「最終的には、あまり主張しすぎないフラットなライティングがうまくハマった」とのこと。
なお、ポケモンのシェーディングについては、ローンチの時点で100匹を超えており、容量を抑える技術的な工夫にも注意が払われたそうだ。
●UIデザインについて
『Ingress』では、右上のボタンをタップして、つぎにボタンをタップして……という感じで操作がやや複雑だったが、『ポケモンGO』では親指でさくっと使えるUIレイアウトが目指された。
また、本作の特徴的な操作ともいえる画面スワイプは、操作の満足感自体がとても高く、それほど正確にタップしなくても目的のアクションができるという利点があるので、採用に至ったとのこと。
両手で操作するのは利便性が下がるので、とくに片手操作にはこだわったようだ。
これについてホワン氏は、「寒い地域では、両手を出したくないですしね(笑)。
でも、こうしたUIによって、『ポケモンGO』はざまざまな人たちに愛されるようになりました。
70歳以上のおばあちゃんが高レベルに達したという話も聞いています」と、UIデザインの成功について語っていた。
●リリース後の思いがけない波及効果と『ポケモンGO』の今後
また、『ポケモンGO』は、社会不安克服の助けになったり、人々の交際・結婚のきっかけとなったり、自閉スペクトラム症患者の助けになったり、小児病院でのリハビリの助けになったりと、開発チームが事前には予想していなかった多くの分野への波及効果をもたらしたとのこと。
さて、気になる『ポケモンGO』の今後についてだが、セッションの終盤にホワン氏からいくつかの気になるキーワードが飛び出した。
そのまま掲載すると、「開発については、まだまだ時間が足りてない状態。
リリース時はやりたいことの10パーセントくらいしか入れられなかった。
入れたいアイデアはまだまだたくさんある」と、これからも多くの仕様を増やしていく可能性があることを示唆。
さらに、「美しい夕焼けも入れたいし、天気も反映したい。
ユーザーの集まるイベントも……『Ingress』では12000人が集まるイベントが東京で行われたりしていますが、『ポケモンGO』でもそうしたい」と語り、セッションの締めとした。
時間帯による画面表示の移り変わりは、前述の、開発途中でカットせざるを得なかった仕様に関する話の部分で少し触れられており、それに近いものをイメージするとよいのかもしれない。
気になるのは“多数のプレイヤーを集めるイベント”についてで、これはいろいろと想像の余地があるところだ。
記者の想像の域を出ないが、たとえば、いまのところゲーム性の面ではそれほど効果的に機能しているとは言いがたい、赤・青・黄3つのチーム分けをうまく活用したイベントや、出現条件が謎に包まれている幻のポケモンを絡ませるイベントなど、『ポケモンGO』プレイヤーが待ち望むような施策が実現することを大いに期待したいところだ。
●セッション後の質疑応答
以下では、セッション終了後に行われたホワン氏と聴衆の質疑応答の中から、気になるものをピックアップしてご紹介しよう。
Q「『ポケモンGO』と公的機関との連携をどう考えていますか?」
A「すでに日本では、自治体と『ポケモンGO』が連携し、地域コミュニティの醸成や観光の盛り上げをする取り組みが行われています。
そうしたものは今後、目指す方向のひとつだと思います」
Q「ジムの仕様を現在の形にした理由は?」
A「当初はポケモンの収集要素に注力していたためです。
今後も進化させていく予定で、より遊び込み甲斐のあるものにしていきたいと考えています」
Q「開発当初のアバターはアニメ風だったようですが、これを少しリアル寄りにしたのはどのような意図ですか?」
A 「ARになじむようにするためのものでした。
認知的不協和を防ぐためです。
それと、対象ユーザーをちょっと上に想定していたこともありますね。
今後は、もっと髪型増やしたり、見た目の年齢を変えたりできるようにしたいな、とは思っています」
Q 「もっとも大きな技術的課題は何だったのでしょうか?」
A 「開発チームが30人程度しかいないので、『ポケモンGO』の開発規模から考えると少ない人数で、どのようにゲームを作っていくかを考えるのが技術的課題だったと思います。
アーティストの作業効率を上げるためのツール開発ですとか、キャラクターパイプラインやシェーディング、調整をどうやって高速化するのかですとか、そういうところですね。
また、国によっては通信料が高いので、できるだけ通信データ量を減らすことにも注意を払いました」
Q『ポケモンGO』の今後の方向性はどのようなものでしょうか。
たとえば、コミュニティを強する方向や、もっとたくさん歩くようにする方向、人々の出会いのきっかけを作る方向など、いろいろあると思いますが……。
A「私たちはプラットフォームとして“現実世界版の○○を作ろう!”となったときの有力な選択肢になりたいと考えています」