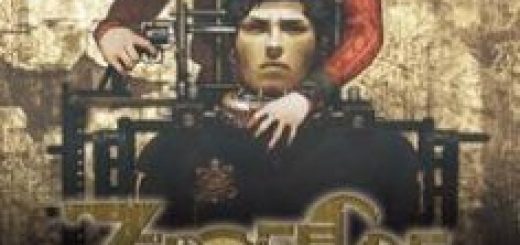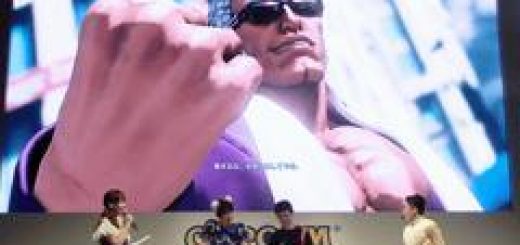<ポケモンGO>首都圏で50キロ歩いてみた
リリースされたとたん、日本中を熱狂に包んだ「ポケモンGO」。
ゲームに潜む危険性が多く報道されているが、ほんとうに危険なのだろうか。
22日の国内上陸と同時にポケモン探しに夢中になってしまった記者が、先週末に首都圏を約50キロ歩き回り、このゲームについて考えた。
◇射幸性は低く、ゲーム性は高い
これまでポケモンシリーズはほとんど未経験、慢性的な運動不足で体重3けた(100キロ超)の記者が、22〜24日の3日間で歩いた距離は47.7キロ。
中日(23日)は34回目の誕生日だったが、終日、真夏の町をうろついて暮れた。
ゲットしたポケモンは、国内の図鑑に載っている全143匹のうち75匹で、まだ道半ばだ。
下半身を中心にひどい筋肉痛に見舞われながらも、時間さえあれば歩きたくなってしまう。
おかげで体重は5キロ減った。
正直に言うと、これまでスマートフォン(スマホ)向けゲームに、いい印象は持っていなかった。
子供のころ、友達と競い合って遊んでいた任天堂の「ファミリーコンピュータ」などの機種で発売されたゲームと違い、「技」を磨く努力を必要とせず、課金額で強さが決まってしまう印象が強かったからだ。
その点、「ポケモンGO」はいわゆる「射幸性」は低く、ゲーム性が高い。
そこが最大の魅力だ。
今回、「手っ取り早く強くなり、ゲームの全容を知りたい」と、5000円ほど課金したが、使い切れず余っている。
なぜなら「ポケモンを集めて育てる」という根幹の部分に関しては「歩く」以外の攻略法はほとんどないからだ。
ひたすら歩いてポケモンとの遭遇を待つか、歩いた距離に応じてふ化する卵を育てるか、がゲームのかなめだ。
ポケモン同士を戦わせる場面では、相手との相性の把握や反射神経も必要で、なかなか奥が深い。
3日間集中的に向き合って、昆虫採集とメンコの要素を合わせたような、このゲームの魅力は十分に理解できたと思う。
◇都会と地方の「格差を実感」するゲーム?
1日目は会社のある東京都千代田区から、自宅がある千葉県船橋市までの約25キロ。
2日目は千葉県内を選び、香取市の田園風景の中や成田市の「成田山新勝寺」付近を歩いた。
3日目は東京都江戸川区の葛西臨海公園から、港区のお台場海浜公園にかけての海沿いを歩いてみた。
へえと思ったのは、歩く場所によって出てくるポケモンの種類が異なることだ。
たとえば、夜の公園の草むらには虫の形をしたポケモンが多く現れた。
水辺はコイを模したポケモン「コイキング」が「大漁」となるなど、芸が細かくて面白い。
地方と都会の「格差」も実感した。
ゲーム内で必要な道具や強くなるための道具が手に入る「ポケストップ」は、観光名所やランドマークなどに設置されている。
都会なら数メートルおきにあるが、田園風景の中ではほとんど見当たらなかった。
地理的な面で、地方のハンディキャップは大きそうだ。
記者の技術はまだ未熟だが、一つだけゲームのコツを挙げるなら、ポケモンGOの醍醐味(だいごみ)とされる拡張現実(AR=AugmentedReality)機能を切った方が、ポケモンは捕まえやすい。
スマホのカメラ機能を使い、現実の世界にポケモンが現れるARは確かに魅力的だが、遠近感がつかみづらくなり、ゲットするのが格段に難しい。
また、ARモードはスマホをあちこちに動かす必要も生じるので、場合によってはその仕草が「盗撮」と勘違いされる危険性もある。
さらに長時間プレーしようと思えば、スマートフォンの充電が不可欠。
ポケモンGOが生み出す経済効果「ポケモノミクス」は、充電機器メーカーに恩恵をもたらしそうだ。
◇注意しなければならないこと
ポケモンGOに限らず「歩きスマホ」は、前方不注意につながるため危険だ。
ただし、目的地を地図上で確認すれば、以降はさほど画面を見る必要がなく、ポケモンが出現すればスマホが震えて知らせてくれる。
むしろ、ポケモンと遭遇して思わず立ち止まることで、後方から来る歩行者や自転車などとぶつかる事故の危険性の方が高いような気がする。
記者もポケモンが出現すると、まず後ろを確認してから立ち止まるように心がけた。
運転しながらスマホをいじり、検挙されるケースも出てきているが、自動車の利用はほとんど意味が無い。
なぜなら、一定の速度を超えて移動すると、移動距離としてカウントされなくなる。
電車で移動してみたが、これもカウントされなかった。
その点、ポケモンGOは、「歩きスマホ」や「ながら運転」による事故を助長する仕組みにはなっていないと感じる。
混乱を避けるため、境内や神域での使用を禁止した寺社もあるそうだ。
確かに大きな寺社は目立つ建造物が多く、ポケストップも多く設置されている。
しかし、成田山を訪れて感じたのは、普通のポケストップや、ポケモン同士の対戦場である「ジム」にたむろするプレーヤーはさほど多くないということだった。
それよりトラブルの元になりそうなのは、ゲーム内の道具の一つ「ルアーモジュール」だ。
この道具は、ある人がポケストップで使用すると30分間、周囲にポケモンが多く現れるようになる。
周辺のプレーヤーの画面にも花びらが舞う目印が現れ、近くに行けば「おこぼれ」をもらうこともできる。
ポケモンGOでの人だかりのほとんどはこれだった。
いつもは人けのない住宅街の小さな公園やマンション入り口などにできた人だかりを住民が不審そうに見守る、という風景もあちこちで見た。
トラブルを防ぐには、こうした場所でルアーモジュールを使わないなどの気遣いが求められる。
暑さにも注意しなくてはならない。
3日間、歩き回ったおかげで減量できたのはうれしかったが、日焼けで顔が真っ赤にほてってしまった。
こまめな水分補給を心がけ、日焼け止めや虫よけスプレーなども用意した方がいい。
◇一過性のブームで終わらせず、前向きな活用に期待
こうした特徴を踏まえて考えてみると、ポケモンGOを「人集め」の道具として使うことができる。
イベントなどの会場内にポケストップがあり、ルアーモジュールを仕掛ければ人集めにつながりそうだ。
開発者側と提携し、地域限定のポケモンの出現を予告するような観光キャンペーンを打つなどの戦略も、実現すれば効果が見込めるだろう。
気になっているのは、ブームが過熱してしまうこと。
この熱狂の中で高いレベルのプレーヤーが増え、初心者が勝てずに「ポケモンGO離れ」してしまうとしたら残念だ。
このゲームは本来、長く愛用されることで健康づくりにも役立つ。
たとえば「ニンテンドー3DS」などで発売されているポケモンのゲームに、ポケモンGOのデータも使えるようにすることで、世界中の人と対戦や交流ができるようになれば、さらに魅力は増すだろう。
ゲームを長く楽しめるような開発者側の工夫にも期待したい。